第四章 町の行財政
第一節 概況
現在の地方財政の推移を知るためには、わが国の地方自治の発展のなかで特に財政制度や財政事情を中心に考察することが最も必要と考えられるので、その変遷をたどってみる。旧幕時代は町村財政に体系的な一定の規則があったわけではなく、その運営は各町村の旧慣と便宜にゆだねられ、地方により大いにその様相を異にしていた。一、自治団体と財政のあゆみ
明治11年7月、府県会規則、地方税規則とともに、郡区町村編成法が制定され、町村もはじめて自治団体としての性格が一応認められるようになった。とはいえ地方税規則の内容は主として府県財政に重点がおかれ、区町村の財政運営は、原則としてこれに拘束されなかった。その後明治17年、区町村会法の大改正がなされ、官選戸長制となったが、町村の運営や財政面では自治団体としての整備が行なわれた。すなわち、当時区町村費は任意の協議制であったが、公財政のたてまえを明らかにするとともに、予算・決算・区町村会の議決報告内容が規定され、財務制度の基礎が確立された。
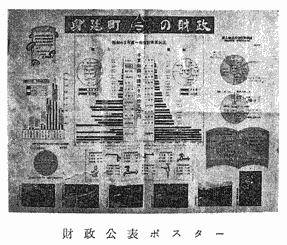 |
1 市町村費の支出ならびに市町村費をもって支出すべき事業はすべて市町村会の議決による
2 郡長が必要と認める場合は強制的にその支出額を予算に加える。
3 町村不動産の売却、譲与等の場合は市町村会の議決のみならず、郡参事会の許可を要する。
4 収入役制度を設ける。
5 決算は町村長が審査して町村会の認定に付する。
二、中央集権体制下の自治体財政
当時のわが国は強力な中央集権のもとで地方支配を確立し、資本主義を急速に発展させるために、軍備と産業の充実に多くの資金を注入する必要から、みずからは有力財源を独占しながら地方に対しては法令によって国政事務を委任し、負担を地方に転嫁する政策をとった。したがって市制・町村制では委任事務に対する強制予算の制度がとられ、収入は財産収入・寄付金・使用料のほか国税と県税の付加税を中心とし、しかも租税の賦課・起債なども内務・大蔵大臣の認可を必要とするように、事実上中央集権的であった。こうして、日本の地方財政は、制度成立の当初から実質的に委任事務の優位と、独立財源の枯渇(こかつ)という特長を有しながら、また、自主性を有しながら自主性をかなり制限された中央集権的なものとして、第二次大戦後まで続けられた。
そうしたなかで、昭和初期の不況下における委任事務の累増と、都市と農村の不均衡をさけるため、国は行政内容の一定水準を確保し、地方団体間の調整をはかるものとして、昭和11年(1936)に臨時町村財政補給金制度を創設した。この制度は次第に拡大されて、昭和十五年地方税制度の大改革とともに地方分与税に発展した。
戦後においても地方財政は敗戦による混乱とインフレーションにあえぎ、多難な歩みを続けたのである。
三、地方自治法の制定と地方財政
昭和22年4月には地方自治法が制定され、地方分与税制度も地方配付税に改められた。これと並行して同年7月、地方財政法が公布された。一方民主化政策による諸法律制度の委任事務は激増し、これによる地方の行財政機構と人員の増加は、自治体財政の台所を大いに揺がせたといえる。インフレーションの抑制のため経済九原則とドッジラインによる徹底した財政緊縮政策がとられ、このため地方財政も配付税の半減、公共事業費の削減で大打撃を受けた。
四、シャウプ勧告とその後の地方財政
昭和24年にシャウプ使節団が来日し、ドッジラインを税制面および財政面から見た地方自治の確立を目的としてこれを補完し勧告を行なったがそれほど効果はあがらなかった。さらに25年7月には税制の大改革(独立税主義)と、地方配付税が地方財政平衡交付金制度にかわり、つづいて昭和29年には地方交付税制度となった。その間には地方自治法および地方財務制度等の改正もいくたびか行なわれ現在におよんでいる。五、身延町の財政
本町合併の初年度である昭和30年度の予算額は、一般会計8,475万9千円、特別会計427万円であり、現在の予算額は(昭和44年度当初)一般会計3億607万2千円、特別会計6,148万4千円である。当時の予算と比較して財政規模が飛躍的に大型化し貨幣価値の変動・人件費・需用費の増額があったとはいえ町財政の充実強化をもの語っているといえよう。今後においても経済成長の上昇により、歳入における地方交付税および町税等の自然増収がはかられるとはいえ、一方歳出面においても、道路、橋梁の整備、統合中学校の建設、産業の振興、福祉、衛生施設等各面の財政需要も増大の一途をたどっている。
町においてはこれらの諸事業を計画的に実施するため、長期建設計画の樹立中であるがこれらの諸経費を賄うためには、財源として国・県支出金および起債等に依存しなければならない実情にある。
また今後増大する経費についても、健全財政を堅持しながら、財政、行政の近代化と合理化につとめ、町民の理解と協力のうえに立って運営をはからねばならない。

