第三章 産業のあらまし
第一節 農業
戦後、わが国では農地改革によって自作農化がすすみ、また、農業技術の改良などにより生産が向上して食糧事情もしだいに緩和され、経済の安定と高度成長に伴って、生活、文化の水準が向上し、都市と農村生活の平均化が進んで、農家の経済は自給経済から現金経済へと移行してきた。本町の農業経営規模は極めて零細であり、大部分は兼業農家で、多く農外所得に依存して生活を支えている現状である。
今後もこの傾向は、一層進むことが予測される。また他産業の伸展によって、農家の労働力は吸収され、世帯の所得は増大し、生活の水準は向上するであろうが、相対的には下降線をたどって進展を期することは非常に困難な状況下にあり、現況は極めて深刻である。
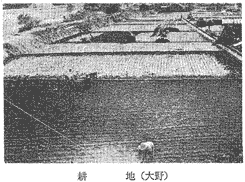 |
一、農地改革
昭和21年、改正農地調整法により第一次農地改革が進められたが、根本的な農地改革のためには不充分であったため、同年12月、自作農創設特別措置法が制定実施され、いわゆる第二次農地改革が強力に推進されたのである。その要点は
(1) 不在地主の所有地、在村地主の所有する小作地で内地平均1町歩(本町では5反歩)、北海道では4町歩をこえる分、および自作地と所有地合計が内地で3町歩、北海道で12町歩をこえる分の小作地は強利買上げの対象となる。
(2) 自作地は原則として強制譲渡の対象とならないが、請負小作地や不耕作地は全面的に買収可能とした。
(3) 土地の買収、譲渡は市町村農地委員会があたり、その構成は地主3、自作2、小作5の割合とした。
(4) 土地の取り上げを制限し、新たに最高小作科率を定めた。すなわち田では総収穫代金の25パーセント、畑ではその主作物の代金の15パーセント以下とした。
 |
身延町の旧町村農地委員会の初代会長はそれぞれ次のとおりである。
下山村 望月 �(自作代表)
身延町 藤田岡波( 〃 )
豊岡村 大沢幸房( 〃 )
大河内村 若林孝義( 〃 )
農地委員はその後一回改選され、農地改革の推進にあたったが、昭和26年に新農地法の制定により、現在の農業委員会制度にうけつがれている。
なお、県下の農地改革推進のため、県には知事を会長とする25名の県農地委員会がおかれ、各市町村よりの訴願の審査その他重要事項の決定にあたったが、本町からは四号委員(学識経験者で大臣の選任したもの)として深沢義守が就任し、小作料審査委員長をつとめている。
この農地改革による自作農化のため農家の生産意欲が高まり、また、適地適作の方式を採用することができ、化学肥料の大量進出、農業技術等の急激な進歩によって、食糧危機を乗りこえることができたので、食糧事情は年々緩和されたが、麦類、豆類、いも類の主要食糧作物の作付けは逐次減少し、現在では食生活の変化もあって、米までも過剰生産という皮肉な現象を呈している。
第二次世界大戦勃発以来、十年余も続いた食糧難時代と現在では、全く隔世の感がある。従来の自作農地も、農地解放によって取得された耕地も、産業の変遷によって工場の敷地、あるいは宅地化し減少が目立ち始めた。最近では、その傾向が特に顕著になってきた。
自作農創設別措置法によって行なわれた農地等の移動状況と、最近1年間の(昭和42年度)農地の転用状況は表1、2の通りである。
表1 自作農創設特別措置法(農地改革)による地区別農地等の移動状況
|
買収面積
|
|||||
| 地目別 地区別 |
田
|
畑
|
宅地
|
採草地
|
計
|
|
反畝歩
|
反畝歩
|
反畝歩
|
反畝歩
|
反畝歩
|
|
|
下山
|
159.7.10
|
298.2.07
|
3.1.05
|
10.1.25
|
471.2.17
|
|
身延
|
201.1.19
|
318.7.08
|
6.3.13
|
65.7.01
|
591.9.11
|
|
豊岡
|
100.8.24
|
168.8.17
|
8.17
|
23.1.08
|
293.7.06
|
|
大河内
|
53.3.01
|
171.2.10
|
2.3.46
|
2.2.12
|
229.1.19
|
|
計
|
515.0.24
|
957.0.12
|
12.7.01
|
101.2.16
|
1586.0.23
|
|
売渡面積
|
|||||
|
地目別
地区別 |
田
|
畑
|
宅地
|
採草地
|
計
|
|
|
反畝歩
|
反畝歩
|
反畝歩
|
反畝歩
|
反畝歩
|
|
下山
|
159.5.06
|
297.6.23
|
3.1.05
|
10.1.25
|
470.4.29
|
|
身延
|
201.1.19
|
318.7.08
|
6.3.18
|
65.7.01
|
591.9.09
|
|
豊岡
|
100.8.24
|
168.8.24
|
8.17
|
23.1.08
|
293.7.06
|
|
大河内
|
53.3.01
|
171.4.23
|
2.3.26
|
2.2.12
|
228.4.02
|
|
売渡未済
|
2.06
|
1.3.01
|
|
|
1.5.07
|
|
計
|
515.024
|
957.0.12
|
12.7.01
|
101.2.16
|
1586.0.23
|
表2 農地の転用状況 昭和42年
|
区分
|
転用地
の合計 |
宅地
|
工鉱業等
施設用地 |
学校敷地
|
鉄道水路
道路敷等 |
植林
|
|
面積
|
アール
493 |
102
|
179
|
16
|
72
|
124
|
|
割合
|
%
100 |
20.7
|
36.3
|
3.2
|
14.6
|
25.2
|
農地の所有権の移転の状況(事由別)
| 事由 区分 |
総数
|
贈与
|
経営の
縮 少 |
耕地(農
業)放棄 |
その他
|
小作地の
譲 渡 |
||
|
譲
渡 件 数 |
実
数 |
総数
|
57件
|
2
|
6
|
1
|
37
|
11
|
|
下山
|
30件
|
1
|
5
|
1
|
20
|
3
|
||
|
身延
|
11件
|
1
|
1
|
|
8
|
1
|
||
|
豊岡
|
3件
|
|
|
|
1
|
2
|
||
|
大河内
|
13件
|
|
|
|
8
|
5
|
||
|
地
区 別 割 合 |
総数
|
100.0%
|
|
|
|
|
|
|
|
下山
|
52.6%
|
|
|
|
|
|
||
|
身延
|
19.3%
|
|
|
|
|
|
||
|
豊岡
|
5.3%
|
|
|
|
|
|
||
|
大河内
|
22.8%
|
|
|
|
|
|
||
|
事
由 別 割 合 |
総数
|
100.0%
|
3.5
|
10.5
|
1.8
|
64.9
|
19.3
|
|
|
下山
|
100.0%
|
3.3
|
16.7
|
3.3
|
66.7
|
10.0
|
||
|
身延
|
100.0%
|
9.1
|
9.1
|
|
72.7
|
9.1
|
||
|
豊岡
|
100.0%
|
|
|
|
33.3
|
66.7
|
||
|
大河内
|
100.0%
|
|
|
|
76.9
|
23.1
|
||
|
譲
渡 面 積 |
総数
|
454アール
|
32
|
42
|
13
|
256
|
111
|
|
|
下山
|
188アール
|
9
|
41
|
13
|
118
|
7
|
||
|
身延
|
54アール
|
23
|
1
|
|
25
|
5
|
||
|
豊岡
|
21アール
|
|
|
|
10
|
11
|
||
|
大河内
|
191アール
|
|
|
|
103
|
88
|
||
二、離農
食べるものさえあれば百姓は暮らせるといった自給経済時代は過ぎ、現金経済へ移行してきた現在において、商業主義の浸透が激しくなるにつれて、農家にとって現金の必要性はますます高まってきた。ところが、それと農業の収益性の停滞とにより、農業経営はますます困難になりつつある。本町においては、農業経営上まことに不利な条件が重なっている。たとえば、農業生産物の換金を望んでも、耕地はすくなく、しかも、山間に存在しているため小規模経営を余儀なくされ、また、消費都市は遠く、その上交通の便もよくないので、せっかく作った農産物の販路も制約される。したがって、耕地には一部を除いてほとんどが昔ながらの主食類中心の自給的農産物がつくられ、商業主義的農業には、ほど遠い現況である。経済の高度成長に伴い、昭和35年頃から、他産業の著しい伸展によって、農業と他産業の所得格差は、年々深まるばかりである。したがって、農外からの現金所得に多く依存しなければ、生活を支えることができなくなってきた。二、三男対策などといわれた就職難時代は過去のこと、労働力は他産業に益々吸収されて、三ちゃん農業、主婦農業といわれているが、これも過去のことになりつつある。
ここ数年来、農業経営の基幹となるべき青壮年層は、日を追って他産業へ流出し、今では主婦までがその傾向をたどっており、農業経営の基幹は、老人層へと移行してしまった感さえある。こうしたなかで、年々農業経営を縮少したり、或は離農する者が多くなってきた。離農者の多くは、農業だけでは生活が維持できないことと、よりよい生活を求めて、若者は都市へ出て他産業に従事し、居を構え、一家揃って転居するというような形で離農してゆく者が多い。また、比較的安定した職業に従事しているものが、生活に余裕がでてくると、転居しないまでも田畑を手放し、経営を縮少してゆく農家も現われており、今後もこの傾向は続くものと思われる。昭和35年世界農林業センサス、昭和40年中間農業センサス、更に昭和43年山梨県農業基本調査の結果、本町は表3の通りであるが、昭和35年から昭和43年2月1日までの8年間の間に、農家戸数は約15.4パーセント(251戸)減少しており、1ヵ年平均、約2パーセント(32戸)の減少率である。
表3 地区別離農戸数
| 地区名 年次 |
下山
|
身延
|
豊岡
|
大河内
|
計
|
| 昭和35年 〜40年 |
戸
17
|
戸
90
|
戸
18
|
戸
37
|
戸
162
|
| 昭和40年 〜43年2月 |
20 |
25 |
17 |
27 |
89 |
|
計
|
37
|
115
|
35
|
64
|
251
|

