第二節 土地改良
一、概説
土地改良という主題から、新田開発や、開墾、土質の改良、排水工事等、今日までの変遷と現況を、考察する。本町の農耕地は、富士川とその支流が、形成する狭小な傾斜地と、段丘上に造成されている500ヘクタール余が、耕地の主なもので、昔から、大規模な土質改良や、排水工事もなく、長い年月の営みの中で、個人、または、数人の共同体による開墾がおこなわれ、時代の推移とともに逐次、農地が拡張され、村落の発展と相まって、今日に至ったものと推察される。
徳川時代以前は、山付地の比較的小規模な山畑が、開墾され、付近の沢水が、用水に利用されて、山田が耕作されたものであろう。
徳川時代になって、幕府の政策としての新田開発の奨励によって、村単位の大規模な用水堰の開削工事がおこなわれ、畑地の水田化が一段と進められ、徳川時代中期に、現在に近い水田面積が、整備されたのは本百姓制度があずかってある力あるものと考える。
富士川河原の水田地帯は、近年になって、開田されているが、村落に近いところは、明治以後の大水害によって流失し、再開田であるという古老の話も聞いている。
いずれにしても、今日までの推移を語る資料に乏しく、わずかに残存している断片的な資料から、推測しつつ、考察する。
二、開田の歴史
本町の農耕に関する記録が残されているのは、戦国時代末期の穴山氏による貫高制で、下山天輪寺の古文書などに記録されているが、町内全体のことについては、知ることができない。慶長9年(1604)村高帳・日ノ村、跡部氏の古文書に、次のように各村の石高が、記録されている。
八木沢村 50石5斗 門野村 12石9斗6升
帯金村 98石6斗1升 大城村 21石 1升
大垈村 2石5斗1升 相又村 15石6斗9升
椿草里村 3石8斗9升 横根村 13石2斗9升
丸滝村 40石5斗6升 中村 24石2斗3升
角打村 63石8斗9升 光子沢村 27石2斗3升
和田村 43石5斗6升 俵子村 24石2斗3升
大島村 78石8斗6升 注(清子村の清を誤記したものであろ
下山村 614石 5升 う。)
波木井村 194石9斗9升 下山南松院 25石
大野村 114石8斗9升 竜雲寺 10石
梅平村 210石8斗8升 天輪寺 3石6斗
小田村 5石5斗7升 西林坊 2石8斗4升
船原村 57石5斗7升 石高合計 1,834石5斗8升
粟倉村、大崩村、樋之上村、身延については記録がない。
総合計1,834石5斗8升の石高が、計算できることから、当時の農耕規模を推量することはできるが、水田面積を算出することは困難である。それは、この石高の中に、水田・畑・山畑・苅生畑まで含まれているからであり、逆算のむずかしさは、次のことからも、理解できる。
甲州風土記に、
土地を量って、反別や、田畑の品等を定め、これを石盛とも斗代とも云う。二毛作田を、麦田とし、上田、中田、下田、下々田に分ける。
上田を三−四所坪刈して、坪平均籾一升あれば、一反歩当り三石とし、これを五分摺にして、米一石五斗を得る。
石盛十五と云い、以上の品等によって、二つ下がりを通法とし、畑の場合は、上畑を中田の六割とみなし、これらの数値を集計反別に掛けたものが、村の石高である。
以上のことから、概算をするとしても、田畑の広さや、等級などの推定が困難である。武田氏滅亡後の、余命を保った穴山氏も、梅雪の横死と、その子勝千代の早世によって、徳川氏の支配地となった。本町でも、大久保石見守の検地が、寛文8年(1668)から、11年までおこなわれている。上田を三−四所坪刈して、坪平均籾一升あれば、一反歩当り三石とし、これを五分摺にして、米一石五斗を得る。
石盛十五と云い、以上の品等によって、二つ下がりを通法とし、畑の場合は、上畑を中田の六割とみなし、これらの数値を集計反別に掛けたものが、村の石高である。
検地水帳の現存するものは、次の通りである。
粟倉村 御検地水帳 寛文八年、九年
帯金村 御検地水帳 寛文九年
下山村 御検地水帳 寛文八年、九年
角打村 御検地水帳 延宝六年
大野村 御検地水帳 寛文十一年(写)
相又村 御検地水帳 寛文十一年(一六七一)
相又村の検地水帳は全巻保存されており、貴重な資料である。帯金村 御検地水帳 寛文九年
下山村 御検地水帳 寛文八年、九年
角打村 御検地水帳 延宝六年
大野村 御検地水帳 寛文十一年(写)
相又村 御検地水帳 寛文十一年(一六七一)
(名寄帳、年貢割付帳も相当数区長宅に保管されている。)
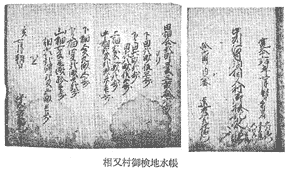 |
田合計 一五町三反 二八歩 刈生畑 二四町五反八畝 七歩
上田 一町三反一畝二二歩 屋敷合計 五反八畝二〇歩
中田 三町五反 八歩 田畑屋敷合計 六四町一反二畝二七歩
下田 五町八反 一六歩 石高 一六二石二斗六升一合
下々田 四町六反八畝一二歩
畑合計 四八町八反八畝二九歩
上畑 六反三畝二九歩
中畑 一町九反九畝二二歩
下畑 五町 八畝 二歩
下々畑 六町 四畝 八歩
山畑 九町八反九畝 一歩
相又村の石高は、検地以後明治まで、変化していない。上田 一町三反一畝二二歩 屋敷合計 五反八畝二〇歩
中田 三町五反 八歩 田畑屋敷合計 六四町一反二畝二七歩
下田 五町八反 一六歩 石高 一六二石二斗六升一合
下々田 四町六反八畝一二歩
畑合計 四八町八反八畝二九歩
上畑 六反三畝二九歩
中畑 一町九反九畝二二歩
下畑 五町 八畝 二歩
下々畑 六町 四畝 八歩
山畑 九町八反九畝 一歩
江戸時代の初期、全国的に石高の増加をねらって、新田開発が奨励され、用水堰の発達は、一層畑地の水田化をすすめ、これらの工事は、村単位の大工事であった。
本町内の新田開発に関する古文書を、次にあげてみると、
寛文13年(1673年)下山村己年改新田水帳
一町一反八畝一二歩
高八石五斗一升九合
中田 二一歩
下田 一反四歩
下々田 一町七畝一七歩
とあり新田開発がみられる。高八石五斗一升九合
中田 二一歩
下田 一反四歩
下々田 一町七畝一七歩
この年(延宝元年・1673年)大野渠の開削が、おこなわれ大野トンネル北口に大野渠開削記念碑がある。建立は、明治20年(1887)9月30日で「用水開基当山六世、日寛大聖人延宝元年癸丑年創鑿」とある。
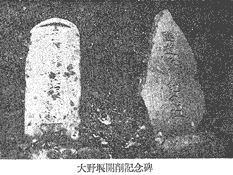 |
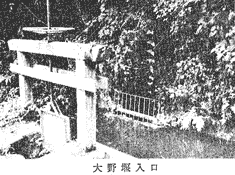 |
大野渠、大野村ニ在リ延宝中柏坂山ヲ鑿スルコト九拾三歩ニシテ、波木井川ノ水ヲ引ク、是時県官ニ望ミ、請テ金九拾参両ヲ借テ、工役ノ費トス、後ニ其ノ金ヲ納メテ、今ハ御普請所トナル云々
村里部に、
大野渠、此ノ山ヲ鑿チ渠ヲ作ル、長九拾参間、山畠尽ク稲田トナレリ
とある。明治25年(1892)の身延村誌に、
「略、南流シテ大野組ノ飲用及ヒ灌漑に供シ、流末字下河原ニテ富士川ニ入ル、長拾町参拾七間、幅五尺、反別九町七反一歩ニ注グ云々
とある。 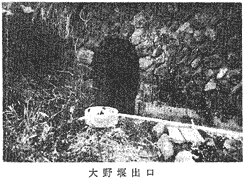 |
水路は非常に巧みに設計され、水を落すと自然に両側へ土砂とともに水が引くようになっており、ほとんど手を加えなくても通水に支障がないほどである。
これら一連の新田開発は、当時の小規模な検地が実証している。
寛文13年(1673)下山村巳年改見取改帳 2反5畝18歩
延宝5年(1677) 相又村巳起見取改帳
元禄7年(1694) 相又村戊□見取改帳
などがある。また次の
天保9年(1838)西之入新田開発の古文書がある。相又村針山(市川まさ子所蔵)定一札之事
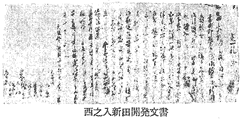 |
西之入新田之儀者明和六丑年、前、町野惣左衛門様、御代官様、新田開発願上申候処、後ニ久保平三郎様ヘ御引渡シ相成リ、江戸表ヘ御窺相成リ、堰入用御引当而者、各○之処御下戻シ相成リ申候処、其後チ、安永五年、畑時一統ニ而相談イタシ、金子借用致右之畑堰引始メ、金子多分相掛リ、樋十八町、但シ七尺□□柱ニ而引通水反別相改、右借用金元利共勘定年々イタシ、御上納同様ニ納メ、御勘定可任筈トリ定メ置申候処、後年々□□堰岩儀ニ候得共、川押付年々クスレ、志フク多金相掛リ申候、又オモ立チ候者ニテ、金子借用致石岩穴堰筋堀通シ候得共クスレ、行々岩切夫銭等相掛リ誠難儀致極、畑時一統ナケカハ敷奉存候処ト、天保九年□□□□一件ニ而多分夫銭相掛リ候ニ付、右参拾五六年前田畑成リヘトリ掛時、相談シ候処、西之入堰之儀ハ、前書通リ、難儀ニ付参拾五年前之内半起之積リ、十五年相立候得共、右借用等モ切ル申可積リ而相談相定メ置候処、当戌年村内ニテ、右相談之通リ起ス可クト、申サレ候処新堰畑時一統申候儀者、誠ニ当春モナン場出来、山切出金掛リ、来ル春モカクヤト申シ、岩参拾間余切申サネハ、水上リ不申候、又々右穴之下、八、九間又穴堀リ申サネハ相叶不申候共、此段村方ヘ申入候得者、役人右之書付被見致趣之事ニトリ仰聞、畑田成、取米二斗五升之所、三ヶ二之積リヲ以、行々トリ下ヶ上納致可定メ仕リ置申候者、以後ニ外畑田成レバ二斗五升、西之入通リ三ヶ二ノ積リ、但シ九升引ニ而、反々一斗六升之トリ米也
天保九戌年(一八三八)極月十日相定メ置申候
長百姓 九兵衛 会合 太衛門
〃 五兵衛 〃 元五郎
〃 治左衛門 〃 佐兵次
〃 弥左衛門 〃 勇蔵
〃 儀兵衛 〃 三右衛門
以上
西之入新田は、豊岡小中学校のある大城川右岸段丘上である。天保九戌年(一八三八)極月十日相定メ置申候
長百姓 九兵衛 会合 太衛門
〃 五兵衛 〃 元五郎
〃 治左衛門 〃 佐兵次
〃 弥左衛門 〃 勇蔵
〃 儀兵衛 〃 三右衛門
以上
寛政11年(1798)早川河原開田の古文書に
書ヲ以申上候事
開田見込予想違之事」 下山村 東宣
早川河原三町歩余、開田
文化三年(一八〇六)
開発延年鍬下延年願 下山村 東宣
以上断片的資料ではあるが、これら一連の過程を経て、徳川時代も後期にはいる。文化11年(1813)の甲斐国志、村里部から、村別石高をみると、開田見込予想違之事」 下山村 東宣
早川河原三町歩余、開田
文化三年(一八〇六)
開発延年鍬下延年願 下山村 東宣
上八木沢村 九四石四斗五升七合 波木井村 一九九石三斗一升三合
下八木沢村 六九石二斗二升一合 大野村 六五石六斗九升三合
帯金村 二八九石二斗五升三合 本遠寺領 四九石二斗 二合
椿草里村 二四石 五升九合 梅平村本遠寺領 二一〇石八斗七升
大垈村 二一石七斗五升九合 小田船原村 一〇六石八斗七升九合
大崩村 二〇石六斗九升六合 門野村 四四石七斗四升五合
丸滝村 六九石 四合 大城村 六〇石六斗九升九合
角打村 一〇三石七斗七升二合 相又村 一七三石三斗五升七合
和田村 一七九石六斗二升二合 横根村 二一石一斗四升四合
樋上村 一五石二斗五升一合 中村大久保村 三六石四斗四升八合
大島村 三五一石 三升九合 清子村 一八六石五斗 八合
粟倉村 一〇〇石一斗一升八合 光子沢村 五二石九斗二升四合
下山村 七七三石 八升四合 石高合計 三、三一九石一斗一升七合
慶長9年の古石高と比較してみると、約2倍に増加していることになる。下八木沢村 六九石二斗二升一合 大野村 六五石六斗九升三合
帯金村 二八九石二斗五升三合 本遠寺領 四九石二斗 二合
椿草里村 二四石 五升九合 梅平村本遠寺領 二一〇石八斗七升
大垈村 二一石七斗五升九合 小田船原村 一〇六石八斗七升九合
大崩村 二〇石六斗九升六合 門野村 四四石七斗四升五合
丸滝村 六九石 四合 大城村 六〇石六斗九升九合
角打村 一〇三石七斗七升二合 相又村 一七三石三斗五升七合
和田村 一七九石六斗二升二合 横根村 二一石一斗四升四合
樋上村 一五石二斗五升一合 中村大久保村 三六石四斗四升八合
大島村 三五一石 三升九合 清子村 一八六石五斗 八合
粟倉村 一〇〇石一斗一升八合 光子沢村 五二石九斗二升四合
下山村 七七三石 八升四合 石高合計 三、三一九石一斗一升七合
慶長9年(1604)から、文化11年(1813)まで、209年間の開発増加を物語っている。
この期間の村別の増加の割合をみると、次の通りである。
下山村 1、2倍
丸滝村・角打村・横根村・中村大久保村・清子村・光子沢村 約2倍
八木沢村・帯金村・門野村・大城村 約3倍
大島村・和田村 4倍強
椿草里村・大垈村・相又村 8倍から11倍
波木井村・大野村・梅平村には変動がない。
塩沢、新宿、門内については、久遠寺領で身延山史に石高二八石八斗五升九合二勺と出ている。
新田開発の黄金時代は、徳川時代の初期で、相又村の石高の推移もこれを証明している。丸滝村・角打村・横根村・中村大久保村・清子村・光子沢村 約2倍
八木沢村・帯金村・門野村・大城村 約3倍
大島村・和田村 4倍強
椿草里村・大垈村・相又村 8倍から11倍
波木井村・大野村・梅平村には変動がない。
塩沢、新宿、門内については、久遠寺領で身延山史に石高二八石八斗五升九合二勺と出ている。
相又村石高の推移と、反別は、次の通り。
慶長 九年(一六〇四) 一五石六斗九升 (跡部氏)
寛文十三年(一六七〇) 一六二石二斗六升一合(検地)
反別六四町一反二畝二一歩
文化十一年(一八一三) 一七三石三斗五升七合(国志)
天保十四年(一八四三) 一六二石二斗六升一合(年貢割付帳)
反別六四町一反二畝二七歩
嘉永二年(一八四八)一六二石二斗六升一合(年貢割付帳)
反別六四町一反二畝二七歩
文久三年(一八六三)一六二石二斗六升一合(年貢割付帳)
反別六四町一反二畝二七歩
明治三年(一八七〇)一六二石二斗六升一合(年貢割付帳)
相又地区の新田開発は、寛文検地以前に、一応完了していると考えられる。このような傾向は、相又地区だけでなく、町内すべての村々にあてはまると思われる。寛文十三年(一六七〇) 一六二石二斗六升一合(検地)
反別六四町一反二畝二一歩
文化十一年(一八一三) 一七三石三斗五升七合(国志)
天保十四年(一八四三) 一六二石二斗六升一合(年貢割付帳)
反別六四町一反二畝二七歩
嘉永二年(一八四八)一六二石二斗六升一合(年貢割付帳)
反別六四町一反二畝二七歩
文久三年(一八六三)一六二石二斗六升一合(年貢割付帳)
反別六四町一反二畝二七歩
明治三年(一八七〇)一六二石二斗六升一合(年貢割付帳)
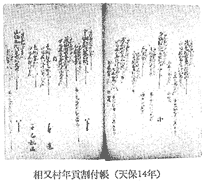 |
梅平村、波木井村、大野村は、慶長検地の石高と、甲斐国志記載の石高に変化がないのは、日蓮宗の本山に近く、鎌倉時代以後、身延山の繁栄の影響をうけて、古くから村落が発達し、慶長以前に新田開発が、完了しているものと推察される。
大野渠は延宝年間(1673)に開削されているが、慶長の古石高と、文化11年(1813)の石高が同じことは、大野渠開削完成の効用が、全然ないことになるが、他に通水路の跡を証する資料もない。ただ本遠寺々領名寄帳その他若干の古文書によれば、
以上開田の歴史を述べてきたが、本町の全貌を明確にすることは、できなかった。しかし、一応、その歴史的過程は、理解できると思う。
明治以後の開田については、土地改良事業のところで記することにする。

