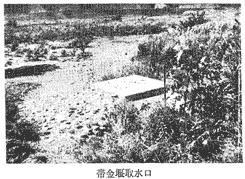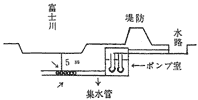三、用水路の開削とその年代
用水路の開削は、新田開発と表裏の関係で切り離すことができないものであり、初期の用水路が、開削された年代も、新田開発と同じ年代である事は論ずるに足らない問題である。勿論初期の用水路は、現代までに、相当改善改良されて、今日に至ったものと思う。
水路関係の古い記録は非常に少なく、わずか甲斐国志にその名を見るだけである。
甲斐国志記載の水路は次の通りである。
大野渠、村里部、山川部に記録されているが、開田のところで記したので省略する。
妙善堰 古蹟部にある。
略□荒墳三基一ハ五輪石塔ニテ、中村の妙善堰下ト云処ノ田中ニアリ云々
とあり、波木井上堰のことで、国志以前の開削であることはわかるが、年代は不明である。丸滝渠、富士ヨリ引ク」
角打渠、鍬柄沢、富士川ノ水ヲ引ク」
大島渠、富士川ノ水ヲ引ク」
以上3用水路が山川部に記録されており、計5水路が国志に記録されているものである。平堰、開削年代については勿論不明であるが、釜川戸の取水口の道上に水神の祠がある。石製で「文化九申年正月」(1812)の銘がある。はたして、水路完成記念のものであろうか。角打渠、鍬柄沢、富士川ノ水ヲ引ク」
大島渠、富士川ノ水ヲ引ク」
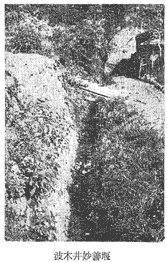 |
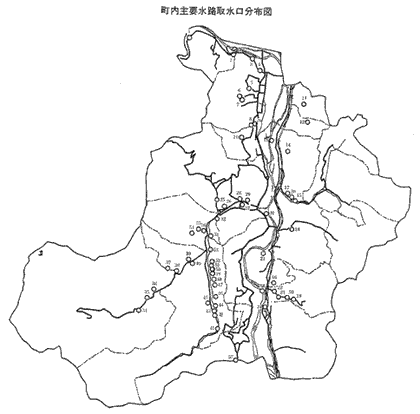 |
本町内の主な水路名を、地区別にあげると次の通りである。(県用水施設調査より)
用水路名一覧表(番号は取水口分布図に記入のもの)
|
番号
|
水路名
|
利用河川
|
経営組合等
|
番号
|
水路名
|
利用河川
|
経営組合等
|
|
1
|
小原島堰 | 早川 | 小原島水路 組合 |
31
|
柏坂水路 | 勝沢 | |
|
2
|
粟倉堰 | 早川 | 粟倉水利組 合 |
32
|
長割水路 | 波木井川 | 長割水路組 合 |
|
3
|
下山堰 | 軽金用水 より分水 |
下山土地改 良区 |
33
|
本田堰 | 波木井川 | 本田水利組 合 |
|
4
|
北沢第3水路 | 北沢 |
34
|
金山水路 | 大城川 | ||
|
5
|
北沢第4水路 | 大沢 |
35
|
馬込水路 | 大城川 | ||
|
6
|
不動沢上堰 | 不動沢 |
36
|
奥川湯平堰 | 奥川 | ||
|
7
|
不動沢下水路 | 不動沢 |
37
|
門野上堰 | 湯沢川 | ||
|
8
|
当子沢上水路 | 当子沢 |
38
|
門野下堰 | 湯沢川 | ||
|
9
|
当子沢下水路 | 当子沢 |
39
|
広河原水路 | 大城川 | ||
|
10
|
宮沢水路 | 宮沢 |
40
|
針山水路 | 大城川 | ||
|
11
|
宮之前水路 | 松葉沢 |
41
|
御内屋敷水路 | 相又川 | ||
|
12
|
中島水路 | 不動沢 |
42
|
火焚水路 | 相又川 | ||
|
13
|
帯金堰 | 富士川 | 帯金土地改 良区 |
43
|
清水中島水路 | 相又川 | |
|
14
|
入の沢水路 | 入の沢 |
44
|
五郎島水路 | 相又川 | ||
|
15
|
林の前水路 | 椿川 |
45
|
小沢水路 | 相又川 | ||
|
16
|
田之沢水路 | 田之沢 |
46
|
前田水路 | 相又川 | ||
|
17
|
山崎水路 | 椿川 |
47
|
井戸尻水路 | 相又川 | ||
|
18
|
桑柄沢水路 | 桑柄沢 |
48
|
祐下水路 | 相又川 | ||
|
19
|
水上水路 | 長戸川 |
49
|
平城東水路 | 相又川 | ||
|
20
|
榎島水路 | 椿川 |
50
|
峠沢水路 | 相又川 | ||
|
21
|
平堰 | 富士川 |
51
|
林先水路 | 相又川 | ||
|
22
|
渡々沢水路 | 渡々沢 |
52
|
正慶寺前水路 | 相又川 | ||
|
23
|
清水水路 | 長戸川 |
53
|
横尾裏水路 | 波木井川 | ||
|
24
|
中河原堰 | 富士川 | 中河原水利 組合 |
54
|
上小田水路 | 大倉沢 | |
|
25
|
橘水路 | 身延川 |
55
|
村添水路 | |||
|
26
|
亥の新田水路 | 波木井川 |
56
|
下小田水路 | |||
|
27
|
大野堰 | 波木井川 | 大野水利組 合 |
57
|
横根沢水路 | 南沢川 | |
|
28
|
波木井上堰 | 波木井川 |
58
|
清子堰 | 富士川 | ||
|
29
|
波木井下堰 | 波木井川 |
59
|
田沢水路 | 長戸川 | ||
|
30
|
勝沢水路 | 勝沢 |
|
四、土地改良事業
富士川河原の大規模な水田開発は、近年のものが多く、下山・大島・帯金地区は、昭和になってからの開田である。各地区の老人の話によると、昔は相当量の水田が富士川河原にあったが、明治以後の大水害によって大方流失してしまった。
近年、富士川河原の開墾の際、土地台帳を調べてみると、以前相当量の耕地があったことが判明したということである。
これらのことから考えてみると、富士川河原の開田は、新開田ではなくて一部復旧による再開田であるといえる。
近年の開田の主なものは次の通りである。
下山 早川表の新田 八町歩 昭和初年(一九二六)
大河内 大島新田 四町歩 昭和八(一九三三)十年(一九三五)
豊岡 大城川新田 六町歩 昭和八(一九三三)九年(一九三四)
身延 大野下河原新田 六町歩 昭和六年(一九三一)
身延 梅平亥の新田 三町五反歩 昭和十年(一九三五)
帯金 帯金地内新田 八町歩 昭和十八年(一九四三)
下山 川除下新田 八町歩 昭和三十二年
大河内 大島新田 四町歩 昭和八(一九三三)十年(一九三五)
豊岡 大城川新田 六町歩 昭和八(一九三三)九年(一九三四)
身延 大野下河原新田 六町歩 昭和六年(一九三一)
身延 梅平亥の新田 三町五反歩 昭和十年(一九三五)
帯金 帯金地内新田 八町歩 昭和十八年(一九四三)
下山 川除下新田 八町歩 昭和三十二年
(一)下山土地改良区
往古下山千軒と謳(うた)われ、下山の田圃で対岸八木沢村の人と話が交わされたと、古老より話し伝えられている。川除下開田面積は、100ヘクタール余あり、これの灌漑用水は、流路不定の早川より取り入れる外なく、年々農民の一大難事業であった。明治40年代、数回に亘る大洪水のため、田や宅地が流され、家と共に人が流されるという悲惨事があった。しかしこの水難にめげず、大正、昭和にかけて約60ヘクタール程の開田が進められた。しかし、灌漑用水の導入は相変らず年々苦難の連続であった。たまたま日本軽金属株式会社が早川の流水を利用して発電事業を計画したのに伴ない、早川の水利権は軽金に移り、軽金の責任において用水並びに飲雑用水を確保することが取りきめられた。以来日軽金の責任において用水の導入に努めて来たが、大雨の都度取入れ口が決壊し農民の不平不満の声が高く、その運営に苦しんでいた。戦後食糧が非常に貴重になり、郷土下山の農業100年の大計を推進するためには、開田事業と用水の円滑な確保が絶対必要であると確信を持った佐野為雄は、昭和28年7月下山水利組合を結成、組合長として率先水利の運営につとめ、さらには、昭和32年土地改良法に基づく下山土地改良組合を結成し、初代理事長となり、所信の実現に挺身した。(改良事業)
・開田事業 8ヘクタール 4号堤東
明治40年(1907)頃以来流失し、ぐみ、柳が生い茂る河原を、昭和23年頃、農林省に一括買い上げられたものを再び払い下げをうけ、ブルドーザー(下山地区の使用は初めて)による開田作業が進められた。
・事業資金 260万円 農林漁業資金を農林漁業金融公庫より借用する。
・組合員数 297名 役員理事長以下13名
昭和34年度、完成し、旧所有者の潜在所有権を認め、希望者にまず配分し、残余の田はその他の希望者に売り与えた。
・灌漑用水路工事
永年苦しんで来た取水方法を改良して、灌漑用水を円滑に充分みたすために、佐野為雄理事長は、日本軽金属の発電用水路・糠沢地沢から分水をうける以外にないと着想し、理事会にはかり、その決議により軽金と交渉し、総工費、1,500万円でその事業の完遂をはかった。
墜道工事は長さ650メートル、幅1メートル、高さ150メートルで事業は、昭和35年完工し、以来、必要にして充分な灌漑用水が確保され、山田をつくるより河原の田の方が耕作が容易であると喜ばれるようになった。全く今昔の感、無量のものがある。以来組合費として、100アール当り、700円を徴収し、返済金に充当すると共に、水路の小修理その他にあてて現在に至っている。
(歴代理事長)
初代 佐野為雄 昭和二二年二月就任
二代 古屋慶信 昭和三五年一二月就任
三代 網野正一 昭和四二年一〇月就任
四代 遠藤百治 昭和四三年一〇月就任
初代 佐野為雄 昭和二二年二月就任
二代 古屋慶信 昭和三五年一二月就任
三代 網野正一 昭和四二年一〇月就任
四代 遠藤百治 昭和四三年一〇月就任
(二)帯金土地改良区
(経過)昭和18年(1943)帯金地内上梵天、下梵天ならびに持木島一帯の荒地約8ヘクタール(私有地および河川敷)の開田について帯金区内の有志が協議した結果、帯金耕地整理組合を設立した。総会において伊藤喜則が組合長に選任され、就任するや県当局の助成を得て、国鉄よりブルドーザーを借りて開田工事を施行した。(当時ブルドーザーを持っている建設業者はないので国鉄より借りた)竣工後農地の配分をなし、区民はそれぞれ耕作に従事し、相当の収穫を得たのであるが、時あたかも太平洋戦争中のことで、食糧難の緩和にも大いに役立ったのである。
昭和34年8月、台風7号により帯金地内の堤防、県道、農地、農道は無残にも流失し、未曽有の大災害をこうむったのである。
一日も早くこれを復興するため、昭和34年10月区民総会を開催、帯金災害復興促進会を設立し、委員長伊藤喜則のほか17名の委員を選び、町や県への陳情などをくりかえし運動した結果、昭和36年には2番堤、3番堤および県道の復旧工事が完成、さらに災害農地も昭和35年5月総工費7,500万円をもって町営工事として着工、昭和36年5月に13ヘクタールの復旧工事が完成したのである。工事費の負担率は国庫補助90パーセント、町費5.5パーセント、地元負担金4.5パーセントであった。
昭和35年の台風災害により八幡神社西側地点以北の田用水路流失のため、工事費予算700万円余りで町営事業として直径1メートルのヒューム管を上流に向かって約500メートル埋設した。
このように大災害から立ち直って農地および水路の完成を見たのであるが、農地の配分は簡単に行なわれなかったので、稲の苗は県事務所よりあっせんを受け、区民の共同耕作により1.2ヘクタールの植付けを36年7月に行ない10月に区民の共同作業により収穫した。
昭和37年1月、災害復興促進会において配分問題をはじめ河川敷払下げ、登記、受益者負担、水路改良工事等について協議した結果、帯金土地改良区を設立することに決定したのである。2月、認可申請書を提出、7月知事の認可を得た。
理事長には、伊藤喜則が選ばれ、理事16名、監事2名がそれぞれ選任された。
土地改良区設立以後の事業としては農地の配分、地元負担金の返済、取水施設および用水路の改良が主なるものであり、いずれも大きな困難があったが、理事長以下役員の指導力と、組合員の協力により着々と解決し順調なあゆみを続けている。
先ず土地の配分は37年1月より5月まで数十回の委員会を開いて協議し、6月には一応終了して田植えができるところまでこぎつけたのである。
また富士川に埋設した前記の取水管はその後も毎年増水の度に破損、流失をくりかえし取水不可能となったので、止むを得ずブルドーザーで河原を掘り割って取水したが多額の経費を要し、一反歩当り3,500円以上の負担を余儀なくされ、大きい悩みのたねとなった。そこで昭和41年の大災害を機として町は復旧改良工事として後述のような近代的工法による取水施設を行なったのである。
この結果、取水についてはどんな災害にも被害をこうむる心配はなくなり、田用水の経費は以前の5分の1の800円内外に軽減されたのである。
さらに用水路についても43年に八幡神社より南へ約500メートルをコンクリート水路に改良する工事に着手、県および町の補助を得て年次的に実施している。
これらの工事により帯金の田用水の揚水施設および水路は全く面目を一新して恒久的近代的なものに生まれかわり、住民多年のなやみはほぼ解消されたのである。
34年災害の復旧工事地元負担金は農林漁業金庫より326万円を借入れ、毎年組合員より賦課金を徴収し返済にあてている。
(現況と役員)
組合員数 一〇六名
事業内容 借入金の返済事務・組合費の徴収・賦課金(四段階に区分)の徴収・水田水路の管理
役員 理事長 伊藤喜則 理事十六名・監事二名
総会 年一回開催
役員会 年三回以上開催
事業内容 借入金の返済事務・組合費の徴収・賦課金(四段階に区分)の徴収・水田水路の管理
役員 理事長 伊藤喜則 理事十六名・監事二名
総会 年一回開催
役員会 年三回以上開催
五、用水路の現状と近代化
本町内の用水路は、大小300近くあるといわれているが、いずれも昔からの古い取水法と、石垣積みの水路が多く、台風時の出水による大きな被害を受けやすい。近年は、災害復旧によって改良整備され、取水口水路も近代化されつつあるが、しかし、この水路は今もなお幾多の問題をかかえている。
出水時の土砂の流入、水路の欠壊、取水口の流失と埋没等、年何回となく用水組合員の補修整備が行なわれ、その負担は実に大きい。このため組合員各戸には、義務人足制が課せられ、また年間を通して用水費が徴収されている。
下山・和田・大島では、軽金属発電所が早川富士川の水を発電用水として使用したため、水位の低下をきたし、従来の田用水としての取水口では取水不可能となり、その補償として、発電用水から給水を受けており、多少その労役負担は軽減している。
帯金堰は、富士川の増水時必ずといってよいほど大被害を受けていたが、昭和40年の台風災害の結果、改良復旧がなされ、昭和43年3月、有孔管理設という新しい工法により近代的取水施設が完備し、面目を一新した。
このことは、本町の今後の用水路に、一大変革をもたらすものである。
各地区で、帯金式取水法が整備されたら、用水利用者の負担は、軽減されて、農業の近代化に、大きな役割りをはたすであろう。
帯金取水口の概略
取水の方法を略図でしめすと次の通りである。
富士川の伏流水を、集水管でポンプ室に導入する。ポンプ・水中斜流ポンプ2台、10HP、揚水管径150MM・15HP、揚水管径200MM・集水管径800MM・長さ162メートル・集水管の深さ、伏流水中5メートル、総工費7,056,000円
灌水可能水田面積、約13ヘクタール
完工 昭和43年3月
清子取水口
昭和44年3月清子開田組合の富士川取水口も、帯金用水路と同じ工法で災害復旧工事として改良復旧された。
(工費5,699,000円)