第三節 農業災害
一、概説
農業災害には、病虫害・干害・冷害・台風や集中豪雨による風水害があげられる。これらの災害は、単発的におこりながらも、台風などの広範囲な災害と重複することが多く、毎年の災害を種類別にまた数量的に収集することは、不可能であった。以上のような阻害条件のために、農業災害の全貌を記することはできないが、一部集録した資料から考察するに、なんといっても台風災害が、農業災害の王座をしめるものであることは、一目瞭然の事である。
二、台風災害
身延町は、富士川の形成する河岸段丘と、河川敷を開田した耕地を主体とし、そのほかに大小の支流がつくる谷間に農地が散在している。このような地形上、田用水などもこれらの河川から取り入れている関係上、一旦台風や集中豪雨があると、水田水路ともに、大きな災害をうけやすい基礎的諸条件をもっている。
(一)水稲被害
過去11年間の台風のもたらした稲作の被害面積と、関連する台風を、表1表2によって、考察する。この表の資料は、農業共済組合の農災保険金の支払いの対象になったもので、被害の割合は30パーセント以上のものである。これ以下は資料の中に含まれていない。
したがって、実際の被害は非常に大きいものではあるが、数量的に把握することができない。
また農家が、災害時に過大な災害評価をして申告することもあり得るが、一応これにかわるべき資料もないのでこれを活用することにする。
次の表1は各年の水稲の作付面積と、被害面積である。
表1 水稲の作付面積と被害面積
| 年 |
作付面積
|
被害面積
|
|
31
|
214.31
|
14.59
|
|
32
|
214.25
|
27.40
|
|
33
|
221.45
|
39.06
|
|
34
|
221.65
|
99.69
|
|
35
|
217.66
|
12.52
|
|
36
|
219.85
|
62.43
|
|
37
|
219.04
|
15.51
|
|
38
|
219.26
|
23.95
|
|
39
|
220.88
|
24.65
|
|
40
|
219.15
|
93.48
|
|
41
|
217.95
|
130.02
|
表1でわかることは、昭和34年と、昭和41年の被害面積が、特に大きいことである。
次に台風と各年の作付面積と被害面積との関連を表2で、考察する。
表2のグラフがしめすように、
昭和34年の7号・15号台風のもたらした被害は、本町の水田作付面積の45パーセントに当る面積が、冠水・埋没・流失などの被害を受けている。
また昭和41年の26号台風は、34年度の被害を上まわって、実にその被害面積は、作付面積の60パーセント以上が集計されている。
一方、直接の影響がなかった昭和31年度・35年度をみると、被害は面積の6〜7パーセントであることから台風のもたらす被害が、いかに大きいかがわかる。
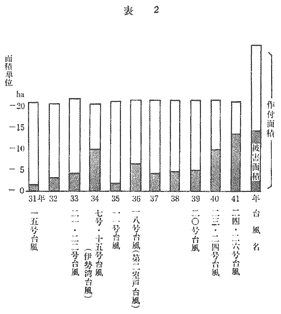 |
(二)農地、水路の被害規模
昭和34年以降の農地、水路の被害を、その復旧に要した工事件数と、総工費からその規模を比較する。表3は工事件数を、農地・水路に分けその復旧工事費を表にしたものである。
表3 年度別被害規模
| 年 |
復旧総工事費
|
農地
|
水路
|
|
34
|
181,372,957円
|
37件
|
183件
|
|
35
|
6,672,246円
|
0
|
1
|
|
36
|
1,851,813円
|
5
|
30
|
|
37
|
240,300円
|
0
|
4
|
|
38
|
1,417,000円
|
0
|
3
|
|
39
|
5,856,000円
|
0
|
5
|
|
40
|
37,118,000円
|
5
|
25
|
|
41
|
234,119,000円
|
72
|
241
|
41年度の工費は査定金額
過去10年本町に大被害をもたらした台風のうち、昭和41年26号台風(9月25日)の災害は、現に復旧工事中であり、まだ工事費も査定額であり確実ではないが、昭和34年の7号台風(8月14日)、また15号台風(9月26日)は私達の記憶にまだ新しく、その恐怖をなまなましく思いおこさせるが、今はもう復旧工事も完成しているので、その災害分布図を別紙でしめすことにする。
この8年間、台風によって受けた町の農業災害は、農地119件、水路492件、復旧総工費518,647,316円にのぼり、町単独では、もとより不可能な大工事であった。
しかし、災害救助法等の適用をうけて、総工費のうち90パーセント程度は、国の補助金で賄われている現状であるが、一日も早く全額保障されるべきである。
三、台風以外の災害
昭和31年以降、陸稲・麦の被害面積と養蚕の被害卵量を数量的にあげ、台風以外の災害推察の一資料としてみたい。(被害30パーセント以上を掲げる)
陸稲は水稲と同じ年に被害がでているが、年によっては、全作付面積に被害がでる傾向がみられるのは、陸稲特有の性質であろうか。
表5は麦作である。
麦作は台風被害には季節的に関係がない作物であるが、被害の原因は病害虫が主となっている。
麦作は、作付面積年々減少し、被害もそれと共に少なくなっている。
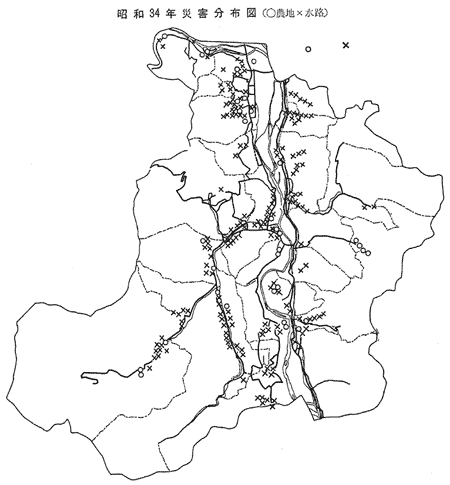 |
表4 陸稲 (単位ha)
|
表5 麦 (単位ha)
|
四、養蚕の被害
養蚕は、春蚕、夏秋蚕、晩秋蚕の3回飼育されており、そのうち春蚕が最も大規模である。それだけに、春蚕の掃立量も多くまた被害量も大きい。表6は春蚕についての表である。
表6 春蚕 単位 箱
|
表7 夏秋蚕 単位 箱
|
掃立量の変動が年々大きいのは絹糸市場の動きによるものであろうか。被害の原因は病害が主なものである。
被害量も掃立量から算出しなければならないが、春夏秋の3回飼育のうち、最も被害の割合の大きいのは、晩秋蚕である。
被害の大小が季節により、年によって変動が大きく、その特徴をつかむことがむずかしい。
表9は農業共済保険金、各年支払金の総額である。
|
表8 晩秋蚕 単位 箱
|
表9 年保険金支払総額
|
この表からもわかるように、台風災害年(昭和34年、および昭和41年)の支払額はすこぶる多く、農地・水路また農作物の被害は、台風災害によるものが最も顕著であることを物語っているといえる。
以上概略を述べてこの項を終わる。
 |
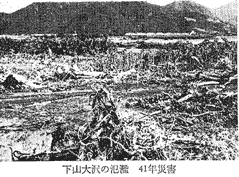 |
 |
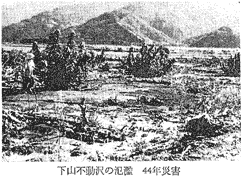 |
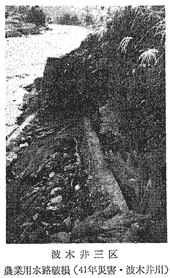 |

