第五節 果樹栽培
一、概況
果樹は相当古くから多種類あったが、本格的な栽培の歴史は浅く、主として戦後に発達したものが多い。本町において栽培されている果樹についておもなものを挙げてみよう。
(一)ぶどう
戦前の昭和初期に、身延地区の波木井で、藤田岡波がわずかにぶどう園として、造成したことはあるが、主として栽培されるようになったのは、戦後の昭和22年頃からである。当時、下山、身延地区の波木井、豊岡地区の清子・相又、大河内地区の塩之沢・和田・帯金・角打等で相次いで、ぶどう園が造成された。その後町においても、果樹としての重要性を認め、奨励もかねて昭和38年から、5ヘクタールにつき、120万円の補助金を出して各地区に奨励してきている。昭和38年以降における本町のぶどう園造成は、表1のとおりである。表1 果樹園(ぶどう)栽培状況と38年以降の補助面積(単位 a)
| 年度 地区 |
37年
以前 |
38年
|
39年
|
40年
|
41年
|
42年
|
合計
|
|
下山
|
76.0
|
83.0
|
54.5
|
20.0
|
6.0
|
—
|
239.5
(163.5) |
|
身延
|
67.0
|
65.0
|
44.0
|
12.0
|
—
|
35.0
|
223.0
(156.0) |
|
豊岡
|
80.0
|
—
|
85.5
|
—
|
12
|
—
|
177.5
(97.5) |
|
大河内
|
25.0
|
43.0
|
30.0
|
—
|
—
|
—
|
95.0
(73.0) |
|
身延町
|
248.0
|
191.0
|
214.0
|
32.0
|
18.0
|
35.0
|
738.0
(490.0) |
(二)もも
缶桃は、昭和30年農林省の推薦によって、本町へ1ヘクタールの割当で、豊岡地区の相又、大久保、横根、清子、身延地区の塩沢、梅平、大河内地区の角打、和田等の畑に奨励されて作られてきたが、結果的には雨量が多く、品質が劣り、罐桃栽培には不適地とされ、昭和37年で終止符をうった。現在栽培されているすももは、下山地区に多く、約1ヘクタールの桃畑から、1万キログラムの収穫をあげ、静岡市の市場に出荷されているが、今後の開拓が期待されている。
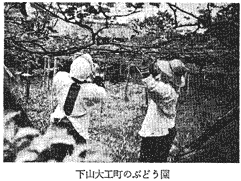 |
(三)かき
昭和27年から、畑地等に植えつけ、栽培されるようになってきているが、現在町全体として、柿の成園は、137アールで、ごく少ない。今後、出荷面での強力な指導が必要である。(四)うめ
果樹として栽培されるようになってから、各地区で盛んに植えられてきた。昭和40年に、町では20ヘクタールにつき80万円(10アール4千円)の補助金を出して、栽培の奨励を行なってきた。価格の不安定な面が多いので、現在栽培している農家への出荷面での指導が急務である。本町で現在栽培されている梅の造園と補助の内訳は、表2の通りである。表2 果樹園(うめ)栽培状況と39年以降の補助面積(単位 a)
| 年度 地区 |
38年
以前 |
39年
|
40年
|
41年
|
42年
|
合計
|
|
下山
|
40.0
|
508.5
|
287.5
|
28.0
|
—
|
864.0
(490.0) |
|
身延
|
60.0
|
83.5
|
164.5
|
19.0
|
35.0
|
362.0
(302.0) |
|
豊岡
|
5.0
|
101.5
|
236.5
|
28.0
|
31.0
|
402.0
(397.0) |
|
大河内
|
15.0
|
214.0
|
263.0
|
58.0
|
5.0
|
555.0
(540.4)
|
|
身延町
|
120.0
|
907.5
|
951.5
|
133.0
|
71.0
|
2,183.0
(2,063.0)
|
二、現況
本町に現在栽培されている果樹は、主としてぶどう、梅、桃、柿等であるが、そのほかまだ数は少ないが、桜桃、りんご、みかん等も作られている地区もある。町の果樹振興五ヵ年計画も、昭和38年度から進められ、果植栽培に対する町の意欲的な取り組みが今後に期待される。本町における果樹栽培の現況と実態を、規模別に昭和35年と比較して、調べたのが表3である。表3の昭和40年以後における果樹の現況は、更に進展している。現在の本町における果樹栽培の実体と、昭和43年農業基本調査の結果を表4に示す。
表3 本町における果樹栽培の実態
|
果樹
|
地 区
|
1960年(35)
|
1965年(昭40)
|
||||||
|
栽培
戸数 |
10a
未満 |
10a〜 30a |
40a〜 1ha |
栽培
戸数 |
(内) 成園戸数 |
未成園 戸 数 |
|||
|
ぶ
ど う |
身延町 |
40
|
18
|
22
|
|
68
|
30
|
38
|
|
| 下山 |
13
|
8
|
5
|
|
25
|
14
|
11
|
||
| 身延 |
8
|
3
|
5
|
|
16
|
5
|
11
|
||
| 豊岡 |
12
|
2
|
10
|
|
14
|
6
|
8
|
||
| 大河内 |
7
|
5
|
2
|
|
11
|
5
|
6
|
||
|
も
も |
身延町 |
47
|
21
|
25
|
1
|
25
|
10
|
15
|
未成園の面積不明 |
| 下山 |
5
|
3
|
2
|
|
|
1
|
|
||
| 身延 |
7
|
4
|
3
|
|
|
0
|
|
||
| 豊岡 |
25
|
7
|
18
|
|
|
4
|
|
||
| 大河内 |
10
|
7
|
2
|
1
|
|
5
|
|
||
|
う
め |
身延町 |
19
|
18
|
1
|
|
|
|
|
記録なし(40) |
| 下山 |
2
|
2
|
|
|
|
|
|
||
| 身延 |
8
|
7
|
1
|
|
|
|
|
||
| 豊岡 |
1
|
1
|
|
|
|
|
|
||
| 大河内 |
8
|
8
|
|
|
|
|
|
||
|
柿
|
身延町 |
36
|
33
|
3
|
|
51
|
13
|
38
|
|
| 下山 |
5
|
5
|
|
|
14
|
6
|
8
|
||
| 身延 |
7
|
7
|
|
|
3
|
1
|
2
|
||
| 豊岡 |
2
|
1
|
1
|
|
8
|
0
|
8
|
||
| 大河内 |
22
|
20
|
2
|
|
26
|
6
|
20
|
||
|
栗
|
身延町 |
3
|
|
3
|
|
|
|
|
記録なし(40) |
| 下山 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 身延 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 豊岡 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 大河内 |
3
|
|
3
|
|
|
|
|
||
表4 本町における果樹園の実態 (単位 戸、アール)
|
地 区
|
下 山
|
身 延
|
豊 岡
|
大河内
|
身延町(全町)
|
|||||||||||||||
|
園 別
|
成園
|
未成園
|
成園
|
未成園
|
成園
|
未成園
|
成園
|
未成園
|
成園
|
未成園
|
||||||||||
|
戸数面積
果 樹 |
栽
培 戸 数 |
面 積 |
栽
培 戸 数 |
面 積 |
栽
培 戸 数 |
面 積 |
栽
培 戸 数 |
面 積 |
栽
培 戸 数 |
面 積 |
栽 |
面 積 |
栽
培 戸 数 |
面 積 |
栽
培 戸 数 |
面 積 |
栽
培 戸 数 |
面 積 |
栽
培 戸 数 |
面 積 |
|
りんご
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
|
1
|
5
|
|
|
|
ぶどう
|
7
|
99
|
68
|
743
|
7
|
95
|
8
|
101
|
17
|
208
|
5
|
47
|
8
|
77
|
9
|
66
|
39
|
429
|
90
|
908
|
|
な し
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
も も
|
5
|
60
|
10
|
40
|
1
|
2
|
2
|
10
|
6
|
27
|
1
|
10
|
7
|
106
|
9
|
122
|
19
|
195
|
22
|
182
|
|
おうとう
|
5
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
60
|
|
|
|
か き
|
6
|
12
|
8
|
50
|
6
|
17
|
6
|
107
|
6
|
21
|
4
|
16
|
18
|
87
|
8
|
45
|
36
|
137
|
26
|
213
|
|
う め
|
15
|
135
|
43
|
395
|
12
|
72
|
27
|
185
|
13
|
88
|
28
|
176
|
16
|
56
|
41
|
241
|
56
|
351
|
139
|
997
|
|
すもも
|
4
|
15
|
2
|
18
|
1
|
2
|
|
|
1
|
30
|
|
|
2
|
13
|
|
|
8
|
60
|
2
|
18
|
|
その他
|
|
|
7
|
15
|
|
|
1
|
2
|
|
|
18
|
85
|
2
|
7
|
3
|
10
|
2
|
7
|
29
|
112
|
|
合計
|
26
|
381
|
72
|
1,252
|
26
|
188
|
30
|
400
|
45
|
374
|
46
|
334
|
43
|
351
|
50
|
484
|
140
|
1,244
|
198
|
2,430
|
(一)出荷組織
どの果樹も、系統的、組織的な出荷態勢は、まだ軌道にのっていないが、一部の果樹は、農協組織を通じて市場に出されている。(二)果樹栽培の将来
本町の果樹栽培の歴史はごく浅く、現況のところで述べてあるように、栽培品種は割合多いが、栽培面積がせまく、収穫量もきわめてわずかである。しかし、本町は県の南部にあって、気候も割合温暖であるから、早生果実地としての好条件も多いので、早生果実栽培を振興して、町民の所得をふやす施策が望まれる。農業経営が近代化されても、農業一本だけで生活がまかなえない本町の実状としては、生産物の販路、資金、補償面、技術面など相当の隘路があるので、強力な行政指導により開拓すべき面が多い。また、この果樹栽培の振興によって、やがて、本町が早生果実地帯として誕生するなら、本町内の需要を満たし、さらに移出も活発になって、本町の産業経済に与える影響は、すこぶる大きいものがあろう。

