第六節 農業生産の概況
一、江戸時代の本町の農業
第一章で述べたように、本町は、東西両河内領に属していて、山岳が多く平地がすくなく、かつては日本三大急流の一つと呼ばれた富士川およびその支流の流域にあるため、毎年大小の洪水によって、すくない田畑を押し流されるという悪条件にあったため、検地によっても明らかであるように、石高もきわめてすくない。米麦など五穀やそれ以外の農作物の収穫高もおのずから少なく、したがって、特筆するような産物もなく、農民の食生活はきわめて粗食で、麦・粟・稗なども相当食べていたようである。二、明治以後の本町の農業
(一)人口政策と本町の農業
日清日露両戦役の連勝と、さらにまた、日韓併合で、領土を約二倍に拡大した日本は、着々世界的強国としての地位を確保しはじめたが、さらに、世界の国家群の中で優位の地位を獲得するためには、一層富国強兵の実をあげねばならなかった。この国策実現のために、政府は軍事力と産業の振興をおしすすめるとともに、人的資源としての人口の増加をはかり、その結果は必然的に大陸への進出となってあらわれた。民族の発展というこの国策は「生めよふやせよ」の合言葉となるまで国民の間に徹底された。したがって、本町においても必然的に人口は増加した。また、時代の進展によって、食生活の改善が生活水準の向上と相まって行なわれ、雑穀食の多かった時代から、米食主食の時代へと移行してきたので、従前から食糧の自給ができない本町では、いよいよ食糧の移入を仰がなければならない状態に追いこまれた。特に旧身延町は、身延山参詣客の食糧消費とあわせて、主食不足のきびしい状態を余儀なくされた。資料がすくなく断定はできないが、大正元年(1912)から3年までの主食の生産及び移入について、旧豊岡村の資料(表1)によれば、米で約30パーセント、麦で約16パーセント移入されていることがわかる。このような状況の本町では農業技術の導入、土質の改良、肥料の科学的利用、農機具の近代化によって、増産増収を求めたが、依然として食糧の自給自足はできなかった。
表1 豊岡村米産額及移入状況(郷土教育資料・豊岡小学校蔵)
|
大 正
元 年 |
大 正
2 年 |
大 正
3 年 |
|||
|
米
の 産 額 移 入 額 |
産 額 |
石 数
金 額 |
1,219
18,286 |
1,280
17,395 |
不 明
不 明 |
|
移
入 額 |
石 数
金 額 |
340
4,760 |
343
4,800 |
443
5,200 |
|
|
麦 |
産 額 |
石 数
金 額 |
1,041
12,505 |
1,043
12,500 |
不 明
不 明 |
|
移
入 額 |
石 数
金 額 |
170
1,400 |
180
1,260 |
280
2,520 |
|
(二)第二次世界大戦と農業
戦争遂行のための軍需工場が増大するにしたがって、平和産業は衰退の一途をたどりはじめ、前に述べたように、農家の主要労力であり管理の責任者たちは、農家から姿を消し、戦争の激化にともなって外国貿易も制限され、さらに、経済封鎖までされるようになった。そのうえ、本町へも東京方面からの学童や一般の疎開者で、出征動員徴用により減った人口も急に増加してきた。そのうえ全国的に食糧不足にあえいでいたので、米麦の移入も困難になってきた。それにもかかわらず本町農家へも米麦の供出が容赦なく強いられてきたから、町の食糧事情は最悪の状態に追いこまれた。老婦女子や、子どもの手によって、山野の開墾が行なわれ、陸稲、さつまいもなどがつくられ、ついに町内小学校の校庭まで耕されるようになって食糧の確保に苦しんだ。しかし敗戦直前には、農家の米麦は、種子を除いてほとんど供出させられる状況にあったから、食糧の欠乏はまったくひどく、更に外地からの引揚者、帰還軍人によって人口が増加したので、町民は配給の果物のカンヅメや僅かの米麦の配給で飢えをしのぎ、コヌカやフスマ、野生の植物なども食糧にし、イタドリの葉を刻んで煙草の代りにすったものである。このような姿は、全国的なものであったが、前に記したような条件下の本町においてはとくにひどかったと思われる。しかし町民はよく困苦欠乏にたえ、新しい国づくり、町づくりに邁進し、社会状勢の落ちつくに従って、独立国家建設への歩みをつづけたのである。三、近代工業の発達と農業
(一)近代工業と農業経営
敗戦、そして世情混乱時代を克服して、日本は、国力を充実させ、ついに昭和26年独立国家となり社会状勢を正常化させ、諸産業は急激に発展し、近代工業化への道を、ひたすらに走りつづけた。そしてついに世界屈指の近代工業国として成長した。しかし、このような全国的な動きの中で、零細農家、兼業農家の多い本町では、諸物価の上昇や人件費の高騰で、米作以外の農作物栽培は、採算がとれない状況となって、農業経営は日にまし苦しくなってきた。昭和35年以降国の高度成長政策は、日本の工業立国政策にいっそう拍車をかけた。その政策遂行のため、また、日本の農家の合理的経営をすすめるために、農家戸数を減らして、離農家の耕地を吸収させ、一戸当りの耕地面積の増大をはかったのである。しかし、本町においては兼業農家が多く、離農者の耕地を吸収しても、専業農家となるだけの耕地の増加は難かしく、また、吸収した農地に要するだけの耕作労力を、他産業にまたは日雇労働にまわして現金収入を得る方が、採算がとれるという現状で農家の合理的経営は行きなやんでいる。さらに、日本の近代工業は、都市の工業地帯や、その周辺に集中されたので、人口の都市や、工場地帯への集中化としてあらわれた。このような現象は、本町へも波及してきた。町内には工場も少なく、さりとて、農家の過半数は、農業収入で生活を支えられない現状であるので若い人々は、続々県外へ就職している。また農業経営の中で、専業化できない農家は、農機具の導入などによって人力による農業労力を最小限にして、余剰労力の活用に、懸命の努力をしている。このような状況の中で昭和41年大河内・下山・豊岡・大島・身延の五農業協同組合の合併によって、身延町農業協同組合が誕生し、金融も円滑になり、種苗・肥料・農機具の購入・農林産物の出荷の取扱いも、しだいにできるようになったので、本町の農業経営も逐次明るみへと移行しつつある。
(二)肥料の変遷
産業革命によって急速に発展した日本の工業の中で割合に発達がおくれたのが化学肥料(金肥)である。本町では、大正5年(1916)頃僅かに金肥が使用された。(旧下山村の部)日本の農家では、昔から人糞・尿・堆肥・刈敷・厩肥・灰などを、使用していたのであるが、逐次満州から輸入された大豆粕や、富士川舟運によって、静岡方面から移入された魚肥を使用するようになり、前述のように化学肥料が使用され、昭和の初期にかけて、多く使用されるようになった。本町においては、化学肥料を取扱う店はごく僅かであったが、各地区に農業会が設立され、肥料を取扱うようになったので、一般肥料取扱店、農業会を通じて、肥料の入手が容易になったことと、時代の進歩にしたがって、農家においては、金肥の使用が激増し、第二次世界大戦を境にして、金肥黄金時代となった。
身延町内農家の化学肥料需要量を、身延町農業協同組合取扱い分だけ表にして掲げる。
なお、一般肥料取扱店の化学肥料と金額は僅かであるのでこれに加えた。
表2 身延町内化学肥料需要量及金額 (身延農業協同組合支所別)
| 年度 |
塩化加里
|
化 成
|
配 合
|
苦土石炭
|
尿 素
|
過燐酸石灰
|
硫 安
|
石灰窒素
|
熔燐
|
日の本化成
|
圭 酸
カルシウム |
合計金額
|
|
|
昭 和 41 年 |
豊 岡 |
45
|
1,205
|
347
|
210
|
65
|
150
|
564
|
266
|
2
|
326
|
|
|
|
31,850
|
1,049,800
|
282,690
|
25,700
|
53,950
|
91,600
|
391,500
|
180,650
|
2,650
|
342,350
|
|
2,245,740
|
||
| 大河内 |
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
—
|
—
|
—
|
— |
— |
— |
— |
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||
| 大 島 |
80
|
642
|
240
|
190
|
50
|
168
|
394
|
160
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
56,800
|
534,700
|
220,000
|
16,800
|
41,500
|
104,780
|
334,900
|
109,500
|
0
|
0
|
0
|
1,418,980
|
||
| 身 延 |
90
|
1,130
|
0
|
328
|
150
|
114
|
180
|
155
|
0
|
0
|
223
|
|
|
|
65,700
|
960,500
|
0
|
49,200
|
126,000
|
70,680
|
153,000
|
102,000
|
0
|
0
|
51,290
|
1,584,870
|
||
| 下 山 |
80
|
1,325
|
0
|
128
|
170
|
160
|
268
|
190
|
0
|
50
|
160
|
|
|
|
58,400
|
1,126,250
|
0
|
19,200
|
142,800
|
99,200
|
227,800
|
113,000
|
0
|
46,500
|
36,800
|
1,889,950
|
||
|
計
|
295
|
4,302
|
587
|
856
|
435
|
592
|
1,406
|
771
|
2
|
376
|
383
|
|
|
|
212,750
|
3,671,250
|
502,690
|
110,900
|
364,250
|
366,260
|
1,107,200
|
525,150
|
2,650
|
388,850
|
88,090
|
7,340,040
|
||
|
昭 和 42 年 |
豊 岡 |
75
|
948
|
635
|
275
|
40
|
140
|
716
|
242
|
0
|
459
|
0
|
|
|
54,357
|
796,825
|
589,500
|
47,400
|
33,300
|
87,000
|
520,250
|
169,900
|
0
|
457,870
|
0
|
2,756,402
|
||
| 大河内 |
45
|
496
|
0
|
0
|
35
|
0
|
100
|
145
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
47,450
|
421,600
|
0
|
0
|
29,400
|
0
|
25,000
|
101,500
|
0
|
0
|
0
|
624,950
|
||
| 大 島 |
79
|
886
|
279
|
115
|
63
|
185
|
443
|
210
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
59,175
|
743,100
|
240,860
|
17,200
|
52,990
|
115,200
|
372,050
|
147,600
|
0
|
0
|
0
|
1,748,175
|
||
| 身 延 |
65
|
854
|
10
|
130
|
25
|
40
|
130
|
70
|
0
|
10
|
40
|
|
|
|
47,450
|
725,900
|
8,500
|
12,500
|
37,900
|
24,800
|
110,500
|
49,000
|
0
|
9,600
|
9,200
|
1,042,250
|
||
| 下 山 |
75
|
1,438
|
0
|
150
|
205
|
196
|
268
|
250
|
0
|
30
|
150
|
|
|
|
53,290
|
1,22,300
|
0
|
22,500
|
172,200
|
121,520
|
227,800
|
175,000
|
0
|
28,800
|
34,500
|
2,057,910
|
||
|
計
|
339
|
4,622
|
924
|
670
|
368
|
561
|
1,649
|
917
|
0
|
499
|
190
|
|
|
|
261,722
|
3,909,725
|
838,860
|
106,600
|
325,690
|
348,520
|
1,255,600
|
643,000
|
0
|
373,150
|
43,700
|
8,229,687
|
||
|
昭 和 43 年 |
豊 岡 |
69
|
785
|
863
|
365
|
65
|
120
|
625
|
220
|
0
|
290
|
0
|
|
|
50,370
|
667,250
|
797,500
|
81,250
|
54,450
|
69,600
|
321,250
|
154,000
|
0
|
353,950
|
0
|
2,549,620
|
||
| 大河内 |
55
|
30
|
67
|
140
|
35
|
36
|
119
|
150
|
0
|
0
|
10
|
|
|
|
40,150
|
25,500
|
56,950
|
22,500
|
29,400
|
22,320
|
101,150
|
73,500
|
0
|
0
|
2,300
|
737,700
|
||
| 大 島 |
85
|
927
|
261
|
80
|
80
|
175
|
390
|
98
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
62,025
|
734,000
|
224,000
|
12,000
|
67,150
|
91,350
|
338,250
|
68,600
|
0
|
0
|
0
|
1,597,375
|
||
| 身 延 |
60
|
870
|
15
|
150
|
50
|
37
|
135
|
67
|
0
|
20
|
80
|
|
|
|
43,800
|
739,500
|
12,750
|
22,500
|
42,000
|
22,940
|
114,750
|
46,900
|
0
|
19,200
|
18,400
|
1,082,740
|
||
| 下 山 |
80
|
1,470
|
0
|
230
|
0
|
210
|
270
|
274
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
58,400
|
1,249,500
|
0
|
34,500
|
0
|
130,200
|
173,500
|
191,800
|
0
|
0
|
0
|
1,837,900
|
||
|
計
|
349
|
4,082
|
1,206
|
1,005
|
230
|
578
|
1,539
|
809
|
0
|
310
|
90
|
|
|
|
254,745
|
3,415,750
|
1,091,200
|
172,750
|
193,000
|
336,410
|
1,048,900
|
534,800
|
0
|
373,150
|
20,700
|
7,441,405
|
(三)農機具の変遷
わが国の農業は、水田を中心とした集約農業であったので、使用農機具は、人力農具が主体で、畜力農具は、犂(すき)、馬鍬(まんぐわ)などが主であった。古くから、本町内で使われていたと思われるものを用途別にあげてみる。
整地用具 鋤、馬鍬、鍬、三本歯、とうぐわ
育成管理用具 筋弓、肥桶、肥柄杓
収穫用具 鎌(草刈鎌、稲刈鎌)
穀物調整用具 千歯、篩(ふるい)、箕、連架、唐箕(み)、筵、鬼歯
園芸用具 摘果鋏、掘とり鍬、剪定鋏
養蚕用具 毛すき、桑切包丁、まぶし、蚕架、蚕網、こも
給飼用具 包丁、押切
その他 斧、つるはし、もっこ、籠、背負子、大八車、熊手
精米精粉用具 籾摺機、木臼、石臼、杵、ひき臼
なお本町では、稲作の肥料に刈敷を多く使ったのと、田圃が河岸段丘上にあるので、土壌が浅いため、刈敷がおちつかない(土になじまない)のでこれをおさえて、田植を便利にするため「大足」という特異なものを用いた。
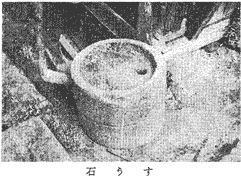 |
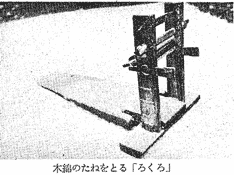 |
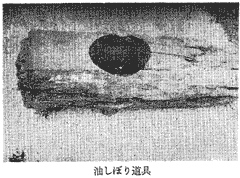 |
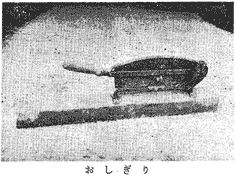 |
 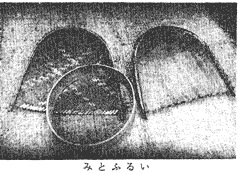 |
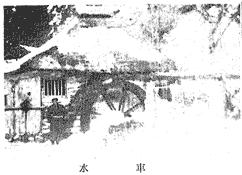 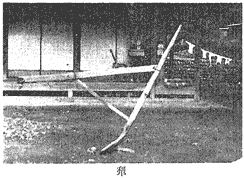 |
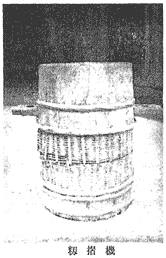 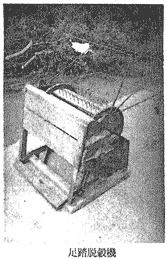 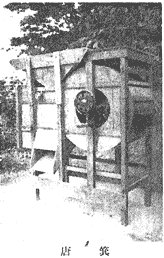 |
表3 農業用機械所有状況 (山梨県農業基本調者)
| 種類 年度 |
耕うん機
|
動力墳霧機
|
動力撤粉機
|
農用トラック
(三輪を含む) |
|
39
|
台
202 |
台
3 |
台
1 |
台
2 |
|
40
|
202
|
3
|
1
|
2
|
|
43
|
254
|
13
|
3
|
7
|
このような原始的な農具を使っていたので、労力の過重は農民を苦しめていたが、大正末期に、農業用扇風機と、運搬用リヤカーが、本町にも登場し、つづいて足踏による脱穀機が導入され、さらに、動力による精米機、籾糶機、製粉機が導入されてきた。しかし、これらは当時高価であったから、一般農家では、購入できなかったので、水車を利用していた精米業者が、機械を購入して定置し営業を開始した。
その後農家の人々が共同してこれらの機械を購入したところもあった。このように、人力、畜力による農具から、作業機械主体へと移行して、第二次世界大戦後、動力農機具が各農家に、導入されるようになった。
本町の農機具設備状況は、表3のようである。
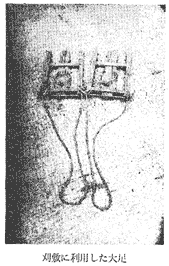 |

