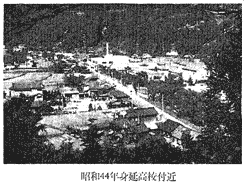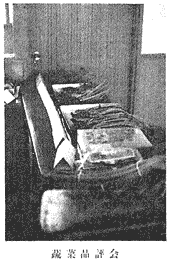(四)農業構造の改善
わが国の産業は、農業立国から工業立国へと移行し、商工業が急速に発展している中で、農業はたちおくれ、また戦時中から戦後にかけて行なわれた食糧配給制度は、一般の人々の食生活を変化させ、更に食生活の改善によって、米麦主食生活時代から、牛乳、肉食、菜食時代へと移行しつつある。米麦の国内需要は減少し、貿易の自由化によって、小麦、果物、乳製品など多くの農産物が輸入品に圧倒され、農業労働賃金や物価の高騰で管理費が増大し、米作以外の五穀の栽培はまったく採算がとれなくなって、農業経営はいよいよ苦しくなってきた。身延町においても、道路の整備拡張・諸官衙の移駐や、山腹にある農家の平地への移住によって、農地は減少の一途をたどっている。戦時中開墾された畑には、杉、梅などが植えられ、雑穀類は、わずかに自家用としてつくられている現状である。
本町においては、このような実状の中で、農家の多角経営を推進し、養豚や、果樹栽培、養鶏(ブロイラー)等も奨励して、換金農産物の増産に力を入れて、農家の危機を打開すべくつとめている。このように行きづまりの現状の中で、農業構造の望ましい改善こそ急務である。
表4
|
山梨県水稲、陸稲、大麦、小麦、作付面積及収穫高 (山梨県統計書)
|
||||||||||
| 作物名 年度 |
水 稲
|
陸 稲
|
小 麦
|
大麦(第6条)
|
大麦(第2条)
|
|||||
|
作付
面積km2 |
収穫高
t |
作付
面積km2 |
収穫高
t |
作付
面積km2 |
収穫高
t |
作付
面積km2 |
収穫高
t |
作付
面積km2 |
収穫高
t |
|
|
昭和33年
|
17,905
|
65,737
|
825
|
1,436
|
8,594
|
20,262
|
8,046.7
|
21,593
|
—
|
874
|
|
昭和34年
|
17,876
|
65,431
|
789
|
1,194
|
8,140
|
22,725
|
7,876.1
|
24,672
|
277.7
|
929
|
|
昭和35年
|
17,788
|
76,587
|
771
|
1,360
|
7,442
|
21,386
|
7,894.9
|
26,271
|
293.5
|
1,509
|
|
昭和36年
|
18,174
|
80,630
|
937
|
1,238
|
8,365
|
25,052
|
6,278.5
|
21,209
|
452.2
|
1,905
|
|
昭和37年
|
17,895
|
79,033
|
907
|
1,124
|
8,308
|
24,380
|
5,410.7
|
17,950
|
613.9
|
1,975
|
|
昭和38年
|
17,528
|
73,877
|
743
|
1,198
|
7,440
|
13,954
|
4,542.0
|
7,420
|
499.8
|
953
|
|
昭和39年
|
17,114
|
73,761
|
658
|
842
|
6,301
|
16,761
|
3,607.0
|
11,615
|
353.0
|
1,091
|
|
昭和40年
|
16,600
|
61,100
|
530
|
551
|
5,600
|
15,800
|
2,930.0
|
9,380
|
280.0
|
870
|
(五)本町の農業の現況
本町においては、早くから養蚕組合がつくられ、さらに最近では、養豚、養鶏、乳牛組合などもつくられた。しかし、蔬菜等の栽培や研究については、熱心につづけられているが、組織化するまでには至っていない。本町には蔬菜栽培に適した気候と土壌をもった所が多く、白菜、玉葱、大根、生姜、馬鈴薯など、移入したものより良質なものを産している。清子、大久保の白菜、豊岡地区の生姜、大野の大野菜などは、多量の生産がともなえば移出も可能である。近年本町においては、各地区公民館が、農業協同組合の後援を得て、蔬菜其の他の品評会を開いて、その研究と栽培を奨励している。
つぎに、山梨県農業基本調査にもとづいて、農産物に関する表6〜10をかかげる。ただし、農産物生産高については、第三章産業のあらましの項に、かかげてある表14を参照されたい。
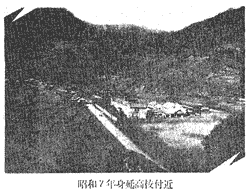 |
| 表7 農産物 豊岡地区昭和43年度の収穫農 家数、収穫面積、販売農家数
|
表8 農産物
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表9 農産物 下山地区昭和43年の収穫農家 数、収穫面積、販売農家数
|
表10 農産物 身延地区昭和43年度の収穫農 家数、収穫面積、販売農家数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||