第八節 指導機関
一、山梨県南巨摩農業改良普及所南部支所
(一)所在地 南部町南部
(二)沿革
昭和22年農業改良助長法が施行され、農家を訪問し、農業技術を指導したり、農民生活の改善を指導するために、都道府県に所属し、市町村を担当する農業改良普及員が任命された。当初山梨県では、普及所を126ヵ所とした。しかし、現在の農業経営の形態が、専門化され企業化の方向にすすんで、高度の技術指導がいよいよ必要となってきたことと、普及活動を、効率的に行なうため、昭和43年機構改革をした。これによって、峡南農業改良普及所を統合して、南巨摩農業改良普及所誕生し、南部支所となる。そして現在6名の職員が、農業の近代化のためにとりくんでいる。(三)職員
支所長 佐野文三 特作指導普及係長 武川充男 果樹、経営指導
技師 渡辺善家 作物、畜産指導
技師 赤池喜久雄 果樹指導
技師 遠藤一城 そさい、青少年指導
技師 深沢静江 生活改善指導
(四)管轄区域と活動
農業改良普及所南部支所管内は、身延町・南部町・富沢町である。活動にあたっては、前記のように職員の指導担当役割をきめ、直接各地区を巡回して指導にあたっている。その他支所誕生以来時報の刊行などをして、指導普及に専念している。
二、身延町農業委員会
(一)事務所 身延町役場内
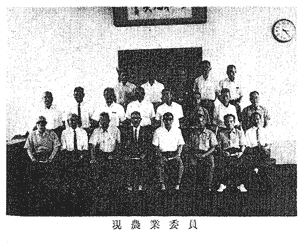 |
(二)沿革
昭和26年3月の第10国会において、農業委員会等に関する法律が成立して、従来からあった農地委員会・農業調整委員会・農業改良委員会を統合して、市町村に農業委員会が設置されることになって、身延・下山・大河内・豊岡の4ヵ町村にも、それぞれ農業委員会が設置されて、農地法等の規定に基づいた事務と、農業振興に関する事務を行なうことになった。昭和30年2月身延・下山・大河内・豊岡の4ヵ町村が合併して、身延町が誕生した。引きつづいて昭和32年7月、前述の4ヵ町村の農業委員会が合併して、身延町農業委員会が誕生して、現在に至っている。(三)合併後の歴代会長
初代 渡辺信作2代 望月善長
3代 松木四郎
4代 佐野治郎
5代 柿島武文(現在)
(四)農業委員名(昭和44年現在順序不同)
会長 柿島武文委員 小山竜夫 望月正明
市川孟 網野正一
市川達男 遠藤百治
望月貞夫 田京駒男
近藤保司 沢田 進
市川正美 佐野治郎
志村国為 四条長治
松野久男 望月忠司
望月秀雄 望月義正
望月脩二 中村孝恭

