第九節 林業
一、概況
本町は、山梨県の南部にあって、気候は海岸的気候であるが、冬の寒さは1、2月の平均気温が四度前後と比較的暖く、夜間を除き日中零度以下になることはほとんどなく、年間の降雨量も多いので、樹木の成育に適している。とくに杉、檜(ひのき)の成育は良好で、身延山の千本杉のように、集団林として全国に誇るべき美林が育っている。山林面積は、10,659ヘクタールで、本町総面積13,047ヘクタールの約82パーセントを占めている。
所有区分別の山林面積は国有林306ヘクタール、県有林2,182ヘクタール、民有林8,171ヘクタール、その他、2ヘクタールとなっている。蓄積量は、針葉樹229,896立方メートル、広葉樹は、251,033立方メートルで、広葉樹の蓄積量の方が多い。
本町の産業は、立地条件からみて、農林業が主体となっているが、農業の耕地面積は約4.1パーセントと狭小なため、経営規模はきわめて零細で、一戸当り0.35ヘクタール、しかも平地が少ないためと、山間に散在する等の悪条件が重なって、その生産性がきわめて低いので、いきおい本町総面積の82パーセントを占める林業経営が主力とならざるを得ない。ところが、林道の不備、労務者の不足、それに伴って起る賃金の高騰により、林業経営は、不振の状態である。
なお、戦後空襲で消失した都市の住宅復興用材として杉、檜(ひのき)、松などがつぎつぎと伐採された。その伐採地は植林されないまま長い間放置されていたが、ようやく経済状態に安定のきざしのみえはじめた昭和25年頃から造林事業に関心が向けられ、植林した山林が多いため、素材生産は減少している。
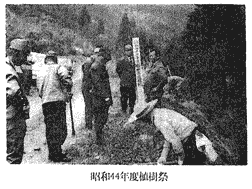 |
また、造林事業においてもここ数年の労務者の不足と、奥地への植林のため出費が重なり単年度に植林する総世帯数は大きな変動はないが、面積は狭小になりつつある。
そこで、造林事業を促進するために国、地方公共団体の援助を得て造林を進めているところもある。
このように、渋滞している林業経営を盛んにするため、現在林業構造改善事業計画が立てられ、これから三ヵ年計画で着々と実施されている。
一方、県有林・国有林においては、林種転換を中心とする経営がなされている。
また、特産物である椎茸(しいたけ)、わさびの栽培にも関心がもたれ組合などを組織して、熱心に研究栽培がなされている。
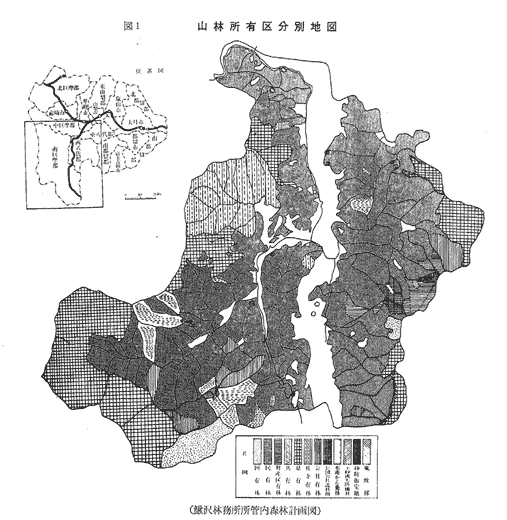 |
二、官有林と民有林の現状
(一)官有林
ア 国有林本町における国有林は少なく、その面積は306ヘクタールである。南部町国有林の続き(椿草里奥の山)にあり、針葉樹林面積64ヘクタール、広葉樹林面積157ヘクタール、除地・崩壊地85ヘクタールとなっている。
針葉樹は、人工林が多く、樹種も杉、檜ばかりで樹齢5、6年が一番多く、伐期齢にはほど遠い。
現在、樹種転換を中心に造林事業が進められている。管理は南部町にある甲府営林署南部担当事務所が行なっている。
イ 恩賜県有林
恩賜県有林は、江戸時代の入会御料地で、明治維新後は官有地に編入されて管理されていたが、明治40年、同43年と二度にわたる大水害にあって疲弊し、塗炭の苦しみにあえいでいる山梨県民をあわれまれて明治天皇が、同44年3月11日山梨県所在入会御料地の全部、実測面積約18万6千ヘクタールを御下賜されたのである。
身延町には、恩賜県有林の属する山林が、2,182ヘクタールあって、山林面積の約20.4パーセントを占めている。
下賜当時の台帳面積は、557.5ヘクタールであった。地区別面積を表で示すと次の通りである。
ウ 県有林の現状
面積2,182ヘクタール、内人工林は333ヘクタール、天然林1,749ヘクタールで天然林の占める割合は80パーセントと非常に高い。昭和39年から、林種転換を中心に造林事業が進められ年ごとに植栽面積の増加がみられるが、人工林が総面積の半ばを占めるまでには、相当の年月が必要である。
最近5ヵ年間の植伐面積を表わすと、次の通りである。
蓄積量は、総計135,123立方メートル、杉、檜で占められている。針葉樹は14.5パーセント(18,587立方メートル)できわめて少ない。これは最近植栽されたものが多いためである。広葉樹の量は115,536立方メートルと非常に多く、伐期に達した森林が所々にあることを明らかにしている。
しかし、このほとんどが奥地に集まっているので林道不備、労務者不足の現在では伐採、搬出は容易でない。
現在、県営大城林道の延長工事が進められているが、予算が少ないため進ちょく状況は余り芳しくない。
| 表1 地区別恩賜林面積表
|
表2 植伐面積表 (単位ha)
|
(二)民有林
民有林の面積は、8,171ヘクタールあり、本町森林面積の約76.7パーセントを占めている。国有林・県有林に対する比率は高く南巨摩郡下では三番目である。表で示すと次の通りである。
表3 所有区分別森林面積と比率 (面積ha 比率%)
|
南 巨 摩 |
町村
|
総数
|
民有林
|
県有林
|
国有林
|
民有林
比率 |
|
富沢
|
7,863
|
7,213
|
650
|
—
|
91.7
|
|
|
南部
|
9,649
|
6,857
|
779
|
2,013
|
71.1
|
|
|
身延
|
10,659
|
8,171
|
2,182
|
306
|
76.7
|
|
|
早川
|
34,838
|
18,458
|
16,380
|
—
|
53.0
|
|
|
中富
|
2,704
|
2,221
|
484
|
—
|
82.2
|
|
|
鰍沢
|
3,970
|
1,941
|
2,029
|
—
|
48.9
|
|
|
増穂
|
5,315
|
2,094
|
3,221
|
—
|
36.4
|
|
|
計
|
74,998
|
46,955
|
25,724
|
2,319
|
62.6
|
わが国の林業の特徴の一つとして、国有林、県有林が多く市町村における山林の半分以上を占めていることがあげられる。
幸に本町では8割近くが民有林であることは、林業経営上好ましい状態といえる。
しかし、山林所有者数をみると、実に2,848人と非常に多く、その一人当りの所有面積は狭く2・3ヘクタールにすぎない。
現在、林業専業で生計を立てるためには20ヘクタールの山林が必要であるが、この10分の1の面積しかもたない本町林業家にはとてもそれは望めそうもない。
したがって兼業者が多いのはやむを得えないことである。むしろ現状では林業のかたわら農業をする人は少なく、農業のかたわら林業をする人のほうが多い。
次に森林所有規模別を表示すると、次の通りである。
表4 森林所有者規模別表 (単位ha比率%)
| 面積 |
1未満
|
1〜3
|
3〜5
|
5〜10
|
10〜
20 |
20〜
30 |
30〜
50 |
50〜
100 |
100〜
200 |
200〜
500 |
500
以上 |
| 所有 者数 |
1,830
|
593
|
183
|
112
|
71
|
27
|
17
|
9
|
4
|
1
|
1
|
| 比率 |
64.3
|
20.8
|
6.4
|
3.9
|
2.5
|
0.9
|
0.6
|
0.3
|
0.2
|
0.03
|
0.03
|
この表で明らかなように1ヘクタール未満が3分の2以上もあり、5ヘクタール未満のものを合わせると90パーセントをこえ、20ヘクタール以上は、わずかに2パーセントにすぎないのである。しかも、この2パーセントが、森林面積の46パーセントまで所有している現状である。資本主義経済下における富の不均衡が、ここにもあらわれている。
さて、次に植伐状況をみると伐採面積については、資料がないのではっきりしないが、ここ3、4年の素材生産が年ごとに減少しているので、伐採面積も減少していることが明らかである。
植林面積の最近5ヵ年の計は、401.08ヘクタールになっているが、前にも述べたように造林戸数は余り変らないが、面積は減少しつつある。
これを表で示すと次の通りである。
| 表5 植栽面積表(単位ha)
|
表6 素材生産実績表 (単位m3)
|
ア 民有林所有区分別森林状況
民有林を細分すると、町財産区有林、共同部落組有林、個人有林、社寺有林、会社および団体有林とに分けられる。
それぞれの面積、蓄積量、その他を表で示すと次のようになる。
表7
|
市町村
財産区有林 |
共同部落
組有林 |
個人有林
|
社寺有林
|
会社及び
団体有林 |
||
|
面 積 (ha) |
人工林
|
66.64
|
214.72
|
2,485.09
|
463.32
|
131.15
|
|
天然林
|
248.78
|
364.52
|
3,303.39
|
409.67
|
21.77
|
|
|
未立木地
|
0.11
|
|
10.72
|
0.71
|
|
|
|
除地
|
0.17
|
0.60
|
5.49
|
38.42
|
|
|
|
伐跡地
|
0.48
|
1.20
|
93.71
|
11.01
|
72.10
|
|
|
竹林
|
|
(40束)
0.09 |
(75388束)
183.15 |
(674束)
2.55 |
(272束)
0.34 |
|
|
崩壊地
|
|
|
17.61
|
|
0.05
|
|
|
計
|
316.18
|
581.13
|
6,099.16
|
945.68
|
225.41
|
|
|
蓄
積 (m3) |
針葉樹
|
1,663
|
6,117
|
116,336
|
83,263
|
2,713
|
|
広葉樹
|
4,320
|
13,060
|
91,404
|
19,233
|
1,568
|
|
|
計
|
5,983
|
19,177
|
207,740
|
102,496
|
4,281
|
|
|
ha当り平均
|
19
|
33
|
34
|
108
|
19
|
以上の内で特別な形態の山林である社寺有林、共同部落組有林、会社及び団体有林の現状について書くことにする。
(ア)社寺有林
沿革
社寺有林の総面積は、945.68ヘクタールあるが、ほとんどが久遠寺寺有林である。その面積は実に861.45ヘクタールにおよんでいる。
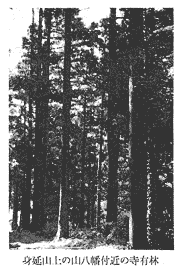 |
ところが、明治2年(1869)版籍奉還の際、境内約4.16ヘクタールを除いて、すべて官林に編入されてしまった。
以後久遠寺は、堂宇の修繕にも事欠くばかりでなく、寺院付近の立木が公売伐採されて、寺院としての風致をそこなうことが著しくなってきたので、明治16年(1883)払下げを政府に請願したが許されなかった。
明治22年(1889)御料地に編入されたので、すぐに御料地委託願いを、御料局へ提出した。
幸に信徒である金原明善・小林小太郎等の尽力があって、明治23年(1890)3月22日付をもって認可された。
それからは、身延山久遠寺の上地御料林は身延山委託林となって、農商務省令の委託林規定に従って経営された。
その後、明治33年(1900)宮内省告示第10号、社寺上地御料林特売規定の発布があったので、門末議会、有力信徒の賛成を得て払下願書を提出したが、明治43年(1910)12月にようやく払下げ価格の指定があった。
しかし、金額が予想外に高かったので、関係者が政府機関に嘆願したところ、山林の一部を現境内に編入することを規定するとともに、払下価格も更正されてきた。
さっそく門末会を召集して、末寺負担額を協定するとともに、山林払下期成会を設立して、負担額の徴収方法、払下代金納入方法を決定、門末、信徒をあげて尽力した結果、大正8年(1919)1月29日に払下代金全額を納入した。
ここに再び久遠寺の寺有林として、永世本山の経営下におかれることになった。そして、大正9年(1920)から新に寺有林施業方法書を作り、その下に林業経営がなされた。
山林現況
大正九年から昭和にかけては、もっぱら身延山寺有林施業方法書によって経営がなされた。
初期においては、委託後25年間にわたって植栽した杉・檜の手入れを中心として行なった。
下刈り、除伐、間伐が一段落したところで、林種転換を主眼にした植栽事業に、力が注がれて年々人工林は増加した。
 |
しかし、昭和34年に山梨県を襲った伊勢湾台風は、この美林を吹き倒し、大打撃を与えたのであった。
見るも無惨な風倒木は、処々その残がいをさらした。その量は実に、231,000立方メートルに及び、面積もまた相当なものであった。
台風後は、もっぱら風倒木の伐採をするとともに、その後の植林に力を注ぎ、10年の歳月を費してようやく完了した。
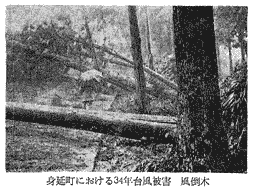 |
伐採は、堂塔伽藍(らん)の修復等に必要な量だけで、他に売って利益を得ることはなされていない。あくまでも風致林の面目は保たれている。素材の加工は、身延山直営の製材所でなされている。
次に最近の林況を表8に示してみよう。
(イ)会社および団体所有林
椿・大島に大昭和製紙株式会社、大城に長谷川木材、大昭和製紙株式会社、相又に本州製紙株式会社と、それぞれの持山があり、植伐事業に専念している。
大資本の下に行なわれる林業経営は、予算も潤沢であるので造林事業はめざましく発展して、人工林面積は約90パーセントに及んでいる。
しかし、敗戦後のパルプブームあるいは、建築ブームの乱伐が影響して、伐期齢に達している森林は少ない。蓄積量は1ヘクタール当りわずかに19立方メートルである。
現在伐跡地も72.10ヘクタールに及んでおり、植林が待たれている。
表8 身延山山林現況 面積ha 蓄積量m3
| 久 遠 寺 境 内 林 |
面積
|
蓄積量
|
|
|
10年未満針葉樹
|
147.69
|
0
|
|
|
10年以上針葉樹
|
338.57
|
67,747
|
|
|
広葉樹
|
279.96
|
16,621
|
|
|
小計
|
766.22
|
84,368
|
|
| 七 面 山 境 内 林 |
10年未満カラ松
|
9.07
|
0
|
|
10年以上ツガ・カラ松
|
59.95
(内人工林5.13) |
14,866
|
|
|
広葉樹
|
3.23
|
781
|
|
|
小計
|
72.25
|
15,841
|
|
|
計
|
838.47
|
100,209
|
(ウ)共同部落組所有林
この山林は、数人から3、40名で経営管理する形態で、その数を名寄帳で拾うと74組もあり、本町山林形態の特色の一つを示している。
この山林の成立過程を考察しようとしたが、資料がなくまとめることができなかったので、2、3の地区の有識者に聞いたところ、この山林は、明治初期その地区で政治力のあった人が山を集め、自分の名儀にしておいたが一人ではとうてい経営ができないので、部落の人たちに分け共同で管理経営をさせたものであるという。また、中には御料地払下げの際、共同で買ったところもあるとのことである。
ともかく、共通するところは、共有ではあるが一人一人の名を登記してその所有を明確にしていることがわかる。
長い間経ているので、最初の登記者はすでになく、現在共有者全員で登記変更を考えている地区もある。
また、共有では管理経営がおそろかになるので分割して個人所有にしたところもある。
また、長い間に所有者同志の間で、権利の売買が行なわれ、登記上の人数は変らないが事実上の所有権者数の変ったところもある。
現在、林業構造改善事業で、これらの共有林を分割して、個有林に計画が立てられている。
地区別共有林数、所有者数、面積を表わすと次の通りである。
この表でわかるように地区によって、所有面積に差があるとともに、所有者数が実に多くなっている。特に豊岡地区は619と全戸数より多くなっており、一人が2〜3の共有林の所有権者になっていることがわかる。
表9 共有林数、面積表 (単位ha)
|
地区名
|
共有林数
|
所有権者数
|
面積
|
|
大河内
|
15
|
組持3
143 村持1 |
28.3650
|
|
下山
|
5
|
134
|
12.0248
|
|
身延
|
9
|
81
|
17.0637
|
|
豊岡
|
45
|
619
|
111.6309
|

