三、造林事業
林業経営は、目前の利益だけを求めて、伐採だけに力を注ぐと、長期的経済力を失ない破たんをまねく恐れがある。理想的な林業経営は、植林、伐採を計画的に行なうとともに拡大造林がなされることが大切ではなかろうか。しかるに、本町においては前述したように、労務者不足とそれに伴う賃金の高騰等により、伐採後の植林が思うようになされないので、拡大造林は無理な状態にある。
この状態が続いたならば、本町林業は衰退の一途をたどるのみである。このような現状を打開するため、国家・地方公共団体が造林を計画し実施している。その種類には、公団造林、県行造林等がある。
(一)公団造林
国家資金で行なう造林方法で、土地所有者が土地を提供し国家がこれを借り受け、森林公団に植林、手入れ、伐採すべてを委託しているもので、利益分配は土地提供者五分、国家五分となっている。本町においても、昭和38年度からこの方法によってすでに94.74ヘクタールの造林がなされている。
地区別、年度別公団造林を表10で示すと次の通りである。
表10 地区別 年度別公団造林表 (単位ha)
| 年度 部落 |
丸 滝 |
樋
之 上 |
大 崩 |
後 山 |
佐
野 道 |
下 山 |
計
|
|
38
|
8.20
|
|
|
|
|
|
8.20
|
|
39
|
15.00
|
|
|
|
|
5.20
|
20.20
|
|
40
|
6.85
|
|
|
|
|
|
6.85
|
|
41
|
|
5.14
|
11.45
|
|
|
|
16.59
|
|
42
|
|
4.37
|
10.07
|
|
10.07
|
|
24.51
|
|
43
|
|
6.04
|
|
8.50
|
3.85
|
|
18.39
|
|
計
|
30.05
|
15.55
|
21.52
|
8.50
|
13.92
|
5.20
|
94.74
|
(二)県行造林
県の資金で行なう造林方法で、本町には相又地区に10ヘクタールある。昭和34年度に、県が相又下の土地を借り受け、山梨県林業公社に委託植林させたものである。
植林後の手入れ、伐採をすべて県が行ない、利益は土地提供者が4分、県が6分という配分になっている。
このように国、県において治山、治水のため、また地域の林業発達のため造林事業を計画し行なっている。
この他、県有地を個人が借り受け、植林して生育させ伐採時には個人7分県3分という利益配分を規定した部分林もある。
本町においては、昭和42年度2名が個人申請をしているほか、古くから仙王外五山恩賜林保護財産区管理会が62.47ヘクタール、姥草里外七山恩賜林保護財産区管理会が5.20ヘクタールを経営している。
四、林道の開設と今後の問題
(一)沿革
本町の林道開削の歴史は、大正15年に着工された豊岡新山の林道に始まる。この林道は、現在の県営豊岡道の前身で、恩賜林林道として開削されたのである。
当時、大城地区の恩賜県有林の蓄積量は膨大で、県がこれを民間に払下げた結果、伐採事業が盛んになり、木材搬出の必要に迫られて、波木井を起点に大城までの軌道が、昭和8年(1933)に敷設されたのである。
さらに、インクラインが設けられて硯島山林地内まで延長された。それからは、山奥に眠る木材がトロッコに積まれて、波木井の宮の花の貯木場まで運ばれ、いかだに組まれて富士川を下ったのである。
時代の伸展とともに、交通機関も発達し木材輸送も身延線が利用されるようになると、一時に大量の木材を駅に集積しなければならなくなった。いきおいトロッコは後退し、荷馬車が台頭して木材運搬に活躍したが、やがてトラックの出現とともにその姿を消していった。
このように交通機関の発達に伴って、林道の拡張をよぎなくされ、軌道は急速に短縮されていった。いきおい貯木場も、宮の花から総門、そして横尾、大城部落下と移り変っていった。現在は赤岩が貯木場となっている。もちろん、軌道は使わないで過去の遺物として残されていたが、昭和35年ごろ撤去された。
現在、県営で大城部落的場(まとば)から、古谷城を経て安倍峠までの林道延長工事が進められている。
この他、町営で4林道が開削されているが、うち2林道は、林業構造改善事業の計画に従って工事が行なわれている。
次に林道一覧表をかかげてみる。
表11 本町林道一覧表 (昭和43.11.1調)
|
路線名
|
主要な経過地
|
延 長
|
着 工
年月日 |
竣 工
年月日 |
所属
|
備 考
|
|
豊岡林道
|
大城部落—大城部 落下土場—古谷城 —安倍峠下—安倍 峠 |
28年度〜43年 度 5.1km |
28年4月
|
|
山梨県
|
工事中
|
|
長野林道
|
大島馬込部落上— 長野 |
(26年度)
540m (27年度) 226m |
26年6月
|
27年
|
身延町
|
26年度は民間で 開設 27度は県単で開 設 |
|
大島林道
|
大島水上—大島大 日向 |
(28年度)
568m (29年度) 292m |
28年8月
|
29年
|
身延町
|
28年度は臨時救 農で 29年度は県単で 開削 |
|
樋之上線
|
樋之上針原—垈 |
(42年度)
1,431m (43年度) 920m |
42年9月
|
44年3月
|
身延町
|
林業構造改善事 業による |
|
大垈線
|
椿草里—大垈 |
3,045m
|
43年9月 4日 |
45年3月 15日予定 |
身延町
|
これから工事す るもの含め 延長3,045m |
(二)今後の問題
県営1、町営4の林道が開設されているが、このうち大垈線は、延長途上にあるが、本町の林野面積1.63ヘクタールに、蓄積量480.929立方メートル、この森林資源に対して生産基盤である林道密度は0.47でまことに低く、このため林業の近代化は遅々として進まない状態である。それ故、林道開削事業は本町林業発展のための急務であるといえる。
五、入会山の沿革
江戸時代における山梨県は、幕府直轄の地であって、山林も御料地と称されて、幕府の管轄下にあった。この御料地は御林山(おへえしやま)と、入会御料地(いりあいごりょうち)に分かれていた。
御林山は、幕府の建築用材・土木用材を生産する山林でひじょうに厳しく管理された。
入会御料地は、幕府が農民から、山租小物成を徴収して自由に山に入らせ、生活に必要な新炭材、小柴、肥料として使う芝草、時には建築、土木用材を採取させた山林である。
生産性の低い田畑は検地されて、貢租を厳しく取り立てられた当時の農民にとって入会権が認められたことは、どんなに生活の助けになったことであろうかと推察される。
さて、この入会山は単村入会から、十数ヵ村入会のものがあり、複雑な様相を呈している。
甲斐国志によると、本町関係の入会御料地は一ヵ所しかなく次のように記されている。
「西山 入会場二箇所アリ一ハ横根、中村、中野ト入会、一ハ本郷、中野ト入会共ニ山租ナシ」と。
江戸時代に、農民生活の支えとなった入会御料地が、本町に一ヵ所しかないのはうなずけないことである。
これに反して、御林山は各地区に一、三ヵ所ずつある。
以下甲斐国志によるが
| 下山地区 | |||
| 御林山 | ○ | 「粟倉村ニ在ル松林ナリ又早川ノ側ニ御竹林アリ」 | |
| ○ | 「下山村ノ南ニアリ」 | ||
| 豊岡地区 | |||
| 御林山 | ○ | 「大城ニ在リ町歩不詳山中ニ駿州三河内日蔭沢等ヘ越ユル小径アリ乙女坂ト云 乙女ハ御留ニテ昔時往来ヲ禁止セラレシ時ノ名アルベシ」 | |
| ○ | 「相又村の西南ニアリ山中小径アリ駿州日蔭沢ヘ通ズ」 | ||
| (大河内地区) | |||
| 御林山 | ○ | 大垈村ノ東ニ在リ」 | |
| ○ | 「角打村ニ在リ長三町横二町小松林ナリ」 | ||
| ○ | 「和田村ノ東ニ在リ東西三町、南北拾壱町小松林ナリ此東ニ平木梨鹿草里アリ」 | ||
| ○ | 「樋上村ニアリ松樅アリ樅拾壱町其東ハ垈山ナリ」とある。 | ||
和田村に関しての古文書をみると次のように記してある。
これでみると、女や子供たちが何回か掟を犯して御林山に入り下枝、芝草、果ては正木までも切っていることがわかる。
この時代になると、お仕置も江戸時代初期の獄門・死罪という重い刑はなくなり、相当寛大になったようである。そのため掟(おきて)破りも多くなったのであろう。
また、御林山の保護育成をすることにより、御伝馬宿入用、6尺給米、御蔵前入用以上三役の免除があったことが、他の古文書に記されている。
この形態の異った2つの御料地も、やがて明治に入り制度が改められて、官地に編入されたのであるが、農民の生活に影響を及ぼす入会慣行は廃止されなかった。
明治22年(1889)に官地は、御料地に編入されて皇室財産となった。
しかし、明治40年(1907)、43年(1910)と二度にわたる大水害に貧窮した山梨県に、明治天皇は従前の入会御料地を下賜された。
この時から入会御料地は、恩賜県有財産として管理、経営されることになったが、県有林が各町村における山林の大部分を占めており、地区民の経済生産に影響を及ぼすことが大きいので、入会慣行を認めることにした。
しかし、従前のように自由に山に入り下草、薪炭材の採取は許されなくなった。
ここに、北富士演習場の入会権問題の起る原因がひそんでいるのである。
以前のような入会慣行の許されない代償として恩賜県有財産保護管理会に対して、保護管理している山林の面積に応じて毎年配当金がある。それは自分の経営、管理している山林を売った際はもちろん全県下どこの恩賜林が売られても、プール計算によって配当がある。
現在、全国的に展開されている、入会林野の近代化の対象になっている林野は、本町においては部落共同組有林であるが、この山林は成立過程がはっきりしないので、従前入会慣行のあったものであるかどうかわからない。
現在の共有林の経営形態をみると、所有権者全員で植林・手入れ・伐採を行ない利益の分配は均等である。
六、林業構造改善事業のあらまし
(一)趣旨
近年、日本の経済は、めざましい発展をとげ、年々国民の生活もよくなってきているが、これを農業と工業あるいは都市と農山村というように分けてみた場合、その生活にはまだまだ差がある。国は、国民の生活のなかにこのような差がなくなるように、いろいろな対策をすすめている。
林業においても、林業を盛んにすることによって、そのような差を少しでも少なくするよう努めてきている。
林業構造改善事業というのは、このような対策のなかのひとつとして生まれたものである。
林業がこのような差を少なくすることに役立つためには、もっと生産性を高めるとともに、生産量を増していくことが必要である。このためには、林業を根本から改善していくことが必要となってきたのである。
林業構造改善事業は、このような林業の根本になっている構造をかえようとする事業である。
そのためには零細(れいさい)な森林の経営規模を拡大し、装備や技術の近代化、機械化をはからなければならない。
このほか、林業の基盤となっている林道の開発もあわせてすすめなければならない。
そして経営規模も大きく、機械力も利用でき、かつ林道も整備された良い森林をもつ経営者をつくっていくことが必要であろう。
しかも経営は、できるだけ協業化することによって、効果的にすることが望まれる。
このようにしてはじめて林業が、格差是正のために役立ち、さらに町の重要な産業として発展していくであろうと考えられる。
(二)経営基盤の充実
ア 入会林野の近代化 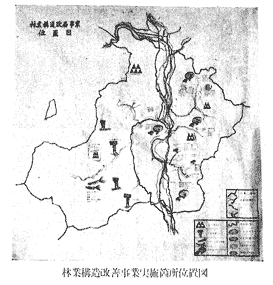 |
イ 林地の流動化
小規模林業経営者が、放置されたままになっている林地や、不在町所有者の林地を購入して経営規模を拡大しようとする事業である。
ウ 林地の集団化
小規模林業経営が、合理的に行なわれるように、地域内の林地を相互に交換分合し、林地の集団化をはかろうとする事業である。
(三)生産基盤の整備
ア 林道の開設事業機械をつかった協業など、その他の林業構造改善事業と密接な関係にある比較的小さな林道をつくることにより、林業経営の改善をすすめようとする事業である。
(四)資本装備の高度化
ア 素材生産施設の設置木を切ったり、運んだりする素材生産を森林組合が機械をつかった協業によって行ない、林業経営の近代化をはかろうとする事業である。
イ 造林施設の近代化
造林地の地拵(ごしら)えをしたり、苗木の植栽や手入れをしたりすることを、機械をつかった協業によって行ない、林業経営の近代化をはかろうとする事業である。
ウ 特殊林産物生産施設の設置
短期間に収入を確保し、育林などの林業生産が安心して、行なわれるようにするため、椎茸、なめこなどの特殊林産物の生産を近代的な施設を使い、協業によって行なうことをすすめる事業である。
(五)早期育成林業経営の促進
生産期間の短い林業経営を確立するため成長の早い外国樹種を導入したり、杉、檜や松などの在来樹種について新しい育成方法を用いたりして、モデル的に造林を行う事業である。(六)協業の推進
林業構造改善事業によって導入される機械施設は、すべて協業によって運営されるので、この活動を推進するために調査し機械の導入と協業の計画をたてることである。(七)特認事業
ア 特殊林産物生産施設の設置地域の実情により林業構造改善事業をすすめるうえに、特に必要な事業は特認事業として実施できることになっている。
これらの事業の受益者は、いずれの場合でも5戸以上ではなくてはならない。
林業基本法、森林法、県条例等に基づいて本町においても、昭和41年度に指定を受けて、昭和42年度から3ヵ年計画で林業構造改善事業を実施している。
表13 林業構造改善事業年度別実施計画表
|
事業
区分 |
事業種目
|
事業主体
|
構成員
|
事業内容
|
事業費
|
備考
|
|
|
経
営 基 盤 の 充 実 事 業 |
入会林野の近 代化 |
身延町
|
128戸
|
4ケ所 87.5ha |
円
350,000 |
43年度 | |
| 分収造林の促 進 |
身延町
|
8
|
1ケ所 5.0ha |
14,000
|
44年度 | ||
| 林地流動の促 進 |
身延町
|
20
|
1ケ所 20.0ha |
63,000
|
44年度 | ||
| 林地の集団化 |
身延町
|
4
|
5件 6.5ha |
26,000
|
44年度 | ||
|
小計
|
160
|
453,000
|
|||||
| 生産基 盤の整 備事業 |
林道の開設
|
身延町
|
350
|
350樋ノ上線、大垈線、2路線、 5,415m |
49,996,000
|
42、43、44年度 | |
|
小計
|
350
|
49,996,000
|
|||||
|
資 |
素材生産の近 代化 |
森林組合
|
540
|
索道1、チェーンソー6台、トラ クター1台、集材機2台、トラッ ク1台、倉庫1棟 |
6,0660,00
|
42、43、44 | |
| 造林の近代化 |
森林組合
|
540
|
刈払機1、薬材散布機1、移動 宿泊施設1棟、機械保管倉庫1棟、 資材人員輸送車1台 |
2,083,000
|
43、44 | ||
|
特 |
しいたけ 生産施設 |
大垈しい たけ組合 |
7
|
作業用建物33㎡、鉄骨パイプ、 乾燥機大宮式3号型2台、乾燥 用建物33.2棟、チェーンソー3台 |
1,140,000
|
42、44 | |
| しいたけ 生産施設 |
大野しい たけ組合 |
5
|
フレーム48.6㎡/、貯水漕10㎡/ |
435,000
|
42完成 | ||
| しいたけ 生産施設 |
大崩しい たけ組合 |
5
|
乾燥用建物3棟、乾燥機3台、 チェーンソー3台 |
1,266,000
|
42完成 | ||
| しいたけ 生産施設 |
垈しいた け組合 |
5
|
作業用建物1棟、乾燥用建物1棟、 乾燥機1台、 チェーンソー3台 |
814,000
|
42、43 | ||
| しいたけ 生産施設 |
針原しい たけ組合 |
5
|
作業用建物2棟、チェーンソー2台 |
592,000
|
42、43 | ||
| しいたけ 生産施設 |
樋ノ上しい たけ組合 |
5
|
乾燥用建物1棟、乾燥機1台、 チェーンソー1台 |
422,000
|
42完成 | ||
|
小計
|
1,120
|
12,818,000
|
|||||
| 早期育 成林業 経営の 促進事 業 |
在来樹種の早 期育成 |
丸谷林業 研究会 |
8
|
すず、ひのき、新植4.5ha、補植、 肥培、保育 |
900,000
|
42、43、44 | |
|
小計
|
8
|
900,000
|
|||||
| 協業の 推進事 業 |
協業の推進
|
森林組合
|
540
|
オートバイ1台、トランシーバー 2組、 測量器具一式 |
334,000
|
||
|
小計
|
540
|
334,000
|
43 | ||||
|
特
認 事 業 |
特殊林産物生 産施設の設置 |
わさび組 合 |
5
|
わさび田、0.3ha、開田 |
5,478,000
|
42、43、44 | |
|
小計
|
5
|
5,478,000
|
|||||
|
計
|
2,183
|
69,979,000
|
|||||
|
予備費
|
7,021,000
|
||||||
|
総計
|
77,000,000
|
||||||

