第十節 特殊農林産物
林業は杉・檜の育成生産だけにあるのではなく、特殊林産物といわれている椎茸・わさび・クリ・クルミ・ナメコの栽培、また竹・薪炭等の生産も忘れてはならない。これらは、林業経営者、或は農家にとって換金が早いので、副業として各地で熱心に研究され、相当の実績をあげている。
町当局も特殊農林産物生産に有利な立地条件を備えている山林は100パーセント活用して、生産を高め収入を多くして、農林業者の経済生活の安定をはかるため、昭和42年度から同44年度までの三ヵ年計画で林業構造改善事業をおしすすめている。
 |
一、わさび
わさびは、本町においては大城、大崩、垈、椿草里・大垈で早くから栽培されていた。わさび栽培は立地的に制約を受けるが、幸いこの地区は水のきれいな沢があり、その近くに林地をもつという条件を備えていたので、生産されるようになったのである。
林地も肥えた土地のところでは、根が腐って適さないのであるが、現在栽培が行なわれている地区の林地は、砂礫(れき)が多いところである上に沢の水が澄んでいて冷たくて、雨が降っても濁ることがないので最適地といえる。
これらの地区は最初は小規模で沢地のわずかな場所に適地を選んで植え育て、徐々に面積を広げ、生産高を高めていったのである。
大城でのわさび栽培は古く、いまから50年前の大正10年(1921)前後であるといわれている。
身延の望月善長が恩賜林の中に適地を見つけ借り受け、20アールほどの面積に植えつけたという。現在、その栽培地は10アールほどになってしまったが、品質のよいわさびが生産されている。
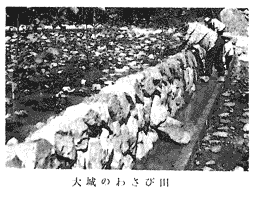 |
垈では、熊谷義正が昭和5年(1930)伊豆に行き、畳石式わさび田の研究をして帰り、30アールの土地を整地して植え付けている。
大崩では古く佐野忠吉・重則父子が明治中葉からはじめ、続いて佐野伴甫も経営した。
現在、各地区とも規模拡大事業が林業構造改善事業の計画の下に行なわれており、42年度から44年までに36アールの開田が計画されている。
大城地区では、すでに12アールのわさび苗が植え付けられて順調に成長している。
現在は、苗を他から求めているが、一本7円、3.3平方メートルに60本の割で植え付けると苗代も相当額にのぼるので、将来、自家で育成する計画も立てられている。
なお、林業構造改善事業前の面積は、56アール、生産量は4,000キログラムで主に静岡方画に出荷されている。
最近わさび組合が結成され、協業体でわさび栽培がなされている。大城地区で5人、大崩、垈地区4人で組織されている。
二、しいたけ
本町の山林は、広葉樹林が多く、椎茸栽培に必要な原木に恵まれ、容易に得られるうえに、降水量も多く温暖な気候なので椎茸栽培には適しており、早くから生産されていた。熊谷義正の談によれば、江戸時代に栽培が始められ、少量ではあるが身延山に納められていたとのことである。松野真一の談によると、真一の祖父にあたる松野武兵衛は、若いころから椎茸栽培に関心をもって研究していたが、24、5歳の時に家督を相続すると、慶応元年(1865)単身伊豆におもむき、台場で椎茸栽培の方法を研究して帰り、前より規模を大きくした栽培を行なった。
ついで弥三郎・真一父子研究栽培をつづけ、昭和27年に全国農林産物品評会において1等賞をうけた。
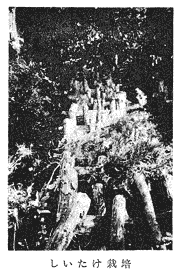 |
 |
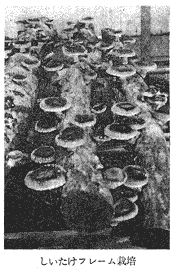 |
しかし、当時の椎茸菌は質が悪く、またこの土地に合わずいたずらに出費がかさんだので、自費を投じて椎茸研究室を作り研究に没頭し失敗に失敗を重ねながらも、ついに目的の地域の気象条件にあった椎茸菌の培養に成功したのであった。
それ以後、椎茸菌による大規模な人工栽培は急速に発展していった。
最近は、生産高を上げる一方品質向上にも力が注がれ、椎茸生産組合が各地域ごとに組織され、昭和43年には町一本の組合が結成され組合長に滝川隆治が就任した。
組合は、品評会などを開き栽培技術の批判検討をしたり、天日乾燥を改善するため、乾燥機購入の計画が立てられている外、共同出荷が実現している。
なお、新しい試みとして、フレームによる椎茸栽培が、大野でごく小規模ではあるが行なわれている。フレーム栽培の最初の椎茸は肉厚く品質もよく今後の経営が注目される。
各地区別の組合員数と生産量を表に示すと次の通りである。
表1
|
事業主体名
|
戸数
(戸)
|
乾燥椎茸生産量 kg
|
|
大垈椎茸組合
|
8
|
700
|
|
大崩椎茸組合
|
12
|
1,100
|
|
塩之沢椎茸組合
|
5
|
100
|
|
垈椎茸組合
|
5
|
950
|
|
針原椎茸組合
|
5
|
600
|
|
樋之上椎茸組合
|
5
|
500
|
|
計
|
40
|
3,950
|
三、薪炭
本町の森林は、広葉林が多く、なお、薪炭用材に必要なナラ、クヌギ、カシ、シデ、ブナ、カエデ等の樹種に恵まれていたので早くから薪炭業が盛んであった。 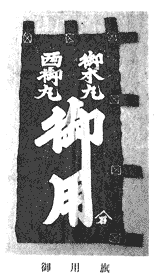 |
明治、大正、昭和と時代が進むに従い、薪炭の需要は増大して、その生産も一段と活発化した。
豊岡地区は、山林面積が多く、しかも広葉樹林に恵まれていたので、特に生産量は多かった。
大正元年(1912)には、約110トン、大正3年(1914)15トンと上昇して大正11年(1922)には、実に339トンに達したのである。
大河内、下山、身延3地区の資料がないので、4地区合計数量を出すことはできないが相当の数量になることが推察できる。
この生産上昇も、第二次世界大戦に入ると、急に下降線をたどったのである。
日に日に若い人々は出征して、生産に従事する人は少なくなり、ついには山からの炭の搬出に小中学生がかり出される始末であった。
終戦直後は、すべての物資が不足して、統制経済がしかれ木炭も自由に売買できなくなった。
昭和25年頃より日本の経済も好転しはじめた上に、朝鮮動乱がもたらした特需で非常に景気はよくなり必需品の統制も徐々に解かれた。
木炭も自由販売が許されると、生産量も急増していった。
規模の大きい焼窯(がま)が作られ、一度に50俵、100俵分が焼かれ大量生産が行なわれた。
しかし、昭和30年前後から電気器具、石油器具が一般家庭に行きわたるとともに、昭和34、5年頃からプロパンガスが使用され始めると木炭生産に大きな影響を及ぼした。これに加えて、里に近い山林には、ほとんど木炭材はなく、奥山に入らなければならない。ところが労働力不足のためいきおい木炭の生産は、急激に減少してきて、いまや斜陽産業として衰微の一途をたどるのみである。
次に昭和29年から同32年までの木炭の生産量を示すと次の通りである。(但し豊岡地区のみ)
木炭の生産量は、逐年減少しており、四地区を合計しても現在の町内需用をも満たすことができないので伊豆方面から移入されているのが現状である。
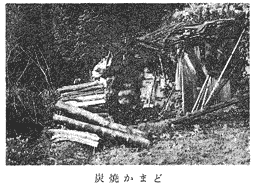 |
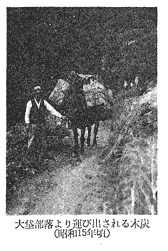 |
|||||||||
表2 木炭生産量の推移(豊岡)
|
四、竹
本町は、竹林のよく育つ土壌、気候と自然条件に恵まれているので、かつては各地区、各処に美しい竹林をみたが、老齢化による開花病のため、7、8年前から真竹が枯れはじめ現在では相当数の竹林がその姿を消している。しかし、いまだに老齢化しない真竹、もうそう竹、はちく等の面積、蓄積束数は相当にあって、竹林総面積186.45ヘクタール、蓄積束数76,374束もある。
竹は、杉檜のように伐期齢が長くないため、毎年切れるので農家や林業家にとっては、現金収入のよりどころであったが、竹林の枯死によって、打撃を受けた人たちの数は少くない。
しかし、枯死した竹林の後にようやく細い竹が生え育っているのをみて、昔の美しい竹林になる日の遠くないことを知る。
なお、本町の竹の質のよさと量の多いことに目をつけ、昭和42年に「静神竹工」が船原地内へ竹工場を立て、もうそう竹で輸出向の種々の容器、花立を生産している。
 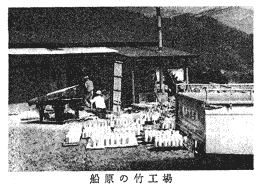 |
五、茶
本町の茶栽培は、霧が深く山の深い沢地という地理的条件に恵まれ、小規模ではあるが、早くから各地区で行なわれていた。なかでも、大城は茶栽培の最適地として古くから栽培され、面積、生産量とも他地区よりはるかに多い。
この大城の茶栽培は、標高5、600メートルの山地に群生していた野生の茶の木をもとにして始められたのであるが、栽培地は畦畔、あるいは焼畑が主で、野菜畑、穀物畑を割いてまで栽培されることはなかった。採算の取れるか取れないかわからない茶栽培をする余分な土地はなかったのである。これは、他地区の茶栽培にもいえることで、畦畔栽培が中心で規模の小ささを物語っている。
そして、本町の茶栽培の生産量は少なく、栽培農家の自家消費量にとどまり、商品として出荷されるまでには至らなかったのである。
しかるに最近10年間の日本の経済成長は著しく、消費経済の波は、農村の生活にも大きな影響を及ぼし、現金収入がなくては、一日として生活できない世の中になり、農家は現金収入を得る途を考え、換金作物の栽培に力を注ぐようになった。
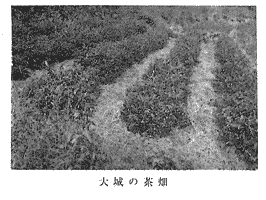 |
それから年とともに、少しずつではあるが栽培面積は増加してきてはいたがまだ、畦畔栽培から抜けでることはできなかった。
ところが、県内各地の人々の間に「峡南地方の茶は、静岡のものより品質、味ともによい。」と好評を得た。ここに本町においても、栽培面積の規模拡大が叫ばれ、町でも再び奨励し、昭和43年「やぶきた」の苗木と実を移入し、1町歩に植えつけさせたのである。
茶は7年たたないと摘めないが、先に植えつけられた「やぶきた」は、すでにその年月を経ているので、摘みはじめられており、以前よりも生産量は多くなってきている。
製茶技術も向上し、手もみから脱却して今は機械による大量生産が、大城の2工場、相又の1工場でなされている。3工場で約1万2千キログラムの生茶を加工するという。
生茶はやはり身延町が大部分で、豊岡地区の全部落と大河内地区の樋之上、大島、身延地区の波木井から運ばれ、1戸平均の量は30〜40キログラムぐらいである。
また、早川町、下部町などからも加工を依頼されるとのことである。
以上身延町の茶栽培について、述べたのであるが、問題点はいくつか残され、早急な解決が待たれている。

