第十二節 畜産業
一、畜産の推移の概要
日本の畜産業は最近世の所産である。すなわち仏教渡来以後の日本人は久しい間宗教的思想に禍いされ、乳・肉を食わない食慣習が徹底したためか、米、麦生産を主とする所謂「耕種農業」に依存して来た。従って家畜を飼育して栄養価の高い畜産物を生産したり、家畜の生産による自給肥料を利用しての農業生産の合理化を図ることを知らなかった。本格的に畜産を農業経営に導入して、合理的な農業をおしひろめたのは、明治初年の北海道開拓時代にアメリカ式の畜産を主体とする農業経営が始められてからのことである。以来日本の農業は畜産を伴う農業経営の線にそって逐年発達して来た。本町においては、明治以前の飼育家畜は馬だけであった。(表1参照)馬は、農村の必需品として確保しなければならない唯一の家畜であった。明治末期から大正初期にかけて、馬のほかに役肉牛が導入されて、馬とならんで厩肥(きゅうひ)の生産に、農耕作業に又、肉食用として、飼育されて来た。表2の町村取調書によると、(第一章町村取調書表参照)身延地区を除いて、下山、豊岡、大河内地区で飼われていた。特に、大河内地区では、馬より多く飼われていたことは注目すべきことである。豚・山羊・めん羊等の中家畜が、本町で飼育されるようになったのは、資料がなくつまびらかでないが、南巨摩郡の統計資料によると、豚は、明治35年(1902)、山羊は大正10年(1921)、めん羊は昭和9年から記録されているので、おそらく、本町においてはこれ以後に飼育されるようになったと推定される。
昭和25年から昭和40年までの本町の家畜の変遷は、表3に示す通りで、これによると、敗戦直後の経済事情の好転と国民生活の安定に伴って、濃厚飼料を必要とする、乳牛・豚・にわとり等がめだって増加した。
特に、乳牛、めん羊が脚光をあびて、各地区に組合が設立され、非常な勢で普及してきた。これと反対に、今まで農耕の主体として飼育されてきた馬・役肉牛は、農耕作業の機械化と、農家の労力不足の影響で、逐年減少をたどり、また一時普及した乳牛・めん羊等も、昭和35年をピークに、安定した世界経済の動きに刺激されて、経営に採算が伴わないために減退して今日に及んでいる。
表1 旧村の馬の頭数 (甲斐国志)
|
村名
|
頭数 | 村名 | 頭数 |
村名
|
頭数 |
村名
|
頭数 |
村名
|
頭数 |
|
粟倉
|
6
|
門野 |
4
|
光子沢
|
2
|
椿草里
|
3
|
樋之上
|
0
|
|
下山
|
60
|
大城 |
9
|
上八木沢
|
5
|
大崩
|
2
|
大島
|
18
|
|
波木井
|
32
|
相又 |
40
|
下八木沢
|
5
|
丸滝
|
20
|
|
|
|
大野
|
2
|
横根 |
2
|
帯金
|
30
|
角打
|
10
|
|
|
|
小田船原
|
8
|
清子 |
5
|
大垈
|
5
|
和田
|
12
|
合計
|
282
|
表2 旧町村の牛馬の頭数 (町村取調書 大正5年)
| 町村名 牛馬 |
下山 | 身延 | 豊岡 | 大河内 | 合計 |
|
馬
|
65
|
84
|
200
|
105
|
454
|
|
牛
|
35
|
0
|
20
|
150
|
205
|
|
計
|
100
|
84
|
220
|
255
|
659
|
表3 家畜家きん頭羽数の変遷 (農業センサス)
| 年次別 家畜名 |
昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 |
|
乳牛
|
2
|
22
|
40
|
25
|
|
役肉牛
|
30
|
54
|
61
|
12
|
|
馬
|
186
|
139
|
41
|
5
|
|
豚
|
203
|
381
|
102
|
390
|
|
めん羊
|
43
|
136
|
153
|
13
|
|
山羊
|
525
|
353
|
259
|
168
|
|
家兎
|
990
|
1,065
|
606
|
|
|
にわとり
|
2,327
|
8,162
|
6,649
|
10,427
|
二、畜産の現況
本町は、山野多く野草豊富であるが、経営規模が零細であるため、畜産の普及率は、極めて不振である。現況は表4の通りである。表4 家畜飼養の現況(昭和43年2月現在)
|
身延町
|
下山地区
|
身延地区
|
豊岡地区
|
大河内地区
|
|||||||
|
戸数
|
頭数
|
戸数
|
頭数
|
戸数
|
頭数
|
戸数
|
頭数
|
戸数
|
頭数
|
||
|
乳牛
|
1
|
7
|
1
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
役肉牛
|
3
|
3
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
|
|
馬
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
|
|
豚
|
繁殖豚
|
15
|
34
|
3
|
7
|
1
|
1
|
4
|
4
|
7
|
22
|
|
肥育豚
|
46
|
476
|
5
|
158
|
5
|
221
|
22
|
44
|
14
|
53
|
|
|
めん羊
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
|
山羊
|
70
|
73
|
12
|
12
|
7
|
7
|
20
|
21
|
31
|
33
|
|
|
うさぎ
|
95
|
289
|
8
|
17
|
13
|
56
|
6
|
14
|
68
|
202
|
|
|
鶏
|
6カ月
未満 |
64
|
12,241
|
4
|
40
|
17
|
1,222
|
26
|
1,708
|
17
|
271
|
|
6カ月
以上 |
399
|
7,030
|
74
|
408
|
81
|
2,632
|
66
|
2,051
|
178
|
1,939
|
|
|
ブロイラー
|
13
|
18,710
|
2
|
4,005
|
3
|
4,005
|
8
|
10,700
|
0
|
0
|
|
これによると馬・役肉牛・乳牛等の大家畜は、年々減退して、現在馬は4頭、役肉牛は3頭、乳牛は7頭である。また、山羊・めん羊・家兎等もわずかの農家で廐肥源として飼育している状態で、これらの家畜は、やがて本町から姿を消すことと考えられる。これにたいし、濃厚飼料を必要とする豚・にわとり等が肉需要の増大に伴って、逐年増加してきた。飼育方法も農家の労力不足と、飼育経費のコスト引下げの必要から、従来の小数飼育より多数集団飼育へと切りかえられて、効率的な経済性の高い経営へと移りつつある。
(一)養豚
農産雑物を利用して、1〜2頭を副業的に飼育するものが大部分であるがなかには経営を企業化して、専門的に多頭飼育するものが各地区にあらわれてきた。(表5、6参照)表5 肥育中の豚の頭数規模別農家数(昭和43年2月1日現在)
|
1〜2頭
|
3〜4頭
|
5〜9頭
|
10〜
19頭 |
100頭
以上 |
合計
|
|
|
戸数
|
32戸
|
3戸
|
4戸
|
5戸
|
2戸
|
46戸
|
表6 肥育豚出荷頭数の規模別の農家数と出荷頭数(昭和42年度)
|
9頭以下
|
10〜
15頭 |
100頭
以上 |
合計
|
総頭数
|
|
|
戸数
|
10戸
|
4戸
|
3戸
|
17戸
|
1,026頭
|
昭和38年には、身延町養豚組合が設立され、優良種豚の導入、制度資金の活用等に力を入れ、養豚の振興に努力したが、販売価額の変動によって、現在は期待した成果を見ることができない。しかし、最近における食生活の改善は肉需要を高めているので、本町における養豚経営は益々伸びる見通しがある。なお、今後の問題として、養豚組合の育成強化、市場取り引きの改善、ふん尿処理の合理化、生産調整対策や、防疫の徹底などがあげられる。
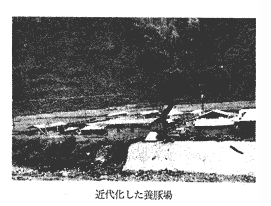 |
(二)養鶏
ア、採卵本町の採卵養鶏は、ほとんどが農家の残物活用で、羽数は、1戸平均5、6羽の少数飼いで、卵は自給用に供しているが、最近ケージ飼育の普及によって、表7に見られるように副業的に多羽化する農家が出てきた。養鶏経営も養豚経営とならんで、本町においては将来性がある。今後の発展策としては、卵価補償対策の確立が先決である。
表7 羽数規模別農家数
| 49羽以下 | 50〜99 | 100〜299 | 300〜499 | 500〜999 | 2,000〜 2,999 |
合計
|
|
|
戸数
|
390
|
4
|
1
|
2
|
1
|
1
|
399
|
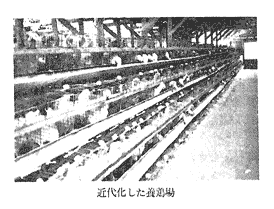 |
新家畜としてブロイラーは、昭和37年塩沢地区の坂本政雄によって始めて本町に導入され、以後、豊岡地区、下山地区に普及され、鶏肉の需要の増大と、気象条件その他の立地条件を生かして、逐年羽数が増加し、現在では、月産2万羽余飼育されている。昭和38年には、組合が設立され、一般農家の養鶏熱も盛んになり、自ら技術経営の研究等にとりくんだ。短期間に商品化され、飼料効率もよいという特色があり、その上に、また価格補償も確立されているので、取引価格の変動もなく、安定した経営ができるので将来更に伸びる見通しである。ブロイラー出荷羽数の規模別農家数と、出荷羽数は表8の通りである。
表8 ブロイラー出荷羽数の規模別農家数と出荷羽数
| 1,000 〜2,999 |
3,000 〜4,999 |
5,000以上 |
合計
|
総羽数
|
|
| 戸数 |
3戸
|
1戸
|
7戸
|
11戸
|
20,000
|
○ブロイラー組合
設立 昭和38年12月
組合員 11名
組合長 遠藤善男
飼育羽数 約2万羽
販売先 東京アサヒブロイラー富士宮支店

