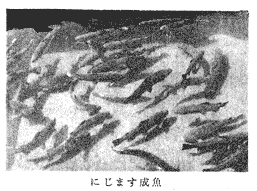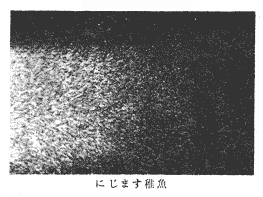第十三節 水産業
一、養魚の黎明
本町の養殖事業は、記録によると大正初期に下山地区で副業として、鯉飼育が行なわれたが詳細は不明で、現在養殖事業としては、大河内地区の椿草里で松野真一が、虹マス養殖をしているのみである。桃源養鱒場
所在地 身延町椿草里一番地
場主 松野真一
沿革
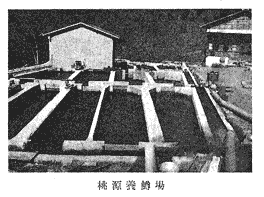 |
昭和32年、再度虹マス卵12,000粒を導入、増殖をはかる。生残った3匹より採卵に成功、養魚池1アールを建設。
昭和36年、60万粒を自家採卵、大小30余の養魚池を作る。
昭和38年、養魚池をコンクリート化。
昭和41年9月、台風26号により養魚池がほとんど全滅、親魚200匹、養成魚11万余匹を失う。
昭和41年、災害復旧、生残った親魚より108万粒を採卵し事業を継続。
昭和43年、半永久的養殖施設を建設。
現況と今後の計画
1 施設
コンクリート池 19面 (面積5アール)
孵化場 1棟 (面積0.4アール 水槽 7面)
魚飼料倉庫 1棟 (0.2アール)
2 養殖魚数
養成魚 約20万匹
育成稚魚 約70万匹
親魚 約500匹
採卵 約130万粒
3 生産量 年産8トン
将来は年生産量を25トンまで増やし、販路を拡大して身延、下部の旅館等の需要をまかなうこと、駐車場の完備による都会よりの観光客誘致を企画している。また、技術面では新品種の改良、特に年2回産卵魚の品種固定化などの研究にとりくんでいる。
二、漁業組合のうごき
(一) 富士川漁業協同組合の沿革
明治21年(1888)3月、富士川漁業取締法が、県令で制定され、簗(やな)、もりの取締りを行なった。明治35年(1902)9月、漁業法が施行され、県漁業取締規則制定公布した。
明治40年(1907)、漁業組合が設立され、淡水魚類の放流と、禁漁期間の励行を実施した。
昭和17年7月5日、富士川水系漁業組合は、時の山梨県知事高野源進を立会人として、日本軽金属株式会社社長中川末吉と次のような漁業補償の協定を締結した。
協定文
| 第一条 | 乙(日本軽金属株式会社)は、乙の富士川水系における水利使用発電事業に伴う一切の漁業損失補償として、甲(富士川水系漁業組合)に対し、十五万円を山梨県を介して、交付するものとす。 | |
昭和24年6月1日から施行した水産業協同組合法、昭和25年施行した漁業法等から内水面における漁業権が確立し、又更に、漁業協同組合の民主的運営とあいまって益々発展が期せられた。
現在の富士川漁業組合の概況は次のとおりである。
組合長 鈴木正巳 (昭和37、2、23、就任)
組合区域 鰍沢町の三郡橋から富沢町の県境まで
漁区 16.18平方キロメートル
組合員数 1,494名(内鮎会員500名)
事業 主たる事業は魚類の放流である。昭和43年度には次のような魚族を富士川の各河川に放流した。
鮎(ビワ湖産)四車 16万匹 約100万円
鯉 4万匹 約10万円
あまご(日光産) 50万匹 約5万円
(二)富士川漁業協同組合身延支部概況
身延第一支部支部長 松野弘一
組合区域 大河内地区(但し上下八木沢を除く)身延地区、豊岡地区
組合員数 500名
身延第二支部
支部長 鮎川 武
組合区域 上下八木沢地区、下山地区
組合員数 50名
事業
1、鮎、鯉、あまご等の魚族を本部から配給を受けて、身延町の各河川に放流して、魚族の繁殖増殖を図る。
2、ます釣り大会等を開催して、内水面漁業の向上発展に努める。
3、やまめの稚魚を魚影の少ない河川に、支部独自で放流する。
4、昭和44年3月1日から、椿川を禁漁区に設定し、既に放流済みの佐野川から採捕したやまめの繁殖を図る。
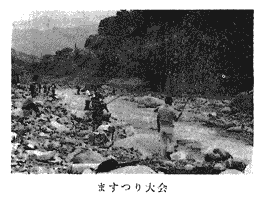 |