第十四節 商工業および発電事業
一、商工業
大正9年(1920)頃までは、甲州街道、駿州街道並びに、鎌倉街道、富士川の三道一水が、山梨県の大動脈であった。本町においては、東海道方面の生産物や塩などが、一切富士川を遡(そ)上して移入されたものであった。その頃の本町の商店は、商業とは名ばかりで、参拝者を主な対象としたものであり、その数も極めて少なかった。大正9年5月富士身延鉄道の開通以後は、商業はもちろんのこと、あらゆる面で一大変革をとげた。戦後二十余年間の本町の商工業の伸展は著しく、特に、最近は、経済成長と消費ブームによって、商業システムも変り、スタンプ・シールサービスや割賦販売を、併用する商法の増加したのが目立っている。概して、小売業は、兼業が大部分を占めている。
表1 身延町商業状況(昭和42年1月現在)
| 分類 |
戸数 |
従業員数 |
| 物品小売業 |
227 |
523 |
| サービス業 |
92 |
235 |
| 物品卸業(含 小売業) |
17 |
79 |
| その他 |
48 |
182 |
| 計 |
384 |
1,019 |
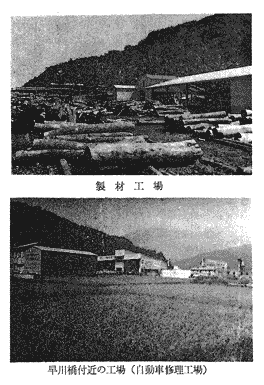 |
身延町の消費購買力106,967万円で、この内観光客流入購買力は32,417万円、流出購買力は57,762万円と推定される。
小売商品は、宗教関係を除けば特殊商品はなく、観光的商品もほとんどが他観光地で扱っている商品と変りばえしないものが多い。
また、戦後出現した新業種にガソリンスタンドがある。現在七ヵ所で営業しているがなお増加の傾向をたどっている。
以前には、水力利用の木製品工業が発生していたが動力源が電力となった現在では、製材工場10社がある。なお、足踏式の木魚製造所が、現在1軒残っている。しかしそれらは、いずれも小企業の域を脱していない。製材業は、素材を製品化するばかりでなく、最近では製紙原料のチップや、新建材等も扱っている。昭和42年には、新建材販売専門店も梅平に開業した。昭和のはじめ頃まで、製糸場が2、醸造業が3、そのほか湯ば、数珠、榧(かや)あめ、素麺などが製造されていたが、現在では、醤油を除いて、湯ば、榧あめなどが少量製産されるに止まっている。
最近自動車修理業と、鉄工業が増加し、鉄工業の事業量は、町内ばかりでなく東海方面にまでのびている。
砂利採取では、京浜地域の多摩川などの採取禁止以来、昭和42年頃より、富士川流域から盛んに採取されるようになって、現在町内に7社があり、年間約20万立方メートルを京浜東海方面へダンプカー輸送している。昭和42年下山に、ブロック製造工場が進出し操業している。昭和元禄の波に乗った業種として、庭石採石業1がある。
戦後町内には身延会館(元町)、商工会館(角打)、下山映劇(下山)の三常設映画館が開かれ一時は唯一の大衆娯楽施設として盛況を呈したが、昭和30年ごろからテレビの普及、レジャーの多様化におされて経営不振となり次々に閉館し、現在は角打商工会館が月に数回程度上映するだけで、全国的な映画斜陽化の姿は本町でもその例外ではない。
家庭工業としては、メリヤス製造、こけし製造など、下山地区にみられるが、小規模のものである。輸出竹工芸品製造工場が昭和42年小田船原に進出し、同年丸滝にメリヤス工場が新設され、さらに43年10月大野にテレビ用チューナー、スイッチの組立工場が町の誘致により進出した。次に製造加工業の状況を掲げる。
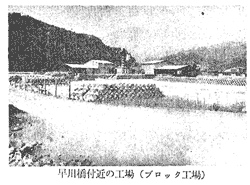 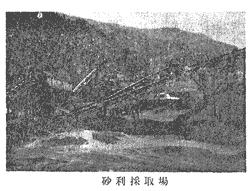 |
表2 身延町の製造加工業業種別の概況(昭和42.1.1現在)
| 業種分類 |
戸数 |
従業員数 |
製造取扱品目 |
| 製材業 |
10 |
164 |
製材、チップ、新建材 |
| オガライト製造業 |
1 |
7 |
オガライト |
| 木工業 |
10 |
37 |
木魚、家具、建具 |
| 工芸 |
2 |
10 |
竹工芸、こけし |
| 電器製造業 |
2 |
110 |
チューナー、ヒーター |
| プラスチック工業 |
1 |
5 |
合成樹脂可塑物 |
| ブロック製造業 |
1 |
16 |
ブロック |
| 生コン製造業 |
3 |
19 |
生コン |
| 印刷業 |
4 |
16 |
とっ版、オフセット |
| メリヤス業 |
2 |
36 |
横編メリヤス、外衣 |
| 醸造業 |
2 |
11 |
醤油、清酒 |
| 製めん業 |
2 |
5 |
めん類 |
| 製畳業 |
1 |
6 |
畳、畳床 |
| 印刻業 |
13 |
24 |
|
| 鉄工業 |
5 |
27 |
|
| 修理製造業 |
10 |
37 |
自動車、自転車修理 |
| 石材加工業 |
2 |
5 |
|
| 塗装業 |
1 |
3 |
|
| 表具 |
2 |
2 |
|
| 左官業 |
3 |
13 |
|
| 砂利採取業 |
7 |
35 |
砂、バラス、礫 |
| 庭石採石業 |
1 |
8 |
|
| 紳士婦人服仕立 |
13 |
18 |
|
| 豆腐製造 |
5 |
9 |
|
| 菓子製造 |
4 |
8 |
|
| 製靴 |
3 |
5 |
|
| 精米 |
7 |
7 |
|
| 素材 |
6 |
6 |
|
| 木製品 |
2 |
2 |
|
| 家具建具 |
8 |
8 |
|
| 板金 |
2 |
5 |
|
| 土木建設 |
22 |
不定 |
|
| 電気工事 |
5 |
8 |
|
| 合計 |
162 |
672 |
二、技能士制度
昭和34年に技能士検定制度が始まり、身延町商工会の設立された昭和35年11月以来急速に資格取得受験者が増加した。1級技能士の受験資格は中学校卒業者で実務経験15年以上、2級は7年の実務経験を必要とし、実務と学科試験にパスすることによって1級技能士は労働大臣から、2級技能士は県知事から資格免許が与えられる。町内の資格取得状況は次表のとおりで、中でも清住町の田中定光は寺院建築の優秀な技術と功績が認められ、昭和43年山梨県知事から表彰されている。この外職業訓練指導員資格試験があり、受験資格は、実務経験15年以上の者で35時間の講習受講、または学科試験合格によって県知事から与えられる資格で町内の資格取得者数は次表のとおりである。
表3 身延町の業種別技能士検定合格者数 (昭和44.4現在)
| 1級 | 2級 | ||
| 建築大工1級技能士 | 20名 | 左官工2級技能士 | 1名 |
| 洋裁工1級技能士 |
1
|
更生タイヤ工2級技能士 |
1
|
| 建具1級技能士 |
1
|
建築塗装工2級技能士 |
1
|
| 畳工1級技能士 |
5
|
板金工2級技能士 |
3
|
| 左官工1級技能士 |
4
|
畳工2級技能士 |
2
|
| 時計修理工1級技能士 |
3
|
||
| 鉄工1級技能士 |
1
|
||
| 表具工1級技能士 |
1
|
||
表4 身延町の業種別職業訓練指導員資格者数(昭和44.4現在)
| 造園工職業訓練指導員 |
1
|
畳工職業訓練指導員 |
1
|
| 鉄工職業訓練指導員 |
1
|
建築大工職業訓練指導員 |
31
|
| 時計工職業訓練指導員 |
2
|
表具工職業訓練指導員 |
1
|
| 配管工職業訓練指導員 |
1
|
洋裁工職業訓練指導員 |
2
|
| 印刷工職業訓練指導員 |
1
|
板金工職業訓練指導員 |
2
|
| 印章彫刻工職業訓練指導員 |
1
|
洋服工職業訓練指導員 |
6
|
| 木工職業訓練指導員 |
5
|
更生タイヤ工職業訓練指導員 |
1
|
| 電工職業訓練指導員 |
3
|
自動車整備工職業訓練指導員 |
1
|
三、発電事業
(一)発電計画
大正10年頃、富士川水力発電事業は、実業家50余名が発起人となって官許を申請した。その内容をみると、第1期は、大島から佐野川に落水し、第2期は清子から佐野川に落水し、第3期は、清子から南部に落水し、第4期は南部から蒲原に落水して、電力136,000馬力の発電が計画されていたことがわかる。大正15年(1926)2月富士川沿岸有志多数が、富士川の治水改修を理由に、猛反対したため実現されなかった。このほか、富士川から取水する発電計画に、甲府電力会社および富士身延鉄道会社の、西島から波木井に落水して30,000馬力、東京電力会社の波高島から清子へ落水して23,000馬力などの計画もあったが、富士川の清子から上流における水利権は、絶対許可されないこととなったため、この計画も中止となった。 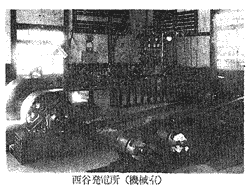 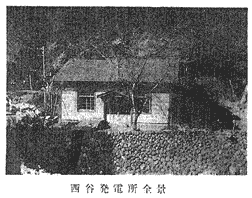 |
(二)身延電灯会社
本町の電灯は栄村(南部町栄地区)の近藤修孝、若林宏明等が中心となって身延電灯会社を設立し、明治45年(1912)4月身延西谷旧祐浄坊跡へ、宇馬の背から身延川上流の水を引き入れ(落差130メートル)て発電所の建設を着工し、大正2年4月30日送電(出力55キロワット・60サイクル)を開始したことにはじまる。開業式には小泉法主をはじめ熊谷知事も出席し、また、身延小学校児童600名も参列して、花火の打揚げや楽隊の吹奏も行なわれるなど盛大なものであったという。
この電灯の出現によって、村民生活にもたらした影響は甚大であったであろうことは想像に難くないのであるが、開業式当日小泉法主の祝辞に「幾千の電燈燦然として俄かに光明を放ち夜猶昼の如し乃ち宗祖遺愛の山水を照らし大士棲神の幽蹤に輝く以て涅槃不滅の無尽燈に擬すべく生死長夜を照す大灯明にも比すべし」、とあるをみても大きな感激であったであろうことが察しられる。
文明の光電灯は、まず本山をはじめ門前町に点灯し次第に各方面に延びていったのであるが、翌大正3年(1914)1月20日には下山へも延長されて200灯がついたと記録されている。
この身延電灯会社は大正10年(1921)10月静岡電力会社と合併し、静岡電力会社は大正15年(1926)4月に東京電力と合併し、東京電力は昭和3年(1928)4月に東京電灯となり東京電灯は昭和17年(1942)4月に関東配電となり、さらに関東配電は昭和26年5月日本発送電株式会社と合併して現在の東京電力株式会社となったのである。
西谷の発電所はサイクルの統一によって50サイクルに切りかえられたため昭和初期からは休業し、昭和24年には解体された。
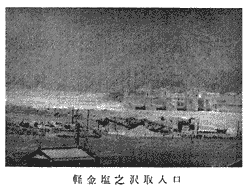 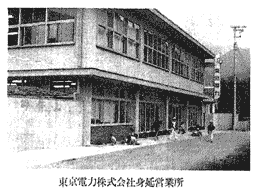 |
(三)日本軽金属株式会社波木井発電所
昭和13年(1938)1月日本軽金属株式会社によって着工された波木井発電所は、下山地内粟倉増野で早川の水をトンネルで取水し、昭和14年(1939)1月完工、発電量19,900KWで、蒲原にある同社アルミ製造工場に送電しており、余剰電力は、商業電力用に供給している。また、同社蒲原発電所は、富士川の水を塩之沢から取水している。 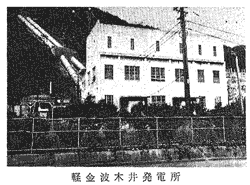 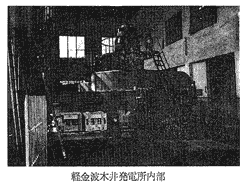 |

