第四章 観光
第一節 概説
一、観光の概要
身延山を中心とする本町の仏都観光事業のきざしは、今を去る700年の昔、宗祖日蓮大聖人が、身延へ入山されたときからはじまるということができる。日蓮聖人ご在山当事から全国各地より弟子、檀越、信徒をはじめ、多数の有名人が往来して、聖人を慕い、身延の風光を愛し、参籠(宿泊)し、身延みやげを購(あが)なって帰ったのである。
大正15年(1926)山梨県庁庶務課内に景勝開発係が設けられ、岳麓・御獄昇仙峡とともに身延地区も全県的な規模のもとに具体的な観光開発計画がすすめられ、昭和11年(1936)交通の発達とともに、観光山梨がようやく軌道にのり、山梨県の観光宣伝に身延も大きく取りあげられ、民謡に観光小唄に、身延の風光が必ず歌われていた。
戦時中は経済統制が強化するにつれて、観光事業はかえり見られなかったが、身延山には戦勝祈願の参詣者が増加して来た。
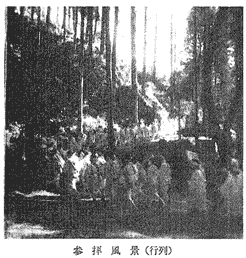 |
また、日蓮聖人の伝記など身延に関する出版物が昔から多数あって、これを題材にした芝居・映画・能楽・音曲・舞踊・演芸などがあり、日蓮聖人とともに身延の風光が広く宣伝された。京都深草の元政上人の「身延道の行記」、十返舎一九の「身延道中記」など、詩文や紀行文によっても身延は広く宣伝されていったのである。
最近のテレビなどにも身延道者のでてくる場面が多く見られ、身延は日蓮聖人のお山として全国的に知られ、身延山や七面山を中心とする身延町の観光は「心のふるさと」、宗教のメッカとして、信仰に支えられながら発展してきたのである。
観光は国際平和と国民生活の安定を象徴するものであり、社会的・文化的・経済的に極めて重要な役割を果たしている。
観光基本法にも見られるように、観光は恒久の平和と、万民相互の理解を深めることを念願し、健康で文化的な生活を享受しようとするものである。その意味では、身延への観光は仏教の目標に近づくための一手段であるといえる。
仏都身延の観光の目標は、霊域を護持し風光を宣伝するとともに、来山者の利便を増進し、気持よく身延山に参詣できる幸を深くあじわえるようにし、さらに正しい信仰に励むことに、自分も励み、人にもすすめるようにすることであり、身延の信仰と観光との関連は、次のように考えられる。
1、身延の参詣(観光)は、この身延山を真の霊山として護持(資源の保護育成と美観風致の維持)することに眼目がある。
2、正しい信仰を広める(紹介宣伝)
3、人々の心のふるさと(旅行者の安全と利便の増進、接遇の向上、施設設備の整備)とする。
このために、僧(山)俗(町方)異体同心となって、身延山(身延町)の発展に精進している。この姿が仏都身延の観光のあり方である。 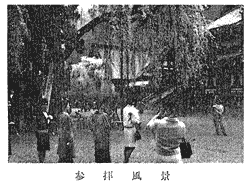 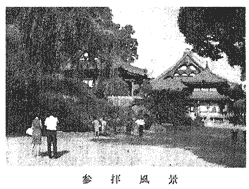 |
二、身延山と参拝観光団体
(一)身延山
日蓮聖人は、身延ご在山中に、身延山を賛(たた)えた数多くの御文書を残されているが、そのなかで「我此山は天竺の霊山にも勝(すぐ)れ、日域の比叡山にも勝(すぐ)れたり、然れば吹く風も、ゆるぐ木草も、流るる水の音までも、此山には妙法の五字を唱えずということなし。日蓮が弟子檀那等は此山を本として参るべし」(波木井殿御書)と述べられ、身延山を、釈尊の法華経を説かれた霊鷲山に比定し、事の寂光土と観ぜられ、霊土さながらの景勝の地とされていることが、身延山御書(建治元年)にも見られる。かくて日蓮聖人は、弘安5年(1282)ご入滅のさい「たとひいづくにて死に候とも、九箇年の間心安く法華経を読誦し奉り候山なれば、墓をば身延山に立てさせ給へ。未来際までも心は身延山に住むべく候」(波木井殿御書)と遺言され、身延山こそ日蓮聖人の御魂を留めている唯一の霊山とされたのである。
日蓮聖人と身延山との関係は、いかに深いものであるかは、他の編で述べているが、日蓮宗では身延山を総本山(祖山)と仰ぎ、全国の寺院・教会・檀信徒はこの山を中心として、また宗門に属していない日蓮聖人の教を仰ぐ人々も、全国から参詣している。このため身延山は仏法の都としてあまねく全国に知られ、一般観光旅行者も、多く身延を訪れているのである。
身延山は、東谷・西谷・南谷・中谷・鶯谷・醍醐(だいご)谷・金剛谷・蓮華(れんげ)谷の八つの谷(みのぶはっさく)にかこまれ、高さ21メートルの三門、287段の菩提梯(ぼだいてい)を登ると、身延山久遠寺がある。奥之院思親閣は、これから4キロメートル登りつめた海抜1,153メートルの身延山頂にあって、ここから、23キロメートルの奥に海抜1,989メートルの七面山がある。
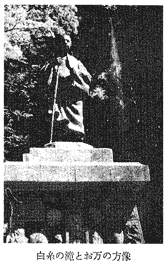 |
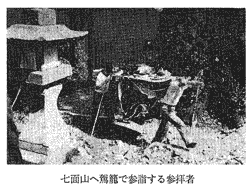 |
久遠寺では、大正13年(1924)の電話の架設をはじめとして、消火栓や、自動火災報知器などを整え、奥之院では、昭和24年電気が、昭和36年水道が、同41年には大孝殿が完成し、七面山も昭和16年(1941)に電気を引込み、同34年に電話を、43年には、水道工事が完成して、ともに近代設備を整え、昔日の不便さは一掃された。
(二)参拝観光団体
開山当初は、6老僧が給仕していたが、後に輪番制(日蓮宗各寺を中心とした檀信徒が順番に身延山へ、参詣しながら給仕する)となって、団体参拝の形を整えはじめたのである。関所が存在していた頃の往還も、身延まいりの通行札を所持することによって、容易に通過できる特典もあり、白装束に身をつつみ、数珠をかけて、うちわ太鼓に合わせて唱題しながら身延に参詣した姿が想像できる。戦後は交通の発達とともに観光ブームと相まって、点から線へ、さらに面への観光へと移行してきたため、身延山参拝を主目的としないいわゆる一般観光客も、そのスケジュールの中へ組み込んで立ち寄る客が、年々増加の一途をたどっている。昭和38年身延山ロープウェイの架設によって、信者とともに一般観光客や、老人幼児で奥之院まで、たやすく参拝することができるようになった。身延線の開通(大正9年)する以前は、わらじをはいて、身延参詣をしたもので、この頃、富士川を端舟(はしぶね)がかよっていた。後に飛行艇も現れたが、今は全くその姿を消して、国鉄電車や、貸切バスを利用して、北は北海道、南は九州から、大団体で来ることも多く、観光客とともに、あらゆる面で近代化しつつあるといえる。
来訪客は、年間約90万人で、この内参拝団が約60万、一般信徒および観光客は、30万にすぎない。利用する交通機関別にみると、貸切バスの団体参拝が約30万、国鉄利用が約40万、自家用車その他20万で県内観光地に比し伸び率は最低である。
身延山の信徒団体には「身延山本願人会」「身延会」など多数の講社があり、毎年のように身延山へ参拝している。このほかに、日蓮宗霊断師である住職が、信徒とともに結成している「日蓮宗聖徒団」や、教団としては、霊友会、立正佼成会、妙智会、仏所護念会、霊法会など多くの団体が身延山へ毎年団体参拝をしている。そのほか、参詣者のなかには高位高官、芸能文化人などさまざまで、山内には、この人々の歌や詩・彫刻・絵画などが数多く残されている。
表1 日蓮宗関係主要教団体
|
教団名
|
人員
|
|
霊友会
|
450万人
|
|
立正佼成会
|
80万人
|
|
妙智会
|
60万人
|
|
仏所護念会
|
50万人
|
|
実顕会
|
34万人
|
|
大慈会
|
32万人
|
|
孝道教団
|
30万人
|
|
霊法会
|
27万人
|
|
思親会
|
27万人
|
|
妙道会
|
20万人
|
|
計
|
810万人
|

