第二節 観光地の紹介
第七編教育と文化第六章などに詳述しているので、ここでは一部にとどめる。一、遺跡
逢(おう)島の遺跡総門付近一帯を逢島と呼び、文永11年(1274)5月17日、日蓮聖人が鎌倉から身延ご入山のさい、領主波木井実長(南部六郎実長ともいわれた)がここに、お出迎えし、ご対面され身延山寄進の約束をされたという歴史的故事から逢島と呼ぶ。聖人が、この時ご休息されたという「腰掛石」は、今もなお玉垣の中に静かにその姿をとどめている。この付近には、天然記念物に指定されている「仏法僧」の繁殖地がある。
日蓮聖人追孝の地
九ヵ年の間、日夜父母恩師を慕い、常に五十余町の峻坂(しゅんぱん)をわけ登り、遥かに東方、房州を望みながら、報恩の回向(えこう)を捧げた遺跡で奥之院思親閣がある。
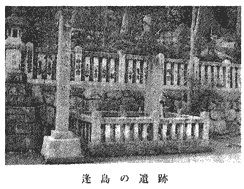 |
「日蓮は、日本六十六ヵ国、島二つのうちに、五尺に足らざる身を一つおきどころなく候ところ、波木井殿のおんはぐくみにより、九ヵ年の間身延山にして心安く法華経を読誦し奉り候山なれば」(波木井殿御書)とあるように、円実寺は日蓮聖人身延山ご入山のみぎり、わらじをぬがれた所で、もっぱら山号で知られている由緒寺の一つである。
大野山本遠寺
本遠寺は、身延山第二十二世心性院日遠上人隠栖の地、開基紀州水戸両家の生母、養珠夫人「お万の方」が報恩のため、一大伽藍を建立して寄進された寺で、上人の法華経行者として正法正義のため家康の勘気にふれた、涙の物語りが伝えられている。またこの寺は「お万さん」とも呼ばれ、お万の方を婦女子の亀鑑として、今もなお多くの参拝者が絶えない。
いちょう寺
例年8月16日愛宕神社のおまつりに打ちあげる「下山の花火」と「お葉つき銀杏」は古くから有名である。上沢寺は「いちょう寺」として知られ、樹齢700年のこのいちょうを文部省は昭和4年天然記念物に指定した。枝が下に垂れさがっていることから「さかさいちょう」とも呼ばれ、葉と実は霊薬とされ、「日蓮聖人の身代りとなった白犬」の伝説がある。
二、名勝
枝垂桜(昭和44年4月町の木に決定)身延山内には、樹齢およそ100年を経たといわれる約200本の枝垂桜が点在している。なかでも、久遠寺境内にあるものは、樹齢約200年、樹勢もおとろえぬまま、今もなお、3月末頃、爛(らん)漫と咲きつづけている。
千本杉
約200年から、300年位の樹齢をもつ大杉が、260本林立して、樹木成長の極致、高さ40メートル以上にも達している。昭和7年(1932)農科大学の嶺学士の調査で、世界一の美林と折紙をつけられた。今上天皇陛下播種の「天皇杉」もこの付近に植林されている。
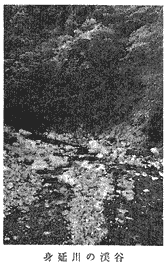 |
三門から祖廟霊域を経て雨乞いの滝に至る2キロメートル程の間は、新緑紅葉が極めて美しく、霊地をいろどる。このあたりの嶺を「蓮華峰」と呼び四季の風情(ふぜい)も格別で、とくに霖雨の風景は、一ぷくの山水画をおもわせる趣きがある。この渓谷に「雨乞の滝」と呼ばれた所があり、高さ8メートル、七面山三十三滝の一つに数えられ、行場として知られていた。日蓮聖人が、この滝で雨乞いの行(ぎょう)をしたという伝えからこの名があった。昭和34年、この付近に治水工事が施され、大堰堤が築かれている。
錦が森
上の山丈六堂付近は「錦が森」と呼ばれ、杉、檜の常盤木と、かえで、もみじなどの紅葉樹が植えられていて、紅葉は特に見事なものである。
安倍峠ハイキングコース
大城と静岡市の梅ヶ島温泉を結ぶ安倍峠は、山梨県と静岡県の境にあり、標高1,416メートルで落葉広葉樹林が多い。頂上は平坦地が続き、繁茂した熊笹や常緑多年生の灌木の中から老木が天を突き、八紘領(こうれい)、七面山の尾根が続いていて、美しい富士の姿が望まれ、春の新緑と秋の紅葉がことのほか美しく、ハイカーで賑わっている。ここを源とする大城川の渓谷は、山女魚(やまめ)の釣り場として太公望で賑わうところである。
 |
三、建造物
総門草創は、寛文5年(1665)9月、寿応院殿妙相日覚大姉の御志として、建立され、三河国刈谷城主三浦家の定紋が、表柱につけられている。「開会関(かいえかん)」の大額は、日潮上人の御筆によるもので、開会とはすべての人々を成仏せしめる意味で、この関門以内は寂光浄土でだれでもさとりを得ることができるということである。
三門
創立は、寛永19年(1642)で、慶応元年(1865)と明治20年(1887)に火災にあい、明治40年(1907)再建したもので、間口42メートル、奥行10メートル、高さ21メートル、豪荘の気横溢(おういつ)した大建築物である。二王尊を祀るので二王門とも呼び、二王尊は相州六浦上行寺にあったものを、六浦平次郎入道が寄進したと伝えられている。なお楼上に十六羅漢を安置してある。
菩提梯(ぼだいてい)
天上に登るような高い石段は菩提梯と呼ばれ、高さ105メートル、287段あって、南無妙法蓮華経の7つに分割されている。寛永17年(1640)ころ佐渡の信者、仁蔵という人が発願し、子孫数代にわたる悲願によって、完成したものである。
祖師堂
宗祖日蓮聖人の御尊像を奉安する祖師堂は、またの名を棲神閣とも呼ばれ、明治14年(1881)日鑑上人代に再建された久遠寺の最大建築物で、間口22メートル、奥行36.4メートルのお堂である。奉安の宗祖像は、中老僧日法上人が身延山中の霊木をもって、斎戒沐浴一刀三礼の式にのっとり、心血をそそいで彫刻した慈眼威容儼然たる尊像である。内陣の虹梁には、昭和6年(1931)今上天皇陛下ご下賜の「立正」の御勅額が輝いている。拝殿正面の「棲神閣」の大額は日鑑上人の御筆である。
身延山聖園
昭和41年、財団法人として身延山聖園が発足し、東谷東南の丘陵「寺平」に堀内良平の墓所をはじめ、100基程の墓碑があり、目下開発計画がすすめられている。
四、行事
(一)観光行事のはじまり(節分会)
本町においては、宗門に関する数多い行事表2の外は、昭和2年(1927)町内有志によって、三門で節分会(豆まき)を行なったのが観光行事のはじまりといえる。第1年次は、80円の赤字を出したが、第2年次からは、黒字となって、三門堂宇の畳替えなどに充てた。第4年次の昭和5年(1930)には、規模を拡大して、久遠寺境内で実施するようになった。以来戦後の5年間は実施されなかったが、現在まで節分会奉賛会が主軸となり、毎年続けられ、節分に集まる1日の信者の数が年々増加して、事故の起る危険性を生じたので、4−5年続けたアトラクションを昭和42年から廃止した。ちなみに昭和43年節分会には、30,000人の人出と報道されたが、集まった自家用車は、門内の指定駐車場のほか、門外も梅平地内通学橋から、小田船原公民館下までの国道上に連なって駐車した程の人出であった。 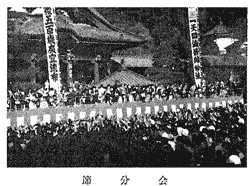 |
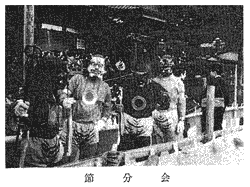 |
(二)納涼身延花火大会
身延町観光協会が行なった最大行事としては、昭和40年8月1日、大野の富士川河原で実施した花火大会がある。夏の夜空をいろどる仕掛花火や、打上げ花火約百本余り、過去本町内で行なった花火では、最大規模のもので、近在からも見物客がくり出して、身延駅通り商店街の飲食商品が底をつくほどの盛会さであった。(三)身延の七夕まつり
戦前戦後、各戸思い思いに飾りつけていたが年々にぎやかさを増し、昭和30年頃が最盛で、近郷でも有名だったが、時期的に盆行事と重なり、人手不足も加わって衰微し、近年クローズアップした平塚(神奈川県)や仙台(宮城県)とは反対に名をひそめてしまい、往年の盛況さはみられなくなった。 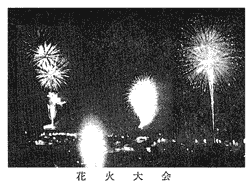 |
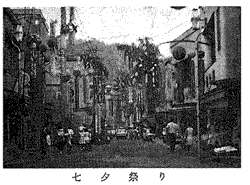 |
(四)万灯
池上本門寺のお会式に行なわれる万灯が、身延でも行なわれるようになったもので、身延山のお会式や、上の山八幡祭典には、つまびらかではないが、かなり古くから門内の各区が当番をもちまわりで行なわれている。万灯はお灯明であり、日蓮聖人が貞応の蓮華にむかえられ、弘安の桜花におくられて一元万了されたことから花を用いるのである。表2 身延山行事表
| 1月 1日 元旦祝祷会 1日−7日 新年読誦会 13日 御頭講会 2月 節分の日 節分会 10日 大荒行出行会 15日 釈尊涅槃会 16日 日蓮大聖人御降誕会 3月 春分の日を中心に7日間 春季彼岸会 4月 6日−8日 千部会 28日 立教開宗会 5月 6日−8日 釈尊御降誕会 12日 伊豆法難会 6月 1日 御更衣式 15日−17日 開闢会 7月 13日−16日 盂蘭盆施餓鬼会 8月 18日 英霊追悼施餓鬼会 9月 12日 竜口法難会 17日−19日 七面山開闢会 秋分の日を中心に7日間 秋季彼岸会 10月 1日 御更衣式 11日−13日 宗祖御会式 11月 1日 大荒行入行会 11日 小松原法難会 12月 8日 釈尊成道会 31日 歳末読誦会 |
 |
 |

