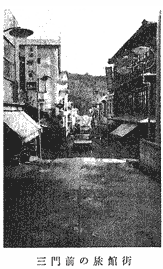第三節 観光施設および観光協会の活動
一、旅館・宿坊・みやげ店
旅館は、大正の初期までは三門付近に5軒ほどであったが、大正10年(1921)日蓮聖人生誕700年慶賛事業が行なわれるのを転機に逐次ふえはじめ、現在では門内に9軒、身延駅付近に5軒、その他2軒で、近代的改造を加えた旅館も2、3ある。身延山内には、万治年間(1658−1660)坊舎が128坊あって、行事坊と宿坊とに区分されていたが、明治中期頃までに現在の35坊に合併された。このうち宿坊は、23坊が西谷、東谷、中谷に分散している。なかでも昭和42年近代的に改造を加えた清水坊会館や身延山荘(南之坊)などは、時代に即した参拝客の要求に応えた新らしい行き方が注目されている。
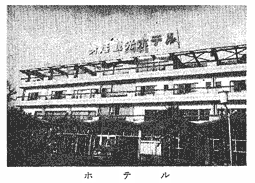 |
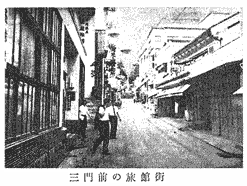 |
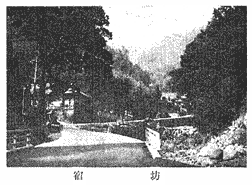 |
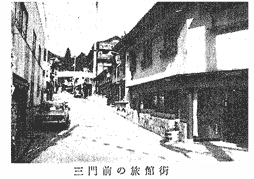 |
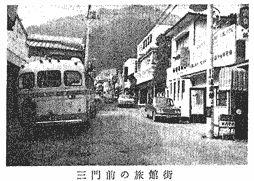 |
|
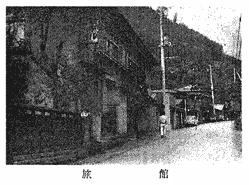 |
三門前近くには、旅館、飲食店とともに、みやげ物販売店が軒を並べている。身延みやげには、仏具、お経本、水晶細工、身延こけし、ゆば、しいたけ、ようかん、まんじゅうなどがある。
表1 身延の宿
|
施設別
|
場 所
|
計
|
収用能力
( )内は団 体の場合 |
|||||
| 門前 | 駅前 | 東谷 | 中谷 | 西谷 | その他 | |||
|
旅館
|
7
|
5
|
|
|
|
4
|
16
|
877
(1,487) |
|
宿坊
|
|
|
7
|
4
|
9
|
|
20
|
1,200
(2,000) |
|
山籠
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
(1,300)
|
|
ユースホステル
|
|
|
|
|
1
|
1
|
2
|
(115)
|
|
計
|
7
|
5
|
7
|
4
|
10
|
6
|
39
|
2,077
(4,893) |
二、休憩所
総門内には、参詣者の休憩所としてのお茶屋がいくつもあったが、今は近代化されて、飲食店、食堂などになっている、また、みやげ店のなかには、休憩所を店内につくったものもある。山内の坊も参詣者の休憩所として利用されている。このほか久遠寺では、総門の茶堂と、久遠寺総受付前の清興殿が休憩所として使用されていたが、清興殿は昭和27年火災により焼失してしまった。大客殿は一般参詣者の休憩所に使用されている。身延駅構内に国鉄が、昭和34年休憩所を構築したが、昭和36年身延線管理長誘致により今は改築して、庁舎にあてられている。
三、駐車場
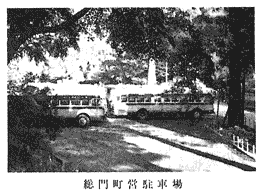 |
四、案内所
三門前広場に、昭和27年立教開宗700年慶賛事業が行なわれたとき、町観光協会により「身延山案内所」が設けられたが、昭和30年に閉鎖された。上町に民間の「身延山案内所」があり、参拝、観光客の紹介や案内に応じている。このほか身延山久遠寺をはじめ山内の宿坊・旅館・みやげ店などでも参詣者の要望によって、案内の便宜をはかっている。また七面山参拝客には要望によっては、強力(ごうりき)(荷物等の運搬人)を兼ねて案内にあたっている者もある。五、公衆便所
昭和30年頃総門わきに立正佼成会がつくった簡易公衆便所をはじめ、三門前などにもあったが、来訪客の増加とともに必要に迫られ、昭和40年身延町によって、総門および三門前に水洗浄化式のものが設置されている。そのほか、久遠寺境内にも近代的な公衆便所が設置されている。六、奥之院周遊道
奥之院思親閣を中心としての遊歩道は、昭和42年3月身延町によって開かれ、表側からは、富士川流域を眼下に、富士山、駿河湾が眺(ちょう)望できる。遊歩道に入ると七面山、南アルプスをはじめ、はるかに、甲府盆地や、八ヶ岳、さらに真下には雄大な早川渓谷(けいこく)が俯瞰(ふかん)できる。 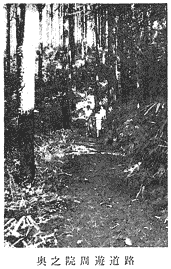 |