第三節 教育委員会
一、教育委員会発足と変遷
戦後新憲法によってうたわれた地方自治の本旨に沿うべく、地方自治制度についての種々の改革が行なわれ、教育の物的管理、人的管理、運営管理を地方公共団体が担当することとなり、各種の法律が制定された。ことに、その原則を明確に打ち出したのが教育委員会法であり、教育委員会の設置によって新体制が実施されることになり、教育行政における地方自治の理念は、昭和23年、教育委員会法が制定され、更に、昭和27年11月、全国の市町村に教育委員会が設置されて、はじめて実現されたということができる。本町の前身である、下山村・身延町・豊岡村・大河内村においてもそれぞれ27年10月、教育委員の選挙が行なわれ、昭和27年11月1日教育委員会がそれぞれ発足した。
教育委員会の構成は、公選による任期4年の委員4名に、議会議員より1名が加わり、教育長は別に任命された。事務局は各町村とも教育長と書記1名によって構成された。
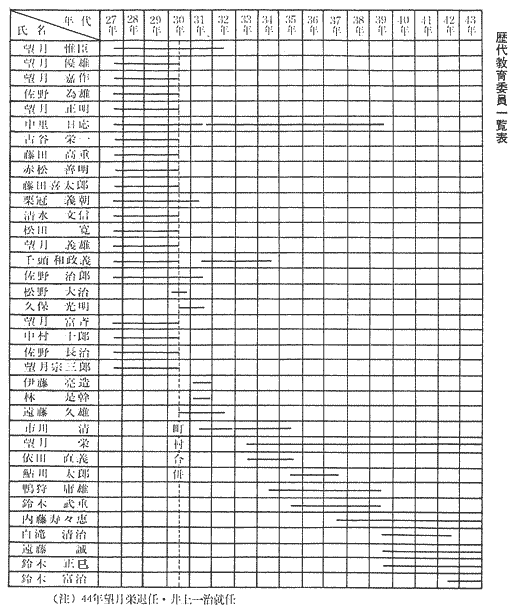 |
昭和31年9月、教育委員会法が改正され、同年10月1日より新しい教育委員会が発足した。新委員会の委員5名は議会の同意をえて町長が任命し、教育長は、委員の中から県教育委員会の承認をえて委員会が任命することとなった。
 |
二、教育委員会の活動
地方公共団体が処理する教育、学術文化に関する事務は極めて広範多岐にわたるものであるが、これら教育関係の事務については、その政治的中立を維持するということが強く要請されるものであり、また事の性質上、行政の安定が必要とされるので、その運営には各委員の調和と連携を保ち、所轄行政庁の助言を得ながら地域性を生かし、民主教育の確立をはかり、教育の中立性を堅持し、学校の管理、教育予算の要求、教員人事、社会教育の施策の指導等教育全般にわたる行政を行なってきた。特に合併後の教育委員会は、施設、設備の充実に意をつくし、下山中学校舎・身延小中学校・豊岡小中学校・大河内中学校の屋内運動場・下山中学校・大河内中学校・身延小学校・帯金小学校のプール、身延地区公民館・豊岡地区公民館・下山地区公民館の建設を行なって来た。また特筆すべきは、学校給食の実施である。昭和35年、下山小学校、豊岡小中学校を初めとして38年度まで4ヵ年で管下小中学校全校に完全給食を実施し、児童生徒の体位、体力の向上と食生活の改善につとめてきた。
また、昭和34年の台風7号には、管下小中学校が大災害をこうむり特に豊岡中学校校庭が流失、復旧途上において、台風15号で再度流失するという災害をうけたが間もなく復旧した。
更に各種の条例・規則・規程を定め、物的・人的・運営の管理を行ない、近代的教育の振興に尽くしてきた。
三、事務局
教育委員会発足と同時に事務局が設置され、教育長の指揮監督のもとに教育事務に従事して来た。町村合併により事務局も統合され、身延小学校内に事務局をおき、執務して来たが、昭和35年、役場内に移転した。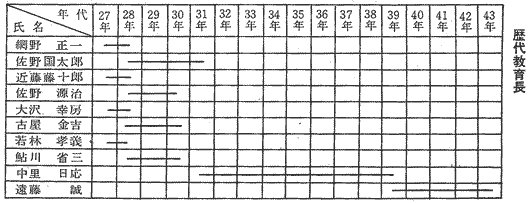 |
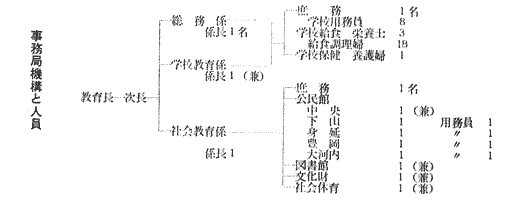 |

