第二節 寺子屋私塾
一、本町における寺子屋、私塾の状況
本町で開設された寺子屋・私塾は多くの文献と町内在住の古老を通じての調査によると、次に掲げるとおりである。その個々をみるに、それぞれ異色のある経営、維持がなされている。しかし、その教育の対象者は一般庶民の子弟とはいっても、実際は一部篤志者の子弟であり、そこに学んだ子弟の数は多いところで六十余名、少ないところで20名位であった。
このうち女子の数は、どこをみても極めて少なかったのである。
| 本町における寺子屋、私塾一覧表 | 空欄−不詳個所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料の収集にあたり、町内に度々火災があったことや経営者の子孫が他府県へ転居したり絶家したものなどがあったりして、その詳細を知ることができない個所があるのは誠に遺憾である。
前記のもの以外に自宅に近隣の子弟を集めて私塾を開設したものとして、山梨県誌編さん会発行の私塾寺小屋に大河内村の伊藤政十郎、片田傅三郎、市川重門、鈴木平左衛門、滝川得平、松野武兵衛、佐野祥友等の名が見えるが詳細はわからない。
二、寺子屋、私塾の教育の実態
先に記した寺子屋、私塾の教育の実態を要約すると次のようであったと考えられる。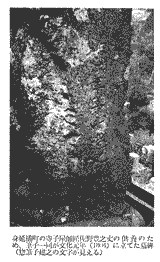 |
(一)寺子屋・私塾の師弟関係
教師のことを「師匠」とよび、就学する児童を「寺子(てらこ)」又は「筆子(ふでこ)」とよんだ。師とは単に知識や技能を授けるという以上に人格的な指導者という高い意味をもち、師の恩は親の恩にまさるとされた。
師弟の関係は絶対的で一たん結んだ以上は生涯消えないとされた。
師は弟子を温情で導き、弟子は師に対して献身するので、その関係は現在の教師対生徒の考え方とは全く違った一種の身分的なものであったと解せられる。
寺子屋の師匠になるには学識素養さえあれば特別の資格はいらなかった。
おそわる方も個人目的だったのである。
就学する目的は無知文盲では役に立たないという実生活上の必要からでたものであった。
(二)師匠の学識素養
本町の寺子屋・私塾の師匠をみるに下山に穴山氏の居館のあったことや身延に隠棲した日蓮聖人のおひざもとで教化を受けたこともあって、医師・僧侶・神官および文筆にたけた篤学の人々等とまことに多士済々(せいせい)である。その学識は祖先から教えられたものもあれば、自力で修めたものもある。
国学より漢学を多く学び、四書・五経・日本外史・十八史略などを修めたものが大部分である。
医師は支那の医術の本である正漢論を、神官は古典・礼法・歌学などを修めたのである。
(三)寺入りの儀式および束脩(しゅう)謝儀
寺子屋または私塾に入門することを「寺入り」といって「寺入り」の時は、両親が付添い束脩という現金を包んで祝儀を差し出した。(金額は師家では定めていなかったものが多い)この外蒸し物を重箱に入れて持参した。(蒸し物とはアンビンまたは赤飯等である)
謝儀としては1年間に金2朱より金1分位を現金で出したものもあれば、盆、正月に農産物を納めたものもあった。 (参考)金1朱は6銭2厘5毛であり、金1分は25銭にあたる。
1分は1朱の4倍である。
(四)就学の状況
本町の寺子屋・私塾に就学した児童数は前記の通りである。その多くは通学であり遠方よりのものは寄寓(きぐう)したものも少しはあった。
就学者は一般に生活に余裕のある家庭の子女が多く、他の者はあまり就学しなかった。
就学者の少ない理由は多くは家計の状態からきたものであり、また、当時は教育尊重の念が薄かった理由もあった。
年齢は6・7歳から13・4歳位までが普通で学習期間は5年ないし8年のものが多かった。
(五)設備
教室は大てい自家の一室をあて、すべてたたみ敷きの部屋を使い、机、文庫などは「寺入り」の際に家庭から持参したものが多く、極めて簡単な設備であった。机の配置は師匠の席は正面にあって、それに向き合って前面と左右に寺子の机をおいた。
男女は学習は一緒にするが席は別々になっていた。習字の道具・用紙などは毎日持参していた。
寺子屋はワン ルーム・ワン ティーチャー(1部屋・1教師)システムと呼ばれる世界でも珍らしい児童教育の方法であった。
(六)学科、学習内容および方法
教科書は大部分の寺子屋が寺子屋本を使った。寺子屋本にはいろは・名頭字・是非短歌日用文章・実語教・国尽・郷尽・商売往来・消息往来・古状揃・庭訓往来の類などがあった。寺子屋本の例
進んだところで四書・五経・十八史略・左伝・唐宋八家文などを教えた。
(四書とは大学・中庸・論語・孟子の総称であり五経とは易経・書経・詩経・春秋・礼記の総称である。)
学習の進め方は、はじめ「いろは」から入り、次いで平仮名交り手本を授け、片仮名に移り、やがて常識的な名頭字・村名尽等の語集に入り、日常生活に必要な文筆を授けるというように、易から難へ、簡から繁へ進むといった学力の進歩に即応した方法を用いた。
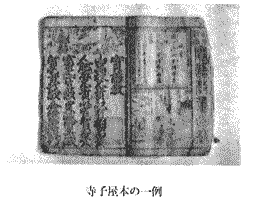 |
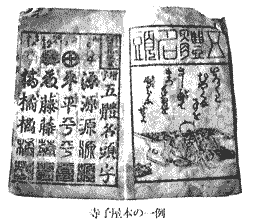 |
習字は春と秋との2回「席書」を催して文字の優劣を調査した。
「七夕」や「書初め」などもやった。
なお1年1回大試験があって1年中学習したことをテストしてその成績を評価した。
(七)日 課
毎日午前8時頃から午後2・3時頃までが日課であり、授業は1日6時間位であった。午前中は読書・和算が主であり、午後は習字が普通であった。学習方法はめいめいの自習学習であった。
この自学をする間に師匠は2、3名ずつを自分の机の側に呼び出して読み方を教えてやったり、字を直してやったりした。
休業は年末、年始の休み、毎月の1の日・15日・25日および五節句、(1月7日・3月3日・5月5日・7月7日・9月9日)盆、祭礼時などで今の夏休みのような長期間の休業はなかった。
私塾の中には毎日通学させるのでなくて、農閑期だけ勉強を教えるものもあったのである。
(八)経営維持
束脩は親の自由にまかせて多くの師家では定めていなかった。全くの私設のもので幕府から何等の干渉も受けないかわり、どこからも補助金など全然なく大方自費でやっていたものである。謝儀なども少ない額であり農産物を納めるのも各人の応分にまかせたので、当時の小農村であった本町の家庭からの納め品も、たいしたことはなかったようである。
従って恒産のあるものは別として、全体的にみて経済は豊かなものではなかったのである。
三、寺子屋私塾の影響
明治5年(1872)に学制が発布されるまでの教育は以上のような状態であった。その歩みは稚拙であったが、日本が現在世界に劣らない教育の充実した国になったのは、明治以後急に始まったことでなくして、すでに徳川時代にその基になるものができ上っていたのである。
いま、われわれは、あらためて先人の苦心のあとに感謝したいと思う。

