第四章 学校教育
第一節 小学校教育草創時代
一 学制発布当時の教育の実情
(一)学校設立の状況
明治維新によって成立した新政府は、文明開化・富国強兵を旗印として諸政策を推進した。当時国民大衆を対象とする教育は、私塾や寺子屋において行なわれたが、就学するのは一部の者に過ぎなかったのでいわゆる文盲の大衆が多く、教育は全国民に対して開放されていなかった。そこで政府は「邑(むら)に不学の戸なく家に不学の人なからしめん事を期す」との大方針のもとに明治5年学制を発布し、近代学校制度の樹立と教育の普及に力を注いだ。その大要は全国を8大学区に分け、1大学区を32中学区に分け、1中学区をさらに二の小学区に分けた。そして全国に大学校8校、中学校256校、小学校53,760校開設という大きな計画を立てた。
山梨県においても政府の方針にのっとり、明治6年4月には全県下を区分して、小学校設立区分案を示すなどして各村々に小学校の開設を促した。
当時行政上巨摩郡34区に属していた現在の下山・身延・豊岡地区においては、明治6年1月当時の34区長佐野清右衛門正意が中心となり区内の各村々の正副戸長と相図り、身延山西谷正修院を仮設学校として区内に1校を設け、漸次各村々に設立することとした。現在の大河内地区においては、明治6年5月当時の八代郡第16区内の各村々に1校を設立することにし、帯金村普門院を仮用して設立した。その後各村々の努力により順次各地に学校の設立が行なわれたが、当初は多くの寺院を仮用し、寺子屋を再編成したようなものであった。
その後幾多の変遷を重ねて、現在の下山・身延・豊岡(清子分校を含む)・帯金・大和の5小学校となった。
表−1 草創時代の小学校開業表
| 当時の 郡 区 |
小学番号 | 名 称 | 設立年月日 | 公有又は 借 家 |
備 考 |
| 巨摩群 34区 |
第1大学区 第44番中学区 第63番小学 |
下山学校 | 明治6年11月 | 寺院 (借家) |
現 下山小学校 |
| 〃 〃 |
第1大学区 第44番中学区 第51番小学 |
身延学校 | 6年1月 | 寺院 (借家) |
現 身延小学校 |
| 〃 〃 |
第1大学区 第44番中学区 第84番小学 |
波木井学校 | 7年12月23日 | 寺院 (借家) |
|
| 〃 〃 |
第1大学区 第44番中学区 第87番小学 |
大野学校 | 7年12月23日 | 寺院 (借家) |
|
| 〃 〃 |
第1大学区 第44番中学区 第92番小学 |
豊岡学校 | 8年4月20日 | 寺院 (借家) |
現 豊岡小学校 |
| 八代郡 16区 |
第1大学区 第44番中学区 第10番小学 |
帯金学校 | 6年6月 | 寺院 (借家) |
現 帯金小学校 |
| 〃 〃 |
第1大学区 第44番中学区 第95番小学 |
八木沢学校 | 7年12月10日 | 新築 (公有) |
|
| 〃 〃 |
第1大学区 第44番中学区 第65番小学 |
大島学校 | 7年5月15日 | 寺院 (借家) |
現 大和小学校 |
| 〃 〃 |
第1大学区 第44番中学区 第79番小学 |
和田学校 | 7年10月8日 | 寺院 (借家) |
(二)生徒職員の状況
小学校が設立された当時は、各校とも就学率は非常に低く、学齢児童の30パーセントにも達しなかった。そして就学児童の多くは比較的恵まれた家庭の子弟であったが、当時の風習等から服装持物等は非常に質素であり、木綿着物に草履ばきで、学習用具は風呂敷包みにして登校した。学用品は主として石筆、石盤、手ならい草紙で、計算や漢字の練習も石盤に石筆で書いては消し書いては消して練習し、また習字は半紙をとじた草紙に白い所のある間は練習するという風であった。また学校での教育は「伝習中無作法の所業は勿論高声雑話一切之を禁ず」とか、「昇校退校とも必ず教官に礼節をなし正課中みだりに他席へ行くべからず」等の教訓に示された通り非常に厳格に行なわれた。
職員については学制によると、師範学校ないしは中学校卒業の有資格者をあてることになっていたが、学制実施とともに登場した非常に多数の教員を、そうした有資格者で満たすことは到底できなかったので、読み書きのできる失職士族や旧寺子屋の師匠たちがそれぞれの学校の教師に採用された。従って新制度下の学校教師としてはほとんど無資格者であり、なお開設当時はほとんどの学校が教師1人で全級の子どもを受け持つ単級教授であったので、新教育の目ざす成果を挙げることは困難であった。
(三)教育内容と生徒就学の模様
ア 教育内容学制を実施し、寺子屋を近代学校の形態へ進ませるためには外形的な学校建築の問題とともに、教育内容及びその指導法の改善こそ重大な問題であった。
文部省は学制発布の翌月、小学校教則を公布し、小学校における教育方法の基本方針を明らかにした。本県においてはこれに準拠し、明治6年(1873)6月山梨県内小学校教則を公布し、小学校を上下二等に分け、下等は6歳より9歳、上等は10歳より13歳に終り、上下合せて在学は8年と定めた。そして上下四ヶ年を各々8級に分け、毎級6ヵ月をもって卒業することとし、その修業する課程は読書・暗誦・習字・算法の4項とした。
その小学校下等課業表は次のようである。
| 等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
| 習字 | 行書 諸券状 日用文 |
行書 十二月帖 世界風俗往来 |
行書平カナ交リ 啓蒙手習文 日本国尽 |
楷書片カナ交リ 御誓文 官省日誌 |
楷書 皇国官名誌 府県名 |
楷書 日本国名 |
楷書 習字本 13号 14号 15号 |
片仮名 平仮名 数字 |
| 読書 | 西洋事情 地学事誌 国史略 |
内国史略 西洋新誌 道理図解 |
農業往来 世界商売往来 究理問答 王代一覧 |
日本地理往来 世界国尽 童蒙教草 |
童蒙必読 日本国名 名家童蒙解 勧善教草 |
単語3篇 本朝三字経 学問のススメ 区戸長心得書 |
絵入智慧環 単語2篇 |
うひまなひ 単語初篇 |
| 暗誦 | 内外国 名山大川 旗章 |
内国人員戸口 内外度量 |
皇国官名誌 世界国名 |
帝号 年号 |
日本国名 苗字尽 |
単語 3篇 |
単語 2篇 |
単語 初篇 |
| 算術 | 諸等加 減乗除 |
諸等 雑問 |
諸等 雑問 |
乗法 除法 |
乗法 除法 |
加法 減法 |
加法 減法 |
九九声 |
なお学業の結果を試す試験は、内試、試検、大試検の3段階があり、非常に厳格で不合格のため昇級出来ない者も相当あった。内試は毎月30日を定日とし、1項を終了すればその校において教師が習業の進否を検した。試験は春秋2回行ない、内試を経4項に習熟して昇級する者を係官が臨席して行なった。大試験は下等小学より上等小学に進学する者を検した。
明治9年(1876)には先に制定された山梨県教則は更に改定され、よりくわしいものになった。その中の課業の一部について記せば次のようであった。
下等小学校第八級
読物。伊呂波五十音・濁音・次清音図・単語図連語図を授ける。
問答。単語図を問答する。
書取及び作文。伊呂波五十音を書取らしめ、正草変様の三を以て単語を綴(つづ)らしめる。
算術。数字図・算用数字図・加算九々図・一より百までの書き方位取りを教ゆ。
習字。仮名
第七級読物。小学字類小学読本巻之一を授く。
問答。小学字類改正色図を問答する。
書取作文。小学字類の文字を書取らしむ。
算術。乗算八八図・ローマ数字図・百より万までの書取位取を教え、容易加法暗算に及ぼす。
習字。楷書
第六級習字。楷書
読物。小学読本巻之二三・地理初歩を授く。
問答。地理初歩・形体線度図・地球儀及び地学の大綱を示す図を問答する。
書取作文。読本中の字句を書取らしむ。
算術。加法・減法・加減法・容易問題・暗算を教ゆ。
第五級習字。楷書
読物。小学読本巻之四・日本地誌略巻之一・本県地理書を授く。
書取作文。小学字類読本中の字句を題に与え、容易の文を作らしむ。
算術。乗法・加減法・容易問題・暗算を教える。
以上のように以前の寺子屋教育から見ると大きな変化であり、また寺子屋教育の方法が個別教育であったのに学制による小学校においては一変して、多数の生徒を対象に豊富な教科内容を、能率的に教授し得る一斉教授法へと改革された。以上新教育を一貫した教育理念は明治5年(1872)の太政官(だじょうかん)布告によってもうかがうことができるように、立身出世主義・実利主義・知識主義をもって貫かれていた。これは後進国日本が先進国にいかにして追い着くべきかの課題を持っていたからである。
イ 生徒就学の状況
学制実施後急速に各地に小学校が設置され、身延町内の当時の各村々にも小学校が設置された。そして学齢児童の就学については、父兄の必ず心がけなればならぬこととして大いに督励したが、確然たる義務制でなかったことや、父兄の経済的事情や、また寺子屋教育から一変した教育制度が当時の地域の実情に適合しなかったこと等により、就学する子どもたちは極めて少なかった。殊に女子の就学は低く男子の半数にも及ばなかったことは、当時一般に女子教育軽視の封建的慣習が根強く支配していたことを物語っている。
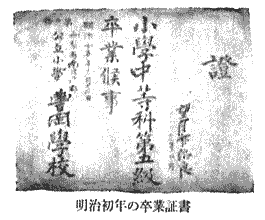 |
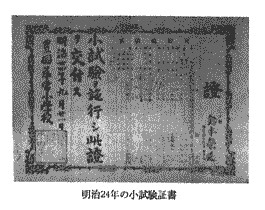 |

