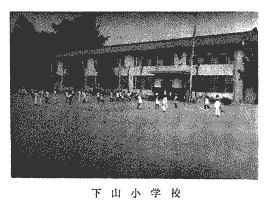| 明治6年11月 |
|
創立第1大学区第44番中学区公立第63番小学下山学校と称し本国寺を借用教授した。 |
| 明治7年1月 |
|
本校を長泉寺に移すためその修繕中、村内石川鳴平宅を仮用授業を行なった。 |
| 明治7年5月 |
|
長泉寺で開校した。東京師範学校卒業生富田精を講師として授業法を習い小学校授業がやや一定した。 |
| 明治9年4月 |
|
校舎狭きため演劇小屋を修繕し教室とした。 |
| 明治10年1月 |
|
下山小学校和算教授法を頒布した。 |
| 明治10年6月 |
|
村名改称により福居学校と改称した。 |
| 明治10年10月 |
|
崇光寺を仮用して粟倉支校を開設した。 |
| 明治10年10月 |
|
改正教育令により門標を山梨県南巨摩郡公立小学福居学校と改めた。 |
| 明治13年5月 |
|
教則改正、甲・乙・丙三種に別れ本校は乙科を採用する旨届け出た。 |
| 明治18年5月 |
|
本建学校を本校の支校とした。 |
| 明治19年5月 |
|
体操用具をはじめて購入した。(亜鈴・球竿) |
| 明治20年3月 |
|
県令第33号により小学校の学科及び程度実施の方法を定められ本校は尋常課程により別に温習科を設置した。 |
| 明治21年1月 |
|
杉山区に仮教場を置いた。 |
| 明治22年2月 |
|
新築校舎が落成した。 |
| 明治22年4月 |
|
粟倉分校が新築落成した。 |
| 明治22年8月 |
|
南部高等学校分教場を本校に設置し高等2学年まで教授することとなった。 |
| 明治31年11月 |
|
補習科を設置した。 |
| 明治32年4月 |
|
村名改称により校名を下山尋常小学校と改称した。 |
| 明治33年4月 |
|
高等科併置を認可された。 |
| 明治34年10月 |
|
校庭東民有地2畝を購入、運動場を拡げ入口道路を南方に移した。 |
| 明治37年6月 |
|
高等科3学年以上に農業科を教授することになった。 |
| 明治39年4月 |
|
校舎狭く竹下区松村近吉居宅を仮用1教室とした。 |
| 明治42年2月 |
|
竹下仮教場を服部徳太郎宅に移した。 |
| 明治42年10月 |
|
新校舎落成式を行った。 |
| 明治44年5月 |
|
粟倉分教場増築落成した。 |
| 大正元年10月 |
|
下山青年団より飲料水用井戸寄付され竣工した。 |
| 大正13年1月 |
|
皇太子御結婚奉祝式奉行。校旗樹立式を行なった。 |
| 大正14年7月 |
|
校庭周囲棚新設(バラ線)した。 |
| 昭和3年8月 |
|
御真影奉安所起工式を行なった。 |
| 昭和8年7月 |
|
少年赤十字団発団式を行なった。 |
| 昭和13年7月 |
|
勤労報国隊結成、隊旗樹立式を挙行した。 |
| 昭和16年4月 |
|
国民学校令実施により校名を下山国民学校と改称した。 |
| 昭和19年5月 |
|
6年児童杉山方面の学校林植樹を行った。 |
| 昭和23年11月 |
|
校章を制定した。 |
| 昭和25年5月 |
|
図書館開館式を挙行した。 |
| 昭和26年4月 |
|
粟倉分校一学級増になった。 |
| 昭和26年7月 |
|
電話敷設完了した。(下山20番) |
| 昭和28年1月 |
|
本校において小さい学校公開研究会が開催された。 |
| 昭和28年7月 |
|
校舎新築のため解体、1・2年本国寺、3・4年中学、5・6年公民館で分散授業を行なった。 |
| 昭和28年12月 |
|
新校舎落成式を挙行した。 |
| 昭和29年7月 |
|
東京都松木孫一より玄関正面校章を寄贈された。 |
| 昭和29年10月 |
|
校歌制定発表会を行なった。作詞米山愛紫、作曲保坂梅芳。 |
| 昭和30年2月 |
|
町村合併により校名を身延町立下山小学校と改称した。 |
| 昭和30年4月 |
|
5年を2学級(1学級増)申請を行なったが許可なく教頭が担任した。 |
| 昭和30年5月 |
|
子ども郵便局を開局した。 |
| 昭和31年8月 |
|
水道工事が完了した。 |
| 昭和31年11月 |
|
山梨県教育委員会ならびに全日本健康学校児童表彰会から健康優良校として表彰を受けた。 |
| 昭和35年3月 |
|
粟倉分校を廃止した。 |
| 昭和35年12月 |
|
給食室が竣(しゅん)工した。 |
| 昭和35年12月 |
|
給食を開始した。 |
| 昭和37年11月 |
|
子ども郵便局が知事表彰を受けた。 |
| 昭和39年5月 |
|
下山財産区管理会より鼓笛隊楽器一式の寄贈を受けた。 |
| 昭和39年12月 |
|
給食優良校として県教育委員会より表彰を受けた。 |
| 昭和42年11月 |
|
子ども郵便局が大蔵大臣、日銀総裁より表彰を受けた。 |