第五章 社会教育
第一節 社会教育の概況
一、社会教育の発達経過
(一)奈良、平安時代
社会教化の事業について、遠く奈良、平安時代にさかのぼってみると、当時すでに仏教教化の影響によって、ようやくそのきざしが見えていた。聖武天皇の朝、諸国に国分寺を建てて民人の教化を進め、また施薬院および悲田院を設けた。孝謙天皇は天下に詔して、家ごとに孝経一部を蔵して、精勤講習せしめられたのは、最も注目すべきことであり、かつ歴代の天皇は大いに孝子を表彰して孝道を奨められた。(二)鎌倉、室町時代
この時代の社会教化もまた僧侶(りょ)によって大いに普及された。かの禅宗が、主として武将武士の帰依する所となったのに対して、浄土宗・法華宗の庶民化は、時とともに益々その濃厚の度を加えた。そして、その僧侶の中には、辻説法と唱えて大道に説教する者もあり、また巡錫(しゃく)と称して地方に行脚(あんぎゃ)する者も多く、かくて教化はもちろん医薬・まじないのことから、茶の湯、活花の道に至るまで、彼等の手によって、民衆の間に教えられたものであった。その他室町時代には、軍記物お伽草紙(とぎぞうし)の類が多く刊行され、また新たに謡曲と称するものが創(はじ)められて教化を助けた。
日蓮聖人鎌倉入りの言葉
如何に強敵重るとも、ゆめゆめ退く心なく、恐る、心なかれ。
縦(たと)ひ頸(くび)をば鋸にて引き切り、胴をひしほこを以てつつき、足にほたしを打ちて錐(きり)を以てもむとも、命のかよはんほどは、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経と唱へて、唱へ死に死ぬるならば、(中略)諸天善神は天蓋を指し、旛を上げて、我等を守護して慥(たし)かに寂光(じゃくこう)の宝刹(さつ)へ送り給ふべきなり。あらうれしやあなうれし。
法華宗の教義も、唯々堅固な信念一つを尊んだもので、上の言葉によく表徴されている。如何に強敵重るとも、ゆめゆめ退く心なく、恐る、心なかれ。
縦(たと)ひ頸(くび)をば鋸にて引き切り、胴をひしほこを以てつつき、足にほたしを打ちて錐(きり)を以てもむとも、命のかよはんほどは、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経と唱へて、唱へ死に死ぬるならば、(中略)諸天善神は天蓋を指し、旛を上げて、我等を守護して慥(たし)かに寂光(じゃくこう)の宝刹(さつ)へ送り給ふべきなり。あらうれしやあなうれし。
(三)徳川時代
徳川時代においては、社会教化の上に多大の貢献をもたらしたものが数々ある。伊勢氏、小笠原氏の礼法、その他諸流の活花、点茶、和唐両様の書法、土佐狩野諸派の絵画等が、国民的情操を涵(かん)養したこと、神道仏教兵学等が、精神界に貢献したこと、皆しからざるはない。殊に通俗民衆の教化にあずかって、力のあったものは、自身番の掲示を始めとし、太平記、平家物語等の軍記類、または謡曲、浄瑠璃(じょうるり)、長唄、講談、小説、俳諧、演劇(歌舞伎、人形浄瑠璃)能楽、角力等である。
これらは、いずれも賢明な諸候に利用されて、民育の上に偉大な成績をもたらした。
また平民儒学ともいわれ、商業道徳を重んじて、主として商人に向って宣伝された、石田梅巌の心学教、農本主義でもっぱら農民の間に行なわれた、二宮尊徳の報徳教については、もちろんいうまでもないことである。
一方徳川幕府は、支配秩序を維持するための成人教育には、絶えず努力をはらってきた。
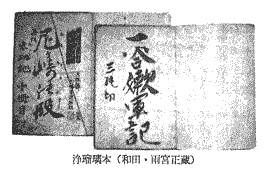 |
 |
 |
このような教諭が、御触書や、禁令として次々に布告され、その徹底のために5人組が利用された。
5人組は、最初浮浪人を取締まる目的であったが、次第に農工商のすべてにわたって組織され、連帯の責任をもち、特に農民の場合には百姓の数の維持と、年貢の確保について責任を負わされていた。今日各地に残っている5人組帳の前書は、上からの諸法令の集成であり、それは機会あるごとに「必名主所え百姓水呑みに至る迄呼寄せ話聞せ常々無解怠相守様」に、申し付けられたのである。
その内容も、次第に衣食住にわたる、細かな干渉指導が加わるのであるが、一般的に御公儀を尊敬し、卑しい自分の地位に満足し、粗衣粗食をもって、貢租を完遂するような農民意識を作り出すための、教育という積極的要素が強く出ていたのである。
またこの時代の若者には、どんな対策がとられていたか。それには、若連中、若衆、若者仲間などと呼ばれるものに、若者制度があった。
この発生は、相当古くからあって、恐らく室町末期頃からであろうと推察される。
これは村落生活の必要に基づいて、祭礼その他の行事に参加し、また公安の維持などにも当たったものであろう。そしてこの集団生活を通して、村落の後継者の訓練も行なわれたのである。若衆組の組織および仕事を規定したものは、これを若衆条目といったが、これは5人組の条目から非常に多くの影響を受けて、規定されたものである。
たとえば、国法や村法を遵(じゅん)守すべきこと、役人に対する礼儀とか、敬老についてとか、または風儀風俗の改善、男女間の取締まりについてとか、賭博(とばく)飲酒喧嘩(けんか)口論などの禁止、宗教に関する規定などがあり、もしこれを犯した際には制裁が加えられたのであるが、このような力が当時の青年を、実際に形成していく大きな力となって働いたものと考える。
以上のような若者制度が、やがて明治になり38、9年(1905、6)頃に青年会となり、その後青年団となって発展する有力な地盤となっているのである。
定法書之事(若衆条目の例)
一、当組伍長元より申渡候御規則は申すに及ばず御制事の旨相背かざる様其組合下々迄申し聞かせ可き事
一、寺院伍長並に村内重立候ものに対し過言無礼之無き様相慎み申す可事
一、若者世話役取定めの儀は旧正月初出会の節年番伍長目鑑を以て申付弐人にして相勤め其節鬮(くじ)に致し壱番にして旧正月より七日迄弐番にして正月十四日迄右弐人に相勤め其組々小頭之儀は時之世話役目鑑之上申付取定め致す可き事
一、道祖神祭礼之儀は年々旧正月十四日世話人宅へ一同出会致世話役小頭共引替り申す可く候其節祭礼入用等掛らざる様成る丈け手軽に取計り申す可き事
一、時の世話役より触当て候諸人足の儀は滞り無く相勤め申す可き事
一、若者の内其組内は申すに及ばず諸々へ出歩行喧嘩、口論等相含み人の腰押等致候もの之有らば見捨置かず世話役にして申聞かせ夫とも聞入之無く候はば年番伍長へ申出可き事
一、何事によらず要事を勧め人之腰押等致し聊の儀を手重く申立て隠忍び寄合致し一味の儀一切仕る間じく候或は申合強淫の体心掛け候者之有るにおいては軽からざる事につき其筋へ申出御処分請ふ可き事
一、大勢集り大酒呑むべからず酒過ぎ候て後の勝負事など致す間じく万一心得違の者之有候はば申出ずべき事
一、若者仲間内にして差 等出来致し候節は成丈け時の世話役にして手軽に相済し以後改心致可き様申聞かせ置く可き事
等出来致し候節は成丈け時の世話役にして手軽に相済し以後改心致可き様申聞かせ置く可き事
一、若者仲間にかぎらずなりくだもの其他へ手出し致し候者之有り候はば見出し次第年番伍長へ申出ず可き事
一、若者の内堂宮へ夜泊り等一切致す間じく若し出歩行候とも十時限り帰宅いたすべき事但時後れ候ては家業差支えは勿論急事の用に相立たず候に付急度制事致す可き事
一、若者仲間入の儀は十歳より三拾六歳迄に相定申す可く候事
但し仲間入りの儀は無限りにあらず
且学校生員中へ諸人足の儀触当て申す間じく候事
前書ヶ条の趣辺々読聞かせ急度相守候様時の世話役より一同へ申聞かされ置く可き様申渡候也
明治十四年 当組年番
旧七月十四日 伍長 松木盛重
並に 伍長一同
若者仲間
時之世話役
滝戸五郎兵衛
佐野彦右衛門
遠藤儀一
若尾丑五郎
且学校生員中へ諸人足の儀触当て申す間じく候事
前書ヶ条の趣辺々読聞かせ急度相守候様時の世話役より一同へ申聞かされ置く可き様申渡候也
明治十四年 当組年番
旧七月十四日 伍長 松木盛重
並に 伍長一同
若者仲間
時之世話役
滝戸五郎兵衛
佐野彦右衛門
遠藤儀一
若尾丑五郎
(四)明治以降
社会教育という術語からも、わが国の社会教育は、「近代学校における教育に対して、一般社会において、社会人を対象に行なわれる教育活動」と解すべきであろう。さらに法制上、また行政上の諸規定を参照して、社会教育の成立を考えるなら、これはそんなに古いものではない。というのは、わが国における近代学校の誕生は明治の初期であって、それ以前には真の意味における学校も、またしたがって学校教育もなかったからである。
それ故、その対立概念としての社会教育は存在し得ないのが当然であって、ただ藩校、寺子屋、あるいは辻説法などがあったにすぎないが、これらを、いわゆる社会教育ということは、前述の通りできないであろう。
そこで、わが国の社会教育の成立と進展を回顧するには、明治以後の近代学校成立以降をみることになるが、もちろん、明治以前にも、いわゆる社会教育らしきものが、全然存在しなかったという意味ではなく、明確に学校教育と対比させて、社会教育を追求したいという意味からである。
そこで、便宜上、わが国における社会教育をつぎの四期に大別して考えていきたい。
第一期 通俗教育期
明治4年(1871)〜大正10年(1921)
第二期 社会教育創始期
大正10年(1921)〜昭和10年(1935)
第三期 社会教育衰退期
昭和10年(1935)〜昭和20年(1945)
第四期 社会教育復興期
昭和20年(1945)〜現在
ア、第一期通俗教育期
明治4年(1871)〜大正10年(1921)わが国の社会教育のいわば胎動期であって、社会教育施設としての博物館、図書館が設けられ、「通俗教育」という名称のもとに、ようやく、社会教育が行なわれ始めた時代である。
他方勤労青年のために、「実業補習学校」が開設され、また青年団に対する指導も始まっている。
明治4年(1871)文部省に「博物局」がおかれ、博物局観覧場が開かれた。
明治5年(1872)博物局に「書籍館」がおかれ、一般に公開された。
明治19年(1887)文部省に書籍館、博物館に関する事務とともに通俗教育に関する事務がとられるようになった。
明治26年(1893)勤労青少年のため「実業補修学校」が開設された。
明治32年(1899)図書館令が公布された。
明治38年(1905)地方青年団体指導に関する局長通達がだされた。
明治44年(1911)通俗教育調査委員会官制が制定された。
明治44年8月に文部省は、東京、広島両高等師範学校に対し、学校教育の余暇に、通俗教育上適当と認める事業・計画・施設などに尽力するよう通牒を表した。
大正4年(1915)「青年団体指導発達に関する件」という文部、内務両省の共同訓令がだされた。これによって修養団体としての青年団の組織化が進んだ。
青年団体の起源は江戸時代中期以後の「若衆制度」に表するものとされている。
しかし近代日本では、日清戦争直後、青年団の問題がとりあげられた。これは当時、「国運の隆盛発展の基礎は青年の教育によるところ、きわめて大である」という識者の主張に基づくものであった。
かくて組織的な「夜学会」などが試みられ、年とともに青年団運動は栄えていったが、さらに日露戦争を迎えて、一段と拍車がかかり、その内容も単に夜学会などの補習教育にとどまらず、気風振作、農業の改善、進歩、隣保公共事業などの助讃、軍事の後援など、いわゆる修養的な範囲を越えて、事業的な方面に著しく進出していった。
しかし、各種の公共、公益事業に関与し始めた青年団は、ややもすると事業団体的性格にはしり、修養団体としての使命を忘れがちになるので、大正4年に前記の通牒「健全なる国民、善良なる公民たるの素質を得せしむる」旨の共同訓令がだされ、青年団設立の主旨が、修養団体にあることを明確にし、その方向を明示したのである。
大正9年には、同じく第三次の訓令が表せられ、同時に大日本連合青年団の結成にまで到達したのであった。
大正6年(1917)寺内内閣に臨時教育会議が設置され、通俗教育に関する調査会が設けられたことと、文部省内に初めて通俗教育の主任官がおかれたことは、特筆すべき事項である。
以上通俗教育として、社会教育が学校教育に、対応するものとして一応の方向をみいだし、わが国の社会教育の基礎を一歩一歩築きつつあったことは、見逃(のが)せないところである。
他方ようやく高まってきた、わが国の自由主義的ブルジョア・デモクラシーの思想を抑えるべく、前記「臨時教育会議」が寺内官僚内閣の手で設置され、「国体の精華宣揚」の教育、忠良なる臣民育成の教育が、絶対主義的指導者たちによりうちだされた。
こうした情勢のなかでの社会教育は、国家の意思による、天下り的な域をでることはできなかったといえよう。
通俗教育の例(紀元二千六百年記念山梨県教育会史より)
一、通俗教育部の設置
明治四十四年十月七日新設事業として本会付属通俗教育部を設置し、下記規程によって実施した。
県よりは、本会事業計画に対して明治四十四年より金三百円の指定補助金を交付せられたが、大正二年には金四百円、大正三年には金五百円、大正四年には金六百五十円と逐年増額せられ、事業経営も年とともにその成果をあげ、爾来本会の事業として継続してきた。
二、山梨教育会付属通俗教育部規程
明治四十四年十月七日新設事業として本会付属通俗教育部を設置し、下記規程によって実施した。
県よりは、本会事業計画に対して明治四十四年より金三百円の指定補助金を交付せられたが、大正二年には金四百円、大正三年には金五百円、大正四年には金六百五十円と逐年増額せられ、事業経営も年とともにその成果をあげ、爾来本会の事業として継続してきた。
二、山梨教育会付属通俗教育部規程
第一条 本部は県下における風教の改良と一般智識の増進とを図るをもって目的とす
第二条 本部は山梨教育会付属通俗教育部と称す
第三条 本部にて挙行すべき事業の概目以下の如し
一、講話
イ、道徳に関すること
ロ、学術に関すること
ハ、体操衛生に関すること
ニ、実業に関すること
ホ、国勢に関すること
二、理科に関する実験
三、展覧会
四、巡回文庫
五、音楽会
六、講演
七、活動写真 幻灯
八、その他
イ、道徳に関すること
ロ、学術に関すること
ハ、体操衛生に関すること
ニ、実業に関すること
ホ、国勢に関すること
二、理科に関する実験
三、展覧会
四、巡回文庫
五、音楽会
六、講演
七、活動写真 幻灯
八、その他
第四条 本部は以下の場所において開会するものとす
一、学校
二、会社、工場
三、その他便宜の場所、以下略
三、通俗教育実施状況
明治四十四年度、明治四十五年二月十八日より九日間一市九郡にわたり各一ヵ所本会付属通俗講演会を開くにいたる所盛況。
明治四十五年度実施(以下当地方に関係のあるものを記す)南巨摩会場、二月二十六日午後七時より同十一時まで睦合小学校において開会、聴衆無慮二千名、島津副支会長の開会のあいさつ、睦合望月校長の戊申詔書奉読についで映画および講演等を行なう
一、地方青年に対する希望
甲府高女校長 内田幾次郎
一、中庸の素読 南部病院長 近藤寛治
大正三年度実施状況
南巨摩支会
開期 大正三年九月より十二月
会場 二十一ヵ所
挙行事項講演餘興(幻灯、蓄音機)
講師 校長、村長、宗教家、郡吏員、実業家、名士
経費 一ヶ所三円
講演会
昭和三年二月十二日午後一時 大和小学校
我が国体の精華について 佐野嘉一郎
第一歩を確に、批判的生活態度 斉藤利信
聴講者 男一一〇 女四 計一一四
昭和四年十月十二日午後一時 下山小学校
社会生活の保証 副会長 堀内文吉
国家心の涵養 幹事 萩原頼平
聴講者 男一七三 女四二 計二一五
昭和四年十二月七日午後一時 帯金小学校
日本国民の行くべき道
身延中学校 内田与八
生活の合理化 幹事 佐野聡彦
聴講者 男一一三 女四八 計一六一
イ、第2期社会教育の創始期二、会社、工場
三、その他便宜の場所、以下略
三、通俗教育実施状況
明治四十四年度、明治四十五年二月十八日より九日間一市九郡にわたり各一ヵ所本会付属通俗講演会を開くにいたる所盛況。
明治四十五年度実施(以下当地方に関係のあるものを記す)南巨摩会場、二月二十六日午後七時より同十一時まで睦合小学校において開会、聴衆無慮二千名、島津副支会長の開会のあいさつ、睦合望月校長の戊申詔書奉読についで映画および講演等を行なう
一、地方青年に対する希望
甲府高女校長 内田幾次郎
一、中庸の素読 南部病院長 近藤寛治
大正三年度実施状況
南巨摩支会
開期 大正三年九月より十二月
会場 二十一ヵ所
挙行事項講演餘興(幻灯、蓄音機)
講師 校長、村長、宗教家、郡吏員、実業家、名士
経費 一ヶ所三円
講演会
昭和三年二月十二日午後一時 大和小学校
我が国体の精華について 佐野嘉一郎
第一歩を確に、批判的生活態度 斉藤利信
聴講者 男一一〇 女四 計一一四
昭和四年十月十二日午後一時 下山小学校
社会生活の保証 副会長 堀内文吉
国家心の涵養 幹事 萩原頼平
聴講者 男一七三 女四二 計二一五
昭和四年十二月七日午後一時 帯金小学校
日本国民の行くべき道
身延中学校 内田与八
生活の合理化 幹事 佐野聡彦
聴講者 男一一三 女四八 計一六一
大正10年(1921)〜昭和10年(1935)これまでの通俗教育が社会教育という名称のもとに再出発し、文部省についていえば、官制も事務も、また人員もおおいに整備、拡充された時期で、いわば社会教育の創始期であるとともに、拡充期ともいえる時期である。
大正10年(1921)文部省官制の改正によって、通俗教育を社会教育と改めた。
大正13年(1924)文部省普通学務局のほかに「社会教育課」がおかれ、その事務をつぎのように定めた。
1、図書館、博物館に関すること
2、青少年団体および処女会に関すること。
3、成人教育に関すること。
4、特殊教育に関すること。
5、民衆娯楽の改善に関すること。
6、通俗図書認定に関すること。
7、その他社会教育に関すること。
大正14年(1925)地方行政機構のなかに「社会教育主事」および「社会教育主事補」が設置された。
大正15年(1926)「青年訓練所令」および同規程が公布され、青年訓練所が設置された。
大正15年4月20日、勅令第70号による所令に続く、同年4月21日の文部省訓令第8号によると、「青年の心身を鍛練して健全なる国民、善良なる公民たるの資質を涵養するは、わが国内外の情勢に鑑(かんが)み頗(すこぶ)る緊切なるを覚ゆ、然るに、現下青年教養の施設は逐年表表の情勢ありと雖(いえど)も尚未だ十分ならざるものあり、これ今回青年訓練の制を定め一般青年に対して適切なる訓練を行なはむとする所以(ゆえん)なり。而も本訓練の結果は兵役に服する者に対し、在営年限の短縮を伴ふが故に、其の国家産業の進展に及ぼすべき効果も亦頗る大なるものあるべし」とあるが、青年訓練所設立の要旨をうかがうことができよう。
また、「令」の第1条「青年訓練所は青年の心身を鍛練して国民たるの資質を向上せしむるを以て目的とす」とその目的を示し、入所資格としては16歳から20歳の男子。設置主体は市町村、市町村学校組合、町村学校組合であって、私人も文部大臣の定めるところにより設置可能とされていた。
訓練項目は、修身および公民科、教練、普通学科、職業科であるが普通学科と職業科の科目は文部大臣が定めることになっており、費用は徴収できない。地方長官の監督のもとに主事および指導員がおかれ、修業年限は4年であったが、軍事教練が主であることはいうまでもない。
昭和4年(1929)文部省普通学務局、社会教育課が独立して「社会教育局」が設置され青年教育課、成人教育課、庶務課の3課がおかれ、事務上、官制上社会教育の整備がおおいに進められた。
昭和7年(1932)全国各市町村に、「社会教育委員」の設置の奨励が、文部省によりおこなわれた。
この「社会教育委員」の法に基づく復活は、昭和24年の「社会教育法」第4章によるが現在は、都道府県および市町村に設置義務が負わされている。
以上のように、わが国の政治、経済、文化の拡充期に乗じて、さらに世界的なデモクラシーの気運に促されて、わが国の社会教育はおおいに充実、整備され、創始期であるとともに、第一次の興隆期でもあったといえる。

