明治24年(1891)山名次郎が「社会教育論」という図書を刊行したが、この時使った社会教育という用語が、わが国で使われはじめであった。
大正に入り社会教育に関する、研究図書が相次いで刊行された。
大正12、3年(1923、4)に至ってようやく公用語となった。
明治時代からなかなか使われなかったのは、当時社会主義が台頭していた折柄だけに、世人の多くは社会主義と、社会教育とが、同義語と考えられていたからであったといわれている。
社会教育活動の一例
豊岡村社会教育委員会大正に入り社会教育に関する、研究図書が相次いで刊行された。
大正12、3年(1923、4)に至ってようやく公用語となった。
明治時代からなかなか使われなかったのは、当時社会主義が台頭していた折柄だけに、世人の多くは社会主義と、社会教育とが、同義語と考えられていたからであったといわれている。
社会教育活動の一例
沿革
昭和7年(1932)7月豊岡村社会教育振興会を組織し会則に従いこれが伸展に努力し来たるも昭和11年7月会則を訂正して豊岡村社会教育委員会と改称し、村長・助役・方面委員・村会議員・小学校教員・学務委員・警察官・宗教家・各種団体長等を委員とし村長推薦し知事の嘱託により委員会を組織して現在におよぶ。
方針
本村民の長所を助長し短所を矯正し時局に対処すべく村是を定め平凡にして近きよりをモットーとしてその実現を期し本村全野にわたる更生開発を図らんとす。
社会教育計画要項(村是の徹底)
昭和7年(1932)7月豊岡村社会教育振興会を組織し会則に従いこれが伸展に努力し来たるも昭和11年7月会則を訂正して豊岡村社会教育委員会と改称し、村長・助役・方面委員・村会議員・小学校教員・学務委員・警察官・宗教家・各種団体長等を委員とし村長推薦し知事の嘱託により委員会を組織して現在におよぶ。
方針
本村民の長所を助長し短所を矯正し時局に対処すべく村是を定め平凡にして近きよりをモットーとしてその実現を期し本村全野にわたる更生開発を図らんとす。
社会教育計画要項(村是の徹底)
1、勅語詔書の御聖旨を奉体し肇(ちょう)国の大義に則(のっと)り、国体観念を明徴にし、日本国民たるの本分を具現すること。
2、勅語詔書の御聖旨を奉体しこれが徹底すること。
3、敬神崇祖の念を涵養し、国民道徳の実践発揚を期すること。
4、立憲自治の精神を培沃(よく)し、もって公民生活の基根を確立すること。
5、勤労精神を発揚し、生産増加を企図し村経済の更生を期すること。
6、隣保共助の農村美風を発揚し、偕(かい)和協調の実を期すること。
7、家庭生活の振興を図り、大衆生活、愛郷観念の作興に努むること。
8、国民精神総動員の趣旨を体し、挙国一致、尽忠報国、堅忍持久の精神強化に努むること。
9、体育を重んじ、保健衛生に留意し、一般体位の向上に努むること。
10、民衆娯楽の改善と、これが振興とを図り、高尚なる趣味の培養に努むること。
社会教育実施状況
| 村是 | 実施事項 | 実施状況 | 反省 |
| 勅語詔書の御聖旨を、奉体し肇国の大儀に則り国体観念を明徴にし日本国民たるの本分を具現すること | 1、勅語詔書の聖旨奉戴 | 家庭小学校各種団体において聖旨の徹底を図る。 | |
| 2、祝祭日国旗毎戸掲揚 | 小学校児童青年学校生徒各種団体員により実施 | ||
| 3、四大節拝賀式参列 | 児童生徒各種団体一般村民 | ||
| 4、尊貴の御写真鄭重取扱い | 各戸に写真帳を設け切抜貼布 | ||
| 5、精神作興詔書奉読日の設定 | 毎月10日小学校青年学校で | ||
| 6、神宮大麻毎戸拝戴 | 村当局社掌学校中心 | ||
| 7、祝祭日の家庭化 | 各家庭 | ||
| 8、御聖旨の印刷毎戸配布 | 小学校児童青年学校生徒を通じて |
当時社会教育委員会は各町村に組織されていた。
ウ、第3期社会教育の衰退期
昭和10年(1935)〜昭和20年(1945)わが国が日華事変から、さらに第二次世界大戦に突入し、敗戦という冷厳な事態に直面するにいたった期間であって、社会教育は前期に比していちじるしく衰退していった。
昭和10年「青年学校令」が公布され「実業補習学校」(明治24年開設)と「青年訓練所」(大正15年開設)とを合併し、青年学校が設置され、同時に青年学校教員養成所が開設、わが国青年教育の制度が表面的には拡充された。
昭和14年(1939)青年学校の義務制が実施された。諸外国にみる義務社会教育の提唱と考えたいが、これは第二次世界大戦突入の直前でもあり、すべての青年に対し、国民精神を振作して時局を担(にな)うにたる軍国青年を、国家の意志によって育成しようとしたものにほかならない。
昭和17年(1942)文部省の「社会教育局」は廃止され、これに代って「国民教育局」が設置された。
世界大戦により、国の行政機構は決戦体制に切り替わり、社会教育の活動は、ここに実質的にまったく停止することになった。
わが国の戦時下教育は、高度国防国家確立のための教学刷新によって、非合理的な国粋主義的傾向と、生産力増強をめざす科学、技術教育の振興という矛盾を内包し、さらに軍事力、労働力強化のため「錬成」という精神修養や体力の鍛練が重視され、教育に対する軍部の全面的介入がその特徴をなしていた。
小学校ですら、昭和16年には国民学校と改称、「皇国の道に則る」少国民の基礎錬成を実施したが、教育現場では戦争宣伝や観念的な説教の注入になったり、体罰の横行がめだち、戦争の激化にしたがって、とても正常な教育は行なえない状態であった。
まして、時局の流れに浮動しやすい社会教育は、前期のデモクラシーの気運とともに、せっかく隆盛にむかいつつあったにもかかわらず、本来の意味で、その機能を停止し、国民総動員の線に沿い、またとくに青年に対し、軍隊教育の予備門としての国民教育に専念させられるのやむなきにいたり、ついには、わが国の社会教育は廃止されるという運命に陥ったのがこの時期である。
エ、第4期社会教育復興期
昭和20年(1945)〜現在
昭和20年10月に文部省に社会教育局が復活、社会教育課・文化課・宗務課・調査課の4課がおかれ、同時に文部大臣から、終戦の混乱に際しての社会教育の方針が示された。
11月には、国民教育課・芸術課が加えられた。
昭和21年文部省訓令により、社会教育課・文化課・芸術課・調査課・宗務課の5課に改められた。
昭和22年教育基本法の制定、その第7条(社会教育)により、社会教育が国および地方公共団体により、奨励されなければならないことが法律により規定された。
昭和23年「教育委員会法」が制定され、「教育の民主化」「教育の自主制」「教育の地方分権」の3原則が確立され、教育行政が一般行政から分離独立した。
昭和24年待望の「社会教育法」が制定され、国および地方公共団体の社会教育に関する任務が明らかにされ、社会教育行政の基礎が確立した。
昭和25年単独立法としての図書館法が制定された。
昭和26年博物館法が制定された。
昭和28年青年学級振興法が制定された。
昭和31年地方教育行政の組織及び運営に関する法律が制定された。
戦後のわが国の教育が、民主主義に基づく国民の生活改造を、その社会的性格としてもっており、社会教育こそ、この生活改造に直結するものである。
このような社会教育は、もはや単なる学校教育の補充や拡張をめざすものではなく、社会変化の激化にともなう社会的要求として、人間の生涯教育の性格をもつものに漸次変りつつあるものになっている。
そのために教育基本法や、社会教育法等の制定をみるにいたった。
同法の施行により、図書館・博物館・公民館等をはじめ諸施設が整備され、青少年、成人、婦人、高齢者、労働者等に対する社会教育活動が活発になった。
またこれ等を指導する機関としての、社会教育委員が設置され、社会教育関係諸団体も発展して、社会教育にとって、過去80年の歴史にかつてみられない飛躍と充実が図られている。
まさに、社会教育の復興期ということができる。この背景には、学校教育の整備が、不安視された六・三制の軌道にのったことにより一段落したことと、他方、わが国民生活の要望や社会課題が公然と問題にされることが可能になった事実を忘れてはならないであろう。
オ、明治期の特徴
(ア)社会圏(けん)の拡大の影響
人間形成という教育現実は、単に学校教育に限ることなく、広く文化が、国民に伝達されるその媒介となるところのものを含めて、考えて見なければならない。
この観点から、明治以降の交通、通信、出版等の発達による、社会圏の拡大が、日本の村落の生活にいかなる変化を与え、人々の形成に対して、いかなる影響を与えたか注目すべきことである。
明治以降の交通関係、自転車、電車、汽車、汽船などの急速な普及発達は、旅の観念を一変して、隣接地はもちろん、都会と村落との往復連絡を、急激に可能増大させて、接触交渉を躍進的に容易ならしめただけでなく、村落の人々の世界を広めることに役立っている。
また郵便制度の確立は、新聞、雑誌の普及とともに、村落に外界の精神文化をもたらし、一大変革を生ぜしめた。
更に郵便制度とともに電信電話の開通は、村落が開放された感がある。
これらの発達は、要するに、国民の視野を広め、その見聞を豊かにし、知識文化の向上と、交換を便利ならしめる上に、大いに助けとなったといわなければならない。
(イ)出版文化の影響
新聞雑誌などのような出版文化が、いかに文化の普及、村民の視野の拡大に対して、貢献をなしているか、その教育的役割の大であることは軽視できないのである。
一体わが国においては、幕末すでに、外国新聞のほん訳などが現われているが、安政頃には、読売りまたは呼び売りと称した不定期刊行の新聞紙ともいうべきものがあった。
しかし、はじめて正式に新聞を発行したのは、元治元年(1864)であり、その後明治に入って、日刊新聞が中央につづいて、地方において刊行され、文明開化のさきがけとなり、また自由民権運動に対して有力な助けとなった。
次に雑誌について見るに、明治6年(1873)に「文部省雑誌」が刊行され、8年には「文部省年報」が刊行された。
ついで福沢諭吉をはじめ、当時の著名学者を、ほとんど網羅(ら)して発行した「明六雑誌」が刊行され、順次民間雑誌が刊行されるようになった。
以上明治初期の新聞雑誌をはじめ、一般出版文化は、政治熱の旺(おう)盛という特殊事情に結びついて発達している。
何となれば、明治初年の政治熱は、初めは多少暴力主義に傾いていたが、後には主として言論戦に終始するようになったので、その言論戦の機関として、新聞雑誌が大いに役立ったのである。
それで、当時のジャーナリズムはニュース本位、報道本位、興味本位というのではなく、真の意味で社会の教化的使命を自覚し、人民の啓蒙(もう)的、指導的、開化的先達となることをもって第一の任務としてる。
当時の新聞雑誌であるが、その精神なり内容なりに至っては、全く当時の啓蒙的開化的な出版物と、多分に共通したものをもっていた。
カ、戦後の特徴
(ア)レクリエーション
レクリエーションが一つの言葉として理解され、一つの運動として展開されて来たのは、日本では戦後のことである。
主として、社会性のある集団の行事として、急速に発展して来たものである。
レクリエーションとは、言葉の上では、ふたたび創造するということなのであるが、戦時中の厚生運動が、団体訓練や、福祉事業、共済(さい)運動だけを強調したのと異なり、われわれが、仕事や勉強などによって、疲れたり退屈したとき、各人が、進んで楽しみや喜びによって、精神的にも、肉体的にも、新しい力をもりかえす、ということに解釈(しゃく)してもよい。
レクリエーションは、何らかの形の自己表現によって行なう楽しみや、喜びに関するすべての活動を含んでいる。
その種類としては、客内および客外ゲーム、スポーツ、音楽、演劇、舞踊、工作その他人間生活のあらゆる分野に見出すことができる。
しかも、それは一つ一つで独立して考えられるばかりでなく、もっと総合的な形態で考えられなければならない。
また、レクリエーションは、決して単なる楽しみや、喜びだけに終ってはならない。楽しみや喜びの中に、明日への準備がひそんでいなければならないので、それは疲れや退屈を解消して行くのと同時に、いつしか生活を楽しむことを学び、生活をリズム化し、規律化し、社会的な協同の精神を学ぶものでなければならない。
さて社会教育の方法の傾向の一つとして、練成的方法から、社交的な方法へ移らねばならぬことである。
人と人と接触を盛んにし、明るい楽しい社交のうちに、教育活動が促進されるように、いわゆるレクリエーションによる相互教育が、社会教育の一つの大きな分野をなしている。
(イ)マスコミュニケーション
二十世紀後半にあらわれた大きな魔物が二つある。その一つは原子力であり、他の一つは、マスコミュニケーションである。
原子力が、物理的な研究によって、外的あるいは物理的な影響をもたらすのに対して、マスコミュニケーションは、人間の心に作用する精神的なものということができよう。
だからこれが正しく利用されたなら、人間を未成熟から成熟へと導き、進歩と発展の上に大きな力となるのである。
ところで、マスコミュニケーションとは何か、簡単にいえば、コミュニケーションとは通信、伝達、通報による意志伝達等いろいろにいわれている。
お互い同志が、通じ合い言語、動作、共通の記号のようなもので、お互いが通じ合うことがコミュニケーションであるが、大体次の四つの型がある。
1、少数の人から少数の人へ
2、多数の人から多数の人へ
3、多数の人から少数の人へ
4、少数の人から多数の人へ
この四つの型のうち、4の型をマス(大衆)コミュニケーション大衆通報と呼び、略してマスコミと称している。
大衆通報手段であるマスコミは、少数が発信して多数が受信するものであるとすれば、それはラジオ、テレビ、新聞、大衆雑誌、映画などが代表的なものといえよう。
これらのものの働きを考えてみると、どれもが一方的にわれわれに働きかけている。
そこには、相互の交流作用はみられないだけでなく、内容的にみて質の善悪ということも問題になる。
そのままうのみにすれば、古い時代の教育と同じであって、それが伝えるままに信じ、動くことになり、ついにそれなしでは、動くことのできない人間になってしまう。
現代社会は、このマスコミが非常に強く働いている社会で、もしこのまま放置しておけば、効果もあるが逆効果もある。
現在社会の中で生活している者は、特にこの働きに注目して、立派な人間となるために、立派な社会を作るために、マスコミを教育的に、しかも効果的に活用したいものである。
マスコミは、現代の魔術でもあるわけで、この現代の魔物の呪(のろ)いからのがれる術は、国民の一人一人が、よくこの原理を理解して、一方的な働きかけをさける以外にはない。
新聞をみても、ラジオを聞いても、テレビを視聴しても、映画を見ても、それが果たして真実か、果たして可能かなどと、考えたり判断してゆける人間にならない限り、この呪咀(じゃそ)からはのがれられない。それには高い知性と、豊かな経験が必要である。社会教育の方法は多彩である以上、マスコミを扱うことも多いはずである。学級や講座の育数計画の中に、織りこんでマスコミと自主的に対処できうるよう受け止め方を、身につけさせることがきわめて大切である。
二、昭和44年度身延町社会教育事業計画
(一)基本方針
理想的な文化生活を営むために、「住みよい、美しい町づくり」を主眼とする人づくりの活動を展開するなかで、社会の変容はわれわれの生活の上に、新しい幾多の複雑な問題を提起している。ここに、社会教育が果たす役割りは、必然的に従来のあり方を大きく、脱皮する必要に迫られており、いわば重大な転機にあるといえる。
本町においても、この重要性に対処し、年々社会教育施設の整備拡充につとめるとともに、人的体制の配備、条件等積極的に促進してきたが、今日的課題解決のためには、地域住民の主体性にまつところは大きい。
本年は、この基礎づくりを解明しながら、確実に積み上げをとおして、本町進展に寄与していきたい。
(二)目標
| 1 | 、地区公民館を基盤とした、部落公民館の内容充実、あわせて住民の主体性を確立する。 |
| 2 | 、住民の健康増進をはかるため、社会体育の振興をはかるとともに、健全なるレクリエーションを普及する。 |
| 3 | 、文化財の愛護と自然の保護運動を促進する。 |
| 4 | 、社会教育関係機関および団体との連絡を密にして、組織の助長、本町の活動家養成発見につとめる。 |
| 5 | 、美しい、きれいな町づくりとして環境の浄化をはかり、一軒一鉢運動を展開する。 |
三、身延町総合社会教育推進会議
戦後23年、わが国産業、経済、文化の驚異的発展は私たちの生活にかならずしも対比しつつ進められて来たとはいいきれず、住民生活の上に新しい問題を提起して来ている現代、社会教育の必要性は日ごとに、その重要度を加えている。本町においては、これらに対処し本年度昭和43年度企画課を新設、町建設の長期計画の策定を急いできた。このときにあたり「社会教育の果たす役割はどのようにすべきであるか」等の究明は急務となっている。
従来ともすると、これを社会全体の問題とせず限られた集団や組織を対象に表面的活動に陥りやすく、時代欲求のなかから根源的な問題を忘れ、余りにも理論に終始してきたうらみがないでもなかった。
こうした観点から広い視野に立って現況を考察し、本町将来の方向にむかって住民のえい知と抱負を傾注して、「みんなでつくるわが町」を期待しながら、地域有志指導者の構成をもって本会議を発足させ、計画の遂行をはかっている。
会議推進委員
町長以下各課長・教育委員・公民館長・管内小中学校長・社会教育委員・町建設審議会委員・社会教育関係団体代表者・学識経験者若干名 計九十名
会議の進行および内容
第一回会議
昭和四十三年十一月二十五日
社会教育の必要性を理解するための話し合いを深め、今後の進め方を協議する。
基調講演「町行政推進上社会教育はどのような役割を果たしたらよいか」
講師、県社会教育課長中楯仁兵
第二回会議
昭和四十三年十二月十一日
住民の要求課題の把握と本町長期計画および目標の展望を探る。
基調講演「県政の基本計画の動向」
講師、県企画管理室副主幹 佐久間実
第三回会議
昭和四十四年一月二十七日
住民の要求問題解決のために
町長以下各課長・教育委員・公民館長・管内小中学校長・社会教育委員・町建設審議会委員・社会教育関係団体代表者・学識経験者若干名 計九十名
会議の進行および内容
第一回会議
昭和四十三年十一月二十五日
社会教育の必要性を理解するための話し合いを深め、今後の進め方を協議する。
基調講演「町行政推進上社会教育はどのような役割を果たしたらよいか」
講師、県社会教育課長中楯仁兵
第二回会議
昭和四十三年十二月十一日
住民の要求課題の把握と本町長期計画および目標の展望を探る。
基調講演「県政の基本計画の動向」
講師、県企画管理室副主幹 佐久間実
第三回会議
昭和四十四年一月二十七日
住民の要求問題解決のために
| 社会教育の | 施設、設備の拡充強化 人的条件整備 運営、組織の近代化 |
現状を分析する。 |
第四回会議
昭和四十四年二月十二日
町社会教育計画の方向と視点の上に立って
各界代表者によるパネル討議
「私たちの町をこのような町にするには、いま町として必要なことはなにか」
パネル登壇者
昭和四十四年二月十二日
町社会教育計画の方向と視点の上に立って
各界代表者によるパネル討議
「私たちの町をこのような町にするには、いま町として必要なことはなにか」
パネル登壇者
| 議会代表 | 議長 | 鴨狩富治 | ||
| 宗教家代表 | 窪之坊住職 | 堀一勇 | ||
| 婦人代表 | 婦人会長 | 佐野数恵 | ||
| 青年代表 | 青年団長 | 阿久津行広 | ||
| 農家代表 | 農協組合長 | 若林孝義 | ||
| 商工会代表 | 青年部会長 | 池上芳広 | ||
| 教育関係者代表 | 校長会長 | 高山巌 | ||
| 住民代表 | 区長会長 | 名取貞雄 |
第五回会議
昭和四十四年三月九日
社会教育研究大会
昭和四十四年三月九日
社会教育研究大会
町づくりと社会教育の必要性の確認と反省、関係者の協力体制の強化、さらに住民の町政参加を期待して研究大会を行なう。
四、新生活運動について
(一)新生活推進運動の目標
| 1 | 、公害など生活を阻害する環境の悪化から、住民による生活防衛の手段として、生活環境の四大原則である安全、健康、能率、快適の現実をめざす住民運動の展開。 |
| 2 | 、農業経営の近代化、住民自治、新しい地域社会の生活秩序の建設などをねらいとする、地域住民による創造と実践の運動展開。 |
(二)新生活運動推進協議会の構成メンバー
町当局関係者、町議会議員、教育委員、社会教育委員、公民館長、社会教育関係団体代表者(小中学校長・婦人会・青年団・PTA・区長会・生活改善グループ等)
(三)生活改善運動
昔ながらの冠婚葬祭のあり方が、物質的向上と結びついて近来これらの行事は次第に華美になる傾向があり、周囲にひきずられたりまた虚栄のために、実力以上に派手を競うような弊害さえ生じている。これに対し一方では若い世代層や、直接台所を預かる婦人層、有識者などを中心に反省と改善の声もあがっている。
昭和43年度、町社会教育委員会は町教育委員会の諮問にこたえて生活改善運動の推進を答申、婦人会をはじめ各種団体や区長を中心に推進組織を作り、これにとり組むよう要望した。
一方町婦人会は、42年度より生活改善にとりくみ43年度には実践目標として次の5項目を決定、町と、町教育委員会および町区長会の協賛のもとに全戸にこれを配布し、お互にこれだけは守ろうとよびかけた結果、かなりの成果をあげている。
しかし、全体としては今なお形式的な虚礼やおつき合いの消費的傾向が改められず、なおいっそうの運動推進が望まれる。
「身延町新生活運動実践五項目」
一、諸会合における時間の励行。
二、出産祝は男女を問わず長子のみとする。
三、節句祝、入学祝は実父母、兄弟のみとする。
四、病気見舞の返礼を廃する。
五、親送りより帰っての振舞いを廃する。
提唱 身延町婦人会
協賛 身延町 身延町教育委員会 身延町区長会
一、諸会合における時間の励行。
二、出産祝は男女を問わず長子のみとする。
三、節句祝、入学祝は実父母、兄弟のみとする。
四、病気見舞の返礼を廃する。
五、親送りより帰っての振舞いを廃する。
提唱 身延町婦人会
協賛 身延町 身延町教育委員会 身延町区長会
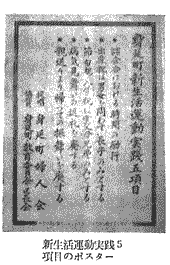 |
また、社会教育活動の面でも、生活改善の推進が年度の重点目標に取り上げられ、各公民館とも事業計画の中に織りこんでいる。
身延公民館は、美化運動推進地域として県の指定を受けたが、環境の美化と、冠婚葬祭の合理化を二つの軸として新生活運動を展開することを申し合わせている。
婦人会も、前記5項目の実践項目に「冠婚葬祭の合理的活用をはかる」をつけ加えて、新たな意欲をもって運動をおしすすめようとしている。

