(四)身延町立豊岡公民館
ア 館名・所在地・沿革身延町立豊岡公民館(身延町相又469)
昭和25年豊岡中学校内に、豊岡村立豊岡公民館を設置した。
昭和30年町村合併により、館名変更身延町立豊岡公民館となった。
昭和30年豊岡支所(旧役場)内に移した。
昭和37年支所廃止につき支所を公民館とした。
昭和38年はじめて専任主事をおいた。
昭和42年5月郡公連から42、3年度にわたり研究を委嘱された。
研究課題 新築公民館の運営と住民滲透(しんとう)活動。
昭和43年4月新築公民館竣工。
総工費 429万3,000円
町費 323万円
内訳 県費補助 70万円
地元寄付金 36万3,000円
歴代館長 主事
| 初代 | 松田寛 | |||||
| 2代 | 鴨狩庸雄 | 遠藤松之助 | ||||
| 3代 | 鈴木富治 | 遠藤松之助 | ||||
| 4代 | 柿島武文 | 渡辺一郎 | 今村知夫 |
(ア)設置区域の状況
| 小部落散在、交通不便、遠隔部落あり、人口 1,938名、最大通館距離 6キロメートル |
| 本館非常勤館長1・主事用務員各1・(共に専任)・運営審議委員 15名・部組織 5部 総務・教養・産業・体育厚生・図書文化 分館8館 小田船原・門野・湯平・大城・相又下・相又上・清子・横光 |
| 木造2階建亜鉛板葺・事務室1・会議室1・講座室1・その他 図書150冊・机21・椅子54・黒板1・テレビ受像機1・ラジオ受信機1その他 |
方針「健康で、明かるい、豊かな郷土建設」
目標
1 会議には進んで参加し時間を励行しよう。
2 お互いに法規を守り交通安全を図ろう。
3 青少年を愛護育成しよう。(家庭の日励行)
4 虚礼を廃して近代生活を築こう。
5 環境を整備し美しい郷土にしよう。
6 あいさつ運動を推進しよう。
昭和43年度の努力点
1 施設設備を充実する。
2 部活動を活発にする。
3 レクリエーション活動を推進する。
4 分館を整備し活動を盛んにする。
5 自主グループの育成につとめる。
6 広報活動を通じ住民滲透を図る。
昭和44年度事業計画
| 月別 | 事 業 名 |
| 4 | 諸計画 |
| 5 | 合同会議 館報発行 婦人学級 地域開発講座 交通安全運動 老人クラブレクリエーション 図書購入 |
| 6 | 青年教室 |
| 7 | 新生活運動推進会議 青少年夏季対策懇談会 青年教室 婦人学級 家庭教育学級 地域開発講座 各部連合視察旅行 郷土調査 |
| 8 | 館報発行 青年教室 婦人学級 家庭教育学級 青少年球技大会 盆おどり大会 俳句会 |
| 9 | 運営審議会 青年教室 婦人学級 家庭教育学級 防災宣伝 園芸サークル研究会 敬老会協力 郷土調査 |
| 10 | 館報発行 新生活運動推進会議 青年教室 家庭教育学級 地域開発講座 交通安全運動 体育祭 読書週間 |
| 11 | 運営審議会 青年教室 家庭教育学級 防火運動 |
| 12 | 公民館祭(講習会農産物品評会文化展) 青少年冬季対策懇談会 青年教室 婦人学級 |
| 1 | 新年懇談会 青年教室 家庭教育学級 短歌会 |
| 2 | 館報発行 新生活運動推進会議 青年教室 婦人学級 家庭教育学級 地域開発講座 |
| 3 | 合同会議諸反省 青年教育 家庭教育学級 防火運動 老人クラブレクリエーション 郷土調査 |
| 通年 | 園芸サークル活動 文芸サークル活動 |
ウ 公民館活動の一例・相又下分館の活動
(ア) 部落の概況
国道52号線沿いで、部落内に小、中学校・体育館・公民館・郵便局等があり、戸数は36戸、15分以内に集合できる。住民の大部分は、農林業に従事しているが、最近県外へ通勤する壮年が多くなった。
(イ) 分館活動
昭和25年豊岡公民館発足とともに、分館をおき寺院を使用していたが、28年部落共有林を処分して独立分館を部落中央に新築した。
| 1、施設 内訳 |
木造平屋建亜鉛板葺25.16平方メートル 講堂・小会議室・炊事場・便所等 |
|
| 2、設備 | 机大10・小6・椅子50・食卓10・黒板1・図書戸柵2、卓球用具1式・座布団80枚・食器類100人分・大小火鉢各2・炊事用具1式(食器類その他希望者には貸し出す) |
| 3、分館役員 | 分館長1 主事1 共に任期2年 運営委員 区役員 団体代表 任期1年 |
| 4、事業 | 分館活動の目標 時間励行とあいさつ運動 |
| イ | 区定例会 毎月5日 部落全戸対象 出席率 80パーセント以上 | |
| ロ | 婦人会 毎月10日 婦人学級開催 | |
| ハ | 育成会 青少年育成と環境整備 | |
| ニ | PTA支部・体育後援会支部 部落懇談会・夏季ラジオ体操の会開催・球技大会参加・レクリエーション推進 | |
| ホ | 子供クラブ 夏季共同学習会・キャンプ・クリスマス・新年を祝う会・公共施設の清掃 | |
| ヘ | 運転者会・交通安全母の会 各種交通安全対策実施 | |
| ト | 消防団 災害防止運動推進・婦人会と協力して環境衛生に留意 | |
| チ | その他 部落全戸参加日帰りの旅行年1回実施・体育館利用夜間バレーボールの練習・自主グループ活動(生花読書等) |
(備考)昭和43年5月活動を認められ、身延町教育委員会から表彰された。
(五)身延町立大河内公民館
ア 館名・所在地・沿革身延町立大河内公民館(身延町九滝653)、昭和28年大河内村立大河内公民館を、大河内体育館内に設置した。
 |
昭和37年大河内支所廃止に際し、同建物を公民館とした。
昭和40年郡公連から40・41年度にわたり、研究を委嘱された。
(研究課題)婦人会活動の実態把握と指導
昭和40年度から、体育館を公民館管理にした。
歴代館長 主事
| 初代 | 鮎川省三 | 望月卓爾 | 武藤正 | |||
| 2代 | 伊藤 太 | 望月卓爾 | ||||
| 3代 | 望月正一 | 望月卓爾 | 市川覚雄 |
(ア)設置区域の状況
人口 2,624名 遠隔部落3あり 最大通館距離 6キロメートル
(イ)公民館の構成
本館 非常勤館長1・主事用務員各1(共に専任)運営審議会委員15名
分館 7館・上八木沢・下八木沢・帯金・塩之沢・角打・和田・大島
(ウ)施設設備
| 木造2階建瓦葺 館長室1・事務室1・会議室1・図書室1・談話室1その他、特に家事実習設備を有す。 図書1,700冊・机5・椅子119・黒板4・16ミリ映写機1・録音機1・プレイヤー1・ラジオ受信機1 |
| 1 | 郷土づくり部落懇談会を開催し、指導者の養成と、よい部落づくりにつとめる。 |
| 2 | 課題解決部落学級を(4〜5ヵ所)開設し、住民による共同学習の成果をあげ、分館活動の拠点をつくる。 |
| 3 | 家庭教育学級(4〜5部落)を開設し、家庭教育の振興を図り、あわせて分館活動の拠点をつくる。 |
| 4 | 小中学校・PTA・子供クラブ・スポーツ少年団等と関連をとり、諸活動を盛んにし少年教育の振興を図る。 |
| 5 | 郷土美化、1鉢運動を展開し、情操純化を図る。 |
| 6 | 生活に直結する自主グループの発見と養成に努め、生活の近代化を進める。 |
| 名 称 | 大河内地区席書大会 | |
| 主 催 | 大河内公民館・大河内地区青少年育成会連絡協議会 | |
| 後 援 | 山梨日日新聞社 | |
| 沿 革 | 青少年の冬の生活指導の一環として、昭和40年1月から実施して来た。第3回までは図画も併せ行なって来たが、運営上から、第4回からは習字だけにした。 | |
| 対 象 | 帯金、大和、身延小学校児童、大河内中学校生徒 昭和44年1月6日実施第5回の状況 |
|
| 会 場 | 大河内公民館・大河内中学校・帯金小学校・大和小学校 | |
| 参加者 | 374名 |
| 賞別 | 特賞 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 褒賞 | 計 |
| 入賞数 | 17 | 25 | 32 | 50 | 99 | 323 |
備 考 回を重ねるにしたがって参加者が増加し、成績も向上している。
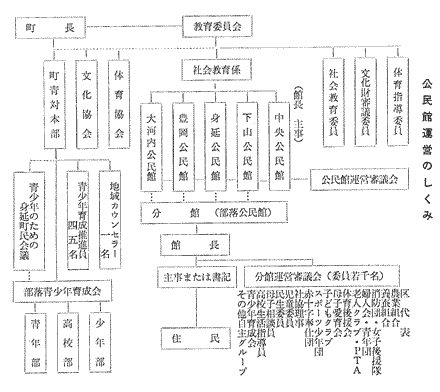 |

