第七節 子どもクラブ
一、子どもクラブの起こり
昭和14年・5年(1939〜40)の頃東京では各界の文化関係者が集まって、児童文化財を良質化するために、運動を展開しこれを児童文化運動と呼称していた。戦後混乱した社会のなかに放置されていた子どもたちを、健康で安全な楽しい集団の遊びを通じて、新しい社会の秩序を学び、前途に明るい希望を与えようと、地域のおとなが協力、援助して生まれた子どもの自主的な集団である。昭和22年に児童福祉法が制定され、すべての児童を健全に育成する社会の責任と義務が示されてから、県や市町村をはじめ、地域社会や家庭においても、積極的に児童の福祉を図るための施策が推進されてきた。昭和23年、山梨県は全国にさきがけて子どもクラブを全市町村に設置した。その後、2・3年たつにつれ、全国に子供クラブが生まれていった。当初の子どもクラブは、子どもの日常の遊び友達を中心にして自然発生的に生まれた集団を主体に、その地域のおとなたちが援助して運営されて来た。昭和26年児童憲章の制定により、新しい児童福祉思想の普及、家庭や地域社会の理解が深まり、その地域を基盤にして、すべての子どもが参加し、民間の篤志家や学校の教師、地域指導者によって具体的活動の指導と助言が行なわれるようになった。昭和32年、天野知事の重要施策である青少年総合対策が実施されるに至り、子どもクラブの活動は地域においてさらに重要視され、地域住民の理解と協力に支えられながら年々着実な発展をとげて来た。一方、青少年総合対策のもとで地域ぐるみの青少年育成会の組織結成が進められ、子どもに対する教育の場に意が注がれ、青少年の健全育成に民間と行成との体制が確立されたことはまことによろこばしいかぎりである。二、身延町子どもクラブの実態
(一) 子どもクラブの数および会員数
(昭和43年調)| 子どもクラブの数 | 会員数 | 小中学校 児童生徒数 |
組織率 |
| 34 | 1,539 | 2,150 | 71.6 |
| (注) | 子どもクラブのない地域も現在は青少年育成会の少年部に所属している。 |
(二) 指導者の状況
今回の調査によると34の子どもクラブに対し、指導者は91人の多きに及んでいるが、育成会の指導者(いわゆる役員)の兼任が多い。1クラブ平均2.7人で指導していることになる。 |
 |
(三) 活動の状況
廃品回収・神社の清掃・キャンプ・火の番等自主的に計画されているところもあるが、他は育成会が主体となっての活動が多く、子どもたちはその参加者となっている。三、子どもクラブ指導者講習会の開催
本町では毎年夏季生活を意義あるようにするため、昭和32年より子どもクラブの幹部、指導者を招集して講習会を開催し、その意識高揚につとめている。この講習会は南部第一連合PTAの提唱によって始められたもので、いまでは町の教育委員会や学校当局の理解ある援助によって年々盛んになってきた。(一) 第12回身延町子どもクラブ幹部、指導者養成講習会のあらまし
ア、趣旨産業、経済の発展は本町にも都市化現象をきたし、青少年の環境は、かならずしも良いとはいいきれず、もとより各家庭を中心に関係機関および団体等の協力を得て、青少年の健全育成は日増しに活発化されつつあるが、非行はあとをたたず、夏季生活をむかえその指導には万全の体制を築かなければならない。このときにあたり、青少年の健全なる育成は野外活動をとおして、自然に親しむなかに奉仕・友愛・郷土愛の共同精神を養うことは、きわめて重要である。よって、この講習会を開催して地域指導の幹部を養成する。
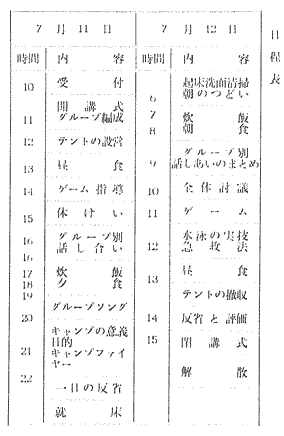 |
身延町、身延町教育委員会、南部第一連合PTA
ウ、期日
昭和43年7月11日〜12日(1泊2日)
エ、会場
身延小学校周辺
オ、参加者
育成会関係指導者、子どもクラブ指導員、PTA役員、青年集団幹部、子どもクラブ幹部(65名)
カ、日程表
四、結び
今後、児童憲章の精神をよく理解し、子どもクラブの育成を推進することは言をまたないところであるが、地域育成会との関連のなかで、はっきりした位置づけをする必要があるということを強く感ずる。(付)
昭和29年5月9日第7回児童福祉週間子どもまつりに際して、山梨県知事より優良子どもクラブとして下山の大庭子どもクラブが表彰された。

