三、町指定のものとその他
(一)建造物
ア、身延山総門 身延町 元町寛文5年(1665)9月建立し、寛保元年(1741)日朝上人のとき改修し、安政7年(1860)日楹上人代屋根替をした四脚門(高麗門)で、欅の角柱、瓦葺である。高さ9.35メートル、間口6.36メートル、奥行3.64メートル、自然石を礎石として、柱正面幅85.00センチメートル、柱側面幅56.00センチメートルで規模広大である。第三十六世日潮上人筆の「開会関」の大額が掲げてある。開会とは一切衆生の仏性を開発させ、すべてまとまる意味で、この関門はそういう信仰の境地に入るしるしという意味である。
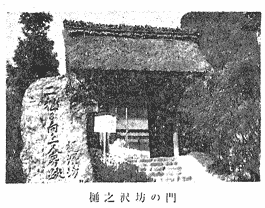 |
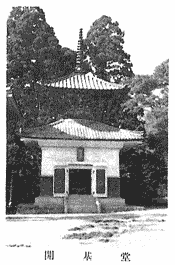 |
昭和44年9月12日町指定
イ、樋之沢坊門 身延町西谷樋之沢坊境内
寛文年間(1661−72)の建立で四脚門、丸柱、茅葺で間口2.25メートル、奥行2.00メートル、高さ4.04メートルである。
昭和41年6月1日指定。
ウ、開基堂(二重塔) 身延山久遠寺境内
間口5.45メートル、奥行5.45メートル、高さ約9.10メートルの建造物で、文明4年(1493)11月、日徳上人勧請により建立した二重塔で、明治24年(1891)第七十五世日修上人代、祖師堂西へ上之山から移転建築したものを更に昭和9年(1934)2月宝物殿の西に移し、丹(に)塗りの古雅な九輪露盤が中央に聳(そび)えている。ここに身延山開基南部六郎実長公の坐像が安置されている。
昭和44年9月12日町指定
(注)昭和54年2月久遠寺本堂建設に伴い、御真骨前に移転した。
エ、本師堂 身延山久遠寺境内
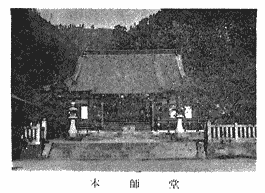 |
奥殿は、間口8.79メートル奥行5.15メートルで川端半兵衛の寄進で、昭和14年5月竣成した。
ここには立像の釈迦像を安置し左右に本山歴代、脇仏間には直檀大檀那の位牌が祀られてある。
昭和44年9月12日町指定
(注)昭和54年2月久遠寺本堂建設に伴い解体された。(指定解除)
オ、鬼子母神堂 身延 上の山
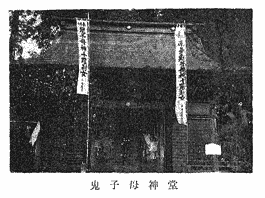 |
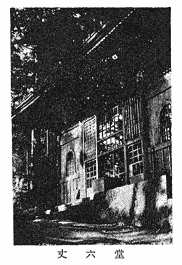 |
昭和44年9月12日町指定。
カ、丈六堂 身延 錦ヶ森
10.91メートル四方の建物で、身延山第二十六世日暹上人代建立、寛永20年(1643)完工した。丈六の釈尊像は京都中正院日護上人の作と伝えられている。堂内に奉祀してある千体仙はお万の方の寄進である。初め本山前庭にあったのを、第二十八世日奠上人代寛文4年(1664)に今に移転したものである。
昭和44年9月12日町指定。
キ、思親閣本堂 奥之院思親閣境内
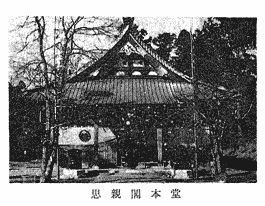 |
昭和44年9月12日町指定。
ク、七面山本殿 身延町 七面山
七面山(1,989メートル)中の1,699メートル地点に建立された、7.27メートルに7.30メートルの堂宇で、構造優雅典麗で、しかも絢爛豪華、極彩色の格天井、欄間に描く天女像も、また留魂丹精の作である。
前に拝殿と幣殿があり、拝殿は13.64メートルに9.09メートル、幣殿は10.08メートルに8.18メートルの神社建築の特殊形式で、一般建築様式の形を破った七面山本社独特の形式であるところから、通称七面造りと呼んでいる。大方の形式は入母屋造りの変形で四面錣葺の入母屋破風となっている。どちらかといえば千鳥破風を四面に寄せ、棟は十字になっている。正面は全面軒唐破風となって現代建築の常識を無視した様式である。
延宝3年(1673)8月9日、本殿庫裡等を建立、前面「七面大明神」の額は、延宝7年(1675)9月関白鷹司房輔卿筆で「宝珠院」の額は、身延山第六十四世日潤上人の筆である。(巻首写真参照)
昭和41年6月1日町指定。
ケ、清正公堂 清住町逕泉坊境内
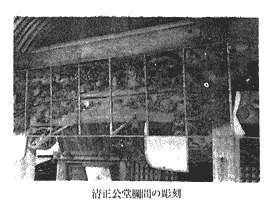 |
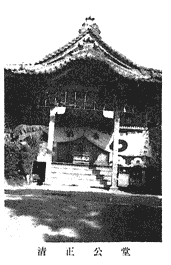 |
昭和41年6月1日町指定となる。
コ、大野山本遠寺本堂(重要文化財) 大野山本遠寺
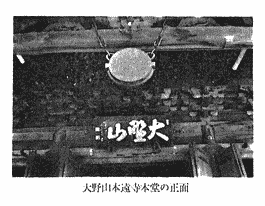 |
昭和41年6月1日町指定、昭和61年1月22日鐘楼堂と共に国指定となる。
サ、一宮賀茂神社本殿 身延町 下山
身舎 間口 2.02メートル
奥行 1.63メートル
向拝 間口 2.08メートル
奥行 1.47メートル
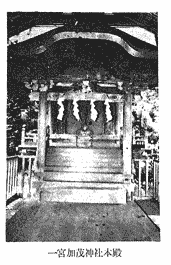 |
一間社流造り欅(けやき)材を使用し、屋根は銅葺である。身舎の表は四手先、裏は二手先、2段の斗拱で支えられ、蛙股(かえまた)の束の中に彩色の菊の彫刻があり、左右の蛙股の束の中に鳳凰(ほうおう)、向拝の蛙股の束には獅子の彫刻がある。社殿は紅穀(べにがら)、彫刻は呉須(ごす)を用いて塗ってあり、桃山期の形式を模した建築物である。棟(むな)札によると、元和7年(1621)十二月念二日、棟梁竹下喜兵衛によって建築したものを、元禄2年(1689)石川伝右衛門、佐野甚左衛門、松村治兵衛等が修理し、更に昭和30年石川信光、松木繁春、佐野富一等によって大修理され、檜皮葺を銅葺にした、拝殿は文久3年(1863)3月19日、牛奥喜兵衛、石川市郎左衛門等によって建築、間口9.09メートル、奥行5.50メートルの茅葺である。本社殿は下山大工の本町内に残した著名な建物として大いに意義ある建築である。
昭和44年4月5日町指定となる。
シ、古仏高祖御厨子 下山 本国寺 蔵
間口 0.98メートル
奥行 0.69メートル
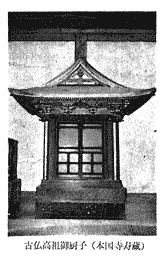 |
昭和44年4月5日町指定となる。

