(二)工芸
ア、覚林坊の磬 東谷 覚林坊 蔵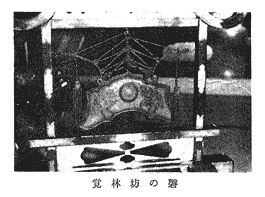 |
昭和41年6月1日町指定となった。
イ、穴山信友夫人使用の椀 下山 南松院 蔵
外側黒、内側朱、塗は幼稚であるが螺鈿(らでん)をちりばめてある。永禄頃(1558—1569)の甲州物の特徴をあらわした信友夫人使用の大小5箇の椀である。
昭和44年9月12日町指定。
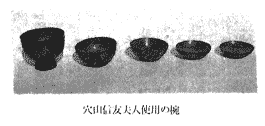 |
古くは金鼓といったが、後世形の上から「ワニグチ」と呼ぶようになった。この鰐口は径36.00センチメートル、厚さ9.00センチメートルで「菩提山長谷寺堯尊改之寛永四丁亥六月十八日施主下山村女中方治工沼上吉次」と鋳造銘をもつものである。
昭和44年9月12日町指定。
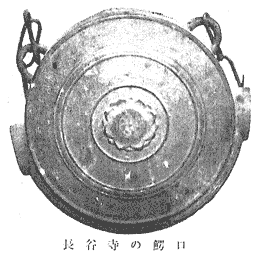 |
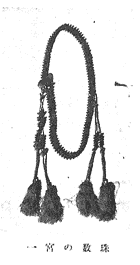 |
材質 ボダイ樹
総丈1.05メートル、主珠丈37.00センチメートル、武田信玄公奉納のものである。数珠は、室町時代より各宗派により自宗の宣伝のために、数珠を改良したが、これは華厳宗の系統をひくものである。おそらく信玄公以前より造られていた特殊な数珠で、あるいは支那から渡来したものと見られる。
昭和44年9月12日町指定。
オ、火玉、水玉の水晶 下山 望月栄 蔵
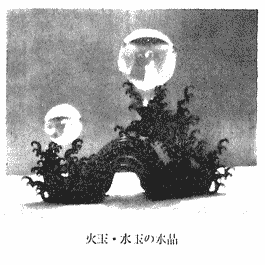 |
昭和44年9月12日町指定。 (注)昭和55年3月 指定解除
カ、太刀一口 下山 望月栄 蔵
無銘であるが、五郎入道正宗の作と鑑定されている。長さ69.39センチメートル、反り1.45センチメートル、目釘穴三ツ、白鞘で鞘書に「五郎入道正宗、長二尺二寸九分、表裏樋有之磨上無銘也明治二十六癸巳三月審査記之洛北鷹峰隠士徳有斉光悦九世之劣孫六十八齢本阿弥長織代七百文」とある。
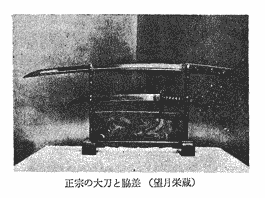 |
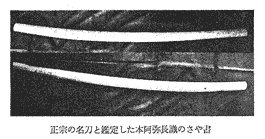 |
五郎入道正宗は嘉暦(1326−28)頃の人で、刃文は五の目乱である。
昭和44年9月12日町指定。 (注)昭和55年3月 指定解除
キ、脇指一口 下山 望月栄 蔵
銘秋広、長さ37.70センチメートル、反り0.60センチメートル、目釘穴二ツ、秋広は相州住で文和(1352−55)頃の人であり、刃文は五の目乱である。
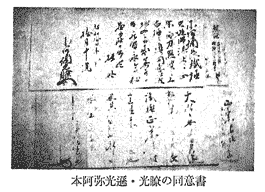 |
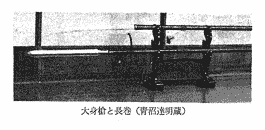 |
ク、大身槍一振 大野 青沼達明 蔵
銘吉秀、嘉永七年寅二月作、長さ53.94センチメートル、反り0、目釘穴二ツ、柄2.18メートル、昭和36年11月29日日本美術刀剣保存会より特別貴重刀剣として認定されている。
昭和44年9月12日町指定。
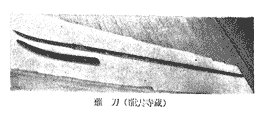 |
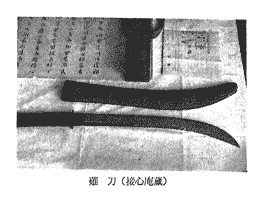 |
銘兼則、長さ35.00センチメートル、反り1.23センチメートル、目釘穴一ツ、柄1.96メートル、甲斐守穴山信縄夫人所持のものと伝えられている。兼則は美濃の住で永正(1504−20)頃の人で今なおすばらしい切味をもっている。
昭和44年9月12日町指定。
コ、薙刀一振 和田 接心庵 蔵
無銘、長さ41.00センチメートル、反り1.30センチメートル、目釘穴一ツ、柄1.00メートル(半分位に切断してある)、貞治2年(1363)接心庵開基の小笠原大学頭義永が使用のものと伝えられている。戦後進駐軍に提出したのを、名刀の故をもって返還された薙刀である。
昭和44年9月12日町指定。
サ、長巻一振 大野 青沼達明 蔵
銘出羽大椽藤原国路、長さ57.57センチメートル、反り1.21センチメートル、目釘穴二ツ、柄1.27メートル、国路は寛永年間(1634−43)の人で山城の住であり、刃文は五の目乱である。昭和36年6月4日、日本美術刀剣保存会より特別貴重刀剣として認定されている。
青貝螺鈿柄薙刀拵 責金鉄地 唐草象嵌 鞘朱塗 石突鉄は昭和36年6月4日特別小道具として、日本美術刀剣保存会より認定されている。
昭和44年9月12日町指定。
シ、太刀一口 大野 青沼達明 蔵
銘次家、長さ62.43センチメートル、反り2.58センチメートル、目釘穴三ツ。次家は承元(1207−09)頃御鳥羽上皇に奉仕した鍛治の1人で備中(岡山県)青江の住で、8月の御番鍛治である。刃文丁字乱。
 |
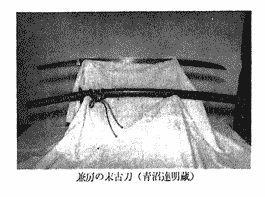 |
金沃懸地梅唐草文鞘太刀拵 目貫梅花図銀地容彫 総金具銀地唐草文毛彫
昭和39年3月22日、日本美術刀剣保存会より特別貴重小道具として認定されている。
昭和44年9月12日町指定。
ス、末古刀一口 大野 青沼達明 蔵
銘関兼房、長さ70.61センチメートル、反り1.98センチメートル、目釘穴二ツ刃文三本杉。兼房は美濃の住、永禄(1558−69)頃の人である。昭和41年3月27日、日本美術刀剣保存会より特別貴重刀剣として認定されている。
茶石地塗鞘打刀拵 縁頭唐武者図 銘奈良春寿造 目貫鐘馗図赤銅地鐔蝶図鉄頭変形
昭和40年9月26日、日本美術刀剣保存会より特別貴重小道具として認定されている。
昭和44年9月12日町指定。
セ、太刀一口 大野 青沼達明 蔵
銘家次、長さ63.94センチメートル、反り1.52センチメートル、目釘穴一ツ、家次は加賀の住、永正(1504−20)頃の人である。刃文五の目乱。
昭和42年4月23日、日本美術刀剣保存会より特別貴重刀剣として認定されている。
昭和44年9月12日町指定。
ソ、脇指一口 大野 青沼達明 蔵
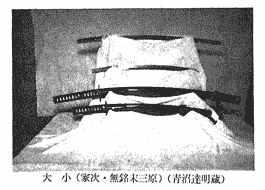 |
 |
昭和44年9月12日町指定。
黒蝋色塗鞘大小拵 縁頭竹虎図赤銅魚子地 目貫虎図赤銅地 鐔竹虎図鉄地丸形高彫 笄家紋唐草 小柄秋草図
昭和42年4月23日、日本美術刀剣保存会より特別貴重小道具として認定されている。
昭和44年9月12日町指定。
タ、脇指一口 大野 青沼達明 蔵
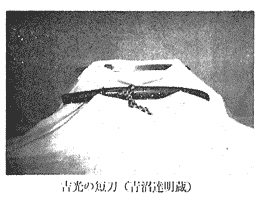 |
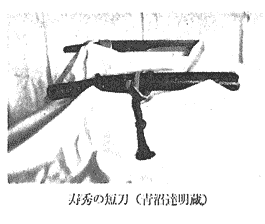 |
黒刻鞘脇指拵 総金具鉄地象嵌 小柄青銅魚子地
昭和38年12月1日特別貴重小道具として日本美術刀剣保存会より認定されている。
昭和44年9月12日指定。
チ、短刀一口 大野 青沼達明 蔵
銘吉光、長さ24.39センチメートル、反り0、目釘穴一ツ。吉光は土佐の住、大永(1521−27)頃の人である。刃文直刃鞘は変り塗短刀拵で、昭和36年11月29日特別貴重刀剣、特別貴重小道具としで認定されている。
昭和44年9月12日町指定。
ツ、短刀一口 大野 青沼達明 蔵
銘寿秀、長さ21.82センチメートル、反り0、目釘穴二ツ。寿秀は土佐の住、文化(1804−17)頃の人物である。刃文直刃。
雲形文塗鞘短刀拵 総金具布袋図 朧銀地目貫犬図 赤銅地 鐔秋虫図鉄地 小柄福禅図朧銀地
昭和43年3月3日、日本美術刀剣保存会より特別貴重小道具として認定されている。
昭和44年9月12日町指定。
テ、短刀一口 大野 青沼達明 蔵
銘兼先作、弘化4年8月日、長さ18.30センチメートル、反り0、目釘穴一ツ。兼先は因幡の住、弘化4年(1847)の作で刃文五の目乱、棟に樋があり刀身に梵字を刻してある。
昭和44年9月12日町指定。
ト、太刀一口 塩之沢 鈴木正臣 蔵
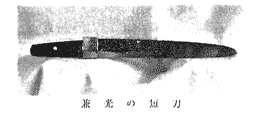 |
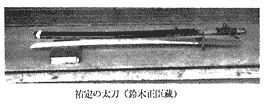 |
昭和44年9月12日町指定。
ナ、脇指一口 西谷 遠藤湛淳 蔵
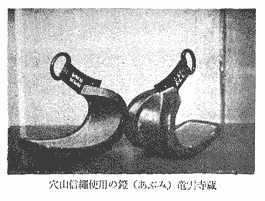 |
銘甲州身延山廣舎、長さ43.20センチメートル、反り1.40センチメートル、目釘穴一ツ。白鞘である。廣含は天文(1532−54)頃の人であるから、武田信玄の活躍した時代の刀工である。飯村嘉章著刀剣要覧によれば「廣舎=甲斐(天文)「廣舎」刃文直刃五の目湾心の足入りもある」と記されてあり、なお甲斐国志には「甲州身延廣舎慶長中(1596−1614)の人なり、小田舟原村に剣工内記なる者の墓所というあり当村は身延の続なり蓋し廣舎というか」とあり。多少年代のずれはあるが、1500年代の刀工であったと思う。残念なことにその作品の現存するものの極めて少ないことである。(巻首写真参照)
昭和44年月日町指定。
ニ、穴山信縄使用の鐙 下山 龍雲寺 蔵
木質で、にかわ固め、漆塗り仕立である。
高さ 26.50センチメートル
長さ 25.00センチメートル
幅 12.00センチメートル
穴山信縄使用の鐙で、普通のものより大きく、飯田系図に「弓法相伝・五人張大勇力、荒馬乗り」とあるによっても、信縄がいかに偉丈夫で剛勇の将であったかが知られる。
昭和44年9月12日町指定。

