(三)彫刻
ア、久遠寺日蓮聖人坐像 身延山 久遠寺 蔵身延山大学の講堂に安置されている日蓮聖人坐像は、身長40.00センチメートル、肩幅29.00センチメートル、膝幅35.00センチメートル、顔の長さ14.00センチメートル、顔幅10.00センチメートル、檜材を使用した寄木造りで、日法上人作と伝えられる尊像である。
昭和44年9月12日町指定。(巻首写真参照)
イ、久遠寺釈迦如来立像 身延山 久遠寺 蔵
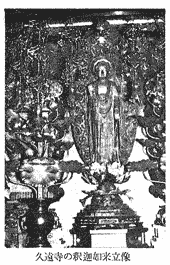 |
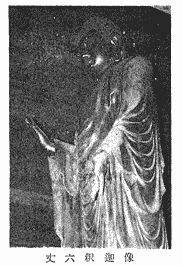 |
昭和44年9月12日町指定。
ウ、丈六釈迦像 身延山 上の山
総丈5.58メートル、面長1.55メートル、面幅1.00メートル肩幅1.76メートルの仏像で、丈六堂に安置せられ、寛永年間(1624−1643)に京都鳴滝三宝寺中正院日護上人の作である。
昭和44年9月12日町指定。
エ、三光堂金銅釈迦如来坐像 身延山上之山 三光堂境内
この釈尊の露坐仏は、61.00センチメートルの蓮華座の上に丈1.82メートル、面長70.72センチメートル、面幅54.55センチメートル、肩幅93.93センチメートル、膝幅160.59センチメートルある坐像で、京極信濃守高勝の寄進により明和9年(1772)造立した金銅釈尊である。
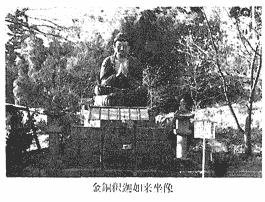 |
オ、三門日荷上人像 身延山 久遠寺 蔵
日荷上人(六浦平次郎入道妙法禅門)像は、貞和4年(1348)8月4日京都四条の大仏師愛憎河島作之丞信紹の作で、首に日荷上人自筆と思われる「妙法」の2字が書かれてある。
総丈45.00センチメートル面長16.00センチメートル、面幅11.00センチメートル、肩幅30.00センチメートル、膝幅49.00センチメートルの坐像である。
昭和44年9月12日町指定。
カ、三門二王尊像 身延山 久遠寺 蔵
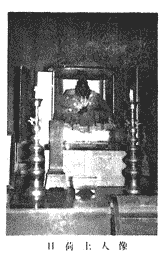 |
昭和44年9月12日町指定。
キ、鏡円坊日蓮聖人像 梅平 鏡円坊 蔵
本像は、檜材を使用し総丈50.00センチメートル、肩幅35.00センチメートル、面長15.00センチメートルで、面幅10.00センチメートル、六老僧日興上人、中老僧日法上人の合作といわれている。台座の下面に
自妙円寺
奉入当山
応安二年乙酉三月十六日
施阿闍梨月澄
寛永十九年壬午九月二十日
当房第□□
祖教円坊日守
敬営
六代日浣判
とあるので、妙円寺より移ったものと思われる。妙円寺は静岡県芝川辺にあった寺であったと思われるが今は判明しない。奉入当山
応安二年乙酉三月十六日
施阿闍梨月澄
寛永十九年壬午九月二十日
当房第□□
祖教円坊日守
敬営
六代日浣判
昭和41年6月1日町指定となる。
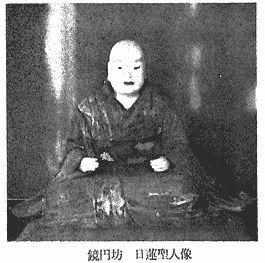 |
木造素地像高さ 1.10メートル、面長9.50センチメートル、面幅7.00センチメートル、肩幅25.00センチメートル。
この像は木喰が82歳の高齢で日本を回国して故郷の丸畑(下部町)に帰るとき、身延を経て帯金に滞在した寛政12年(1800)10月26日の作で、日本千体仏の一つである。
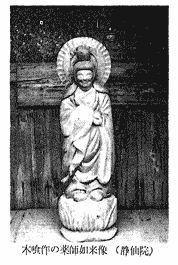 |
笑顔をした仏像の多い木喰の造像の笑いは、飛島時代の仏像の微笑を思いおこさせる。
だがそれは堅苦しい形式の中の表情に生気を与える一つの工夫だったらしく、必ずしも普通に考える微笑ばかりを意味したものでなかった。
ところが木喰彫刻の笑いは、円満な心からくる真の微笑であって、木喰に至って初めて日本の仏像は笑ったといわれている。
昭和41年6月1日町指定となる。
ケ、南部六郎実長公坐像 身延山 久遠寺開基堂内
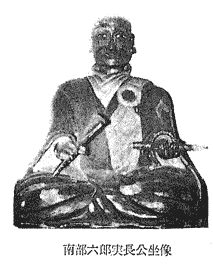 |
その昔南部師行等が輿にのせ戦場を疾駆し、南朝のため忠勤をぬきんでたと南部文書にある由来ある尊い像である。
昭和44年9月12日町指定。
コ、龍雲寺の十一面観音像 下山 龍雲寺 蔵
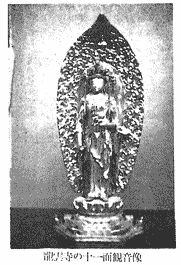 |
 |
昭和44年9月12日町指定
サ、長谷寺の十一面観音像 下山龍雲寺 蔵
総丈台座共60.00センチメートル、面長9.00センチメートル、面幅6.50センチメートル、肩幅18.00センチメートル檜の寄木造りで空洞である。首のまわりなどに朝鮮風の彫刻が現われていて、鎌倉末期高麗の国稽首仏師の作であると伝えられている。
昭和44年9月12日町指定。
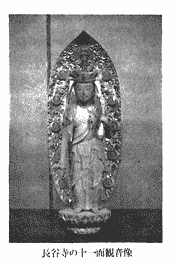 |
総丈台座共47.00センチメートル、面長5.00センチメートル、面幅3.50センチメートル、肩幅9.4センチメートル。
 |
昭和44年9月12日町指定。
ス、南松院のいだてん像 下山 南松院 蔵
総丈73.50センチメートル、面長8.20センチメートル、面幅7.70センチメートル、肩幅19.20センチメートルの御心体の観音像は台座を含めて16.70センチメートルの檜の一木造りで運慶の作と言い伝えられている。いだてんの背後に、「御心体運慶の作文化七庚霜月日新躰安置焉」と記してある。御心体は葵庵尼の看経仏と伝えられている。
昭和44年9月12日町指定。
セ、南松院の釈迦仏
下山 南松院 蔵
 |
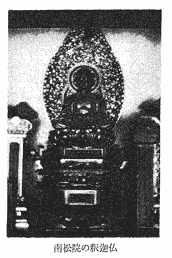 |
昭和44年9月12日指定。
ソ、本遠寺木造釈迦如来立像 大野山 本遠寺 蔵
この仏像は総丈97.70センチメートル、面長11.00センチメートル、面幅9.4センチメートル、肩幅23.50センチメートル、で内刳のある檜の寄木造り、布張り漆箔の本格的な立像で、頭部内部にかすかにのこる墨書によって、今から七百余年前の文永3年(1266)5月法橋、覚慶等によって作られたものと知られる。
台座も時代は古く極めて精巧、厨子もまた工芸的価値の高い優れた品である。一説にこの像は、慶長14年(1609)本遠寺の創建以前からこの寺の庵寺に安置されてあったともいわれ、文永11年(1274)日蓮聖人入延以前におけるこの地方文化を物語る貴重な文化財である。
昭和44年6月1日町指定。
タ、日蓮像 塩之沢 金龍寺 蔵
木造素地(樟材)
総丈 25.00センチメートル
面長 8.00センチメートル 面幅 6.50センチメートル
肩幅 12.00センチメートル 膝幅 18.00センチメートル
像の背部に
千体之内
聖朝安穏 増宝寿
日蓮大僧師 木喰五行菩薩
天下安楽 興正法 八十四歳花押
寛政十二庚申歳正月十二日成就
五十歳 日得
台座の裏に
奉読誦妙経三十部 陀羅尼 南無日蓮大菩薩
開仏知見
享和元年酉十二月三日より二年正月三日迄
寒中修業
と記されてあり、像の顔の円満な心からくる真の微笑は木喰ならでは刻むことのできぬものである。聖朝安穏 増宝寿
日蓮大僧師 木喰五行菩薩
天下安楽 興正法 八十四歳花押
寛政十二庚申歳正月十二日成就
五十歳 日得
台座の裏に
奉読誦妙経三十部 陀羅尼 南無日蓮大菩薩
開仏知見
享和元年酉十二月三日より二年正月三日迄
寒中修業
この像ものみ、小刀、なた、鋸の4種類の工具で彫刻したものであろう。
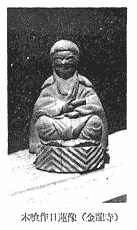 |
昭和44年9月12日町指定。
チ、本国寺蔵木鼻の唐獅子 下山 本国寺 蔵
欅材
右高さ 28センチメートル
横 45センチメートル
厚さ 20センチメートル
左高さ 27センチメートル
横 42センチメートル
厚さ 19センチメートル
この唐獅子は、明治8年(1875)国の重要文化財旧睦沢小学校を建築した松木輝殷(てるしげ)の作品で、下山大工の堂宮建築として最後を飾る優れた技術を偲ぶ数少ない作品である。
なお高さ55.00センチメートル、横80.00センチメートルの雲形も同様保存してある。
昭和44年4月5日町指定となる。
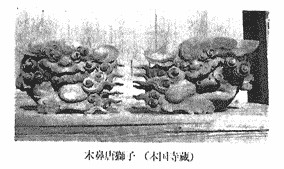 |
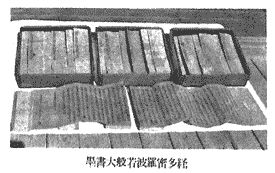 |

