(四)書跡
ア、墨書大般若波羅密多経 600巻 下山 南松院 蔵各巻縦25.70センチメートル、横9.50センチメートル、厚さ1.80センチメートルの経本で、600巻を100巻ずつ六つの箱に蔵めてある。康暦二年庚申(1380)より至徳二年乙丑(1385)に至る間の奥書あるのを穴山伊守豆信友再修したものであり、経師高野山教順坊又助椽名員の名がある。天文16年(1547)10月穴山信友が天輪寺に納めたものが南松院に移った経本である。
昭和44年9月12日町指定。
イ、法華経 8巻 下山 南松院 蔵
応仁元年(1467)正月15日の奥書である。縦15.20センチメートル、横5.00センチメートル、8冊の厚さ12.50センチメートルの経本で箱に収められ信友夫人葵庵尼所持のものである。
昭和44年9月12日町指定。
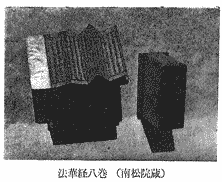 |
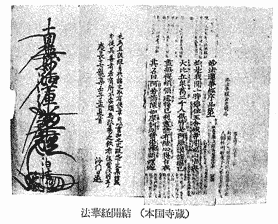 |
縦31.00センチメートル、横10.50センチメートル、厚さ各巻ともことなる折本である。
この経本は身延山第二十二世日遠上人の出版で、巻末に学校妙玄庵常什慶長十七竜集壬子盛夏日と記してある。
西谷壇林廃校のとき、関係寺院に什器を頒ち本国寺什物となった法華経出版史の中に残るものである。版本の原稿は日遠上人筆のもので、立正大学にあるが宗門中貴重の版本とされている。
昭和44年9月12日町指定。
エ、刺繍の法華経 1巻 下山 本国寺 蔵
幅13.50センチメートル、長さ5.57メートルの白絹布に、紺糸で1センチメートル角の字で縫いとった経巻で、はじめのところを、17.00センチメートル位切りとっておるのはお守にしたためである。
序品第一見法大衆得末曽有より方便品第二終りまで、養珠院殿の丹念こめて縫った巻物で、刺繍経は全国稀のものでその信仰の深さには頭のさがる思いがする。
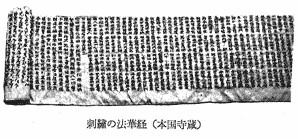 |
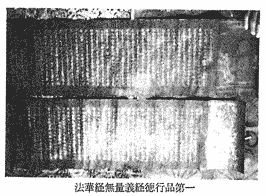 |
オ、無量義経並に観普賢経の二品写経 下山 龍雲寺 蔵
法華経無量義経徳行品第一
幅25.00センチメートル、長さ8.38メートル、初め15.00センチメートルは文珠菩薩のかけた理由が書いてあり、終り12.00センチメートルには文字がない。
仏説観普賢菩薩行法経
幅25.60センチメートル、長さ7.35メートル、初め15.00センチメートルに文珠菩薩の図がかいてあり終り3センチメートルには文字がない。
両巻とも紺紙に金泥で書いてある経巻で、日蓮聖人の真筆ともまた所持したとも寺にいい伝えられているが、書体から見て所持していたものと思う。
武田信玄が身延山に強請し貰い受けて、2巻を竜雲寺に納め他の8巻は甲府の大泉寺に納めてある。
昭和44年9月12日町指定。
カ、日蓮聖人書翰断片 梅平 近藤たねじ 蔵
 |
キ、匠家雛形増補初心伝 6冊 下山 本国寺 蔵
文化年間から近年に至るまで、堂宮建築に従事する大工の必読書として全国的に著名の書である。文化9年(1812)の発行以来、版元も何回か変り明治になってからも出版されている。この書の内容は、
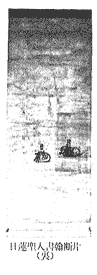 |
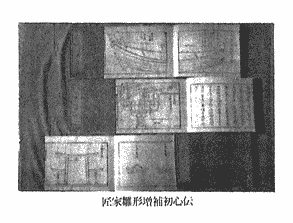 |
中巻2冊……きざはし、脇障子、扉前、屋根の仕方、箱棟
下巻2冊……鳥居、三間社、神輿、玉垣
となっていて、本殿建築の木割りの順を基本として一応堂宮建築の標準を系統づけての書である。
この本の著者石川七郎左衛門は、源重甫、源重郷、源重豊とも称し、担当の頭脳と学力のある人であって、稀に見る傑出した人物であったことが想像される。
昭和44年8月12日町指定。
(五)天然記念物
ア、本遠寺の大クスノキ 大野山本遠寺 境内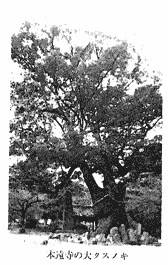 |
大野山本遠寺の創設は慶長13年で(1608)このクスノキはその当時または直後植えたものであろう。
したがって樹齢は320年位と推定される。
本県のような寒地では珍しい大木で、おそらく県下一の大樹であろう。
昭和41年6月1日町指定となる。
イ、常福寺のお葉付イチョウ 下山 常福寺境内
根元の周囲 6.91メートル
目通り幹囲 4.19メートル
樹高 約20.00メートル
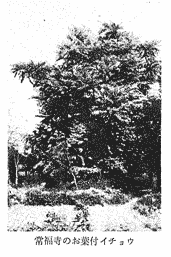 |
ただ寺の火災の際に幹の一部が焼けているのは残念である。果実は普通、葉上共に顕著で顆粒もまた大である。
昭和44年4月5日町指定となる。
ウ、長谷寺のお葉付イチョウ 下山 竜雲寺所有
根元の周囲 9.39メートル
目通り幹囲 3.94メートル
樹高 約23.90メートル
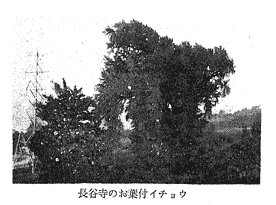 |
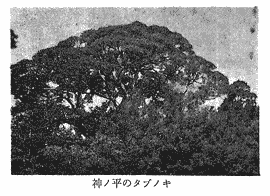 |
葉上結実、普通結実と相混じている。
昭和44年4月5日町指定となる。
エ、神の平タブノキ 波木井一区 坂八幡神社境内
根元の周囲 3.40メートル
目通り幹囲 2.70メートル
樹高 約12.00メートル
樹令約300年ないし400年と推定される。タブノキは暖地性の常緑の大高木で、本州、四国、九州の暖地の主として海岸に多い。5、6月頃黄緑色の花を開き、初秋のころ実は黒紫色に熟し、果柄は赤色を帯びる。鳥によってたやすく分布し、その分布は気候を示すものとして興味がある。別名をイヌグスまたはタマグスともいい、本地方ではタマと呼んでいる。タブノキは富士川をさかのぼって北上し、富士川の両岸標高約400メートルまでの地に分布し、身延が本県における北限となっている。
本樹は県下においてはタブノキの分布の北限にあり、その上相当の大木で、しかも自然の樹形を呈し、学術上きわめて貴重な資料である。
昭和44年4月5日町指定となる。
オ、湯平のツクバネガシ 湯平 八幡社境内
根元の周囲 3.85メートル
目通り幹囲 3.60メートル
樹高 約14.50メートル
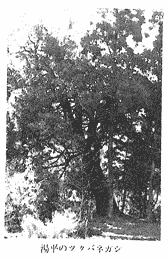 |
本樹のようなものは山梨県としては珍しい大木である。
身延町にはアラガシ・シラガシ・ウラジオガシ、ツクバネガシの4種のカシがはえている。
昭和44年4月5日町指定
カ、清子のヤブツバキ 清子水久保 望月織重宅地
根元の周囲 2.50メートル
目通り幹囲 2.50メートル
樹高 約8.50メートル
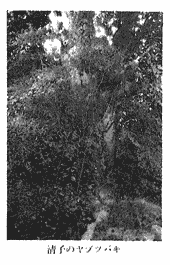 |
本樹は種類的巨樹として県下稀に見る貴重な椿である。
昭和44年4月5日町指定となる。
キ、山田屋裏のお葉付イチョウ 身延 山田屋裏
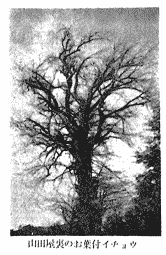 |
目通り幹囲 5.30メートル
樹高 約25.00メートル
地上10メートル位のところから、南にのびた大きい枝に大きい気根が、その下の小さい枝に小さい気根が数本ずつ垂れている。樹勢は旺盛で、2、3年生位のいぬかやが着生している。
昭和44年4月5日町指定となる。
ク、蓮華谷のお葉付イチョウ 元町 花の坊境内
根元の周囲 5.00メートル
目通り幹囲 5.00メートル
樹高 約30.00メートル
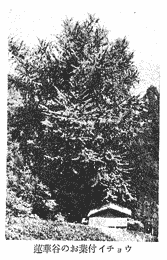 |
南天、のきしのび、木づたなどが着生している。お葉付の現象は少ない。
昭和44年4月5日町指定となる。
ケ、本遠寺のシダレザクラ 大野 本遠寺裏の傾斜地
種類 イトザクラ
本樹は大野山本遠寺庫裡裏の東面した傾斜地に立っているもので、その規模は根元周囲3.40メートル、目通り幹囲2.90メートル、地上約5メートルで三幹に分かれている。枝張りは東約11.00メートル、西約8.20メートル、南約9.00メートル、北約8.20メートルであるが南東と北西にのびた枝は更に長く伸びている。
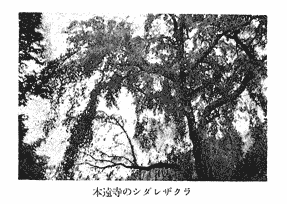 |
花期は3月下旬で他にさきがけて咲き、その美しさは賞賛の的である。
幹に空洞もなく、枝先に少しの枯損を認めるが、樹勢は極めて旺盛である。
昭和44年9月12日町指定

