第七章 文芸と芸術
第一節 文芸
一、俳句
全山の紅葉錦に輝ける 日静身延の俳句は、大崩の寺に残る其日庵列山と、暁鳥亭百哺宗匠の選による奉額に文政八酉歳(1825)九月とあり、他の一面に一字庵
これ等の額から考えて身延の俳諧はこの頃から盛んになったものであろうと思われる。
(一)身延の俳人とその作品
| 一字庵−一世鳳州 | ||
| 二世 |
池上重兵衛 | |
| 三世鶯村 | 望月宗太郎 | |
| 四世米融 | 松野義路 | |
| 五世松旭 | 松野喜一 | |
| 六世仔兆 | 志村久一 | |
| 山彦庵−一世雨光 | 僧侶 | |
| 一世花中 | 望月儀兵衛 | |
| 三世初音 | 望月清十郎 | |
| 四世一華 | 望月京太郎 | |
| 松久庵−一世花笑 | 遠藤正蔵 | |
| 二世美月 | 笠井美充 | |
| 春曙庵−一世花山 | 佐野丑太郎 | |
| 二世花山 | 佐野繁雄 | |
| 三世花山 | 佐野正 | |
| 花王庵−一世連曜 | ||
| 遠藤梅洲 | 遠藤源十郎 | |
| 梅廼本−一世松軻 | 今村松吉 | |
| 二世仙兆 | 山本金次郎 | |
| 天外庵−一世弘人 | 佐野弘 | |
| 二世碧園 | 市川清 | |
| 鏡香園−一世竹風 | 田中孝一 | |
| 二世秀兆 | 望月秀雄 | |
| 松琴軒−一世美月 | 笠井美充 | |
| 二世嶺兆 | 笠井信明 | |
| 清流庵−一世旭扇 | 望月祥 | |
| 二世三七三 | 望月二郎 | |
| 南松園−一世藍丘 | 小林由太郎 | |
| 二世枕流 | 小林彦三 |
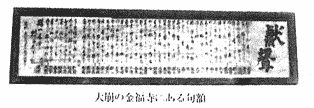 |
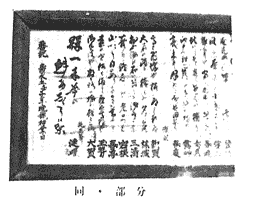 |
行く先を照らす枯野の月夜かな  旭
旭
落ちるとは思わぬ色の椿かな 米融
する墨のうつるや梅の匂う月 松旭
元朝や甲斐に富士あり身延あり 仔兆
一人前水も働く鳴子かな 雨光
月雪に優る眺めや花の中 花中
嘴よせて子に餌をやる親雀 初音
美しき俳泉塚や春の月 一華
秋高し気も晴れやかの大自然 美月
雲海の彼方に浮ぶ不二の峯 花山
南天の実の赤赤と時雨哉 連曜
梅咲いて維摩のよとぞなりにけり 梅洲
わけて香の深き今年や菊盛る 松軻
手をついて飲みし跡あり岩清水 仙兆
山の色田の色秋をしかと知る 秀兆
初笑い豊に子等の寝覚め居り 嶺兆
濡れまじと思えば狭し露の道 旭翁
動かざる影一ついて余寒の灯 三七三
お彼岸の太鼓朝から鳴りにけり 枕流
落ちるとは思わぬ色の椿かな 米融
する墨のうつるや梅の匂う月 松旭
元朝や甲斐に富士あり身延あり 仔兆
一人前水も働く鳴子かな 雨光
月雪に優る眺めや花の中 花中
嘴よせて子に餌をやる親雀 初音
美しき俳泉塚や春の月 一華
秋高し気も晴れやかの大自然 美月
雲海の彼方に浮ぶ不二の峯 花山
南天の実の赤赤と時雨哉 連曜
梅咲いて維摩のよとぞなりにけり 梅洲
わけて香の深き今年や菊盛る 松軻
手をついて飲みし跡あり岩清水 仙兆
山の色田の色秋をしかと知る 秀兆
初笑い豊に子等の寝覚め居り 嶺兆
濡れまじと思えば狭し露の道 旭翁
動かざる影一ついて余寒の灯 三七三
お彼岸の太鼓朝から鳴りにけり 枕流
(二)身延俳団
鏡香園竹風(田中孝一)初代団長として俳誌「仏法僧」を36号まで発行したが、第二次世界大戦のため休刊となった。戦後「雲海」と改め、2代松久庵美月(笠井美充)、3代梅廼本仙兆(山本金次郎)、4代昌笑庵仔兆(志村久一)、5代松久庵美月(再選)とつづき、200号に達している。雲海誌友は他町村にまで及んでいる。
寺町の桜に宿を選びけり 美流
石切りに疲れし身体干し布団 紅石
激しき雪静かな雪と降り積る 千陽子
新しくペン先も替え事務始め 三三子
風群を抜いてさゆらぎなきまでに 柳兆
大炬燵離れて愛の便り読む 孝信
襟足の美しき女白き足袋 玉泉
法鼓止めば合の静寂の又寒夜 ただし
運動会白き分列青き空 新生
つなぐ手の伸び縮みして雪解道 九十
月見草寝るをも惜しむキャンプ哉 花城
眼に泌みる青葉若葉の旭を返す 暁風
月蒼く出水の怒濤靄の這う 辰畝
紅梅や家点々と村貧し 英夫
卓上の花に松虫来て楽し 松風
久方に笛の音流る小正月 秀臣
大磯に波の砕ける良夜かな 智恵女
梅三分乙女の望ひそと告ぐ 酔子
名の高き滝にひたりて雨を乞ふ 勝久
里遠く暮るる山路や閑古鳥 美声
集い寄る羽音妖しく誘蛾灯 五浪
百合の香の流るる朝の小径かな 花峯
理髪舗の鏡の中の大夕立 東晃
県境の標識白し青嵐 了声
霜続く野辺に岨立つ法の山 耕子
石切りに疲れし身体干し布団 紅石
激しき雪静かな雪と降り積る 千陽子
新しくペン先も替え事務始め 三三子
風群を抜いてさゆらぎなきまでに 柳兆
大炬燵離れて愛の便り読む 孝信
襟足の美しき女白き足袋 玉泉
法鼓止めば合の静寂の又寒夜 ただし
運動会白き分列青き空 新生
つなぐ手の伸び縮みして雪解道 九十
月見草寝るをも惜しむキャンプ哉 花城
眼に泌みる青葉若葉の旭を返す 暁風
月蒼く出水の怒濤靄の這う 辰畝
紅梅や家点々と村貧し 英夫
卓上の花に松虫来て楽し 松風
久方に笛の音流る小正月 秀臣
大磯に波の砕ける良夜かな 智恵女
梅三分乙女の望ひそと告ぐ 酔子
名の高き滝にひたりて雨を乞ふ 勝久
里遠く暮るる山路や閑古鳥 美声
集い寄る羽音妖しく誘蛾灯 五浪
百合の香の流るる朝の小径かな 花峯
理髪舗の鏡の中の大夕立 東晃
県境の標識白し青嵐 了声
霜続く野辺に岨立つ法の山 耕子
(三)身延山ホトトギス会
昭和27年創設、責任者は上田正久日で毎月1回例会を身延山宿坊で開いている。例会にはホトトギス同人「裸子」主宰堤俳一佳の指導を受けて時には吟行会をも催し会員数は約30名ほどである。已に、高浜虚子、星野立子、高野素十、山口青邨等を招いて句会を催したこともある。上田正久日の句集「句道仏心」は昭和25年より昭和37年までの作品の中、400余句を載せたもので仏教者として特徴ある作風がにじみ出ている。
 |
本山の枝垂桜の庭を掃く 正久日
客殿に僧ざわめきて松の花 きよ
春の風屋上に人歩きをり 五百里
一と本の広き庭占め大ざくら 達子
西谷の桜に埋もれて坊十戸 志華絵
坊々に法鼓鳴り継ぎ明易し 星光
西谷の梅に囲まれひそと住む 稲花
参拝の信徒もてなす冷やし麦 多香子
卯の花や参詣しげき御本山 螢光
師の坊の追悼供養春の宵 東晃
坊の庭鳩の歩みに春暮るる 芳蘭
峰々の修行太鼓や紅葉散る 冬月
住み馴れて仏の町に菊作る 南石
老僧の尊き筆や花便り まさえ
番傘の僧のゆくえに花のあり 照雄
鳥鳴いて谷間の春の出店旗 碌山
堂広し残る寒さに経を誦す 妙昭
花の坂下り来し杣は無愛想 春江
ここに又枝垂桜が松の中 之妍
線香の香はよきものぞ春の風 玉泉
団参の勧誘ばなし春の風 ただし
句のゆかり花のゆかりと重なりて 美保子
山門へ七夕の町つづき居り 耕子
客殿に僧ざわめきて松の花 きよ
春の風屋上に人歩きをり 五百里
一と本の広き庭占め大ざくら 達子
西谷の桜に埋もれて坊十戸 志華絵
坊々に法鼓鳴り継ぎ明易し 星光
西谷の梅に囲まれひそと住む 稲花
参拝の信徒もてなす冷やし麦 多香子
卯の花や参詣しげき御本山 螢光
師の坊の追悼供養春の宵 東晃
坊の庭鳩の歩みに春暮るる 芳蘭
峰々の修行太鼓や紅葉散る 冬月
住み馴れて仏の町に菊作る 南石
老僧の尊き筆や花便り まさえ
番傘の僧のゆくえに花のあり 照雄
鳥鳴いて谷間の春の出店旗 碌山
堂広し残る寒さに経を誦す 妙昭
花の坂下り来し杣は無愛想 春江
ここに又枝垂桜が松の中 之妍
線香の香はよきものぞ春の風 玉泉
団参の勧誘ばなし春の風 ただし
句のゆかり花のゆかりと重なりて 美保子
山門へ七夕の町つづき居り 耕子
高浜虚子等来身のときの句
本山の春の夕の詣で人 高浜虚子
鐘聞いて水鳴楼に春惜しむ 星野立子
七面の雲より落つる春の水 山口青邨
照らさるる皆僧ばかり虫かがり 高野素十
仏法僧鳴く夜もあらな坊泊り 堤俳一佳
鐘聞いて水鳴楼に春惜しむ 星野立子
七面の雲より落つる春の水 山口青邨
照らさるる皆僧ばかり虫かがり 高野素十
仏法僧鳴く夜もあらな坊泊り 堤俳一佳
(四)下山俳句会
下山本町松木仁三郎は古見豆人の指導をうけて俳句の道に入り、昭和18年下山において朱日等とともに俳誌大富士に加入、下山俳句会大富士支部を結成毎月会員宅において句会を開き主幹豆人を年1、2度招いて修練につとめた。昭和33年豆人の句碑
「天の川安房へ久遠に流れいて」
を本国寺境内に建立し、同時において記念大会を開催、参会者数十名盛大であった。
昭和34年豆人の没にあい、雲母に転じ支社となり再度主幹龍太を迎えて指導を仰いだ。
瞬けば秋光蝶となりにけり 素人
鵯鳴いて小雪の谷をひろげけり 柚高
立冬の風に押さるる鶏の尻 朱月
大夕立馬糞をほぐし上りけり 一善
胎動に穂麦の青さ見ていたり 希佐女
行水におしろいの花ほの白し 和女
緑陰に子を負い寄りし老婆たち 一史
夏の虫思案の壁の白すぎて 草半
坂東太郎鼻に荒々しき別れ 爽星
空梅雨や壁の割目に蜘蛛の糸 秀河
うそ寒や台風の目の大きな陽 雪魚
別るるも会うもこの辻椿咲く 素吟
ちちははの声のかへらぬ法師蝉 積水浪
女工らの素顔に菫うつりけり 貞女
冬銀河黄河はいまも濁りをらむ 延麓
雲垂るる道暑し女蛇を打つ 岳春
炎天や真白きベット傍観す 高尾
死はすでに定まる舌に黒ぶどう 白路
蜂疲れをり美しき夕焼に 白燕
父ねむる土より重く雪降れり 学梁
鵯鳴いて小雪の谷をひろげけり 柚高
立冬の風に押さるる鶏の尻 朱月
大夕立馬糞をほぐし上りけり 一善
胎動に穂麦の青さ見ていたり 希佐女
行水におしろいの花ほの白し 和女
緑陰に子を負い寄りし老婆たち 一史
夏の虫思案の壁の白すぎて 草半
坂東太郎鼻に荒々しき別れ 爽星
空梅雨や壁の割目に蜘蛛の糸 秀河
うそ寒や台風の目の大きな陽 雪魚
別るるも会うもこの辻椿咲く 素吟
ちちははの声のかへらぬ法師蝉 積水浪
女工らの素顔に菫うつりけり 貞女
冬銀河黄河はいまも濁りをらむ 延麓
雲垂るる道暑し女蛇を打つ 岳春
炎天や真白きベット傍観す 高尾
死はすでに定まる舌に黒ぶどう 白路
蜂疲れをり美しき夕焼に 白燕
父ねむる土より重く雪降れり 学梁
(五)豊岡公民館文芸サークル作品
八十年見なれし山は緑して 大木
麦の秋そこここ小さき部落見ゆ 柴山
朝曇りはるか水鶏の遠たたき 暁風
都入り入学の子とつれだちて 茂
藤の花下刈りの手をしばし止め 吉久
土手に並ぶ写生の児等に春の風 嘉久
枯草の中に見かけし蕗のとう つや子
勝手より柏餅よと児等を呼ぶ 喜代子
暮れなずむ平和の里の春の雨 迪子
山吹きの車窓に楽し甲斐に入る 申女
長梅雨やほたるぶくろは深く垂る 耕子
麦の秋そこここ小さき部落見ゆ 柴山
朝曇りはるか水鶏の遠たたき 暁風
都入り入学の子とつれだちて 茂
藤の花下刈りの手をしばし止め 吉久
土手に並ぶ写生の児等に春の風 嘉久
枯草の中に見かけし蕗のとう つや子
勝手より柏餅よと児等を呼ぶ 喜代子
暮れなずむ平和の里の春の雨 迪子
山吹きの車窓に楽し甲斐に入る 申女
長梅雨やほたるぶくろは深く垂る 耕子
(六)身延の句碑
ア、俵石の句碑所在地 身延元町岩の鼻
建立 天保2年辛卯仲夏
御命講や油のような酒五升 芭蕉
此の山の茂りや妙の一字より 蓼太
法華経とのみ山彦も鳥の音も 完来
イ、梅ヶ丘句碑此の山の茂りや妙の一字より 蓼太
法華経とのみ山彦も鳥の音も 完来
所在地 身延上之山梅ヶ丘
建立 昭和14年4月
訪ふ人の心のままに梅かほる 如々
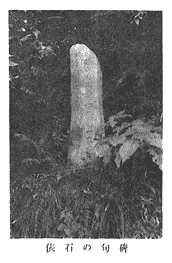 |
所在地 身延山菩提梯畔
建立 昭和27年11月1日
法鼓鳴り全山の霧動き初む 水心子
この句碑は南巨摩郡身延町、身延山久遠寺(望月日滋法主)の境内(菩提梯〈二八七段〉の石段の登り口、南部実長公銅像右わき)にある。裏面に「昭和28年9月1日、身延町観光課建之」と刻まれている。県立図書館で「山梨新十景句集」(昭和28年6月15日発行、山梨日日新聞社)を見ると、この時の新十景として、「甲州葡萄郷と宮光園、差出の磯と万力林、能見城趾の展望と新府城趾と坂井遺跡、夜叉神峠、早川渓谷と西山温泉郷、身延山と七面山、四尾連湖、小室山と益母富士、甲府(舞鶴城、愛宕山、積翠寺温泉と千代田湖、湯村温泉郷)、「坊ヶ峰展望」などが選ばれ、新十景に寄せる俳句を公募し、選者に飯田蛇笏と富安風生が当ったことが解かる。
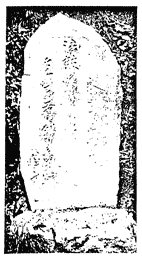 |
1席 法鼓鳴り全山の霧動きそむ 三重県、石谷水心子
2席 久遠寺や七百年の木下闇 千代田、末木青雲
3席 枯蔓を滴りもして法の水 甲府、加賀美子麓
秀作 老杉も峙立つ磴も時雨つつ 身延、赤堀春江
秋深し祖師にすがりて小商売 柏、小林喜山
磴道を雪駒け降り駈けのぼり 富士吉田、刑部たけみ
仏の灯うごかしてゐる大蛾かな 富士吉田、浅間柳葉
さて、句意は「勤行(ごんぎょう)の太鼓が鳴っているが、その音と共に、霧が動きはじめ、なにか、全山が動く様だ」であろうか。動的、観入の名句といえようか。日蓮聖人七百遠忌に詣でてこの霧をつぶさに見たい。
エ、芭蕉句碑
所在地 丸滝不動滝畔
建立 不詳
酒のみにかたらむかかる滝の花 芭蕉
オ、芭蕉句碑所在地 光子沢谷津
建立 不詳
春も漸けしきととのふ月と梅 芭蕉
カ、豆人句碑所在地 下山本国寺境内
建立 昭和33年3月30日
天の川安房へ久遠に流れゐて 豆人
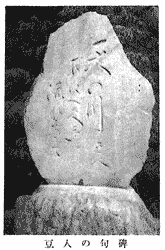 |
所在地 梅平笠井美充邸内
建立 昭和28年4月
万まで趣味に栄えて親子皇沙 美月
同邸池のほとりに、故宗匠だちの辞世の句碑がある。起されて居る寝心や春の雨 花笑
寒牡丹こもりそこねて仕舞いけり 竹風
別れても亦逢う春の待たれけり 弘人
虫さまざま寂深みたる夜なりけり 嵐山
寒牡丹こもりそこねて仕舞いけり 竹風
別れても亦逢う春の待たれけり 弘人
虫さまざま寂深みたる夜なりけり 嵐山

