第二節 書道
一、身延山全国書道展覧会
昭和23年、身延山全国書道展が、加藤雲洞(松戸市)後藤松渓、市川雲渓等の努力により、身延山久遠寺主催のもとに祖山学院(現身延山短期大学)を会場として開催された。爾来、中里日応、若尾雲峯、野島小舟、池上荒一、佐野淳司、佐野越堂、長田白水、依田竹邸、望月七弥等の協力により15ヵ年間つづけられ、本町書道教育の振興に大きな足跡をのこした。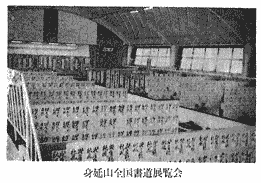 |
しかしながら、昭和37年、第15回展を最後に種々の事情により中止のやむなきにいたった。
二、過去の書道家
釈雲山 大野山本遠寺第四十一世住職で昭和3年(1928)より昭和11年(1936)までその職にあった。当時、昭和の三筆といわれその能筆をうたわれた。しかし本町に在住することが少なかったので、その墨跡はすくない。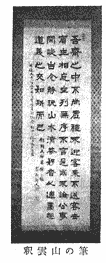 |
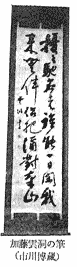 |
三、現在の書道家
市川雲渓 加藤雲洞に師事する。日本教育書道連盟審査員、日本教育書道連盟能力検定試験委員、大阪書道研究研精会総務として活躍するかたわら、塾を開き指導に専念している。中里日応 加藤雲洞、上田桑鳩に師事する。身延山短期大学、県立身延高等学校の書道指導を担当のかたわら塾を開き、近隣子弟の指導にあたっている。
若尾雲峰 加藤雲洞に師事する。身延小学校教諭、身延高等学校書道講師を歴任し、現在塾を開き、児童、生徒の書道指導に専念している。
望月松洞 市川雲渓に師事する。特に役場職員と余暇を利用して書道を修練しその技術向上を図り、身延町が山梨県町村事務能率増進協議会書道の部に優秀な成績を収めているのはその指導に負うところが多い。かつて塾を開き児童、生徒の書道指導に貢献した。

