第五節 音楽
一、身延町の音楽
身延町の音楽が盛んになり、世に認められるようになったのは、やはり学校音楽が皮切りだろう。昭和30年ころ、身延小学校教諭の近藤博の指導によって、器楽合奏のクラブ活動がはじめられ、県下の大会にも出場するようになった。
昭和30年ころからは、身延中学校教諭の渡辺正巳を中心に身延小・中学校や、身延高校のブラスバンド部で、器楽に合唱に音楽活動が活発になり、さらに町内の各学校もこれに呼応し、音楽教育に力を入れるようになった。
昭和37年ころになって身延町を「音楽の町」にしようとの声があがり、青年団の合唱グループも現われた。これを町民全体のものにしようとして、身延町音楽愛好会が誕生し、事務局長に深沢徹が就任し、会員も教師・商店主・保母・店員・主婦・会社員など六〇余名となり、レコード収集家の畑野稔・佐野利雄も加わり、定期的にレコード鑑賞会を開いた。
この会はやがて渡辺正巳・佐野隆子・近藤博等の指導によって、合唱の練習もはじめるようになった。
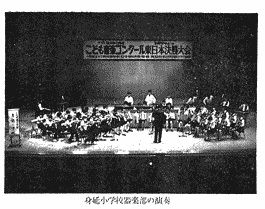 |
やがて、第1回の身延町民音楽祭につづいて昭和38年には、東京立正高校のブラスバンドを招いて、第2回の町民音楽祭も開催された。
一方学校の音楽については、昭和37年度に豊岡小学校清子分校は、文部省の指定によりへき地における情操教育として、音楽について研究しその成果を発表した。
また身延小学校は、器楽合奏で県内のみならず、全国大会にも出場し優秀な成績をおさめている。
昭和40年には身延町文化協会が結成され、以来年々文化祭が開催され、音楽祭にかわってその行事の一つに、音楽がとり入られている。
今後の課題として、文化協会が中心になり、町内の音楽愛好家を結集し、リーダーをも育て、名実ともに「音楽の町」としたいものである。
なお、身延町独特の歌題目をはじめ、日蓮聖人のゆかりの歌をも宣伝すべきであろう。
二、本町出身の音楽家
山田宗次郎身延仲町に生れ、現在コロムビアレコード会社の指揮者など勤めている。
渡辺正巳
山梨師範出身で、富里小学校・山梨大学付属小学校・身延中学校に勤務し、山梨県教育委員会の指導主事となり、昭和41年早川南小学校長となった。
指導主事在任中、文部省の命により、音楽指導のため沖縄へ派遣されたことがある。
身延町婦人会歌をはじめ、多数の作曲がある。
なお現在県下小・中学校音楽研究連盟の会長である。
望月真也
旧姓遠藤、現在数寄屋橋ビヤホールニュー東京に勤務し、同店の全国四十数ヵ所の支店楽手に得意の器楽の指導をしている。
なお、幼時よりアコーデオンを得意としていた。

