七、児童福祉の概要
日本国民に憲法があるように、日本のこどもには児童憲章がある。日本の児童はこの憲章の精神によって育成されなければならない。児童憲章は昭和26年5月5日に定めらたもので、前文には、 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるためにこの憲章を定める。
「児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。」
とあるがまだ充分に理解されていない。児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。」
| 表6 心身障害児数調 | 児童福祉施設 入所状況 (昭和44年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種々の事情から福祉に欠ける児童に対しては、法的援助の道がひらかれている。こどもに関する相談をうける機関としては、児童相談所があり、福祉事務所や保健所も相談に応じている。相談は、こどもの保護者や親戚、児童委員、学校等の連絡によるが、相談事項によりそれぞれ適切な処置がとられる。例えば、児童福祉司や精神薄弱者福祉司、社会福祉主事や児童委員による指導がとられたり、助産施設、母子寮、乳児院、養護施設、精神薄弱児施設、同通園施設、盲ろうあ施設、情緒障害児短期治療施設、教護院等への入所措置がとられ、時に家庭裁判所へ送られる場合もある。
本町における施設入所児童の状況は上表のとおりである。
八、保育所の沿革と現況
児童福祉法第1条にすべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれかつ育成されるよう努めねばならない、とあるが、保育所はこの原理に基づき保育に欠ける乳幼児(1歳未満より就学前)を保育することを目的とする第2種社会福祉事業である。保育に欠けるとは、父母や家族が子供の面倒を見られない状態であるが、法律上保育に欠けるかどうかは児童福祉法による保育所への措置基準がよりどころとなっている。子どもを保育所へ入所させるか否かは市町村長(措置権者)の権限であり、左に掲げる措置基準に照らして決定される。| 1、 | 母親が日中居宅外で労働することを常態とする。 |
| 2、 | 母親が日中居宅内で児童とはなれて日常の家事以外の労働を常態とする。 |
| 3、 | 母親のいない家庭(死亡、行方不明、拘禁等) |
| 4、 | 母親の出産等、出産前後、又は疾病の状態または心身障害がある。 |
| 5、 | 疾病の看護(母親が病人の看護にあたる) |
| 6、 | 家庭の災害、火災、風水害、地震等の災害により居宅が破損した時。 |
| 7、 | 特例、前各号以外で保育に欠けると市町村長が認め、知事が承認した時。 |
保育所は託児所から発展してきたもので、児童福祉法の成立によりいよいよその使命が重くなって来た。現代社会においては女性の職場進出により共稼ぎの家庭が増大し、母親に代って乳幼児を保護育成する保育所はなくてはならない施設である。
下山では昭和10年(1935)頃婦人会長望月寿和乃が中心となり婦人会員の有志により、田植期に小学校農休みの校舎を借用し、季節託児所が開設され地区の幼児を集めて保育に当った。これがきっかけとなり毎年託児所が開かれて来たが戦後は取り止めとなった。いち早く保育の重要なる事に着目して集団保育の道を開いた先覚者の功績は大である。町内他地区においては季節託児所の開設されたことを聞かない。
昭和23年には前記託児所を継承して下山立正保育園が開設された。食糧事情が逼(ひつ)迫しておやつはそら豆4、5粒という苦難時代であったが、25年には副食給食が実施され、漸く前途に光明を見出した。昭和26年には大野山保育園が開設され、大島保育園が昭和31年開設された。
本県では一般に民間保育所に対しては、概して措置権者である市町村長の公的助成は少ないが、本町においては建設補助、運営費等他町村に見られない多額の助成を行なって保育の充実に努めている。
(一)社会福祉法人下山立正保育園
| 設立年月日 | 昭和23年9月12日 | |
| 認可年月日 | 昭和23年10月16日(山梨県指令第313号) 昭和41年11月30日、社会福祉法人となる。 |
|
| 収容定員 | 幼児100名、乳児10名 | |
| 理事長 | 秋山智孝 | |
| 理事 | 望月惟臣 土橋隆四郎 松本幹之甫 佐野繁 | |
| 監事 | 松木四郎 | |
| 園長 | 秋山智孝 | |
| 職員数 | 園長 1名 保母 6名 炊事婦 1名 園医 2名 | |
| 歴代保護者会長 | 望月惟臣、土橋隆四郎、佐藤理、熊王軍治、渡辺七六、石川頼行、松木正巳、佐野繁、加藤彦四郎、井上年一(現) |
 |
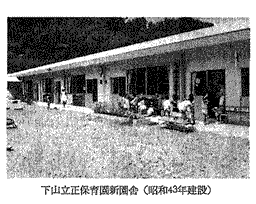 |
(二)私立大野山保育園
| 設立年月日 | 昭和26年6月1日 | |
| 認可年月日 | 昭和26年9月1日 | |
| 収容定員 | 115名(内3歳未満12名) | |
| 園長 | 西尾きく | |
| 職員数 | 園長 1名 保母 6名 炊事婦 2名 園医 2名 | |
| 理事長 | 片田為丸 | |
| 理事 | 西尾貫一 沢村清一 | |
| 監事 | 深沢徹 青柳功 | |
| 歴代保護者会長 | 赤塚一一、市川正夫、深沢徹、千須和芳郎、沢田成一(現) |
 |
 |
(三)社会福祉法人、大島保育園
| 設立年月日 | 昭和31年10月15日 | |
| 認可年月日 | 昭和36年10月23日 | |
| 収容定員 | 55名(内3歳未満児5名) | |
| 理事長 | 沢村清一 | |
| 理事 | 若林孝義 雨宮愛紀 | |
| 監事 | 滝川隆治 若尾享一 | |
| 園長 | 沢村清一 | |
| 職員数 | 園長 1名 保母 3名 炊事婦 1名 園医 2名 | |
| 歴代保護者会長 | 片田銀五郎、伊藤亮造、市川正美(現) |
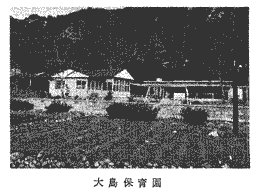 |
大野山・大島両保育園では40年以降の砂利採取によるダンプカー激増、交通事情激化に伴い、徒歩による園児の通園送り迎えは危険になったので、合同して通園バスを購入し安全通園をはかっている。バスは町補助、有志の寄付および父母負担によって購入された。
(四)児童遊園地
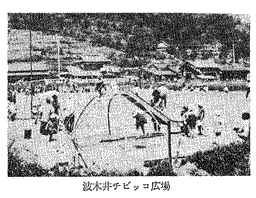 |
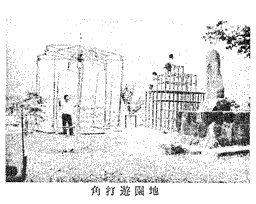 |
県は青少年育成のための総合対策の一環として児童遊園地を奨励し、町においても共同募金の配分や町自体の補助金により児童遊園地の設置整備につとめてきた。町内各地区においても資金を拠出し、協力奉仕により、スベリ台・ブランコ・鉄棒等を設置し、地区によってはピンポンの練習場を建築したところもある。昭和43年度事業として波木井部落では県より3分の1の助成を得、60数万円で「チビッコ広場」を設けた。
本町における設置状況は次のとおりである。
| 表7 身延町児童遊園地 | ||||||||||||
|
(五)身延町保育協議会
町内保育所にはそれぞれ保護者会があり、県・郡連合体と直結し、活動も盛んであったが、更に横の連絡を密にし保育の前進を図るため、昭和39年町内各保育所保護者会長が中心となり、身延町保育協議会が結成された。事業として、保護者の研修会、保育推進のため関係機関への運動等があげられる。これに刺激され、南巨摩郡保育協議会の結成機運が生まれた。
初代(現)会長は、深沢徹である。
九、母子福祉法と相談員の任務
母子福祉法は母子家庭の福祉に関する原理を明らかにし、母子家庭の生活の安定と向上のため必要な措置を講じ、母子家庭の児童がすこやかに育成されるための諸条件と、その母親の健康で文化的生活を保障しようとするものである。国および地方公共団体は母子家庭の福祉を増進する責務を有し、母子家庭の母はみずから進んで自立を図り家庭生活の安定向上に努めねばならない。この法令によれば、都道府県に母子相談員をおくことになっているので、本町では旧町村各1名ずつ計4名が委嘱され、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに対し、身上相談に応じ自立に必要な指導を行なっている。現職母子相談員は下山松木いつ代、身延池上愛子、豊岡大村とよ子、大河内市川喜美子である。
本町の母子世帯は現在81戸251人であり、そのうち生活保護世帯は8戸24人である。
母子福祉資金
母子福祉法第3条によれば都道府県は母子福祉資金を貸し付けることができる。この貸付金制度の概要はつぎのとおりである。
(貸付対象)
20歳未満の子どもをもつ死別または生別などの母子世帯および20歳未満の父母のない児童。
(資金の種類と貸付金額の限度)
事業開始資金(21万円)事業継続資金(10万円)技能習得資金(月額2,500円)生活資金(技能習得資金を借りている期間中月4,500円)住宅資金(15万円)転宅資金(12,000円)就職支度資金(15,000円)修学資金(高校・高等専門学校1〜3年月額1,500円・大学・高等専門学校4〜5年月額3,000円)就学支度資金(25,000円)
となっており本町においては昭和43年度利用状況は、貸付総額3,240,400円で、81人が利用している。内訳は事業開始資金は405,000円で16人、事業継続資金765,000円で19人、住宅資金550,000円で8人、修学資金1,244,400円で、37人、技能習得資金36,000円で1人となっている。
十、母子福祉会
母子福祉会はその名のごとく母子家庭の福祉を図る会であって、初め未亡人会という名称のもとに、各市町村を単位として結成された。後に母子福祉会と改められ、本町においては旧町村単位のまま活動している。事業として、母子家庭の児童激励のための各種行事、各種団体との連絡提携、県女子福祉会館維持費獲得のための購買等を行なっている。近く町連合会結成の運びになっている。十一、愛育会
愛育会は初め愛育班と称して、旧町村地区の婦人会において、婦人会活動の一環として組織し活動していた。後に町連合婦人会が結成され、昭和41年に身延町愛育班が生まれ町婦人連合会会長が愛育会長を兼ねることになった。各地区においても役員は婦人会役員が兼ねる場合が多かった。しかし愛育会活動が活発になるにつれて会の性格が婦人会活動と本質的に異なる点があるので独立しなければならなくなり、昭和43年度より専任の会長が選出され、44年度より各地区においても同様に選任される傾向にある。役員は顧問若干名、会長1、副会長2、理事4、会計1、監事2である。昭和43年10月12日、会活動の趣旨を周知させ理解と協力を得るため第一回愛育祭を実施し、身延町中央公民館を会場として、多彩な催しをおこない成果をおさめ今後の発展が期待されている。
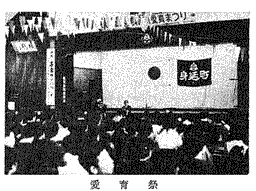 |
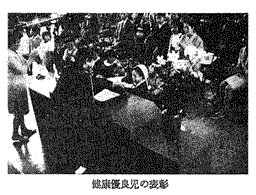 |
十二、助産婦会
本町における助産婦は身延保健所管内助産婦会に属していて、保健所の指導により、家族計画の指導、妊産婦や乳児の保健衛生の指導に努めている。本町における受胎調節実施指導員は、広島かつ江・松木求女・望月えいじである。昭和42年より身延町は、家族計画指定地区に指定され町保健婦、指導員により受胎調節の実施指導が計画的に行なわれている。指導は農閑期を利用し婦人学級などグループ活動の一環としても取り入れられている。低所得層には町補助により器材薬品等も支給されている。
| 表8 立会者別出生数と率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

