十三、老人福祉と身体障害者福祉会
(一)老人福祉
古来わが国においては、儒教道徳の影響から敬老思想が普及していた。戦後新らしく制定された国民の祝日の中にも敬老の日があって法に規定されているように、ひろく国民が老人の福祉についての関心と理解を深め、かつ、老人が自らの生活の意欲を高めるような行事を実施して来た。しかしながらたった1日の祝日ではとうていできないことであって、年寄り子どもといわれながら、児童福祉法におくれること15年にして、昭和38年10月はじめて老人福祉法が制定されたことは遅きに失した感がある。老人福祉法によれば、福祉事務所は、老人の福祉に関し必要な実情の把握および調査指導を行ない、老人福祉指導主事がおかれることになっている。保健所は、老人の保健衛生面を担当することになっており、市町村長は毎年期日または期間を指定して厚生大臣の定める方法により健康診査を行なわなければならない。町においては毎年老人の健康診断を実施し保健上遺憾のないよう努めている。法令によれば65歳以上の老人は、その福祉を図るため必要に応じて種々の措置がとられる。
 |
老人クラブは、年寄りの孤独感、欲求不満、非社交性などの特性を、年寄り自らの力によって克服して、生活を豊かにしようとする団体で、町には旧町村地区単位のクラブがあり、下山は和楽翁会・身延は延寿会・豊岡は楽寿会・大河内は老人クラブと称している。町には連合会があり身延町老人クラブ連合会と称し、郡県の連合会と連絡している。現会長は伊藤正一・副会長松木豊寿・小笠原政義・鴨狩喜道である。
敬老会は各地区まちまちに行なわれ、婦人会社会福祉協議会各種団体の協力により実施されていたが、町村合併以来全町一本化した敬老会の要望があったので、明治百年を機に漸く一体化し身延レジャーセンターを会場とし、身延町社協共催で、婦人会等の協力により盛大に催され、有志の余興に楽しい一日を過ごしている。
昭和44年3月の議会で、本町としては初めての「敬老年金」条例が議決され、ささやかながら町の老人福祉行政に明るい話題を添えた。44年度の支給対象者(満77歳以上)は約360名である。
以下、敬老年金条例全文を掲げる。
身延町敬老年金条例
(目的)
第一条 この条例は老人福祉法(昭和三十八年法律第一三三号)第五条に基づく敬老の日の行事として敬老年金を高齢者に給付し、その長寿を祝福するとともに家庭の平和と町民の敬老思想を高揚し、あわせて老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第二条 敬老年金は、九月十五日現在において満七十七歳以上であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)により町内に住居を有する者に対して給付する。
(年金の額)
第三条 敬老年金の額は、年額壱千円とする。
(資格の喪失)
第四条 敬老年金の給付を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、敬老年金の給付を受ける資格を失なう。
一、本人が辞退したとき
二、その他町長が年金の給付が適当でないと認めたとき。
(委任)
二、その他町長が年金の給付が適当でないと認めたとき。
(委任)
第五条 この条例で定めるものを除くほか、この条例実施に関し必要な事項は規則で定める。
付則
この条例は公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
この条例は公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
| 表9 老人クラブ | (昭和43年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表10 身延町敬老会該当者 | (昭和43年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)身体障害者福祉
身体障害者福祉法は、第1条に、身体障害者の更生を援助し、その更生のために必要な保護を行ない、もって身体障害者の福祉を図ることを目的とする、とあり、第2条には身体障害者は自ら進んで、その障害を克服し、すみやかに社会経済活動に参与することができるように努めなければならないとあるように、身体の不自由な人々の更生を助けたり、更生するために必要な保護をしたりすることを目的として診査・更生相談・更生医療の給付・補装具の交付・修理および身体障害者更生援護施設への収容などを行なう法律である。この法律による援助をうけるためには、身体障害者手帳の交付をうけなければならない。手帳は、眼・耳・口・手足などに一定程度以上の永続する障害があるもので、障害の種類により、重い方から一級より六級に区分され、これに該当する者に交付される。
本町における身体障害者の実体は表11のとおりである。
| 表11 身体障害手帳保持者調 | 昭和43.11.1調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア、身体障害者福祉会
身体障害者福祉会は、身体障害者福祉法が施行されると間もなく大河内に結成され、次いで下山・身延・豊岡にも結成された。町村合併と同時に、会員160名をもって連合福祉会が結成された。地区結成当初は運営資金に乏しく、物品販売や映画会等による資金獲得をおこない苦難をのりこえて来た。
事業として、会員の相互扶助、親睦と研修を兼ねたバス旅行、会員福祉のための政府への運動等を行なっている。
初代役員は、会長市川笹市・副会長望月利春・鍋島良知・沢田進であり、2代会長望月利春、3代現会長は鍋島良知である。一時独立した傷痍軍人会との合同の気運が見られる。
イ、傷痍軍人会
傷痍軍人会のおこりは、日本廃兵会であるというが、本町においての活動については知る材料がない。該当者も少なく、ほとんどが物故してしまった。戦前は大日本傷痍軍人会と称し、県・郡・町村に支部がおかれていた。しかし傷痍軍人の数は少人数であり、町村単位の支部をつくることは困難であった。下山は南巨摩郡第四支部に属し、都川、本建と3ヵ村合同であった。遠藤松之助が支部長で年に1、2回会合した。身延・豊岡には該当者が少なく、会という程の活動もできなかった。大河内は西八代郡の支部に属し望月竜吉が中心であった。
昭和21年マッカーサーの指令により、解散の止むなきに至ったが、身体障害者福祉法の成立により、身体障害者福祉会に属することになった。昭和27年山梨県傷痍軍人会が復活し、下部組織がなされた。本町においては、県支部身延分会が設立され、会長は望月竜吉、副会長木内悦治、同遠藤松之助(庶務会計兼任)会員67名をもって発足し、現在恩給受給者12名である。
傷痍軍人は国家のため犠牲となった人々であり、一般の身体障害者とは異なる点があり、会員もこれを誇りとしている。しかしながら、身体障害という立場から、互いに励まし合い、時に社会国家に対して働きかける場合もあり、また行政上からも、窓口を一本にした方が援助し易いという意見もあり、傷痍軍人会と身体障害者福祉会とは近く何等かの形で一本化される方向にある。年とともに会員の減少する傷痍軍人会の実情を考える時、一日も早からんことが望まれる。
ウ、肢体不自由児父母の会
身体障害者の中で、特に児童の福祉を増進するための団体として、身延町肢体不自由児父母の会がある。
昭和43年9月16日に会員52名をもって結成された。先天的または後天的な肢体不自由児の保護者の集まりである。事務局を身延町役場住民課内におき、療育相談・研修会・レクリエーション・重症児の慰問・会員相互の連絡・町の身障児年金制度請願・各種事業への参加協力等の事業を行なっている。
会長深沢徹・副会長佐野治郎・波田野政男・深沢孝・手塚久夫・事務局長石川金雄である。
エ、身延町心臓病の子どもを守る会
先天性心臓病の子どもを持つ父母および本会の趣旨に賛同するものの集まりで、昭和39年4月結成され、現在会員15名である。
事務局を身延町役場内におき、役員は左のとおりである。
会長深沢徹・副会長穂坂泰三・事務局長柿島洋美・会計石川金雄
(事業のあらまし)
昭和39年、町内の先天性心室中核欠損症の子どもを手術するため、有志の協力と募金に端を発し、県の心臓病の子どもを守る会、身延保健所等の協力により、児童福祉法による「育成医療」の適用を受け、手術に成功した。
その後患者の発見、療育相談、相互の激励、知識の向上、手術の援助等の活動をつづけており、前記募金の残額10万円を基金として広く体の不自由な子どものためにと、助け合いの「愛育基金」を設け運営にあたっている。
十四、保護司制度と保護司の活動
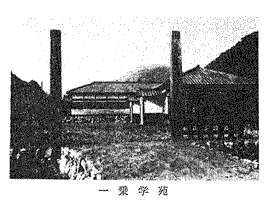 |
丸山海昇 小松浄祐 望月本啓 渡辺政則 佐野源治 望月正夫 林是幹 秋山信一 長谷川寛慶 鈴木武重 鈴木正巳 粟冠義朝 芦沢はなよ 山本岳乗 望月武雄 秋山智孝
なお、林是幹は、昭和39年6月12日法務大臣表彰をうけ、昭和32年9月3日関東地方更生保護委員会委員長表彰をうけている。なお、長谷川寛慶も昭和34年6月18日関東地方更生保護委員会委員長表彰を受けている。
十五、遺族会
終戦後軍人遺家族は靖国会を結成した。本町においては、郡初代会長になった松田寛等が中心となり、県下有志とともにこの結成や運営に努めた。靖国会は旧町村ごとに県支部がつくられていたが、後に中央が遺族会と改称したためにこれに従い、遺族会と改めた。家庭の柱を失った会員の福祉を図り、国の援護に対し強力な運動を展開した。また遺児や遺族の靖国神社参拝、戦没者の慰霊祭等を行なった。階級に応ずる扶助料10年間に5万円を支給される弔慰金、更に10年間に3万円を支給される線香料等は会の強力なる運動によるものである。町村合併後は町連合体を組織し、地区会長が1年交替で会長に就任している。婦人部青年部等がある。遺児は既に成人し会員も年々減少していくので、将来を考えて、国が靖国神社を護持するよう、立法を要望しその実現に努力している。
現地区会長は、下山・松木豊寿、身延・井出亀治、豊岡・木内昌博、大河内・松野大治である。
十六、旧在郷軍人会
現役でない軍人すなわち予備、後備、補充、国民兵役にある軍人の団体であり、一朝有事の際、動員に応ずるための団体であった。明治43年(1910)に結成され、それまであった各種の団体を統合して帝国在郷軍人会と称した。町村にも分会が設けられ、富国強兵の国策に沿い、忠魂碑の建設、戦没者の慰霊、軍事思想の普及等の活動をし、特に第二次世界大戦中の銃後の活躍は目ざましかった。戦後は解散し、慰霊祭は社会福祉協議会等に引きつがれている。十七、下山愛郷同志会
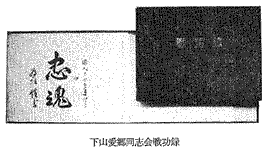 |
十八、戦没者慰霊祭
慰霊祭は戦時中町村の主催により、在郷軍人会が中心となって毎年実施され、各種団体や学童等も参列することが慣わしになっていた。敗戦より講和条約発効までは、占領軍の命令で慰霊祭も中絶のやむなきにいたった。しかし国民感情や遺族の心情からそのまゝにしておくことはできなかった。下山において、昭和23年佐野為雄が戦時中の責任を痛感して村内の遺族を招いて、本国寺において慰霊祭を行なったのも、このような社会事情の下であった。やがて講和条約による独立後、公的団体としての社会福祉協議会が設立され、町村の財政援助により慰霊祭が復活し今日に及んでいる。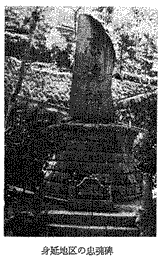 |
 |
身延では総門内の忠魂碑の前において、社協主催により本山より導師を招き毎年慰霊祭を実施してきた。
豊岡においては、正慶寺内忠魂碑の前において社協主催により、毎年盛大に行なってきたが、身延と同じく全戸日蓮宗である関係上、こゝ両3年来、久遠寺仏殿において合同慰霊祭を行なうようになった。太平洋戦争戦没英霊追悼歌「英霊に誓う」が合唱され、盛大である。
| 日蓮宗宗務院監修 | ||
| 太平洋戦争戦没英霊追悼歌 | ||
| 「英霊に誓う」 | 作詞 細井鵲郎 | |
| 作曲 南部都留夫 |
一、生きて再び還らじと
躬をかえりみず 征きませり
国の鎮めと 今は亡き
勇士の名のみ とどめけり
南無妙法蓮華経
二、自由平和をかちとりて
国栄えます よろこびは
散りにし花の 実りぞや
いつの世にかは 忘るべき
南無妙法蓮華経
三、今日の集いに 誓いてよ
くりかえすまじ よこしまの
醜なる軍 戦かわじ
御霊安かれ とこしえに
南無妙法蓮華経
大河内地区においても、他地区と同様毎年社協主催で、旧役場地内の忠魂碑前において地区寺院神社協力のもとに慰霊祭を執行している。
躬をかえりみず 征きませり
国の鎮めと 今は亡き
勇士の名のみ とどめけり
南無妙法蓮華経
二、自由平和をかちとりて
国栄えます よろこびは
散りにし花の 実りぞや
いつの世にかは 忘るべき
南無妙法蓮華経
三、今日の集いに 誓いてよ
くりかえすまじ よこしまの
醜なる軍 戦かわじ
御霊安かれ とこしえに
南無妙法蓮華経

