第二節 法律改正と事業の変遷
昭和13年7月より施行となった国民健康保険事業は、変転する社会情勢に対応し、給付および運営の改善をはかるため、昭和33年全文改正をするまでの間、8回にわたり法律改正を行なってきたが、その主なものについて記すと次のとおりである。昭和17年(1942)2月、組合の強制設立化、保健医制度の確立、組合員加入義務の強化などを主題として改正した。
昭和23年6月、戦後のはげしい社会情勢の変化、経済変動により、事業休廃止の組合の続出する状況に対応し、保険運営制度の整備建てなおしをはかるため、連合軍司令部の強い進言もあって、法律の根本的な改正をした。従来までは組合法人で、組合会議員、理事長をもって運営されていたものを、市町村の公営とし、被保険者の強制加入、療養担当制度の採用その他、全面にわたって改正したので、全く新しい性格をもつものとなった。
昭和26年、地方税法の改正により、国民健康保険税が創設された。
昭和31年、保険税課税限度額を3万円から5万円に引き上げた。
昭和33年、国民皆保険体制を確立するため、全文改正を行ない、新国民健康保険法が誕生した。
同法は国の強い指導により、その後市町村に普及し、昭和36年に全市町村実施となり、国民皆保険が達成された。
その後も十数回にわたって法律改正を行ない、給付改善、国庫補助率の引き上げをはかり、4ヵ年計画をもって、全員7割給付の強い指導が行なわれ、昭和43年1月から、全国市町村に、全員7割給付が実施されることになった。
当町においては、昭和35年2月1日から全町実施となり、現在に至っているが、給付内容は当時全員5割給付であり、助産費1,000円葬祭費500円であった。
昭和36年4月1日、歯科診療における補てつ(入歯など)が給付の対象となった。
昭和37年7月1日、助産費2,000円葬祭費1,000円に改められた。
昭和38年10月1日、世帯主だけが7割給付となった。
昭和41年1月1日、全員7割給付が実施された。
昭和43年4月1日、国民健康保険運営審議会(公益、被保険者、医療機関、代表各4名ずつ委員12名構成)の答申意見により葬祭費2,000円に改められた。
昭和44年4月1日より助産費が5,000円に改正された。なお昭和45年度より助産費10,000円とする計画である。
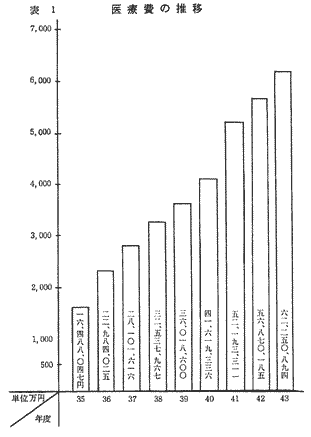 |

