第四節 鉄道とバス
一、富士身延鉄道と身延線
甲府−富士間88.1キロメートルのほぼ中央、身延駅を眼下に見おろし、身延山と七面山を仰ぐ小高い山頂、通称丸山公園に高くそびえる記念塔……それは身延線創設50周年を記念して昭和38年に建てられたものである。塔の下には富士身延鉄道創設の功労者6氏(小野金六、根津嘉一郎、堀内良平、河西豊太郎、小泉日慈、小野耕一)の胸像ブロンズが飾られ、永遠にその偉業を伝えている。  |
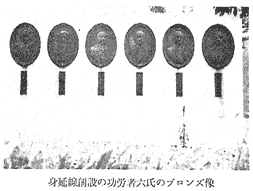 |
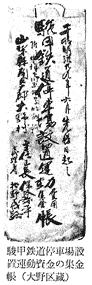 |
その内容をみると、鉄道側では設置場所として丸滝地内か帯金榎島のいずれかを考えていたものらしく、3区同盟は身延山本山への正面玄関として丸滝が好適地であること、架橋にも河幅狭く容易であることを強調している。30年1月25日の文書にはほぼ目的の位置に確定したとして運動資金残金の精算をしているところを見ると、この時の計画がかなり具体化していたことがわかる。
このように民間から鉄道敷設の運動と要望が盛り上るにおよんで、山梨県会においても明治33年(1900)12月、時の内務大臣に対し次のような意見書を提出してその促進をうながしている。
甲府岩淵間鉄道の速成を請う意見書
山梨県下甲府より静岡県下岩淵に至る鉄道路線は鉄道敷設法において第二期に属するも元来本線は東海道線より中央線に通じ更に中山道線及び北越線に通ずる連絡線たるのみならず、其南端は特別輸出港たる清水港を控ゆるの故に、東海、東山、北陸諸道を連絡して地方産業の発達を促進し、国家経済に利益を与ふること極めて大なり。加えて本線の工事は平易にして工費も小額なるをもって本線を竣成せば之に由て現に起工中なる中央幹線の準備線として鉄道経費にも多大の便利を与ふるものなりと確信す。
政府はさきに事の緩急を謀り第二期線に属する篠井線を第一期に編入したる例あり、而して本線達成の急務なるは決して篠井線に譲ることなく、希くは国家経済のため将また沿道各道のため、本線工事を達成するの計に出られ度、府県制第四十四条に依り意見書呈出致候也
明治三十三年十二月十六日
山梨県会議長 野口英夫
明治42年(1909)には東海道線の岩淵、鈴川両駅の中間に富士駅が設置され、甲駿を結ぶ新らしい起点として脚光を浴びることになる。山梨県下甲府より静岡県下岩淵に至る鉄道路線は鉄道敷設法において第二期に属するも元来本線は東海道線より中央線に通じ更に中山道線及び北越線に通ずる連絡線たるのみならず、其南端は特別輸出港たる清水港を控ゆるの故に、東海、東山、北陸諸道を連絡して地方産業の発達を促進し、国家経済に利益を与ふること極めて大なり。加えて本線の工事は平易にして工費も小額なるをもって本線を竣成せば之に由て現に起工中なる中央幹線の準備線として鉄道経費にも多大の便利を与ふるものなりと確信す。
政府はさきに事の緩急を謀り第二期線に属する篠井線を第一期に編入したる例あり、而して本線達成の急務なるは決して篠井線に譲ることなく、希くは国家経済のため将また沿道各道のため、本線工事を達成するの計に出られ度、府県制第四十四条に依り意見書呈出致候也
明治三十三年十二月十六日
山梨県会議長 野口英夫
明治43年3月衆議院において、「甲府より岩淵に至る鉄道急設に関する建議案」が通過し、いよいよ建設の機運が熟した。翌44年には中央線甲府−名古屋間も開通し、両幹線を結ぶ身延鉄道の重要性は富国強兵、産業振興の国策や軍事上からもますます強まったのである。
(一)富士身延鉄道株式会社の設立と敷設工事
このような機運のなかで、明治44年(1911)6月22日、小野金六を代表発起人として「富士身延鉄道株式会社」が資本金400万円で設立発足し、静岡県大宮町(現在の富士宮市)より甲府市までの鉄道敷設認可を得、大正元年には、富士−大宮間も許可され大正2年より着工したのである。鉄道会社としては富士川西岸、現在の国道に沿ったコースを計画したが、土地をつぶされる地主の猛反対にあい、止むなく富士川東岸の山沿いコースに変更した。このコースも用地買収の声で地価は一斉に上昇し、良い水田は10アール630円、並の田畑で320、330円が通り相場となった。
この頃の米1石8円23銭から考えても、非常な高値であったことがわかる。会社は大正6年10月の身延山お会式までに富士−身延間を開通させる目標を立て工事の進捗をはかったが、この工事は地盤が悪く、トンネルや橋梁の連続で非常に難工事であったうえに、水災などの障害、加えて第一次世界大戦による物価高騰、資材の値上り等、あらゆる困難に悩まされ、遅々としてはかどらなかった。
然し大正7年(1918)にはようやく十島−内船間が完成、翌8年に内船−甲斐大島間が、9年5月18日遂に甲斐大島−身延間が開通し、ここに夢の富士−身延間鉄道が全通したのである。
開通はしたものの駅員の確保・乗客の確保に苦しみ、経営はいつも火の車であったという。機関車、貨車、客車すべて国鉄の中古品、蒸気機関車が小さな客車を2両引っぱって走るというもので定員は120人、運賃は富士−身延間が大人で1円71銭であった。大人の1日日当が70銭そこそこの時代であるから、乗客が少なく、わらじばきや舟運の旅客に敬遠されるのも無理はなかった。汽車とはいっても馬力が小さく、急坂では子供が追いついては車掌に叱られたり、発車時顔見知りの客が手を上げると待っていて乗せてくれたというからのんびりしたものであった。
鉄道会社は身延山参拝の便をはかって、従来渡船によっていた身延駅−大野間の富士川に大正12年(1923)8月身延橋を建設した。この橋は〝東洋一の吊り橋〝と称し、往復通行料各10銭を徴収し、余り評判のよくない「名物」となった。
第2期工事の身延−甲府間の建設工事はしばらく停頓の形となっていたが、政府は第一次世界大戦後の全国鉄道計画のなかで甲府−丸滝線の重要性を認めてこれを採択、大正9年の臨時国会において、国の手によって敷設することを決定した。しかし当時の緊縮財政方針で予算が計上されず、結局民営により建設することになったのである。
大正14年(1925)着工された工事は昭和2年市川大門まで、昭和3年(1928)3月遂に甲府まで全線開通し、ここに東海道と甲州街道を結ぶ大動脈が完成したのである。昭和2年には身延まで電化され輸送力も急増した。
大正2年着工以来実に15年、身延町を中心とする沿線住民の悲願が実ったわけで、当時の人々の感激がしのばれる。
この開通により、身延参拝客の主流も鉄道のほぼ独占するところとなり、産業・文化・教育・観光の各面において身延町のめざましい発展をうながす要因となったのであって、身延町にとってまさに新らしい時代の夜明けであったといっても過言ではない。
(二)国鉄身延線へ
この民有富士身延鉄道も、運賃は日本一といわれながら赤字続きで経営難に苦しみ、昭和13年(1938)国との折衝が成り民有国営となり、さらに日華事変の激化対米戦争機運の情勢下に国家的方針もあって昭和16年5月1日、買収費1,900万円で国鉄に移管され、線名も身延線となったのである。戦時中は国鉄も軍事色にいろどられ、身延駅のホームには出征兵士を送り出し、また戦死、戦病死者の無言の帰還を迎えた町民の歴史がきざまれている。軍需物資の特別輸送、町内からの木材や薪炭等の供出物資の輸送も行なわれた。戦後は復員業務に、荒廃した鉄道施設の確保と復興に苦闘のあゆみがつづけられ、列車は買出しや、ヤミ物資を運ぶ人々でふくれ上り、窓からの乗り降りはふつうのことだった。切符も発売制限がきびしく、窓口には長い行列ができた。戦後の国鉄復興の歴史は、日本の再建の歴史でもある。
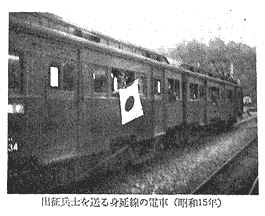 |
(三)身延線今後の課題と展望
通勤通学客の増加、観光開発の進展、さらに首都圏拡大のおよぼす影響など、時代の進展とともに身延線の重要度はますます強まり、赤字路線とはいいながら、沿線地域住民の身延線にかける期待と要望は強いものがある。昭和28年に発足した身延線改善期成同盟(静岡、山梨両県下の沿線各市町村が加盟)は、本町を中心として身延線の複線化、スピードアップ、中央線、東海道線の乗入れ、東京−身延循環列車の運行などを要望して運動を続けている。また、身延線沿線観光協議会が発足し、積極的な観光客誘致にものり出している。
今後本町の地域開発の中で、道路の改良開発とならんで、身延線の近代化、改善は大きな柱となることであろう。
身延線の沿革
一、会社の創立と増資
明治45年4月26日資本金400万円を以て富士身延鉄道株式会社を創立
大正10年12月25日資本金を800万円に増加
大正15年7月2日資本金1,600万円に増加
一、鉄道敷設と運転開始
明治45年4月26日資本金400万円を以て富士身延鉄道株式会社を創立
大正10年12月25日資本金を800万円に増加
大正15年7月2日資本金1,600万円に増加
一、鉄道敷設と運転開始
| ・ | 明治44年6月23日富士身延鉄道株式会社発起人小野金六外弐拾九名に対し、静岡県大宮町を起点とし、山梨県甲府市に至る鉄道敷設の免許が与えられた。 |
| ・ | 大正元年12月5日富士鉄道株式会社鉄道敷設特許権(東海道富士駅を起点とし静岡県大宮町に至る間)を富士身延鉄道株式会社に譲渡の許可が与えられた。 |
| ・ | 大正2年7月21日東海道富士駅大宮町間(10.3キロメートル)工事竣工運転開始 |
| ・ | 大正4年2月20日大宮町芝川間(約9キロメートル)工事竣(しゅん)工運転開始 |
| ・ | 大正7年8月10日芝川、十島間(約5.8キロメートル)工事竣工運転開始 |
| ・ | 大正7年10月8日大島、内船間(9.65キロメートル)工事竣工運転開始 |
| ・ | 大正8年4月8日内船、甲斐大島間(5.63キロメートル)工事竣工運転開始 |
| ・ | 大正9年5月18日甲斐大島、身延間(3.9キロメートル)工事竣工運転開始 |
| ・ | 大正9年8月中臨時帝国議会において丸滝−甲府間(44.73キロメートル)の工事は政府において施設することに決定 |
| ・ | 大正13年5月31日身延、市川大門間(26.4キロメートル)の工事の施行認可される。 |
| ・ | 昭和2年3月28日市川大門駅、甲府間(18.35キロメートル)の工事施行認可される。 |
| ・ | 昭和2年6月富士、身延間電化完成 |
| ・ | 昭和3年3月30日工事竣工富士駅、甲府駅間88.1キロメートル全通運転開始 |
| ・ | 昭和13年10月1日国営に移管 |
| ・ | 昭和16年5月1日国鉄に買収される。 |
| ・ | 昭和36年5月管理長制度発足 |
| ・ | 昭和38年準急富士川号運転開始、その後急行となる。 |
| 初代 | 小野金六 | |
| 二代 | 堀内良平 | |
| 三代 | 根津嘉一郎 | |
| 四代 | 河西豊太郎 | |
| 五代 | 小野耕一 |
二、町内の各駅
身延町民の利用駅は主として波高島、塩之沢(停留所)、身延、甲斐大島である。身延駅
開業は大正9年5月18日(富士身延鉄道会社線)昭和15年国鉄買収日本国有鉄道(公社)中部支社静岡鉄道管理局所属の現業機関たる一般駅(貨物を取扱わない駅は特殊駅という)である。
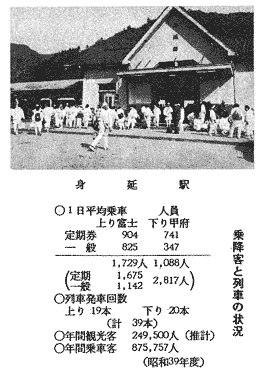 |
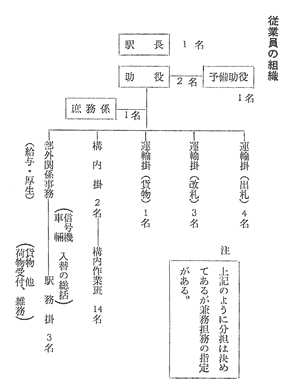 |
観光客の概況(月別・昭和39年度)
|
別
月 |
団体 | 一般 |
| 1 | 497人 | 24,339人 |
| 2 | 116 | 16,913 |
| 3 | 963 | 17,971 |
| 4 | 2,082 | 19,506 |
| 5 | 4,207 | 23,081 |
| 6 | 10,460 | 16,297 |
| 7 | 4,195 | 18,653 |
| 8 | 919 | 28,505 |
| 9 | 307 | 12,973 |
| 10 | 1,420 | 15,442 |
| 11 | 1,714 | 13,972 |
| 12 | 94 | 12,208 |
| 計 | 29,684 | 219,860 |
合計249,544
| 貨物・貨車 | ||||||
発着回数(1日)
|
||||||
発着トン数(年)
|
身延駅の特長
一、旅客は身延山参拝の信徒をはじめ全国各方面より来町するので山間駅としては乗降客数の割に発売高が大きい。
二、県南部の中心地として通勤客が多い、通学生も多い。
三、身延線の中心駅、貨車の仕訳作業も行なわれている。当駅だけ乗務員(機関士・車掌)の交代がある。
四、中心駅の業務機関が集中している。
五、身延山、白鳳渓谷、南アルプス、西山温泉等への観光客が増加している。
六、身延線の輸送改善によって将来、東京、長野、静岡から直通列車が運転されるようになれば中心駅としての重要度は益々高まるであろう。
七、複線化の促進も運動されている。
甲斐大島駅甲斐大島駅は、身延町下大島地内にあって、大正8年4月8日富士身延鉄道が大島まで開通し、開通と同時に大島駅も開業し国営移管を経て現在に至っている。現在駅長1、助役1、一般職員5の8人で運営に従事している。
昭和43年度(43年4月より44年3月まで)甲斐大島駅利用客は、一般・通勤・通学を合わせて143,443人で1日平均393人となり、貨物はほとんど大部分が砂利で年間72,260トン積み出している。
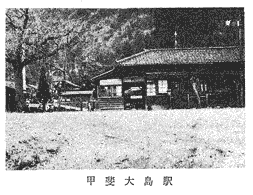 |
身延町帯金塩之沢にあって身延駅長が管理している職員無配置駅で、昭和8年9月1日の開設である。
昭和43年度(昭和43年4月より44年3月まで)の年間利用客は、一般・通勤・通学を合わせて90,521人で、1日平均248人である。
かつて貨物も取扱ったこともあったが今は扱っていない。

