三、身延登山鉄道
大正末期に登山鉄道(身延駅−身延山総門)と、ロープウエイ(塩沢−奥ノ院−赤沢−白糸滝・感井坊−鷹取山−七面山−角瀬−七面山)の建設計画が立てられたことがあるが、大野地内で一部着工した鉄道敷設工事も中途で挫折し、机上プランに終った。昭和36年、身延山の大本願人田中正二郎をはじめ信徒有力者が、三井鉱山社長山川良一ら三井系財界人の協力のもとに「身延登山鉄道株式会社」を設立(資本金5,000万円)昭和38年に西谷より奥ノ院に至るロープウエイを総工費2億1,000万円で建設、営業を開始した。
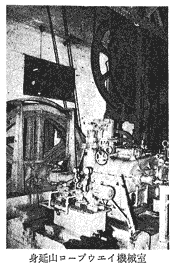 |
○区間 久遠寺駅−奥之院駅(標高1,153メートル)
○着工 昭38、3、1
○完成 昭38、8、23
○施工者 日本ケーブル株式会社
○ロープウエイ方式 三線交走式並通索道
○線路長 1,665メートル
○ゴンドラ乗車人員 41人 2基
○鋼索 支索 ロックドコイル 56m/m
曳索 フイラー 24m/m
平衡索 フイラー 20m/m
○支柱 4基 最大高さ 28m
○運転回数 1日平均 30回
徒歩で2時間のところを8分で頂上まで達することができる。頂上からは富士の霊峰、南アルプスをはじめ四囲の連峯、富士川沿岸一帯、遠く駿河湾まで遠望でき眺望雄大で清浄な環境とともに参拝観光客の感嘆するところとなっている。○着工 昭38、3、1
○完成 昭38、8、23
○施工者 日本ケーブル株式会社
○ロープウエイ方式 三線交走式並通索道
○線路長 1,665メートル
○ゴンドラ乗車人員 41人 2基
○鋼索 支索 ロックドコイル 56m/m
曳索 フイラー 24m/m
平衡索 フイラー 20m/m
○支柱 4基 最大高さ 28m
○運転回数 1日平均 30回
四、自動車交通の発達
(一)馬車、人力車から自動車へ
明治29年ごろ身延村地内に馬車鉄道設置の計画があったが、地元からは反対運動がおこり結局実現には至らなかった。この時大野、梅平両区より出された反対の上申書には、当時の人々の考え方がよく現れていて興味深い。
 |
馬車鉄道敷設ニ付上申書
当身延村地内へ軌道条例ニヨリ馬車鉄道敷設ノ儀出願人有之趣伝聞仕リ候
処右ハ地元村民ノ意向等御上問相成リ候事ト存シ候ヘドモ杞憂ニ堪ヘズ左ニ其ノ弊善ヲ具申シ併テ御採用不相成様奉請願候
当村ノ道路ハ極メテ狭隘ニシテ身延山参詣人群集致シ候節ハ肩摩接踵頗ル雑踏ヲ極メテ常通路取拡ゲノ必要ヲ感ジ居候折柄道敷中央ヘ軌道ヲ敷キ馬車往来致シ候テハ道路ハ馬車ノ為ニ占領セラレ人馬ノ通行ヲ障碍スルノミナラズ参詣人輻湊ノ砌リハ婦女老幼ノ到底通行スル能ハズ特ニ梅平大野間ノ如キ一方ハ削ルガ如キ山腹ニテ一方ハ富士川ニ臨ム県崖ナレバ身延山法会ノ時期ハ毎々死傷ヲ生ズル危険有之地元村民ノ憂慮不尠候条何卒該出願ノ儀ハ御却下相成度此段奉懇願候也
明治廿九年一月十四日
山梨県南巨摩郡身延村大野区人民総代
松野義路
片田辨治
海野太左衛門
穂坂弥平
片田愛治郎
片田国太郎
身延村梅平区人民総代
近藤善左衛門
佐野儀兵衛
遠藤吉三郎
前書上申之趣相違無之ニ付奥印仕候也
右村長代助役
遠藤緑
山梨県知事 桜井勉殿
当身延村地内へ軌道条例ニヨリ馬車鉄道敷設ノ儀出願人有之趣伝聞仕リ候
処右ハ地元村民ノ意向等御上問相成リ候事ト存シ候ヘドモ杞憂ニ堪ヘズ左ニ其ノ弊善ヲ具申シ併テ御採用不相成様奉請願候
当村ノ道路ハ極メテ狭隘ニシテ身延山参詣人群集致シ候節ハ肩摩接踵頗ル雑踏ヲ極メテ常通路取拡ゲノ必要ヲ感ジ居候折柄道敷中央ヘ軌道ヲ敷キ馬車往来致シ候テハ道路ハ馬車ノ為ニ占領セラレ人馬ノ通行ヲ障碍スルノミナラズ参詣人輻湊ノ砌リハ婦女老幼ノ到底通行スル能ハズ特ニ梅平大野間ノ如キ一方ハ削ルガ如キ山腹ニテ一方ハ富士川ニ臨ム県崖ナレバ身延山法会ノ時期ハ毎々死傷ヲ生ズル危険有之地元村民ノ憂慮不尠候条何卒該出願ノ儀ハ御却下相成度此段奉懇願候也
明治廿九年一月十四日
山梨県南巨摩郡身延村大野区人民総代
松野義路
片田辨治
海野太左衛門
穂坂弥平
片田愛治郎
片田国太郎
身延村梅平区人民総代
近藤善左衛門
佐野儀兵衛
遠藤吉三郎
前書上申之趣相違無之ニ付奥印仕候也
右村長代助役
遠藤緑
山梨県知事 桜井勉殿
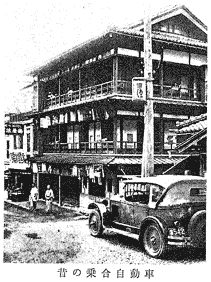 |
しかし、大正9年(1920)5月富士身延鉄道が身延まで開通し、11年11月には大野トンネルの開設、12年に身延橋の架橋が実現し、草深い身延の里も一躍近代化への歩みをふみ出し、参詣客も急激に増加した。
馬車業者もこれに対応して従来の「ガタ馬車」に代り改良されたゴム輪の「高等馬車」を走らせるなどして、日増しに活発化する交通の花形となっていたのであるが、大正14年に新しい時代の主役、自動車が登場するにいたり陸上交通の様相は一変するのである。
大正14年4月10日長谷川栄三郎が中心となって身延自動車株式会社が設立され、身延駅と身延山の間に定期バスの運行を開始した。当時これを乗合自動車と呼んだ。
資本金は10万円、社長は長谷川栄三郎、専務は諏訪源敏で、藤田佐一郎、藤田文太郎、深沢豊治、望月九房が重役であった。
自動車といっても当時のことですこぶる小型のものであり、T型フォード8人乗り2台、6人乗り3台という陣容だった。料金は身延橋の渡橋賃10銭を含み片道40銭だった。当時、散髪料が35銭だったことと比較すれば非常な高値であり、地元の利用客はごく少なかった。
身延鉄道も1日僅か4往復であり、乗合自動車もこれに応じた運行回数だったが、総門の坂も今より急坂で、車の馬力が弱くて登り切れず、坂にかかると乗客も降りて車の後押しをする珍風景も見られたという。
この自動車出現で打撃を受けたのが馬車、人力車の業者で、自動車会社が認可になる以前から組合が結束して死活問題だとばかりに猛烈な反対運動を展開しこれを阻止しようとした。自動車が動き出してからも両者の間には紛争が絶えず、自動車のすぐ前を空の馬車がわざとノロノロ走って妨害し追い越しもできないので自動車の客が怒り出すというようなこともあったが、しょせん時代の流れには勝てず、間もなく馬車も人力車もかげをひそめ、自動車の独壇場となったのである。
(二)富士川飛行艇
大正12年(1923)、身延弘通株式会社により運航計画が立てられた。天竜川で使用していたものと同じ幅広の木造船の後尾に飛行機用のエンジンを取り付けプロペラの推進力で水上を疾走するという当時としては珍らしい交通機関であった。3月より試験運航、7月営業を許可され、3隻をもって身延鰍沢間1日3往復の運転を開始した。従来の和船による舟運とはしばらくの間競争関係にあったが、身延線の開通、バスの発達に押されて寿命は短く、ともに昭和初年には姿を消して行ったのである。身延鰍沢間上りは所要時間2時間で運賃3円、下りは1時間半で1円70銭であった。
(三)自動車会社の発展と山梨交通
昭和3年に富士身延鉄道株式会社が身延自動車を買収し資本の90パーセントをにぎり社長は堀内良平の弟堀内宗平、専務は諏訪源敏となった。その後資本力にものをいわせ、近隣の群小自動車会社とその路線を次々に買収統合するほか路線を拡大し、やがて甲府−岩淵に至る本県陸上交通の大半を支配する後の山梨交通への基礎をきずいて行くのである。
 |
昭和6年富士川自動車株式会社を買収、芝川−岩淵、芝川−内房芝川−西山の3路線を獲得、バス3台、タクシー4台をもって運行した。またこの年甲府市内、甲府駅−南口間の乗合バスも買収した。
昭和7年(1932)には市川−甲府間の市川自動車、甲府−御嶽間の御嶽自動車を買収したほか市川−鰍沢線も認可され、甲府−身延山間の長距離運転も開始した。
昭和8年には総門−中野間の新県道、榧ノ木トンネル、開通を機に南部、万沢方面の道路も改修され身延−芝川間直通運転を開始した。
昭和13年9月、富士身延鉄道の国営化にともない、身延自動車株式会社は鉄道とはなれ独立経営となった。15年5月には身延−新倉間30.4キロメートルのバス運行も開始された。その後も増強、発展の一途をたどったが、昭和18年5月、政府の戦時経済政策により企業整備統合が行なわれ国中方面のバスが合併したのに次いで身延自動車株式会社もこれらと合併する。当時の身延自動車の規模は従業員75名、大型バス27台、タクシー16台、資本金27万7,500円であった。
昭和14年頃より戦時経済統制下に入り、ガソリンの規制強化により薪木炭等代用燃料を使って運行を続けた。19年頃からは戦局の激化にともない、従業員は召集、徴用のため半減し、代用燃料の薪・木炭さえ欠乏し自動車にとって不可欠のオイル、部品も全く入手不能となったため大部分の路線は運休の止むなきに至り、辛うじて身延駅−身延山、身延駅−新倉間を維持しつつ、苦闘のうちに終戦を迎えたのである。
昭和20年5月、企業合同による統合会社を一本化して「山梨交通株式会社」が発足したが、文字どおり甲府盆地一円、峡北、静岡方面を独占する公共的企業として、敗戦による極度の経済混乱のなかで住民の足となり、新規路線の開発、車の大型化、スピード化、改良、増発をはかり、今日の姿まで発展して来たのである。
現在身延営業所管内で、定規走行距離1日約4,000キロメートル、従業員240名、車輌総数84両である。
(四)山梨交通身延営業所の機構と概況
 |
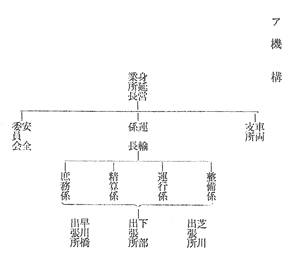 |
イ 従業員および車両
| 身延営業所分 | 芝川出張所分 | 計 | ||||||
| 区分 項目 |
男 | 女 | 車両 | 男 | 女 | 車両 | 人員 | 車両 |
| 事務所 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | |
| 観光 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | |
| 定期 | 40 | 35 | 30 | 15 | 11 | 11 | 101 | 41 |
| ハイヤー | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 |
| 整備 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| ライト | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 107 | 50 | 62 | 20 | 11 | 13 | 188 | 75 |
ウ 路線発車回数
| 下部線 | 36 | |
| 飯富線 | 12 | |
| 奈良田線 | 21 | |
| 雨畑線 | 4 | |
| 甲府線 | 14 | |
| 南部線 | 19 | |
| 身延山 下部線 |
9 | |
| 身延駅 身延山線 |
53 | |
| 南部循環線 | 12 | |
| 梅ヶ島線 | 8 | |
| 天子湖線 | 4 | |
| 甲府 奈良田線 |
2 | |
| 計 | 194 |
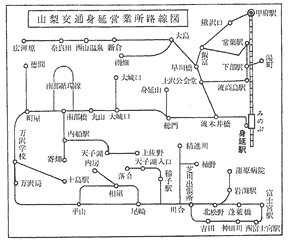 |
昭和42年度 10,794枚 14,552,475円
昭和43年度 9,963枚 13,869,545円
(五)身延タクシー株式会社
ア 沿革参拝客をはじめ陸上交通の激増にともないタクシーの需要も増大したので、従来山梨交通1社だったところへ昭和33年に佐藤善一を中心として身延タクシー株式会社が設立され、同年7月26日認可され営業を開始した。資本金は150万円で、当初丸滝480に本社をおき、車両数3両で営業したが、その後年々増加する旅客の需要にこたえて増車および営業所増設の認可を受けて現在に至っている。
 |
1 営業所
本社営業所 身延町梅平竜ヶ鼻(波木井橋)
身延山営業所 身延町仲町
身延駅営業所 身延町角打(身延駅前)
下山営業所 身延町下山上沢
2 従業員数 18名身延山営業所 身延町仲町
身延駅営業所 身延町角打(身延駅前)
下山営業所 身延町下山上沢
3 車両数 11台
(六)日本通運身延営業所
ア 日本通運の初期明治以来飛脚業の貨物運送への転業、小運送業者の乱立により運送業界は行きづまった。
本町においても駅前に
昭和19年、小運送の地区統合により十島−甲斐常葉間の各運送業者を統合して身延通運株式会社となったが、昭和20年8月1日日本通運株式会社に合併し、名古屋支社身延支店となった。営業区域は国母−十島間となった。
イ 身延営業所
昭和35年まで支店として従業員34名、作業員50名を有し、木材林産物、鉱石、一般貨物などの荷扱いも盛況を示した。特に軽金波木井発電所建設工事、早川電源開発工事等の資材運搬に果たした役割は大きいものがあったが、時代の推移にともない貨車輸送が自動車輸送に移行したこと、周辺にこれといった生産工場もないことなどによって業務量も逐次減少したので、会社の合理化方針により昭和36年営業所に縮少され、現在事務員3名、作業員7名で営業している。
所有施設としてベルトコンベヤー1基、3トンクレーン1基、トラック3台がある。
現在町民の利用する長距離陸上運送機関としては日本通運のほか、山梨貨物、鈴与定期貨物運送、石坂運送などの各会社がある。

