第二章 通信
第一節 通信の沿革
郵便や通信電話の通信が、国家をはじめ人類の集団生活に大きな役割をもち、この円滑な疎通が、政治・経済・文化などのあらゆる分野を、高い水準で動かしていることは疑う余地のないところである。このようにわれわれの生活に強く結びついている通信が、いつ頃から発達し、どのような経過をたどって、今日の姿を築いたかを考えることは、通信の歴史を知るばかりでなく、その時代の世情を知ることにおいても、ゆるがせにできない大事なことである。
いつの世から通信が行なわれていたかは判然としないが、文字がまだ使用されていなかった頃においても、自分の用件を他人に依頼して口伝えしたり、木の切り方の長短や紐の結び方などによって、自己の意志を伝えるという一種の通信方法があったようである。
通信方法が制度の上でやや形態が整ったのは、大化の改新のとき、諸国に駅馬、伝馬を置いて、公用、軍事の伝達を行なったのが始めてであろう。しかも、人事の交流、物資の交易等は小地域でしか行なわれていなかった時代のことであるから、軍公用通信さえ少数で、私用通信に至ってはごくわずかであったことが想像される。このような状況で、その後通信制度は大きな進歩はなかったようである。
鎌倉幕府に至って駅馬の制度を廃して、飛脚を置くようになり面目を一新した。それまで京都−鎌倉間は6日から7日を要したものが、5、6日で到着するようになったので、当時としては、この飛脚制度はかなり画期的な進歩であった。
降って戦国時代には、各部将とも領内だけの交通通信に留意したが、国内事情が他国に漏れることをおそれて、、国外との通信は厳重に取締まりむしろ他国の動静は、隠密を放って情報収集に努め、その行動を監視することを怠らなかった。国外との通信はこんな変則の方法で行なわれていたが、国内の通信にはいろいろの方法を講じ、戦場などからの急を要する通信には早馬や、また替馬をおいて、つぎつぎ馬を乗り継ぐ方法などが用いられた。しかし、一刻を争う火急の場合には、更に早い通信方法が欲しかったので篝(かがり)火通信が考案されたのであろう。
武田信玄は、国内の治安と充実をはかり、天文16年(1547)甲州法度五十五ヵ条を制定したが、通信に関しては特に逓送人夫の制度を定め、また、篝火通信について躅躑(つつじ)ヶ崎の館を中心に、国境や占領地区まで見通しのきく山頂に順次狼烟(のろし)台を設けて敵軍来襲に備えた。
永禄4年(1561)8月の川中島合戦に、信玄の出陣が「早きこと風の如し」であったのもこの篝火通信によるものといわれている。篝火通信について赤岡重樹は次のように述べている。
のろし、又は、かがり火といい、狼烟、狼煙、烽燧、烽火、飛火、野狼矢、烽火飛脚(ひきゃく)、飛脚篝などと、いろいろの名前が用いられているが、要するに戦時中、最も早く通信を行なう方法である。狼の字を用いたのは狼糞を乾かして、口火にすれば火付が早いと諸書に記されているからである。昼間揚げるのを「のろし」といい、夜間用いるのを「かがり火」といって、専ら煙と火とにより信号するのである。煙にも赤白紅黒紫の五種類あり、光にも十一種類の違いがあって、それぞれ秘密に製造されていた。戦国時代各群雄が競って利用した方法で、甲州の武田信玄も、またその例に洩れないのである。甲州の狼烟に関する記録は、いまだ発見されないが、現在国内各地に烽火台、のろし台、城山、御前山と称して、その遺跡が多数残っている。
本県内の当時の烽火台は大体に湯村山と愛宕山の鏡台山とを基点として、信州、駿河および武州、相州の三方面に放出していたようである。烽火台址調(甲斐国志)によると55項目にもわたっているが、特に身延近隣のものをあげてみる。一、西島村に篝火焼場あり、高敞にして府を望むべし。篝場、狼烟場、物見塚あり。飛脚篝火と云。
一、西島村、久成村、粟倉村に城山あり。
一、福士村に福士城址あり。烽火台で原大隅警固せり。
一、万沢村に白鳥の砦あり。城取山と云。打揚山と云う名称山中にあり。
一、寺所村の南岩の下村の北に城山あり。岩山峠立、山頂平なり。市川古城山より相伝へて鴨狩にも亦城山あり。
一、椿草里、大崩二村の東、御林の中にも小新城と云山あり。烽火台の址なり。
一、十島、 原嶺に旧塁址あり。東山の山吉備ヶ社と云処の左右に、東遠見、西遠見とて古址あり。高敞遠望。南行間山富士川の南は白鳥山
原嶺に旧塁址あり。東山の山吉備ヶ社と云処の左右に、東遠見、西遠見とて古址あり。高敞遠望。南行間山富士川の南は白鳥山 屋嶺の上より西北廿九町井出村の高岡にも狼烟場あり。是れ烽を伝へしならん。
屋嶺の上より西北廿九町井出村の高岡にも狼烟場あり。是れ烽を伝へしならん。
一、最勝寺村に城山あり、亭候を置し所か。
一、鰍沢村に観国台あり。くにみ平と云処あり。西郡筋にかかれり。
これによれば、本町の椿草里、大崩の東に烽火台があったようであるが、現在その遺跡が判然としないのは残念である。徳川時代の通信は、近いところは「お使い」的であって、書状を持って歩いたのである。名主(なぬし)などが文書を村内に配るときは、小使のような者を抱えておいて、それに配らせ、その者のことを「状夫」といった。後にこれを「歩(あり)き」ともいった。村から村へ継送りの書状は「廻状」といい、急を要するものには「夜中御継送り下されべく候」などと朱書していたものである。代官所の役人が村々を巡視するに先立って予定の順路を知らせ、宿泊、食事の準備を命ずるために「先触」という文書を発し村送りとした。これはリレー式の通信である。
天保7年(1836)2月に、紀州分家の西条少将が身延山に参詣され、横根村佐野為八宅が小休本陣となった。現存その御用留帳の一部に
(塩沢、望月勅雄提供)
従城州伏見佐屋廻り 夫より 身延通り 品川宿迄宿々問屋中
尚々此先触早々順達之上品川宿ニ 留置拙者江 可被相戻候 以上
泊附
尚々此先触早々順達之上品川宿ニ 留置拙者江 可被相戻候 以上
泊附
| 十一日 | 十二日 | 十三日 | 十四日 | 十五日 | 十六日 | 十七日 | 十八日 | 十九日 | 廿日 | 廿一日 | 廿二日 | |||||||||||
| 枚方 | 伏見 | 大津 | 石部 | 関 | 四ヶ市 | 桑名 | 宮 | 岡崎 | 吉田 | 浜松 | 日坂 | |||||||||||
| 廿三日 | 廿四日 | 廿五日 | 廿六日 | 廿七日 | 廿八日 | 廿九日 | 晦日 | 二月朔日 | 二日 | |||||||||||||
| 丸子 | 奥津 | 万沢 | 身延 | 万沢 | 吉原 | 箱根 | 大磯 | 藤沢 | 川崎 |
徳川幕府が瓦解(がかい)し、明治政府が誕生したが、定飛脚問屋は相変わらず各駅の伝馬所から人馬の供給を受けて、信書および貨物運送の営業を続けていた。江戸が東京となり、政治の中心がここに移ってこの事業はいよいよ繁昌(はんじょう)してきたが、政府は新式郵便の官営を企てて着々その準備を進めた。
明治3年(1870)5月郵便の生みの親である前島密翁が駅逓権正(ごんせい)となり、従来飛脚問屋の手によって行なわれてきた信書の取扱いを欧米先進国の例にならって、これを官業とし、全国に生き渡るよう諸般の準備を開始したのである。
政府は明治4年(1871)3月1日(旧暦)を期して、東京−大阪間に新式郵便制度を実施した。
これにより二百数十年間続いた民間飛脚営業は廃止の憂目となったが、一部の飛脚問屋を官営に移管させるという方法を取りながら、またこの救済策として飛脚業者に内約したのが、陸運会社の設立であった。これが後の内国通運会社となったのである。
身延地域にも飛脚業者が相又にあったであろう。それは、陸運会社が相又にあった事で想像できる。
「陸運会社定書−相又駅」(市川喜洋蔵)には、宿屋12名、木銭宿1名、人足25名、馬壱疋29名、馬差1名、計68名の者が連署して、申合規則を明治5年に定めており、これらの人が旅客物品の継立にあたっていたようである。また、この陸運会社が通達会社と改称したことも次の文書(市川喜洋蔵)で知ることができる。
以書付御届奉申上候
巨摩郡第三十四区
相又駅 市川三右衛門
右奉申上候陸運元会社通運会社ト改称シ御国内之通運を開キ各道公私之旅客物品ヲモ継立致シ候儀官ノ御准兌ヲ蒙り候趣ヲ以テ各地便利之向々江協議有之候ニ付当駅之儀者私継立方引受且物資運送向都テ元会社之規則ニ照準シ其開業之月ヨリ諸般不都合無之様継立方営業仕候ニ付此段御届奉申上候 以上
明治七年十二月
右駅右元社取扱所
継立引受人 市川三右衛門
戸長 市川九兵衛
山梨県令 藤村紫朗殿
政府は明治4年(1871)12月には、大幹線として東京より東海道筋長崎まで郵便を開いたが、同時に枝道郵便も開いた。すなわち、本県にあっては、同年12月、甲府でかつての飛脚問屋加藤源六郎所有の柳町の建物を甲府郵便役所として開設し、東海道吉原駅から甲府まで郵便が開かれて、その12月16日を初日として、毎月1、6の日に郵便を逓送した。巨摩郡第三十四区
相又駅 市川三右衛門
右奉申上候陸運元会社通運会社ト改称シ御国内之通運を開キ各道公私之旅客物品ヲモ継立致シ候儀官ノ御准兌ヲ蒙り候趣ヲ以テ各地便利之向々江協議有之候ニ付当駅之儀者私継立方引受且物資運送向都テ元会社之規則ニ照準シ其開業之月ヨリ諸般不都合無之様継立方営業仕候ニ付此段御届奉申上候 以上
明治七年十二月
右駅右元社取扱所
継立引受人 市川三右衛門
戸長 市川九兵衛
山梨県令 藤村紫朗殿
新式郵便制度実施にあたって、わが山梨県で駿州路線が最初に開かれたのは興味あることである。もちろん従前の飛脚業者の手を煩わしたことであろうが、方法経路などの資料がないのが残念である。
郵便事業が開始されて漸次郵便線路が伸張し、明治5年7月1日には国内一般諸道に信書送達の便を開くこととなり、従来の宿駅を利用して郵便取扱所を開設した。本県では先ず甲州街道に八ヵ所が開かれて、東京甲府間の郵便が実施された。ついで6年6月には甲府上諏訪間が開かれ、河内地方の郵便線路が開かれたのは、その翌7年5月1日であった。
すなわち、甲府郵便役所から東海道奥津(おきつ)までの沿道を開始し、毎月奥津から2、4、7、9の日、甲府から3、8、5、10の日をもって往復した。
七年五月十二日 布達一〇八
今般甲府柳町駅より東海道奥津迄郵便相開き別紙駅々江取扱所を設け、毎月彼の地より二、四、七、九の日、当地より三、八、五、十の日を以往復候条信書其外共差出方の儀は都而郵便規則に照準致志最寄取扱所へ可差出事
右の趣管内無洩相達する者也
明治七年五月十二日
山梨県権令 藤村紫朗
鰍沢駅、八日市場駅、相又駅、南部駅、万沢駅
右の趣管内無洩相達する者也
明治七年五月十二日
山梨県権令 藤村紫朗
鰍沢駅、八日市場駅、相又駅、南部駅、万沢駅
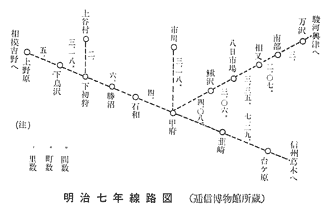 |
したがって、当町においては相又郵便取扱所が最初である。明治7年6月28日付で藤村県令の発した布達には、甲府を中心とした各地への郵便物の逓送経路を詳しく指示しているが、関係個所のみを次にあげる。
一、甲府ヨリ万沢ヲ経テ奥津駅ヘ通スル郵便継換地等従前ノ通唯回数ヲ増加且甲府鰍沢ヨリ発スル脚夫ハ布施ヘ鰍沢相又ノ脚夫ハ八日市場切石下山ヘ立寄郵便物請渡可致事 但静岡県管下駅々ヘハ別ニ相達候事
一、下山ニテハ鰍沢仕出シノ脚夫往復共立寄候筈ニ付郵便物受渡可致事
前述の相又駅陸運会社の内容などからみると、この相又駅内に郵便継換の専門脚夫がいたのであろうか。当時の相又地区は交通運輸の要所となっていたのであろう。しかし、明治11年(1878)11月1日付の豊岡村通運会社の資料によると、福居村(今の下山)から睦合村中野まで新道路が11月中に落成するので、清子で通運継立事務を行ないたい旨の願書が藤村県令あて提出され、11月11日付第7829号で聞届け許可の文書(市川喜洋蔵)があるところから、甲駿の往還も相又から清子に移ったのであろう。この相又郵便取扱所も明治14年(1881)の郵便線路図からは、その名称が消えており、何年頃廃止となったか判然としていない。
こうして明治4年政府の手によって始まった東京−大阪間の新式郵便は各地方に大きな変動を与えながら、早くも翌5年7月には全国の主要街道のほとんどに郵便の道を開き、着々と地歩を固めてその通信網を拡げていった。そして、確実、迅速、低廉の公共性に沿って発達し、ついで便利な電信電話と、一般に与えた利便は実に計り知れないものである。さらに大正、昭和とますます興隆の道をたどり明治100年の今日、この通信機関の発展充実ぶりは、一世紀前を偲(しの)べばただただ驚くばかりである。

