第二節 通信機関
山梨県における明治以後の通信の発達は、もちろん甲府市が中心であり、5年7月に甲府郵便役所が開設されて、東京−甲府、甲府−上諏訪、甲府−奥津間の主要線路が開き、9年に貯金業務、ついで電信、電話業務が開始されて、明治時代45年間に通信は目覚ましい発展をとげた。この間、明治8年に郵便役所等を一律に郵便局と呼称することとなったが、当時、全国各地に政府の手によって郵便局舎を新築することは到底望めないことで、地方の有志に局長を委嘱して、その自宅の一部を局舎にあて使用することとした。それが今日でも各地に特定郵便局として、地域の通信機関を担い、郵便事業に大きな役割を果たしているのである。
当町では明治時代に先ず下山郵便役所、ついで身延郵便局、大島郵便局(大河内局)、身延郵便受取所(身延山局)が開設された。大野に開設された身延郵便局は19年(1886)に大野郵便局と改称して身延山参詣客の利便するところであったようである。電信業務については、門前町にある身延郵便局(身延山局)が明治40年(1907)末に町内にはじめて電報受付配達事務を取扱い、ついで43年3月から下山・大野郵便局でも同様事務が開始された。
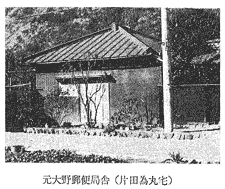 |
昭和時代、20年まではその大半を戦争によって費やされた時代であったが、昭和5年(1930)10月3日、大野郵便局は位置と利便の上から梅平地内に移転して身延郵便局と改称した。また、この年下山郵便局で電話20加入が開通して交換事務が開始された。大河内郵便局でも昭和8年7加入開通の交換事務を開始した。また、相又地区に新たに豊岡電信電話取扱所が昭和17年に開設され、昭和20年6月豊岡郵便局となった。
終戦の昭和20年8月以降は、敗戦から立上った民主国日本の大変動の社会情勢の中に、通信の使命ばかりでなく、政府の金融機関として郵便局の果たした役割も大きかった。そして、伸展する文化、社会、経済とともに通信機関としての郵便業務もますます増大し、身延山郵便局の電信通信も昭和37年従来の音響通信から、東京と直通の中継加入局となりタイプ送信に機械化され、峡南地区の集中局となった。
農村集団自動電話は昭和40年大河内郵便局区内の大島、和田、樋之上、角打部落の180戸に開通し、続いて上下八木沢、帯金、塩之沢、丸滝に開通、大河内地区に一挙に474戸が開通、42年には豊岡郵便局区内267加入が開通して、身延町内の電話普及度は急激に増加した。
これによって、かねてから身延町の町村合併の条件にもなっていた電報電話局設置が、普及度と加入者の熱望と相俟って実現することとなった。すなわち43年5月、町内の身延山、大河内、下山、豊岡郵便局の電信電話業務を統合して、日本電信電話公社直営の身延電報電話局が梅平に誕生し、待望の全国通信可能のダイヤル即時通話が開通し、加入者も増えて電話は家庭の必需品とまでなり、ここに町内の通信機関は大きく近代化された。
一、町内郵便局の沿革
明治初年、相又駅陸運会社には専用の脚夫により郵便継換が行なわれたようであるが、取扱所開設とならず、7年(1874)7月1日に先ず下山(2357番地)に下山郵便取扱所が開設された。続いて13年(1880)6月1日身延郵便取扱所と大河内郵便取扱所が開設された。後者は大島に開設されたが、これによりその翌年静岡方面への郵便線路が、富士川の両岸を通って確立したのである。(線路図参照) 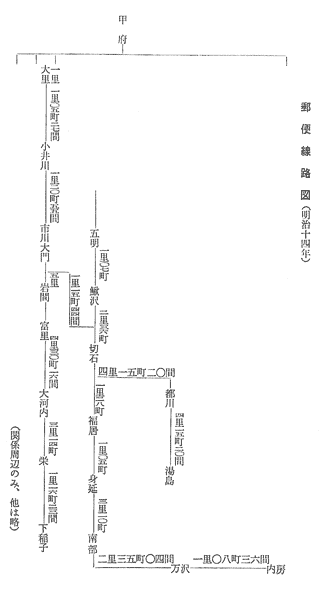 |
郵便制度の最初の開設は波木井の佐野太郎左衛門と云う人であったが、一年程の間に当時の金額約三〇円程を損したといふので廃業し、その後を現在の身延郵便局長の祖父片田愛次郎が継承して、大野に「身延四等郵便局」を開局した。
また、この請継書により、引継高、引継品を列記してみる。 現金弐拾壱円拾銭弐厘
壱銭切手百九十枚、弐銭切手二百五十七枚、四銭切手百三十七枚、壱銭端書三百六十枚、
秤壱基、郵便箱一ヶ、掛札壱枚、日附印壱ヶ、郵便規則二冊、郵便切手見本類拾四枚、金子入書状取扱用紙綴二冊、諸印達書百十七通、監察掛見合印鑑壱枚
この内容で郵便業務が行なわれたのであるが、経済事情の相違とはいえ現在の7円はがき1枚が、当時では700枚になることを思うと、想像できない驚きである。また、この内訳などから推察すると、壱銭はがきの売行きは悪く、ほとんど封書が用いられたようである。壱銭切手百九十枚、弐銭切手二百五十七枚、四銭切手百三十七枚、壱銭端書三百六十枚、
秤壱基、郵便箱一ヶ、掛札壱枚、日附印壱ヶ、郵便規則二冊、郵便切手見本類拾四枚、金子入書状取扱用紙綴二冊、諸印達書百十七通、監察掛見合印鑑壱枚
次に、この時の郵便御用受書を掲げる。
郵便御用取扱方左ニ御請申上候
一、切手ハ凡積ヲ以テ御渡相成候ニ付売捌並残高共御勘定表江記載シ一ヶ月限り御定則之通り渋滞無之様差上可申尤売捌代金ハ御差図次第上納可仕候事
一、切手売下手数料之義ハ売上高百分ノ四被下候事
一、市内江配達之書状並日誌新聞紙之義ハ一本ニ付金壱厘五毛づつ被上候事
一、非常之節ハ切手並売捌代金共専一ニ持退族様可仕候事
右之通り御聞届相成候上者何時被命候共諸事御差支無之様取扱此外御規則之趣屹度相守り精々御用弁相成候様可仕候依之証人連署受書差上候也
山梨県下甲斐国南巨摩郡身延村平民
郵便取扱人 片田愛次郎
山梨県下甲斐国南巨摩郡身延村平民
身元引受人 片田弁治
明治十四年一月十五日
駅逓総官 前島密殿
これを見ると、請負制度としての郵便御用をかしこまって取扱う当時の姿がうかがえ、お上(かみ)のことならばの世相も偲(しの)ばれる。山梨県下甲斐国南巨摩郡身延村平民
郵便取扱人 片田愛次郎
山梨県下甲斐国南巨摩郡身延村平民
身元引受人 片田弁治
明治十四年一月十五日
駅逓総官 前島密殿
明治17年頃、「身延郵便局所轄郵便切手売下所及函場取調表」によると売下人(現在の切手売捌人)が2名いた。即ち
開函証印番号第壱号、身延村393番地坂上昇泰(明治14年2月許可)
開函証印番号第二号、豊岡村戸長役場清水為八(明治16年7月許可)
となっている。当時の函場(はこば)という言葉は現在でもそう呼称している。
また、身延郵便局から取調べ郡役所へ送った郵便取扱量や区内状況報告書があり、明治17年7月から12月までの実績であるが、当時が偲ばれる資料として抜粋(ばっすい)して次に掲げる。
郵便物数 差立 三、一五三個 貨幣封入 十七個
配達 三、九一八個 貨幣封入 三五個
切手売下代 身延局 五六円 売下所 三六円(以上六か月間のもの)
郵便区内、市外の戸数と人口
区内 八三八戸 四、三七八人
市外 五一二戸 二、四三五人
区内の状況
配達 三、九一八個 貨幣封入 三五個
切手売下代 身延局 五六円 売下所 三六円(以上六か月間のもの)
郵便区内、市外の戸数と人口
区内 八三八戸 四、三七八人
市外 五一二戸 二、四三五人
区内の状況
地勢−南ハ睦合村ニ接シ、北ハ福井村ニ隣シ南ヨリ北ニ引キ、東ハ富士川ニ沿ヒ、西ハ身延七面ノ諸峯及ヒ大城山ヲ頂キテ元建村ニ界ス、地味瘠土多シ、道路最モ険難ニシテ羊腸馬背ノ苦ム所ニシテ物貨の運輸最モ不便ニシテ此隣江交通繁ナルヲ得ス。近隣為換局ハ鰍沢局ヘ六里余、南部局エ三里余アリ、民間ノ生業ハ別段盛衰ヲ見ス。他方トノ取引アリ殖産興業ニ注意ス。区内著名ナル山ハ身延七面ノ二山、寺ハ久遠寺本遠ノ二寺アリ故ニ諸国ヨリ為換等ノ振出振込専ラアリ為換局ノ遠隔ヲ歎ス
物産
米千石、麦千二百五十石、大豆五百石、三椏八十駄、粟四十石、
諸官衙諸会社
米千石、麦千二百五十石、大豆五百石、三椏八十駄、粟四十石、
諸官衙諸会社
戸長役場一(豊岡村ノ内小田舟原ニアリ)、公立学校三(波木井一、身延一、針山一)、運輸会社四(大野、波木井、清子、光子沢)、通運会社一(清子ニアリ)、□エ会社一(大野ニアリ)
輸出と輸入
輸出−大豆二百五十石 九十五円
三椏八十駄 弐百円
輸入−鰍沢地方ヨリ入
米五百石 代価三千百廿五円
駿地ヨリ入
塩百三十五石 代価三百七十八円
身延局区内とは、旧身延町と豊岡村を含めた区域であったろうと察せられるが、未だ為替業務を取扱っていない不便さを歎いているのが判る。また、貯金取扱もないが、翌18年から開始されたであろうことは次のような書類が現存することで推察できる。輸出−大豆二百五十石 九十五円
三椏八十駄 弐百円
輸入−鰍沢地方ヨリ入
米五百石 代価三千百廿五円
駿地ヨリ入
塩百三十五石 代価三百七十八円
御受書
今般当局江貯金取扱方御命可相成筈ヲ以テ事務御伝習相成候ニ付テハ左ノ件ニ御請仕候
一、服務規則承諾之事
(但書略)
一、逓送請負命置承諾之事
但逓送料ハ南巨摩郡南部郵便局江壱日往復一回金拾銭
一、同村第四百六拾壱番地平民戸主片田藤一ヲ身元引受ニ相立ヘク事
右之通リ相違無之候也
甲斐国南巨摩郡身延村第四百七十二番地
戸主 片田愛次郎
駅逓□□属 皆川克己殿
身延郵便局は大野に位置し、郵便取扱所から郵便局となったが、明治18年末か19年1月頃に提出したと思われる局名改称願の草案が現片田為丸局長の手許にある。全文を次に掲げる。今般当局江貯金取扱方御命可相成筈ヲ以テ事務御伝習相成候ニ付テハ左ノ件ニ御請仕候
一、服務規則承諾之事
(但書略)
一、逓送請負命置承諾之事
但逓送料ハ南巨摩郡南部郵便局江壱日往復一回金拾銭
一、同村第四百六拾壱番地平民戸主片田藤一ヲ身元引受ニ相立ヘク事
右之通リ相違無之候也
甲斐国南巨摩郡身延村第四百七十二番地
戸主 片田愛次郎
駅逓□□属 皆川克己殿
郵便局改称御願
甲斐国南巨摩郡身延郵便局
四等取扱役 片田愛次郎
右奉上願候当局義明治十三年五月御開設以来身延郵便局ト称シ候処身延村ノ義旧大野村梅平村波木井村又旧身延山門前ト右四ヶ村合併セシ称ニシテ当郵便局所在地ハ旧大野村ニアリ右身延山ハ県道ヨリ三十丁餘山間江遠隔セシ地方ニテ全ク甲府奥津間ノ郵便線路ヲ隔絶セシ山間ナレハ単ニ身延郵便局ト称スル中ハ不都合ナル場合多々有之右ハ地方監察御掛方ニ於テモ御巡回ノ節当局ノ位置ヲ誤リテ迂路ヲ御順回被成候御方モ有之加フルニ本年十月ヨリ貯金預所ヲ当身延郵便局江御開設ニ相成リ身延貯金預所ト称シ猶又身延山門前ニ身延村貯金預所ヲ御開設相成同村ニテ身延貯金預所ト身延村貯金預所ト両所アリテ只村ノ一字アルト無キトノ区別ノミナレハ己ニ御本局ニ於テモ貯金事務ニ関シ用紙御下ケ等モ別段ノ御配慮合可有之況ンヤ人民ニ於テテハ其誤解不尠己ニ近頃不都合モヲ生セシ事縷々有之且又通運会社代人順回等モ地方不案内ナル者ハ三十丁余アル身延山マデ紛込ミ初テ其誤ヲ悟リ又三拾丁余ヲ立戻ル等実地不都合不尠夫レ如斬ナレバ他ノ人民ハ申ニ及ハス実ニ身延郵便局ナレハ其身延山ニアル事ト想像シ意外ノ時日ヲ費ス事云フ可ラス夫レ如斬キ誤リアリテノ故カ己ニ隣局南部郵便局ノ如キモ睦合村ナレ共南部ト称シ富川村ノ如キモ万沢郵便局ト何レモ其地名ヲ局名ニ被仰付タルハ殊ニ以テ其宜キヲ得タル義ト深ク奉感銘候抑々身延郵便局ト称スルハ合併セシ村名ヲ用ヒタルモノニシテ全ク土地ノ状況地理便用ニ適セス前述ノ如キ実地ノ不都合アリ全ク土地山間ニ散在セシ村名ノ総称ヲ以テ最初御開設ノ際身延郵便局ト奉出願候弊ヨリ生スル場合ニ御座候且水陸ノ要路ニ当リ候土地ニテ従来ノ目的モ有之以テ猶又前述ノ如キ不都合ヲ生スル事不尠場合ニ付何卒地名ヲ以テ大野郵便局ト御改称之程伏而奉願上候
従前実地不都合ニ付改称ノ義多年熱心仕リ居リ候得共局名改称ノ如キハ御本局ニ於テ容易ナラサル御手数ノ義ト奉察候ニ付乍思延引罷在候処今回地方監察御掛田村義忠殿御巡回ニテ右号不都合モ実地御目ニ触タル由ニテ御下問ノ次第モ有之候ニ付御本局ノ御手数モ不顧奉出願候何卒此段深ク御洞察ノ上身延村豊岡村中央水陸要路ニ当リ県道郵便線路ノ沿道旧大野村ノ地名ヲ以テ大野郵便局ト御改称御聞届ケ被成下度伏而奉懇願候 以上
この願書が効を奏したのであろう。明治19年(1886)3月25日付大野郵便局と改称されている。甲斐国南巨摩郡身延郵便局
四等取扱役 片田愛次郎
右奉上願候当局義明治十三年五月御開設以来身延郵便局ト称シ候処身延村ノ義旧大野村梅平村波木井村又旧身延山門前ト右四ヶ村合併セシ称ニシテ当郵便局所在地ハ旧大野村ニアリ右身延山ハ県道ヨリ三十丁餘山間江遠隔セシ地方ニテ全ク甲府奥津間ノ郵便線路ヲ隔絶セシ山間ナレハ単ニ身延郵便局ト称スル中ハ不都合ナル場合多々有之右ハ地方監察御掛方ニ於テモ御巡回ノ節当局ノ位置ヲ誤リテ迂路ヲ御順回被成候御方モ有之加フルニ本年十月ヨリ貯金預所ヲ当身延郵便局江御開設ニ相成リ身延貯金預所ト称シ猶又身延山門前ニ身延村貯金預所ヲ御開設相成同村ニテ身延貯金預所ト身延村貯金預所ト両所アリテ只村ノ一字アルト無キトノ区別ノミナレハ己ニ御本局ニ於テモ貯金事務ニ関シ用紙御下ケ等モ別段ノ御配慮合可有之況ンヤ人民ニ於テテハ其誤解不尠己ニ近頃不都合モヲ生セシ事縷々有之且又通運会社代人順回等モ地方不案内ナル者ハ三十丁余アル身延山マデ紛込ミ初テ其誤ヲ悟リ又三拾丁余ヲ立戻ル等実地不都合不尠夫レ如斬ナレバ他ノ人民ハ申ニ及ハス実ニ身延郵便局ナレハ其身延山ニアル事ト想像シ意外ノ時日ヲ費ス事云フ可ラス夫レ如斬キ誤リアリテノ故カ己ニ隣局南部郵便局ノ如キモ睦合村ナレ共南部ト称シ富川村ノ如キモ万沢郵便局ト何レモ其地名ヲ局名ニ被仰付タルハ殊ニ以テ其宜キヲ得タル義ト深ク奉感銘候抑々身延郵便局ト称スルハ合併セシ村名ヲ用ヒタルモノニシテ全ク土地ノ状況地理便用ニ適セス前述ノ如キ実地ノ不都合アリ全ク土地山間ニ散在セシ村名ノ総称ヲ以テ最初御開設ノ際身延郵便局ト奉出願候弊ヨリ生スル場合ニ御座候且水陸ノ要路ニ当リ候土地ニテ従来ノ目的モ有之以テ猶又前述ノ如キ不都合ヲ生スル事不尠場合ニ付何卒地名ヲ以テ大野郵便局ト御改称之程伏而奉願上候
従前実地不都合ニ付改称ノ義多年熱心仕リ居リ候得共局名改称ノ如キハ御本局ニ於テ容易ナラサル御手数ノ義ト奉察候ニ付乍思延引罷在候処今回地方監察御掛田村義忠殿御巡回ニテ右号不都合モ実地御目ニ触タル由ニテ御下問ノ次第モ有之候ニ付御本局ノ御手数モ不顧奉出願候何卒此段深ク御洞察ノ上身延村豊岡村中央水陸要路ニ当リ県道郵便線路ノ沿道旧大野村ノ地名ヲ以テ大野郵便局ト御改称御聞届ケ被成下度伏而奉懇願候 以上
なお、この書類によれば山門前に「身延村貯金預所」が存在していた。明治34年(1901)身延郵便受取所として開設した現在の身延山局の前身でないとしても、門前町の何処かに開設されていたことである。位置や実績が不明であるのは残念である。
その頃の身延山は明治14年、今の祖師堂が落成して六百遠忌を行ない、16年には法喜堂、19年には大客殿が再建されるなど身延山の隆盛期で、従って身延村は門前町はもちろん村全体が活気に満ちていたことと思う。
身延、下山、大河内の各郵便局で貯金事務を開始したのは明治19年10月1日である。
郵便事業も着々とその実をあげており、明治18年10月に各郵便路線の等級を改めて指定した。
明治十八年十月二十九日駅逓局報附録(抜粋)
全国郵便線路「中線路ノ部」
甲府−興津線
甲府、小井川、市川大門、鰍沢、切石、福居、身延、南部、万沢、宍原、小島、興津
郵便物逓送時間「中線路ノ部」
甲府興津下り便三等速度十七時間三六分
同 上り便三等速度十七時間三六分
当時は郵便運搬人を脚夫といって、郵便局から郵便局へ足早に往復し、この速さを逓送速度といった。そして、1等速度は1時間に2里半、2等速度2里、3等速度1里半と規定で定められた。脚夫の服装は饅頭(まんじゅう)笠、ハッピ、股引、すべて黒一色で、草鞋がけといういでたちに、天秤棒の先に行嚢(こうのう)をくくりつけて担ぎ、貸与の丸型逓送時計を肩からさげ、時間に遅れないよう歩いたそうである。この頃、すでに富士川には舟便が運行されていたが、郵便物はこれを利用していなかったようである。しかし、その後、明治33年(1900)10月1日から水路郵便線路として鰍沢−岩間に限ってこの富士川が利用され、郵便物が水上を上下した。全国郵便線路「中線路ノ部」
甲府−興津線
甲府、小井川、市川大門、鰍沢、切石、福居、身延、南部、万沢、宍原、小島、興津
郵便物逓送時間「中線路ノ部」
甲府興津下り便三等速度十七時間三六分
同 上り便三等速度十七時間三六分
明治中期の甲府−興津間の路線はなかなか整備されず難所の多いところであった。当時の甲府郵便電信局長から出された文書にも、「興津線ニアッテハ富士川ニ沿ツテ道路峻嶮又早川ノ源流アツテ一朝天変ニ遇フトキハ迂回スルニ道ナク終ニ郵便物ノ逓送ヲ遮断スル患アル」(甲府郵便局80年誌)とあり、水害や山崩れなど、自然の猛威の前には、逓送の途絶もしばしばであったと思われる。
為替業務は、大島(大河内)郵便局が早く明治22年12月6日、下山郵便局で明治23年11月1日から開始している。大野(身延)郵便局ではまだこの頃取扱っておらず、明治27年逓信大臣黒田清隆あてに「郵便為替貯金事務御開設願」が出されており、また、この年の同局区内状況調書には次のように記されている。
最近為替貯金取扱所へ距離
北ハ下山郵便局ヘ一里卅五丁当区内ヨリ下山局区内ニ至ル連山ヲ以テ界ス、南ハ南部郵便局ヘ二里十九丁当区内ヨリ南部局ノ境界ハ小丘一里余ニシテ人家ナシ、東ハ富士川ニ臨ミ西八代郡と相対シ、西ハ連山重畳シ駿河ノ国ニ界ス、駿河ノ国梅ヶ島温泉ヘ通スルノ道アリト雖モ三里余ノ里程中人家更ニナシ
大野局では17年頃より為替取扱の開設願を申請し、27年にも提出しているが結局開始したのは明治29年5月1日からである。どうして遅れたかは不明である。明治34年3月15日身延総門内元町に身延郵便受取所(今の身延山局)が開設された。そして40年1月6日身延郵便局となり、41年12月11日に仲町に移転した。この間のことを身延教報誌昭和25年4月号「身延町の今昔」には次のように書かれている。北ハ下山郵便局ヘ一里卅五丁当区内ヨリ下山局区内ニ至ル連山ヲ以テ界ス、南ハ南部郵便局ヘ二里十九丁当区内ヨリ南部局ノ境界ハ小丘一里余ニシテ人家ナシ、東ハ富士川ニ臨ミ西八代郡と相対シ、西ハ連山重畳シ駿河ノ国ニ界ス、駿河ノ国梅ヶ島温泉ヘ通スルノ道アリト雖モ三里余ノ里程中人家更ニナシ
明治三十四年三月十五日身延狐町の阪上延太郎氏が現在の島屋呉服店の処に郵便受取所を開き、同四十年十月二十六日望月宗太郎氏の時に無集配三等局に昇格、同時に局舎を仲町の現在の郵便局前に移し、同年十二月二十六日より電信を取扱った
狐町とは今の元町のことで、元町から現在位置(昭和44年4月移転地)に移築したのである。前局舎は電話交換業務のために新築されたもので、大正14年4月16日から昭和44年4月までの満44年間、山の郵便局として門内住民と身延山参詣者に利用された局舎である。電報の受付と配達をするようになったのは、やはり身延局(身延山局)が早く、峡南地方でも、鰍沢(24年)、南部(30年)、岩間(34年)、切石(36年)についで、身延局で40年12月16日に開始された。記録によると、最初の電報配達手である米山大太郎の採用日付が、この開始日となっているので確かであろうが、そうすると電信業務は先ず元町で始まったこととなる。なお、この時の電信回線は、静岡−甲府で、回線内に南部局と共に含まれていた。つづいて、43年3月31日から、下山、大野局で同時に取扱うようになった。
大正初期における関係回線名と接続局名をあげると次のようである。
静岡甲府線=静岡、万沢、内船、南部、大野、身延、甲府
甲府下山線=鉄道甲府、甲府、岩間、西島、切石、飯富、下山
簡易保険、郵便年金業務が始まったのは大正時代であるが、保険は大正5年(1916)10月1日全国郵便局で一斉に開始され、年金は大正15年10月1日から同様開始となった。当町では未開局の豊岡局を除いて4郵便局でこの取扱を始めている。甲府下山線=鉄道甲府、甲府、岩間、西島、切石、飯富、下山
大正12年、これまで大島にあった大河内局は、身延駅前に1月移転したが、この年の8月に身延橋も開通した年であって、村民や参詣者の利便も大きかったであろう。
電話が郵便局につけられ、いわゆる郵便局へ行って電話がかけられるようになったのは大正13年4月26日からで、町内では先ず身延局(身延山局)と下山局でこの通話事務が開始された。このため個人架設の要望が大きく、その翌年には身延局で交換事務が開始されて54の加入者が電話開通した。下山局の交換開始はこれより遅れて昭和5年1月21日、大河内局は昭和7年6月11日である。
大野郵便局(身延局)は駅前に大河内局が移転してきたため、富士川をはさみ相対することとなり、一方、梅平地内には県立中学校が開校(大正12年)されるなど将来の峡南文化の要地としてクローズアップされたため、昭和5年10月3日梅平(現在地)に移転し、同時に身延郵便局と改称した。これに伴い従来の門内の身延郵便局は身延山郵便局と改称された。
当時、大野局が身延局と改称されることは、身延局では全く予想しておらず、また、自局が身延山局と改称されることも知らなかったようで、仄(そく)聞して慌(あわ)てて、この年9月20日にこれに対する質議の文書を提出した事が、身延山局の記録簿に記載されている。続いて次のような記事が記されている。
昭和五年十月一日
右当局照会文書ニ対シテハ何等ノ回答ヲ交付為ササルノミカ局名改称ニ干スル件ト題シテ下記ノ如キ命令的通知ノ送付ヲ受ケタリ
規郵第一四九四八号
東京逓信局規画課長
右当局照会文書ニ対シテハ何等ノ回答ヲ交付為ササルノミカ局名改称ニ干スル件ト題シテ下記ノ如キ命令的通知ノ送付ヲ受ケタリ
規郵第一四九四八号
東京逓信局規画課長
来ル十月三日大野郵便局ハ身延村大字梅平一三六〇番地ニ移転シ局名ヲ「身延」ト改称ニ付右に伴ヒ貴局モ又局名ヲ「身延山」と改称セラルヘキニ付了知相成度
追而電信区 異動ニ干シテハ別途令達セラル(原文ノママ)
追而電信区 異動ニ干シテハ別途令達セラル(原文ノママ)
右当局長ノ致セル質議ニモ窺ヒ知ルヘク当局ノ憂慮ニ堪ヘサル処ハ単ナル局名ノ改称ヲ論スルモノニ非ス今ココニ明治四十年以来称ヘツツアリタル「身延」ヲ全ク同一局名ヲ他ノ局然モ隣接ノ局名トシテ呼称セシムヘキ新シキ規画ノ地方的情勢ニ即セサルヲ謂フ也
長い間の「身延郵便局」の呼称が解消される寂しさと、それが隣接局で称えられる不満を述べたのであろう様子がうかがえる。大身延町となった今にして思えば、往時の語り草として今昔の感がするのである。豊岡村に豊岡電信電話取扱所が開所されたのは、第二次世界大戦勃発の翌年17年(1942)8月21日で、電報と電話を取扱い、昭和20年敗戦直前、6月11日豊岡郵便局となって、郵便為替貯金、保険年金の業務も取扱うようになった。これで現在の5郵便局が揃ったわけである。
町内各郵便局の沿革と歴代局長
| 局名 | 下山郵便局 | 身延郵便局 | 大河内郵便局 | 身延山郵便局 | 豊岡郵便局 | |
| 開 局 |
名称 | 下山郵便取扱所 | 身延郵便取扱所 | 大河内郵便取扱所 | 身延山郵便受取所 | 豊岡電信電話取扱所 |
| 年月日 | 明治7.7.1 | 明治13.6.1 | 明治13.6.1 | 明治34.3.15 | 昭和17.8.21 | |
| 場所 | 下山2357番地 | (波木井) | 大島1,181番地 | 身延村元町 | 相又林先下610番地 | |
| 郵便局となった年月日 | 下山郵便局 明治8.1.1 |
身延郵便局 (不明) |
大河内郵便局 (不明) |
身延郵便局 (明治40.1.6) |
豊岡郵便局 昭和20.6.11 |
|
| 局名改称 | 福居郵便局 再び下山郵便局 となる (年月日不明) |
大野郵便局 (明治19.3.25) 身延郵便局 (昭和5.10.3) |
大島郵便局と称 したことあり |
身延山郵便局 (昭和5.10.3) |
||
| 局舎移転と新築 | 下山2,360番地 の1に新築移転 (昭和38.11.17) |
梅平645番地に 新築移転 (昭和5.10.3) 同所に新築 (昭和42年12月) |
角打744番地に 新築移転 (大正12年1月) |
身延村823番戸 に新築移転 (明治41.12.11) 身延3,750番地 に新築移転 (大正14.4.16) 身延3,756番地 に新築移転 (昭和44.4.28) |
||
| 集配、無集配局の別 | 集配局 | 集配局 | 集配局 | 無集配局 | 無集配局 | |
| 歴代局長と 就任年月日 |
芦沢九左衛門 芦沢九左衛門 芦沢忠男 |
片田愛次郎 片田浅治郎 片田為丸 |
名取新作 片田作市 佐野助蔵 佐野弥録 佐野昭 |
阪上延太郎 (明治34.3.15) 阪上孝平 (明治36.3.20) 望月宗太郎 (明治40.10.26) 阪上治良 (大正10.10.22) 望月佐門 (大正11.1.24) 阪上治良 (大正14.9.19) 池上三郎 (昭和13.6.20) 片田為丸併職 (昭和33.11.8) 池上荒一 (昭和34.7.17) |
市川政一 市川や江 市川政一 市川喜洋 |
|
町内郵便局業務開始日一覧表
|
局名
区分 |
下山郵便局
|
身延郵便局
|
大河内郵便局
|
身延山郵便局
|
豊岡郵便局
|
| 郵便 | 明治 7. 7. 1 | 明治13. 6. 1 | 明治13. 6. 1 | 明治34. 3.15 | 昭和17. 8.21 |
| 貯金 | 明治18.10. 1 | 明治18.10. 1 | 明治18.10. 1 | 明治34. 3.15 | 昭和20. 6.11 |
| 為替 | 明治23.11. 1 | 明治29. 5. 1 | 明治22.12. 6 | 明治34. 3.15 | 昭和20. 6.11 |
| 簡易保険 | 大正 5.10. 1 | 大正 5.10. 1 | 大正 5.10. 1 | 大正 5.10. 1 | 昭和20. 6.11 |
| 郵便年金 | 大正15.10. 1 | 大正15.10. 1 | 大正15.10. 1 | 大正15.10. 1 | 昭和20. 6.11 |
| 電信 | 明治43. 3.31 | 明治43. 3.31 | 昭和 6. 3. 1 | 明治40.12.26 | 昭和17. 8.21 |
| 電話通信 | 大正13. 4.26 | 昭和13.10.11 | 昭和 6. 3. 1 | 大正13. 4.26 | 昭和17. 8.21 |
| 電話交換 (開始時加入者数) |
昭和 5. 1.21 (20) |
昭和 7. 6.11 (7) |
大正14. 6.16 (54) |
昭和17. 8.21 (1) |
昭和時代となり郵便、為替貯金、保険年金、電信電話の各業務体制が整った郵便局は、国策国情に沿って各事業とも充実し発展していったが、20年の敗戦までの間はとりわけ戦争遂行のために動員され、郵便、電信電話も専ら軍事優先の状況であった。軍事郵便、検閲、弾丸切手、国債、貯蓄債券、保険1戸1口運動等、すべてが明治、大正人には何とも言えない戦時中の数々の思い出である。
昭和20年7月6日、寸時にして甲府市は焦土となり、間もなく敗戦の日を迎えたが、その後の郵便局業務も、立直しの国の施策に沿って努力と労苦は大変なものであった。特に経済は悪性インフレーションに襲われ、その対策として21年2月に金融緊急措置令が施行され、新円の切替が実施された。すなわち1ヵ月に世帯主300円、その他の世帯員1人につき100円以内に制限し、その払戻しを認めるというのである。これは郵便局と銀行で取扱ったが、当時の町内各郵便局前は行列を作っての混雑を呈した。ついで8月には第二封鎖貯金の設定で、郵便貯金の最高預入制限5,000円で3,000円未満は第一封鎖となり、3,000円以上も家族合わせて3万2,000円まではこの制限を受けなかったので、制限を受けた預金者は割合少なかった。この第二封鎖は23年7月解除となった。
昭和24年6月、逓信省も郵政と電気通信に分割し、その電気通信省も27年日本電信電話公社となった。そして、特定郵便局で取扱う電通業務は公社の委託業務とされた。身延町にも43年5月には電々公社直営の身延電報電話局が誕生して、町内各郵便局の電通業務は一切移管すると同時に電話はダイヤル自動化となった。郵便局は郵政省本来の郵便、為替貯金、簡易保険のみの事業に専念することとなった。
古い伝統と歴史を持つ町内5郵便局は郵政事業の使命に燃えて、今後も身延町の発展とともに力強く歩み続けるであろう。

