(三)農村集団自動電話の開設
旧大河内村を区内とする大河内郵便局は、昭和7年に加入者7の電話開通以来30年を経た昭和38年にも加入電話180個という状態であった。これは身延駅周辺が商店街で発達したのに反し、他部落は農家や俸給生活者の地域であることと、南北に長い地勢であるため、「地域外」の地域が多くて、電話設備と維持費がかさみ、単独申込者が少なかったためでもあろう。しかし、戦後20年、電話も家庭必需品という時代を迎え、また、日本電信電話会社でも、農山漁村の無電話部落解消のため地域団体加入電話、農村公衆電話設置の普及につとめていた時でもあり、大河内地区の農村部落にも電話架設の要望は高まってきた。
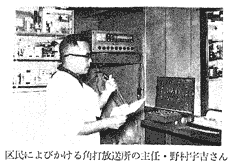 |
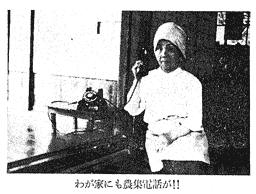 |
団体加入電話加入申込書
下記の団体加入電話の加入申込をします。
昭和三十九年九月九日
加入組合の名称
大島和田地域団体加入電話組合
住所
山梨県南巨摩郡身延町大島二五八〇番地
代表者名
組合長 若林孝義
鰍沢青柳電報電話局長殿
一、組合交換設備の設置場所
身延町大島二五八〇番地大島農業協同組合内
二、本電話機の数(組合員別及び設置場所別)一五六個
別紙組合員名簿の通り
(別紙組合員一五六名の名簿省略)
そして、山梨電気通信部、関東電気通信局に陳情するなど、就任2年目の現大河内局長佐野昭も加わって活発な運動が展開された。しかし、たまたま電々公社では「農村集団自動電話」の普及も合わせて奨励しており関係法がこの頃国会を通過して、10月1日から新たに施行実施されることとなった。下記の団体加入電話の加入申込をします。
昭和三十九年九月九日
加入組合の名称
大島和田地域団体加入電話組合
住所
山梨県南巨摩郡身延町大島二五八〇番地
代表者名
組合長 若林孝義
鰍沢青柳電報電話局長殿
一、組合交換設備の設置場所
身延町大島二五八〇番地大島農業協同組合内
二、本電話機の数(組合員別及び設置場所別)一五六個
別紙組合員名簿の通り
(別紙組合員一五六名の名簿省略)
農村集団電話とは、①無人自動交換機を設置して多数共同電話を収容、②市内通話は相互間では自動交換で行ない、一般電話とは電話取扱局で接続、③市外通話は発着信とも手動で電話取扱局で接続、④創設費は設備料と債券で負担というものである。その説明資料によると概要は次のとおりである。
制度の概要
同一電話加入区域内に、公社が定めた定数以上の電話機で、これを自動交換機からの一回線に5個以上10個までを取付け、自動交換機と電話取扱局の交換機を回線で結んで通過するもの。(図参照)
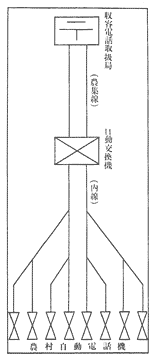 |
1、設置条件
| ① | 2以上の電話加入区域にわたらない最低200名程度の集団加入申込、自動交換機から5キロメートル以内、農・林・漁業が大部分の地域。 | |
| ② | 1回線に5個以上10個以内の電話機をつける。 | |
| ③ | 7級局までの電話取扱局で設置できる。 |
2、主要料金
| ① | 創設時−加入料300円、設備料10,000円、債券60,000円 (1加入につき) |
線路設備費は普通加入区域外にあって自動交換設備から4キロメートル以上の電話機に区域外分の設備費を課する。
| ② | 月々の使用料−普通加入区域5級局は470円、区域外同670円、(注 大河内局は5級局となるので5級局分のみ記す。) | |
| ③ | 付加使用料(交換設備から4キロメートル以上のもの)−地団に準ずる。 |
和田部落に自動交換機が設置され大河内局と結び、ついに昭和40年6月8日開通したがこれは関東通信局管内でも第3番目であり、非常に画期的なものであった。
若林組合長、佐野局長の東奔西走の努力、組合員積極的な熱意もさることながら、郷土出身、電々公社出身の鈴木強参議院議員の功労を忘れてはならない。
創設費の加入申込者負担は計70,300円であったが、実際には債券を売却したので17,000円ですみ、また身延町の補助金54万円と合せて360万円でこの完成を見たのである。
ダイヤル式の便利な電話の出現に、北部の帯金地区からもこの設置運動が起ったのは当然であった。しかし、この地域には大きな難関があった。農村電話は同一加入地域でなければならないのに、上八木沢、下八木沢部落は下山郵便局の電話特別加入区域となっていたからである。
先ず、この加入区域を大河内局加入区域に変更しなければ両部落には農集電話はつかないわけである。電話加入区域の変更は当該局長の申請によるものであるが、従来から調査等日時を要し、なかなか実現は難かしい状態であった。
40年9月佐野為雄町長と組合代表鮎川太郎の連名で区域変更に対する陳情が公社に提出され、また両部落民全員署名の次のような陳情書も提出された。
電話加入局変更に関する陳情書
(陳情の要旨)
山梨県南巨摩郡身延町大河内地内の上八木沢、下八木沢両部落は、下山郵便局の特別加入地域になって居りますが、大河内郵便局の加入地域に変更して戴きたいための陳情書
(理由)
前記両部落は、旧大河内村に所属していた関係上児童生徒の教育をはじめ、地区行政上の行為の凡てや、その他あらゆる日常生活が、大河内地区の他の部落と同型の上に営まれておりますが、電話のみは要旨に記した通り、富士川の対岸である下山郵便局の管轄に所属しているため、部落住民の日常生活に支障をきたしております。
この度、大河内農村集団電話設置の話が出たのでこれに加入することによって上記の障害を克服出来るものと部落民一同等しく喜んでおりました。ところが関係筋の説明によれば他局の加入地域に存在するものは、この大河内農村集団電話に加入できない由ですが、つきましては、両部落の実情をとくと御明察の上、大河内郵便局への加入区域に変更して下さるよう関係住民の署名をもってお願い致します。
昭和四十年九月二十五日
代表者 米沢節三
鮎川太郎
上、下八木沢が下山局の特別加入区域になったのは、下山局の電話開通が大河内局より早く昭和5年であり、同時に波高島駅に電話が開通している。この近辺の両部落は大河内局より遠距離にあるので、波高島駅周辺発展の将来性から下山局特別加入区域となったものと想像される。(陳情の要旨)
山梨県南巨摩郡身延町大河内地内の上八木沢、下八木沢両部落は、下山郵便局の特別加入地域になって居りますが、大河内郵便局の加入地域に変更して戴きたいための陳情書
(理由)
前記両部落は、旧大河内村に所属していた関係上児童生徒の教育をはじめ、地区行政上の行為の凡てや、その他あらゆる日常生活が、大河内地区の他の部落と同型の上に営まれておりますが、電話のみは要旨に記した通り、富士川の対岸である下山郵便局の管轄に所属しているため、部落住民の日常生活に支障をきたしております。
この度、大河内農村集団電話設置の話が出たのでこれに加入することによって上記の障害を克服出来るものと部落民一同等しく喜んでおりました。ところが関係筋の説明によれば他局の加入地域に存在するものは、この大河内農村集団電話に加入できない由ですが、つきましては、両部落の実情をとくと御明察の上、大河内郵便局への加入区域に変更して下さるよう関係住民の署名をもってお願い致します。
昭和四十年九月二十五日
代表者 米沢節三
鮎川太郎
当時、すでに下山局加入電話として両部落に農村公衆の4共同電話があったが、農集電話に加入できるならば返上してもよいという部落民一同の了解と、身延電報電話局実現の見通しも明るく近い将来加入区域の問題も解消されることが予想され、更に町当局、両部落、大河内局の三者一体の熱意が電々公社を動かして、ついに実現するに至った。
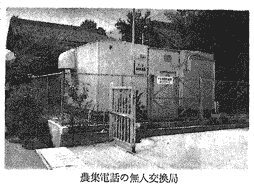 |
大河内郵便局加入の農村集団自動電話の実現によって、農家が大半を占める旧豊岡村地域にも便利好評の農集電話に関心が高まり、豊岡局への照会がひんぱんとなってきた。豊岡局長市川喜洋は各区長に呼びかけ、鰍沢青柳電報電話局から担当課長を招いて、説明会を開いたのが昭和40年10月1日であった。この第1回の説明会により急激に農集電話架設の要望が盛り上って、11月には「豊岡農村集団自動電話促進委員会」が誕生し、委員長に町議の柿島武文が選ばれた。また役員も各部落から選出され、副委員長7名、会計1名、書記3名、監事2名、委員22名が決定したが、なお会合の回数がひんぱんに行なわれるということで代議員制をとり、申込者5人に1人の割合で代議員48名の組織作りがなされた。
11月18日代表者柿島武文をもって296名の集団加入申込がなされた。各部落別内訳の申込数は下のとおりである。
船原23、小田22、門野17、湯平13、大城41、相又下24、相又上29、光子沢19、大久保19、横根27、清子62
ところが、船原部落は身延山局の電話普通加入区域であるので農集電話申込から除外される羽目となった。早速船原区長大村益三から豊岡局加入区域に変更されたい旨の陳情書が出されたが、到底見込もなく、身延総門下一帯も同地区であるため、身延山局電話加入者もあって、大河内の上、下八木沢部落と同じ状況とならないので、結局船原部落20名は41年4月農集電話申込を取消し、新たに身延山局に2共同電話で申込み、この促進を農集委員会とともに行なうこととした。委員長、役員をはじめ豊岡局長は機会あるごとに折衝、陳情と十数回に及ぶ涙ぐましい努力が繰り返された。また鈴木強参議院議員の大きな力添えもあって年末には工事に着工し、相又下に無人交換機も設置されて、翌42年3月14日267加入が開通したのである。身延町から補助金1加入3,000円、計80万1,000円が助成され、個人負担70,300円も債券売却によって17,500円ですみ、剰余金は開通後の電話料、維持資金にあてた。船原部落の2共同加入も申込者20名の熱意が報いられて5月には開通、喜びの全加入者は5月30日関係者を招いて豊岡小中学校屋内運動場で盛大な開通祝賀会を開催した。
この委員会は事業達成により解散し、43年1月14日新たに豊岡農村集団自動電話組合として発足し、農集電話の改善と電々公社に協力する規約を作り、現在もなお活発に運営されている。
(四)身延電報電話局の設置と経過
昭和30年、町村合併により新しい身延町が発足したが、その時の条件の一つとして電報電話局設置がとり上げられていた。しかし当時町内4郵便局の電話加入数を併合しても四百余りで、実現には程遠いものであり、合併直後の町行政もあわただしい時期であったので、巷間に全くその声は聞かれなかった。昭和34年の台風7号と15号は身延町にも大きな爪跡を残したが、災害見舞に鈴木強参議院議員が来町し、その折町内各郵便局長と会合が持たれた。鈴木議員は、既に町議会で決定されている電報電話局の実現に積極的に協力されたい旨の要望があったが、局長側から大体次のような意見が出された。
| 1、 | 町発展のために電報電話局の実現には賛成である。 |
| 2、 | 町議会で決定されていても何等われわれとの話し合いがない。 |
| 3、 | 町議会の決定が電話加入者の総意とは考えられない。 |
| 4、 | 四局それぞれ地域状況が異なり未だ加入者の意見が徴されていない。 |
| 5、 | 以上の理由で時期尚早と考えられる。 |
一方、社会状勢は経済の発展、生活の向上とますます電話の需要度を高めたが、申込電話はなかなか開通しない現状であった。しかし身延町では35年から四ヵ年で163人が開通しており各局長の積極的な意欲の結果といえるであろう。同時に加入者の電話統合の関心も漸く高まり、利用度の高い身延山、大河内局の加入者は統合賛成意見が多く見られたが、下山、豊岡局加入者は一挙に賛成し難い状況であった。
町議会でも電報電話局設置促進特別委員会が設けられて、各郵便局長としばしば会合を開き意見の交換を行ない、また、部落の会合も開いて積極的にその必要性の普及につとめた。
電々公社の電信電話拡充長期計画は、28年度を初年度として第1次五ヵ年計画がスタートした。第4次の終る47年には全国99パーセントがダイヤル即時化を目標とするもので、山梨県下でも逐次自動化が進められていた。これは郵便局の電気通信施設の改廃も含まれて自動改式する計画であり、いわゆる電通合理化計画である。
これまで町内4郵便局の電通業務を一ヵ所にそのまま統合する案がすすめられたきたようであったが、電報電話局の建設による合理化計画がクローズアップされてきた。
39年度においては4郵便局の電話総数600加入でまだダイヤル化には難点があったようである。
このような状勢のためか、身延電報電話局は無人局、すなわち無人の自動交換機だけを設置するという情報がもたらされてがく然としたのであった。直ちに町当局はもちろん各局長も関係筋に有人局設置となるよう強力な要請を行なう一幕もあった。
40年に大河内局では農村集団自動電話474加入が一挙に開通し、また、身延山局の電報業務は37年に東京中央電報局の電報中継交換加入局となって機械化され、同時に下山局以南の、8郵便局を受け持つ集中局となった。なお、40年3月には電話業務も大局を端局とする集中局となって、電報電話局実現の夢もいよいよ大きく前進した。
この頃電々公社でも町内に建設用地を求めており、町当局も積極的に協力し、特に佐野正企画管理室長があっせん担当として、ついに身延の一等地ともいうべき現在地約2810平方メートルの買収が確定した。この敷地確保の書類はぼう大なもので同氏の労苦は、今では関係者のみが知るところで、隠れた功績というべきであろう。
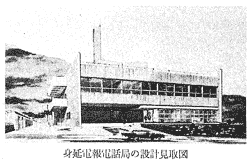 |
翌42年に入ると電々公社関係職員の身延入りもひんぱんになり、各郵便局との打合せもしばしば開かれた。各郵便局も大きく成長した電通業務を更に盛り上げ優秀な身延電報電話局誕生に最後の努力をつくした。豊岡局ではこの年3月14日、大河内局に続いて農村集団自動電話267加入の開通を見た。(農集電話の項参照)
下山郵便局では未開通申込者(積滞)70名の開通に従来から努力したが施設関係で解決に至らず、この年5月山梨電気通信部長より、この積滞解消には身延〜下山間に100回線増設を要するが経費がかかり過ぎ、自動改式開局には間に合わない旨の知らせがあった。時に農村集団自動電話300名の加入申込もあり、これと合せて是非とも開局時に開通されるよう、既設者組織の「下山電話組合」とともに、東京に、甲府にと陳情のお百度を踏んだ。その結果8月に可搬形交換機を下山地区に設置して救済することに決定したが、農村電話を一般単独と2共同申込にするよう勧めもあって、急遽これに切替えて明るい見通しに一同ほっとした。同一町内に2交換機は設置出来ない定めもあったが、新局は集中局との理由で特別扱いという温かい電々公社の配慮もあった。
身延山局区内にもドッと加入申込者が殺到した。そして5月町議鍋島良知を委員長とする「身延電話促進委員会」が発足したが、2共同加入を主とし、自動化開局と同時に開通を目標とするものであった。2共同262名、単独22名計284名が申込み、電々公社を大いにあわてさせた。部落別内訳は下の通りである。
清住町11、上町14、仲町12、橘町29、元町20、梅平73、塩沢28、波木井85、船原11、大野1
説明会や打合せ会が毎夜のように開かれ、自動改式同時開通を目指して大いに気勢をあげたが、電々公社では既に計画ずみであるとしてこれには大いに難色を示した。しかしながら全員の熱意と特に鍋島委員長をはじめ役員の奔走努力で、電々公社でも機械施設の変更に踏み切って明るい見通しをもたらした。9月頃には新築局舎も梅平地区にその威容を見せて、機械装備、地下ケーブル工事なども始まった。10月末には加入者に対し「05566−2−0000」と新電話番号決定通知が、鰍沢青柳電報電話局長から発送されて実現真近の感を深くした。
歳末、各郵便局には「電気通信施設改廃計画調書」が通達されて、深刻さを加え、職員の動揺も感ぜられたほどであった。計画調査の大要は次の通りである。
規一第3297号(42.11.29)別紙
電気通信施設改廃計画調書
| 局名 | 計画種目 | 電配事務 | 要 員 措 置 計 画 | 実施 予定 期日 |
||||||
| 定員関係 | 発生 過員 数 |
転出または 配転先局名 |
人員 | |||||||
| 合併局 | 被合併局 | |||||||||
| 現在 | 改正 | 増減 | ||||||||
| 身 延 山 (身延報話) |
直営 | 身延報話へ統合 | 34 | 3 | △31 | 31 |
身延報話局 甲府報話局 |
49 | 43.5 | |
| 身延 | 電配直営 | 19 | 18 | △1 | 1 | |||||
| 身延報話 | 下山 | 自集 | 身延報話、本建、飯富 郵便へ分割統合 |
16 | 12 | △4 | 4 | |||
| 大河内 | 自集 | 身延報話へ統合 | 20 | 13 | △7 | 7 | ||||
| 豊岡 | 自集 | 身延報話へ統合 | 5 | 1 | △4 | 4 | ||||
幸いなことは、身延電報電話局が集中局で有人局であるために、郵便局の過員職員がほとんど犠牲者を見ずに配置転換できる状態であったことで、関係郵便局長にとって大きな安堵であった。また、当初から憂慮されていた電報配達事務もすべて移管されることとなった。
翌43年2月、東京郵政局から各郵便局長あてに次のような通達がきた。
規一乙第四一号 昭和四十三年二月十四日
○○郵便局長殿
第二郵務部長
第二人事部長
上記について、さきに規一第三二九七号(四十二、十一、二十九)により通達した計画の実施予定期日は昭和四十三年五月二十六日(午前〇時)に決定したから了知されたい。
文中の通達文書は「改廃計画調書」のことである。この通達によって身延電報電話局の誕生日が確定したわけで、電々公社も郵便局もますます多忙となった。更に身延電報電話局準備室長、主幹(初代の局長、課長)が電々公社より発令されて、身延に赴任し連日連夜開局準備に専念した。○○郵便局長殿
第二郵務部長
第二人事部長
上記について、さきに規一第三二九七号(四十二、十一、二十九)により通達した計画の実施予定期日は昭和四十三年五月二十六日(午前〇時)に決定したから了知されたい。
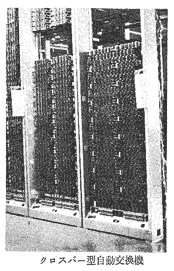 |
 |
5月26日午前0時、身延山・大河内・下山・豊岡郵便局の何十年来の電信電話業務も一瞬の中に切断されて、深い感慨と寂寥(せきりょう)の中に身延電報電話局が呱々(ここ)の声をあげたのである。ちなみに開局時の身延電報電話局の横顔を紹介する。
身延電報電話局
所在地 身延町梅平1602番地
敷地面積 2794.6平方メートル
局舎規模 鉄筋コンクリート造、3階建
建坪 1513平方メートル
収容施設 C460形クロスバー自動交換機(1400端子)
下山電話交換施設 C11×2 クロスバー自動交換機(480端子)
総工費 2億900万円
内訳 局舎 5,500万円
施設 1億5,400万円
改式時加入数、1,500加入
内訳 一般加入 750加入
農集加入 750加入
(継承電話加入数内訳、身延山局440、大河内局632、豊岡局312、下山局94)
局長 松尾辰五郎
庶務課長 小池寿巳
業務課長 鈴木忠太郎
施設課長 炭山英彦
なお、身延電報電話局は開局と同時に南部、富河、万沢郵便局の市外集中局となった。敷地面積 2794.6平方メートル
局舎規模 鉄筋コンクリート造、3階建
建坪 1513平方メートル
収容施設 C460形クロスバー自動交換機(1400端子)
下山電話交換施設 C11×2 クロスバー自動交換機(480端子)
総工費 2億900万円
内訳 局舎 5,500万円
施設 1億5,400万円
改式時加入数、1,500加入
内訳 一般加入 750加入
農集加入 750加入
(継承電話加入数内訳、身延山局440、大河内局632、豊岡局312、下山局94)
局長 松尾辰五郎
庶務課長 小池寿巳
業務課長 鈴木忠太郎
施設課長 炭山英彦
従来は鰍沢青柳電報電話局が親局であったが、新局開局により業務、施設全部を同局が受持ち、峡南地域の電通業務の殿堂が確立したのである。
開局前の身延山局、下山局に申込まれた多数の申込電話は残念ながら5月26日には開通とならなかった。たまたま電話設備料が改正され、従来1万円のものが単独3万円、2共同2万円となったが実施が5月13日となり事務上の関係で間に合わず、一時は関係者や申込者を戸惑いさせたが、いずれも6月までに全部開通した。
電報電話局開設の裏には政治的に活躍された鈴木強参議院議員、金丸信衆議院議員の名も忘れることはできない。金丸議員は郵政政務次官となったこともあり、常に陰の力となって推進に活躍した。電通出身の鈴木議員には特に多くの難題の陳情がなされたが、終始変らぬ努力でこれを解決した。42年12月3日に開かれた「電話組合関係者合同集会」には下記のような一括陳情がなされたのも同氏の偉大な手腕を物語るものであろう。
陳情事項は、①帯金・大島和田・豊岡三農集電話の統合について、②既設電話回線の増設について、③ブロック組合せ電話数の減少(3〜5個)について、④電話の増設について(帯金80個、大島和田20個)、⑤大崩部落への電話設置について、⑥旧身延地区(門外)単独及び二共同電話設置促進について、⑦北清子単独電話設置について、⑧身延電報電話局開局に際し、普通区域の大幅拡張について、⑨下山多数共同電話の設置促進について、
身延電報電話局は開局以来44年3月末までに電話新設720個、農集電話付加増設は帯金73個、大島43個を開通し、また大形赤ダルマ(公衆電話機)10個を主要個所に取付けた。年度末現在施設は、一般電話1,500個、農集電話850個であり職員総数71名となっている。今や身延電報電話局も近代化された通信施設と最良のサービス提供に努力しており、南部局の農集電話751加入の開通、続いて富河局、万沢局の農集電話も800加入が開通間近いとのことで、この方面のダイヤル自動化も近い将来である。
科学技術のめざましい進歩の中に、社会経済の発展、国民生活の向上に寄与する電通業務として今後身延町の興隆発展に大きく貢献することは間違いないであろう。

