第五節 激増する交通事故とその対策
一、交通事故発生と原因の探究
南部署管内の主要道路の幅員は7.2メートル以下の狭隘道路であり、長距離輸送および砂利等を運搬する大型ダンプカーの運行が激しく、狭い道路での追い越し等も無理を生じこれに加えて小中学校児童生徒のほとんどが国道を横断しての登下校であり、更に市街地化した商店街においては青空駐車が列をなし、狭い道路を更に狭くし、この管内に発生する事故の大部分はこのようなことに起因している。 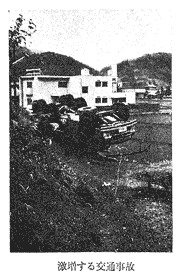 |
交通事故発生状況
| 内 訳 |
件 名 |
人身物 体の別 |
発生場所 | 死傷者 | 内訳 | 損害額 | ||||||||||||
| 町 別 | 道路別 | |||||||||||||||||
| 人身事故 | 物体事故 | 身延町 | 南部町 | 富沢町 | 国道 | 県道 | 町道 | その他 | 死者 | 負傷者 | 幼児 | 小学校 | 中学校 | 高校生 | 一般 | |||
| 件 数 | 102 | 63 | 39 | 53 | 26 | 23 | 71 | 24 | 4 | 3 | 4 | 82 | 2 | 2 | 4 | 4 | 74 | 5,136,000 |
| % | 62 | 38 | 52 | 25 | 23 | 69 | 24 | 4 | 3 | 8 | 92 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 86 | ||
| 事故運転者居住調 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||
| 管内 | 管外 | 事故原因別 | 事故車種別 | ||||||||||||||||||||||
| 身 延 町 |
南 部 町 |
富 沢 町 |
計 | 県 内 |
県 外 |
計 | 運 転 者 の 身 体 原 因 |
歩 行 者 自 転 車 介 入 |
徐 行 違 反 |
安 全 運 転 義 務 違 反 |
前 方 不 注 意 |
速 度 の 出 し す ぎ |
い ね む り |
追 越 し 不 適 当 |
無 免 許 |
め い て い |
そ の 他 |
大 型 貨 物 |
大 型 |
普 通 貨 物 |
普 通 業 務 用 |
軽 | 原 付 1 種 |
自 動 3 輪 |
そ の 他 |
| 24 | 17 | 11 | 52 | 14 | 36 | 50 | 90 | 12 | 3 | 30 | 13 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 25 | 42 | 1 | 14 | 24 | 4 | 12 | 5 | |
| 24 | 17 | 11 | 51 | 14 | 25 | 49 | 88 | 12 | 3 | 28 | 13 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 25 | 41 | 1 | 14 | 23 | 4 | 12 | 5 | |
時間関係
| 時 間 |
0-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 計 |
| 件数 | 4 | 13 | 11 | 9 | 18 | 11 | 10 | 15 | 6 | 5 | 102 |
| % | 4 | 13 | 11 | 9 | 17 | 11 | 10 | 14 | 6 | 5 | 100 |
場所関係
| 場 所 |
市街地 | 非市街地 | 総合計 | 合計 | |||||||||||||
|
交叉点
|
曲線
|
直線
|
踏切
|
合計
|
比率
|
交叉点
|
曲線
|
直線
|
踏切
|
合計
|
比率
|
交叉点
|
曲線
|
直線
|
踏切
|
||
| 件数 | 9 | 8 | 23 | 0 | 40 | 6 | 20 | 30 | 1 | 57 | 59 | 15 | 28 | 53 | 1 | 102 | |
| % | 22.5 | 20 | 57.5 | 0 | 100 | 41 | 10 | 35 | 53 | 2 | 100 | 15 | 27 | 57 | 1 | 100 | |
交通事故発生状況
|
月別
年度別 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 比率 |
| 40 | 8 | 6 | 20 | 12 | 10 | 15 | 13 | 13 | 7 | 8 | 10 | 14 | 136 | |
| 41 | 15 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 11 | 17 | 8 | 12 | 11 | 102 | 75% (前年比) |
二、本町における交通事故対策
交通事故を絶滅して明るい住みよい町をつくるために、昭和37年6月29日身延町議会は、県内他町村に先がけ、身延町を「交通安全の町」にすることを下記のように宣言した。交通安全宣言
最近における自動車などの交通機関の異常な発達とともに、交通災害もまた加速度的に増加し今や人間生活の新たな脅威となり、交通事故の防止は国民運動として盛りあがろうとしている。
身延町は南部町とともに静岡県に接近し、静岡県とは富士川に沿って南北に縦貫する国鉄富士身延線と、一級国道五十二号線(清水市韮崎回り甲府市)によって主たる交通が行なわれているが、身延町内には日蓮宗総本山である身延山久遠寺があり、なお木材などの林産業が盛んで、このため身延山への参詣客や、木材等の自動車による輸送が国道に集中される関係から、近年急に国道における交通が激増し、これに比例してその道路環境等から交通事故も多発地区となり、道路交通に不安と恐怖の影が絶えずつきまとっていることはまことに遺憾(かん)である。しかし、この国道は山静両県を結ぶ唯一の道路であり、輸送には重要な幹線である関係から、この道路を有効且つ安全に活用することが必要であるとも考える。
身延町は南部町とともに静岡県に接近し、静岡県とは富士川に沿って南北に縦貫する国鉄富士身延線と、一級国道五十二号線(清水市韮崎回り甲府市)によって主たる交通が行なわれているが、身延町内には日蓮宗総本山である身延山久遠寺があり、なお木材などの林産業が盛んで、このため身延山への参詣客や、木材等の自動車による輸送が国道に集中される関係から、近年急に国道における交通が激増し、これに比例してその道路環境等から交通事故も多発地区となり、道路交通に不安と恐怖の影が絶えずつきまとっていることはまことに遺憾(かん)である。しかし、この国道は山静両県を結ぶ唯一の道路であり、輸送には重要な幹線である関係から、この道路を有効且つ安全に活用することが必要であるとも考える。
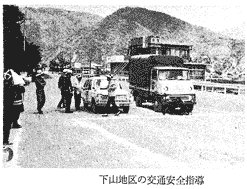 |
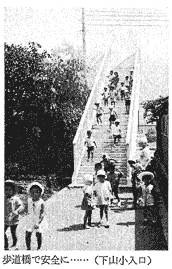 |
思うに交通事故の防止は、基本的には自動車の運行需要と道路の許容量の均衡をはかるとともに、交通秩序を維持することにあることは申すまでもないが、頻(ひん)発する交通事故の大半は人的原因によるものであり、したがって人間の努力によってこの災害を未然に防ぐことができるものであるが、従来のように、警察機関等の一部の機関や団体の事故防止活動のみでは、最近の交通事故の激増および交通事情からして事故を防止し、交通安全とその円滑化をはかることは、困難な情勢に立ち至っていることが明瞭である。したがって、われわれ身延町民も自らの手で交通の不安から自分自身を守り、交通の安全を取締まり機関にのみ委ねることなく、進んでこれに協力し自他ともどもの生命を尊びいとおしむ精神を基調として、互いに交通道徳を守り交通安全の知識を身につけ、悲惨な交通事故の絶滅を期するよう力を合わせるべきである。よって身延町議会はここに全町民がこの地域社会の暖かい愛情をもって心を一つにして、絶えず安全交通確保の町ぐるみ運動を強力に進め、もって交通事故を絶滅し明るい住みよい町をつくるため、身延町を「交通安全の町」とすることを宣言する。
昭和三十七年六月二十九日
昭和三十七年六月二十九日
身延町
しかし41年度中における南部署管内事故発生状況を見るに、102件の半数53件が本町において発生しているので事故防止については万全を期し、次のような対策がとられている。(一)交通取締まりの強化
交通量の激増と現在の道路状況では、取締まりを強化して事故防止にあたることが急務と認められるので、南部署は独自の計画取締まりの外、外勤々務員による常時取締まりを強化して事故防止に当たっている。(二)指導、教育の徹底
警察署は関係機関団体と緊密な連絡のもとに、雇用者、運転者、幼稚園、保育園、各小中高校およびその他一般民衆に対して講習会、座談会、交通安全教室等の開設による指導教育をして事故防止にあたっている。(三)安全施設の整備
危険箇所にカーブミラー、ガードレール、危険標示柱、横断歩道、横断旗等各種の施設を整備し、また学童、園児の通路の設定をして事故防止にあたっている。  |
(四)交通規制の実施
速度制限・追越禁止区域・学童横断歩道・駐車禁止区域等の設定に加え、歩道橋の架設、歩道設定の促進などによって事故防止の万全を期している。(五)住民の協力
交通事故防止は、地域住民の総ぐるみ体制が必要であるので既存の交通安全協会、運転者会、学校安全会自治班等の強化をはかるとともに、交通安全母の会、その他職域運転者会の結成、町内会へ交通安全の部落設定等により、各団体員内部からの事故防止に対する意識の高揚をはかり、事故防止対策の一環としている。(六)交通災害共済制度の発足
交通災害の激増という状況の中で、昭和41年に埼玉県川口市が独自にはじめた自治体の交通共済制度はたちまち全国にひろまった。住民がわずかな掛金(1日1円ていど)を出しあって、交通事故による死傷の場合、すみやかに見舞金がおくられるというアイデアは、既成保険・共済制度にない便利さが好評をよんで、市町村単位、さらに全県単位で実施するところが多くなった。山梨県においても、昭和43年より県町村会が主体となって全県的な規模でこの制度を実施しようという計画がなされ、昭和44年10月1日より、県下57町村で「山梨県町村交通災害共済組合」を設立、いわゆる〝1日1円交通共済〝を発足させることになったのである。
本町においても、9月4日の臨時町議会でこの共済組合への加入を議決、ただちに町民にたいする主旨の説明と徹底、区長を通じての加入奨励にのり出した。11月30日現在の加入申込者数は、3,817名(加入率30.53パーセント)である。
制度の概要
| (加入資格) | 県下の町村に住所を有する者で、住民登録または外人登録のすんでいる人。 | |
| (共済掛金) | 1人年額365円 | |
| (共済期間) | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
| (災害見舞金) | 死亡の場合50万円 傷害の場合10万円(全治6月以上) 5万円(全治3月以上6月未満)
3万円(全治2月以上3月未満)
2万円(全治1月以上2月未満)
1万円(全治2週間以上1月未満)
5千円(全治1週間以上2週間未満)
|
|
| (対象災害) | 電車、モノレール、トロリーバス、自動車、航空機、船舶、原動機付自転車、農耕用テイラー等の交通により受けた災害(死亡・傷害など) | |
| (請求期間) | 災害を受けた日から5年以内 | |
| (見舞金の請求) | 請求書に組合員証、警察署長の事故証明・診断書(死亡のときは検案書・戸籍謄本)をそえて町役場へ提出する。 |

