第二章 消防
新しい消防団の運営は、戦後町村自治の基本に立脚した消防組織法(昭和22年12月23日法律第226号)および消防法(昭和23年7月24日法律第186号)が制定公布され、明治以来長い間警察の指揮監督下に置かれていた消防は、組織法第24条の「消防及び警察は、国民の生命、身体及び財産の保護のために相互に協力しなければならない」の条文を残して警察から独立し、消防の責任及び権限のすべてが市町村に委譲された時から始まる。消防組織法の第1条には「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害に因る被害を軽減することをもって、その任務とする」と消防の目的及び任務が明示され、更に同法第6条に「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する」また同法第7条に「市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する」と規定され、又同法第8条に「市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない」とあり、ここに消防の維持管理運営の全責任は、当該市町村が負わなければならない事となり、旧来の古いしきたりや伝統から脱皮し、近代消防へと発展して来たのである。
消防法はその第1条に「この法律は火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあり消防本来の目的として、火災の未然防止とその鎮圧、火災や地震等の被害の軽減をその責務とする消防活動の基本理念を明示して、第1章総則(第1条−第2条)、第2章火災の予防(第3条−第9条)、第3章危険物(第10条−第16条の6)、第4章消火の設備(第17条−第21条)、第5章火災の警戒(第22条−第23条)、第6章消火の活動(第24条−第30条)、第7章火災の調査(第31条−第35条の3)、第8章雑則(第36条−第37条)、第9章罰則(第38条−第46条)、付則(第47条−第48条)の9章48ヵ条にわたり消防活動の基本的活動事項を定めている。
この消防組織法と消防法及び水防法(昭和24年6月4日法律第193号)のいわゆる消防三法制定公布により、市町村における消防の組織並びに施設の整備充実強化が着々となされ、近代的機械化消防団建設へとたくましい前進が続けられて来た。
第二次世界大戦の終結による敗戦の痛手の中にあって、戦後いち早く制定公布を見たこの消防三法により、占領軍治下における唯一の認められた自衛団体としての消防団の活動は、戦後の極度の荒廃と混乱した世相の中で、一糸乱れぬ統制を堅持しながら地域住民の安寧秩序を守り、水火災の防圧に身をもって挺身(ていしん)し、祖国復興に大きな役割を果たしたのである。
昭和30年2月11日、一町三ヵ村合併による新町の発足に伴い、各種団体の統一に率先して団の再編成を行ない、「身延町消防団」として近代的自治消防の建設に努力し、機械器具の整備充実に、規律訓練の徹底強化に、消火防犯思想の普及宣伝に、輝やかしい成果をおさめて今日に至ったのであるが以下今日まで本町消防の発達と沿革のあとをたどってみることとする。
第一節 消防の沿革
一、消防三法とその意義について
敗戦による極度の荒廃と混乱の中から新しい日本の再建が始まり、新憲法の施行に伴う国内諸制度の一新に即応して、消防についても法律的に飛躍的な改正が行なわれ、自治消防が確立されてきた。昭和22年5月・勅令第1180号で消防団令、同年12月には消防組織法が制定され、23年3月、警察法とならんで施行され、消防は長い伝統から脱却して警察から分離独立、官設消防は全面的市に町村に委譲され、根本的な大改革を遂げることとなったのである。そこで毎年3月7日を全国一斉に消防記念日と定め、火災予防運動を実施し、大々的に記念行事をすることとなった。
昭和23年7月には消防法が成立、8月1日から施行されることとなり、従来の消火一点張りの消防行政機関として予防、警戒等の措置はもちろん、火災現場における執行権、火災調査権などを付与され、消防組織法とともに、消防の二大法典として、組織・運営・活動面が法律によって定められ、その面目を一新、新しい時代に即応する消防として発展の道が開かれることとなった。
新消防制度の確立により、県においてもその事務一切を警察部より総務部に引き継ぎ、警察署で担任していた事項は地方事務所において行なうこととしたが、県はあくまでも助長行政的な面の指導を行なうのみであって、消防の組織並びに施設の整備充実強化はすべて自治体である市町村に委ねられた。
当時の旧身延・豊岡・大河内・下山等の町村においては、消防の画期的な制度の改革に伴い、いち早く消防団条例・消防団規則・消防委員会規程・火災予防条例、等々の制定を行ない、着々として行政面における整備を充実し、自治体消防の発達を図ってきた。
昭和28年7月、消防施設強化促進法(法律第87号)が制定され、その第1条に「この法律は、市町村の消防の用に供する施設の強化を促進し、もって社会公共の福祉を増進することに寄与することを目的とする」とあり、消防施設の強化に対する地方自治体の財政的困難を補うために、消防施設の整備・機械器具の購入等について、その費用の一部を国が補助することとなった。このため地方町村においても消防の機械器具の整備、防火施設の設置等が急速に行なわれ、本町においても消防団員の涙ぐましい努力と相俟(ま)って、消防の整備充実強化を行ない、急速に近代化消防へと発展してきたのである。
二、身延町消防団条例とその内容
昭和30年2月11日、旧身延・旧豊岡・旧大河内・旧下山の一町三ヵ村を合併して身延町として発足した本町は、長い歴史と伝統を持つ四ヵ村消防団の物心両面にわたる完全なる統一をはかるために、消防組織法と消防法とに準拠した関係条例・規則を制定公布し、本町消防団の指揮系統の確立をはかった。次に本町消防団条例の主なる条文を抜粋してみることとする。
身延町消防団条例(身延町条例第26号)
(通則)
第一条 消防団員(以下「団員」という)の定員・任免・給与・服務についてはこの条例に定めるところによる。
(定員)
第二条 団員の定数は七四〇人とする。
(任命)
第三条 消防団長及び副団長(以下団長および副団長という)は消防団の推薦に基き町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より町長の承認を得てこれを任命する。
一、本町に居住する志操堅固、身体強健の男子であって年齢十八年以上四十五年未満であること。
但し団長・副団長・正副分団長等にして特に必要がある時はこの限りでない。
但し団長・副団長・正副分団長等にして特に必要がある時はこの限りでない。
二、団長の場合は志操堅固・身体強健であって団長たるに足るものとして消防団より推薦された者である事。
(服務規律)
第七条 団員は団長の招集によって出動し、服務するものとする。召集をうけない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知った時は、予め指定するところに従い直に出動し、服務に就かなければならない。出動した団員が解散する場合は人員及び器械器具につき団長の点検を受けなければならない。
第八条 団員は予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
(給与)
第十二条 団員には次の手当を支給する。
出動手当、一回一〇〇円(現場において事務に従事した者に支給する)
技術手当、月額五〇円 被服手当 年額二〇〇円 その他臨時必要と認めたもの
出動手当、一回一〇〇円(現場において事務に従事した者に支給する)
技術手当、月額五〇円 被服手当 年額二〇〇円 その他臨時必要と認めたもの
二、前項の手当の給与額は右の基準により毎年予算の範囲内でこれを定める。
第十三条 消防組織法第十五条の四の規定に基く、消防団員の公務災害補償は山梨県町村消防団員公務災害補償組合に加入し、山梨県消防団員公務災害補償条例に定める補償を以ってこれに充てる。
以上通則・定数・任命・退職・懲戒・服務規律・給与等13条、付則2条によって成り立ち、全文15条に及んでいる。次に本町消防団規則の主なる条文を抜粋してみよう。
身延町消防団規則(身延町規則第2号)
(団の設置)
(団の設置)
第二条 消防団に団長・副団長・正副分団長・部長・副部長及びその他の団員を置く。団長は団の業務を統轄し、団員を指揮して法令・条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対しその責に任ずる。
正副分団長・部長及び副部長等の役員は団員の中から団長がこれを命免する。
正副分団長・部長及び副部長等の役員は団員の中から団長がこれを命免する。
第三条 団長事故あるときは副団長が、団長及び副団長とも事故あるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行なう。但しこの場合、団長が死亡、罷免退職又は心身の故障によってその職務を行なうことのできない場合を除いては正副分団長・部長及び副部長の命免を行なうことはできない。
第四条 団長・副団長・正副分団長の任期は二ヵ年とし、部長副部長の任期は一ヵ年とす。但し重任は妨げない。
(消火及び水防等の活動)
(消火及び水防等の活動)
第十条 水害その他の災害に現場に到着した消防団は設備、機械、器具及び資材を最高に活用して生命身体及び財産の保護に当り損害を最少限度に止めて、水火災の防禦および鎮圧に努めなければならない。
第十一条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は次に揚げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
一、消防団長指揮の下に行動しなければならない。(消防団長は町長所轄の下に行動しなければならない。)
二、消防作業は真摯(し)に行なわなければならない。
三、放水口数は最大限度に消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害を最少限度に止めなければならない。
四、分団は相互に連絡協調しなければならない。
五、服務中に功を争い又は持ち場を離れるようなことがあってはならない。
第十二条 水火災その他の災害場において死体を発見したときは、責任者は町長に速かに報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(別表)
| 分団名 | 区(大字)域 | 備考 |
| 下山分団 | 下山・粟倉 | |
| 身延分団 | 身延・梅平・波木井・大野 | |
| 豊岡分団 | 小田船原・門野・大城・相又・清子・光子沢・横根中 | |
| 大河内分団 | 上八木沢・下八木沢・帯金・大垈・椿草里・丸滝・角打・大崩・和田・大島 |
(教養及び訓練)
第十六条 団長は団員の品位の陶冶(や)及び実地に役立つ技能の錬磨に努め定期的にこれが訓練を行なわなければならない。
第五条 別表による各分団の区域は次表の通り。(前掲)
下山分団
(一部)下山(二部)下山(三部)粟倉
身延分団
(一部)身延(二部)波木井(三部)身延(四部)大野(五部)梅平
豊岡分団
(一部)清子(二部)横根中・光子沢(三部)相又(四部)小田船原(五部)門野・大城
大河内分団
(一部)上八木沢・下八木沢(二部)帯金(三部)大垈・椿草里・大崩・塩之沢
(四部)角打(五部)和田・樋之上(六部)大島(七部)丸滝
旧一町三ヵ村の消防団をそれぞれ四箇分団とし、その責任区域を別表に定め、以下団の設置・宣誓・水火災その他の災害出動・消火及び水防等の活動・文書簿冊・設備資材・教養及び訓練・表彰・制服等全文23条にわたり、消防団員の火災及び水防等の活動の基本的事項を定めてある。(一部)下山(二部)下山(三部)粟倉
身延分団
(一部)身延(二部)波木井(三部)身延(四部)大野(五部)梅平
豊岡分団
(一部)清子(二部)横根中・光子沢(三部)相又(四部)小田船原(五部)門野・大城
大河内分団
(一部)上八木沢・下八木沢(二部)帯金(三部)大垈・椿草里・大崩・塩之沢
(四部)角打(五部)和田・樋之上(六部)大島(七部)丸滝
かくして町村合併と相呼応して新発足した身延町消防団は、町村自治の基本線にそって自治消防の態勢を確立、近代的消防団としてますますその組織を強め、消防本来の防火・防災の業務に挺身し、逐年発展してきたのである。
三、消防委員会制度について
戦時下警防団令(昭和14年勅令第20号)に依って統制されていた消防団も、消防団令(昭和22年4月勅令第185号)の発令公布により、防空等の任務が除かれ、消防本来の使命遂行のため、幾多の改善がなされたのである。以下消防団令の主なる条文を抜粋して、当時の改正のあとを回顧して見ることとする。消防団令(昭和22年4月30日勅令185号)抜粋
第一条 消防団は郷土愛護の精神をもって社会の災厄を防止することを目的とし水火災の予防警戒及び防圧、水火災の際の救護並びに其の他の非常災害等の場合における警戒及び救護に従事するものとする。
第四条 消防団は消防団員を以ってこれを組織する。消防団員は市町村長がこれを命免する。消防団員は当該市町村の住民の中から消防委員会の推薦した者をこれに命じなければならない。
第八条 市町村は消防委員会を設置しなければならない。但し特別の事情のある市町村においては条例で其の区域を分けて各区域につき消防委員会を設置することができる。消防委員会は市町村長消防団長所轄消防署長及び所轄警察署長並びに市町村会議員及び学識経験のあるもの若干人をもってこれを組織する。消防委員会は消防団に関する重要事項について関係行政庁の諮問があったときはこれに意見を答申しなければならない。消防委員は前項の事項について関係行政庁に建議することができる。消防委員会は市町村長の求めに応じこれに消防団員たるべき者を推薦しなければならない。この勅令に定めるものの外消防委員会に関し必要な事項は市町村が条例でこれを定める。
第九条 消防団は警察部長又は警察署長の所轄の下に行動するものとする。
第十条 消防団は警察部長又は警察署長の命令があるときはその区域外においても第一条の業務に従事しなければならない。
(旧身延町消防団例規より、以下略)
全文20条にわたる本法の公布により、従来の警防団令は廃止され、逐次自治消防へと移行して行くのである。(旧身延町消防団例規より、以下略)
本法は消防組織法の施行になるまでの団令であり、いまだ全く旧来の官治統制から脱却したものではなかった。それは本法第9条第10条を見れば明らかであろう。
しかし本法施行により各市町村は第8条により、消防委員会を設置し、戦争によって大打撃を受けた消防団の組織再編成、機械器具等の内容整備に乗り出し、消防本来の意気と誇りの伝統を身につけた優秀な幾多の先輩の努力によって、着々とその充実強化が図られた。
昭和30年度(町村合併時)
大河内消防団指揮系統一覧表
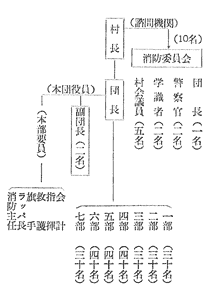 |
注(第4条による委員の構成を示す)
次に本町合併時における身延町消防委員会規程について主なる条文を抜粋することにする。身延町消防委員会規程(抜粋)
第一条 身延町消防団運営に関する諮問機関として身延町消防委員会を置く
第二条 委員会は左に掲げる事件につき調査審議する。
一、身延町消防団規則第十五条に規定する設備資材に関する事項
二、身延町消防団規則第十七条に規定する表彰に関する事項
三、身延町消防団条例第五条に規定する懲戒に関する事項
第三条 委員会は十人を以ってこれを組織する。
第四条 委員会は左に掲げる者の中から町長が委嘱する。
一、町会議員 五人
一、学識経験者 五人
前項の規程による委員のうち町議会議員については議会の議決でこれを指名し、学識経験あるものについては町長が委嘱する。
以上全文9条にわたって規程してあるが、町村合併にともなう消防団の統合等に依り、また消防組織法・消防法等の新法の趣旨徹底により、消防委員会の活動並びにその機能が充分発揮されないままに廃止された。第二条 委員会は左に掲げる事件につき調査審議する。
一、身延町消防団規則第十五条に規定する設備資材に関する事項
二、身延町消防団規則第十七条に規定する表彰に関する事項
三、身延町消防団条例第五条に規定する懲戒に関する事項
第三条 委員会は十人を以ってこれを組織する。
第四条 委員会は左に掲げる者の中から町長が委嘱する。
一、町会議員 五人
一、学識経験者 五人
前項の規程による委員のうち町議会議員については議会の議決でこれを指名し、学識経験あるものについては町長が委嘱する。
合併時における大河内村消防団指揮統一覧表を前頁に掲げたので参考とされたい。
四、本町消防の沿革
(一)明治以前
旧幕時代、定火消、大名火消及び町火消があり、定火消は慶安3年(1650)徳川三代将軍家光のとき、四千石以下の旗本を頭として置かれたのが、官設消防の始めとされている。大名火消は享保年間の創始で、大手方・桜田方・上野寛永寺等の要所を譜代大名が受持ち、外様大名はそれぞれの藩邸にこれを置き、火災発生時に備えた。享保3年(1718)いろは47組の町火消が創設され、江戸八百八町の消火活動を行なったのが、わが国自治消防の始まりであり、威勢のよいハッピ姿に象徴されている。本県の消防は今より309年前の万治3年(1660)甲府町火消制度の設定を発祥とするが、当地方には確たる組織的なものはなく、わずかに各部落に自衛的なものがあったに過ぎなかった。
(二)明治時代
明治維新による庶政の一新は、近代日本の黎明となり、消防も定火消、大名火消を廃して、町火消の自治消防組織だけを残すこととなった。明治5年(1872)江戸の華とうたわれた町火消のいろは組を廃し、消防業務を司法省警保局に属せしめ、同7年警視庁の創設に際し消防事務一切を管理させ、以来昭和22年12月消防組織法が制定公布されるまで、消防は警察の指揮監督下に置かれたのである。本県においては明治11年3月県令藤村紫朗により「消防組規則」が制定公布され、消防組近代化への第一歩がふみ出され、次いで明治27年(1894)2月10日勅令第15号に依る消防規則の公布により、甲府市はじめ十九ヵ村の消防組が認定設置された。これが本県最初の法的地位を持った公設消防であり、自主的な火消の制度から法的な裏付けを伴う指揮命令系統を持った消防の組織が生まれたのである。これにより、消防の技術も次第に発達し、破壊消防から冷却消防へと、近代的消火技術が漸次普及して行った。
明治28年(1895)には12ヵ村、29年には3ヵ村、39年に20ヵ村、40年には12ヵ村と年々増加し、明治45年(1912)には113組の消防組が設立され、消防組の充実強化が促進され、明治後半における本県消防の飛躍的発展のあとを窺(うかご)う事ができるのである。
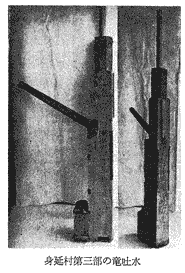 |
旧豊岡村においてはその沿革史を見るに「豊岡村警防団ハ想フニ昔若衆組ナル各称ノモトニ自治体ノ火災水難ノ衝ニ当リ之ガ防止ニ努メシガ明治二十八年山梨県告示第四号ニ拠リ器具ヲ設備セル私設消防組ニ始リ令三十五年五月県令第二十一号消防組規則ニ基キ之ガ設備の完成ヲ期シ云云」とあり、豊岡分団第三部(相又部落)に明治43年購入の腕用ポンプ1台が現存しているのを見ても、明治後半における本県消防の飛躍的発展と公設消防組の設置勧奨の機運に即応して、各旧村とも着々として近代消防への組織編成を行ない自衛的火消組から指揮命令系統を確立し、内容の整備充実、機材器具の設備等に鋭意その努力を結集しながら、破壊消防から冷却消防へと消防近代化への発展に多大の熱意を傾注した事が立証されるのである。
当時の峡南地方は狭隘(きょうあい)な山間に小部落が点在し、産業も少なく交通機関はわずかに富士川の水運に頼るのみの寒村が多かったのであるが、明治改元以来の隆々たる国運の隆昌と文明開化の時運を敏感に反応し、時勢の進展に遅れる事なく、県下でもいち早く消防近代化への道を開いたのは特筆すべきことである、
(三)大正・昭和および戦時体制下の消防
大正から昭和にかけては「消防山梨」の声価を高らしめた本県消防の黄金時代が訪れるのであるが、これは上述の幾多先輩が熱情を傾けて消防近代化への道を開いた豊かな精神的土壌の上に、自治消防の基本理念を開花させた本県消防の輝かしい成果であると言えるであろう。これはまた、本県の地勢峻険(しゅんけん)であって季節風強く、一度火災発生するや常に大火災を誘発し、また富士川の激流は毎年に大洪水をもたらし、峡南地方の山間僻地に点在する部落住民は絶えず水火災の危険にさらされて生活しなければならなかった風土の特殊性からも、郷土愛護のためには水火も辞せない勇猛心と旺盛な犠牲的精神とが自然の中に育(はぐく)まれて来た結果とも言える。更に消防組は地域住民の安寧秩序と生命身体財産を災害から防衛する一方、地方自治体の中堅団体として町村自治の振興に大きく寄与し、統制ある団体としてその存在を確固不動のものとし、地域住民に最も信頼さるべき団体としての印象を強く位置づけたことも、消防発展の大きな原動力となったのである。又消防の神様として全国にその名をはせた偉大な指導者小宮山清三(中巨摩郡池田村出身)により本県消防の進歩、改善、発達が促進され、逐次郡部に消防の整備強化が図られ、消防山梨の名を今に残していることも忘れてはならない。
このようにして消防組の内容は次第に強化され、大正4年(1915)8月30日山梨県令第35号山梨県知事添田敬一郎の名によって、消防組規則施行細則が制定された。
この細則は第一章通則により組織をはじめ機械器具及びポンプ置場、備付簿冊、演習に至るまで25条によって規定し、第二章命令及び服務は全文9条によって規定、第三章信号は二ヵ条、第四章消防線によって出火場所の保存等四ヵ条を規定、第五章給与は五ヵ条、第六章表彰及び懲戒は七ヵ条に規定、全条52条にわたりこまかいところまで規定してあり、当時の本県消防の全貌がうかがえる。なお付則を見るに「明治三十一年五月山梨県令ニ十一号消防組規則施行細則ハ之ヲ廃止ス本令施行前ニ設ケタル消防組ノ機械器具及被服等ニシテ本則ニ適合セサルモノハ大正六年十二月三十一日迄ニ本則ニ依リ改定スベシ但シ前項ノ期限満了ニ際機械器具及被服等改定シ難キ特別ノ事由アルトキハ其ノ事由ヲ詳具シ認可ヲ受ケ従来ノモノヲ使用スルコトヲ得」とあり急速に近代的消防への内容の整備強化と機械器具の充実、指揮命令の確立とが着々として図られて行ったことが立証されるのである。さらに大正6年(1917)には県下消防組の統一指導機関の設立の機運が高まり知事を総裁、警察部長を会長として正式に山梨消防協会が民間の後援団体として設立され、各地において消防の団体訓練等を指導し活発な運動を展開している。これは後日小宮山清三等の活躍によって全国的統一機関である大日本消防協会へと発展していくのである。
かくて大正年間に入り、旧大河内村、旧下山村、旧身延村、旧豊岡村の消防組も次第にその消防形体を確立した。
昭和年代に入るや、満州事変、支那事変など相次ぐ対外戦争の進展に伴い、消防組も機構・人員・機械等の整備充実に目ざましい発展をとげ、その活動は単に消火活動にとどまらず、社会奉仕に、水防施設の強化に、水利や道路整備にまで及んだ。
このようにして本県消防組は益々その内容形式を充実し、昭和8年(1933)には全県公設消防化の一大目標が打ち出され、昭和11年4月遂にこれを完了、山梨県下1市14町223ヵ村全部に公設消防組を設置し、その数238組、組員36,486人に達し、後援団体も青年後援隊65隊、隊員3,964人、女子消防隊19隊、隊員773人となり、名実ともに本県消防の黄金時代を迎えるのである。
また消火思想の普及は子供から家庭への合言葉とともに、各小学校に少年消防隊を組織、275隊、隊員23,491人に達する盛観を呈したと記録に残っている。
この頃より内外の時局はいよいよ急迫を告げ、支那事変は拡大の一途を辿り、遂に昭和14年(1939)4月1日消防団令が公布、ここに従来の消防組と防空の民間自治団体としての防護団とが合併して「警防団」と名称をかえ、戦時国策遂行の協力団体として、新たなる誕生を見たのである。
昭和14年勅令第20号を持って公布された警防団令の第一条には「警防団は防空・水・火、消防其の他の警防に従事するをもってその目的とする。」とあり、支那事変の拡大による内外の情勢は日に日に急迫を告げ、防空態勢の強化が要求され、戦時体制下の緊迫した情勢がひしひしと感じられるのである。
昭和17年2月、従来の各婦人会も大日本婦人会として統合され、好むと好まざるとにかかわらず戦時体制一色に塗りつぶされて行った。
昭和17年5月10日には大日本警防協会総裁梨本宮守正王来臨のもと、県下全警防団員を甲府に集結してその威力を示したことも、本県警防団史を飾る1ページである。
この御視閲に団員を引率して参加した本町関係者は、大河内村警防団長鈴木音次郎、下山村同山内椿房、身延町同望月源次郎、豊岡村同大沢幸房等であった。
しかし国運を賭して戦った第二次世界大戦は、わが国に未曽有の破壊と混乱を残して終戦となり、このきびしい戦中戦後を通じて郷土の安寧保持に身をもって挺身してきた消防団のみは辛くも解体を免(まぬ)がれ、戦後いち早く制定公布された消防関係法令の施行により、消防団は長い官治統制から脱して警察から独立、官設消防は全面的に市町村に移譲されることになり、ここに全く消防本来の業務に専念できることとなった。
思えば明治27年消防規則の公布を見てより73年間、長い伝統的組織形体を守り続けて来た消防も、新憲法の施行に伴う国内諸制度の一新に即応する民主的組織を確立、自治消防として新しく再出発し、地方自治体の発展とともに地域社会の中核的団体として一般住民の付託にこたえながら、消防近代化への限りない前進を続けることとなったのである。

