第二節 本町消防団の活動
一、各地区消防団の活動
(一)旧下山村消防団の沿革とその活動
旧下山村は往時下山千軒と称せられ、甲駿街道の中で最も殷賑(いんしん)を極めた宿場であり、古くから下山氏、穴山氏が居所を定めた所であり、火消制度もそれなりに自衛手段としてある程度組織立ったものがあったであろうと推測されるのであるが、遺憾ながら立証する記録なく、極(きわ)めて近代に至るまで制度上の点については記述することができない。明治以降になって、下山地区は度重なる風水害、大火災がしばしば起り、里謡にも「下山焼けた又焼けた。三度目にゃ、役場も焼けて気の毒」とあるように、火災の多い地区としても有名である。この事は他地区のように部落が点在せず、古くから河内路の重要拠点として、戦略的に又経済的に交通の要衝であり、ここに一大集落を形成し、人家が密集していたことにもよるのであり、その殷賑(いんしん)さを立証するよすがでもある。
主なる火災の記録としては、明治25年の大火がある。「下山村経済更生計画」(昭和12年)の下山村沿革によれば、罹火戸数245戸、半焼35戸とあり、役場も焼けて古文書及び書類悉く烏有に帰したとある。明治初年頃の下山村の戸数は、およそ440戸とあるから、6割を越える家屋が灰燼に帰したわけである。又昭和18年3月18日、大工町に発生した火災は、これ又風速20メートルの強風で忽ち竹下部落まで猛火の中に包み、焼失家屋50軒に達する大災害を引き起している。
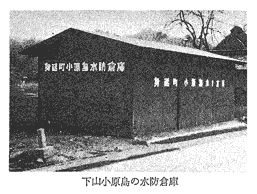 |
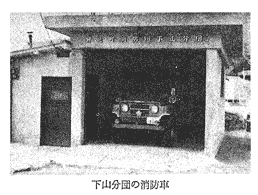 |
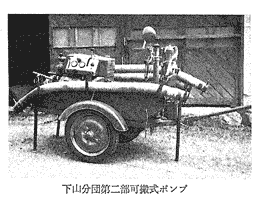 |
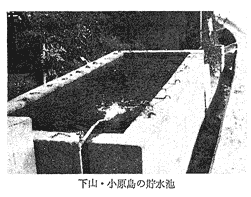 |
こうした下山地区の歴史的背景の中できびしい幾度かの試練を経て、ますます強固なる団結を保持しながら消防組の使命遂行に献身的努力を傾注して来た結果、優秀な消防人が輩出している。
次表に旧村当時の歴代団長の氏名を掲出する。
旧下山村消防団歴代組頭並団長
| 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
| 土橋守吉 | 消防組 | ||
| 望月亀次郎 | 明治42年 | 大正2年 | |
| 佐野寛 | 大正2年 | 〃 5年 | |
| 佐野慶蔵 | 〃 12年 | 〃 14年 | |
| 深沢豊祐 | 〃 14年 | 昭和4年 | |
| 望月� | 昭和4年 | 〃 6年 | |
| 遠藤忠治 | 〃 6年 | 〃 8年 | |
| 望月考一 | 〃 8年 | 〃 11年 | |
| 深沢英雄 | 〃 11年 | 〃 13年 | |
| 山内椿房 | 〃 13年 | 〃 19年 | 昭和14、4、1より警防団 |
| 望月栄 | 〃 19年 | 〃 22年 | |
| 佐野為雄 | 〃 22年 | 〃 23年 | 昭和22、5より消防団 |
| 近藤保 | 〃 23年 | 〃 24年 | |
| 古屋慶信 | 〃 24年 | 〃 25年 | |
| 石川剛 | 〃 25年 | 〃 27年 | |
| 望月定年 | 〃 27年 | 〃 28年 | |
| 羽賀竜王 | 〃 28年 | 〃 29年 | |
| 網野正一 | 〃 29年 | 〃 30年 | |
| 上平浅蔵 | 〃 30年 | 〃 30年 | 昭和30、2、11より身延町消防となる。 |

