(四)旧大河内消防団の沿革とその活動
旧大河内村は富士川東岸に位置し、南北四里にわたり細長い区域に点在する小部落を合せた村で、明治以前における消防の記録はほとんどうかがい知ることが出来ないが、おそらく他村と同様に各部落毎に自衛的手段によって火災水難の衝に当たってきたものと思われる。 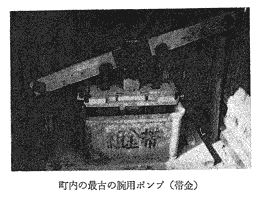 |
明治28年4月16日の村会議事録には次の如く記録されている。
「議長ハ郡長ヨリ諮問ニナリシ消防設置ノ件ヲ議スル旨ヲ宣告ス
第十一番議員曰く本村ノ如キ四里ノ間ニ点々散在シアリ最モ僻陬ノ村落ニ付消防組ノ組織ハ成立スルヲ得ザルニ付従来ノ慣例ニ依リ水火ノ消防ニ任ズル事ニナシタキ旨ヲ述ブ
別ニ異議ナキヲ以ッテ議長ハ十一番ノ説ニ賛成直ニ起立ニ問ウ起立満場
以上の議事録に見られる様に、当時時期尚早にして公設消防設置の件は否決されているが、明治39年3月25日、時の村長望月吾三郎により村議会に提案後に決定を見たのである。第十一番議員曰く本村ノ如キ四里ノ間ニ点々散在シアリ最モ僻陬ノ村落ニ付消防組ノ組織ハ成立スルヲ得ザルニ付従来ノ慣例ニ依リ水火ノ消防ニ任ズル事ニナシタキ旨ヲ述ブ
別ニ異議ナキヲ以ッテ議長ハ十一番ノ説ニ賛成直ニ起立ニ問ウ起立満場
下に当時の村会議事録を掲載する。
消防組ヲ左記方法ニ依リ設置セラレン事ヲ陳ブ
方法 本村ヲ六部ニ分チ上下八木沢ヲ第一部トシ帯金塩之沢区ヲ二部トシ大垈椿草里大崩ヲ第三部丸滝角打区ヲ四部トシ和田区ヲ五部トシ大島ヲ六部トシ各部ニ部長一名副部野一名小頭一名ヅツノ役員ヲ置キ而シテ之レヲ総轄スル組長一名ヲ置く事トシ組長ハ村会ニ於テ投票セラレン事部長以下ノ役員ハ各部ニ於テ選任スル事
決議
満場一致ヲ以テ設立スル事ニ可決確定シ然シテ組長ノ投票ヲ行ヒシニ左記ノ氏名当選ス
拾点 名取新作
午後八時閉会ス
上のごとくして明治年代において公設消防の設置を見ていることは、当時の村の指導者がいかに大きな期待を消防によせ、またいかに消防をよりよく理解していたかという証左であり、特筆するにたることであると思う。方法 本村ヲ六部ニ分チ上下八木沢ヲ第一部トシ帯金塩之沢区ヲ二部トシ大垈椿草里大崩ヲ第三部丸滝角打区ヲ四部トシ和田区ヲ五部トシ大島ヲ六部トシ各部ニ部長一名副部野一名小頭一名ヅツノ役員ヲ置キ而シテ之レヲ総轄スル組長一名ヲ置く事トシ組長ハ村会ニ於テ投票セラレン事部長以下ノ役員ハ各部ニ於テ選任スル事
決議
満場一致ヲ以テ設立スル事ニ可決確定シ然シテ組長ノ投票ヲ行ヒシニ左記ノ氏名当選ス
拾点 名取新作
午後八時閉会ス
以来鋭意消防の発展興隆に努力を傾注し、明治四十年代には第一部、第二部、第五部等で最新の腕用ポンプを購入、明治後半にはほとんどの部が機械器具の整備を完了したのである。
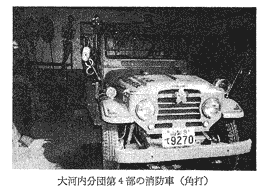 |
 |
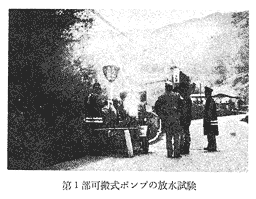 |
|
本消防組発展の跡を見るに、歴代団長の大多数が村長として村政にも縦横の才腕をふるっていることを見てもいかに優秀なる人材をその幹部に擁していたかがわかる。
昭和27年には、角打丸滝地区の人口増加に伴い、本村中央部における消防力の飛躍的増強をはかるため丸滝地区に新しく第七部を増設し、第四部より分離独立せしめ、昭和31年12月には最新鋭の手引ガソリンポンプを地元の協力により購入し配置したことは、大河内消防団の消防力強化に対する画期的な組織拡充であった。
明治の後半、隣接町村にさきがけて公設消防を設置して以来、富士川の激流とけわしい山間に挟まれて南北に細長く点在する部落の災害防衛については、常に厳しい指揮統制によって団の規律を守り、訓練と実践活動を通じて団員の士気を鼓舞し、長い伝統的精神によって培われてきた結果、消防人としての優秀な人材を数多く輩出している事も、消防団の輝かしい成果といえる。
次表に旧村当時の歴代団長の氏名を掲げる。
旧大河内村消防団歴代組頭並団長
| 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
| 名取新作 | 明治39年 | 消防団 | |
| 伊藤孝 | 〃 39年 | ||
| 小笠原博文 | 〃 43年 | ||
| 望月安則 | 大正4年 | 大正5年 | |
| 松野弥三郎 | 〃 5年 | 〃 6年 | |
| 片田栄三郎 | 〃 6年 | 〃 10年 | |
| 長谷川栄三郎 | 〃 10年 | 〃 12年 | |
| 佐野幸一 | 〃 12年 | 昭和3年 | |
| 市川政則 | 昭和3年 | 〃 6年 | |
| 佐野祥盛 | 〃 6年 | 〃 8年 | |
| 佐野武茂 | 〃 8年 | 〃 9年 | |
| 渡辺政則 | 〃 9年 | 〃 10年 | |
| 穴山睦治 | 〃 10年 | 〃 11年 | |
| 鈴木音次郎 | 〃 11年 | 〃 17年 | 昭和14.4.1より警防団 |
| 鈴木武重 | 〃 17年 | 〃 18年 | |
| 佐野幸一 | 〃 18年 | 〃 19年 | |
|
佐野
|
〃 20年 | 〃 22年 | |
| 佐野治郎 | 〃 22年 | 〃 24年 | 昭和22.5消防団 |
| 市川正美 | 〃 25年 | 〃 25年 | |
| 雨宮永伯 | 〃 26年 | 〃 27年 | |
| 千須和弘毅 | 〃 28年 | 〃 30年 | |
| 鈴木正巳 | 〃 30年 | 昭和30.2.11より身延町消防団となる |
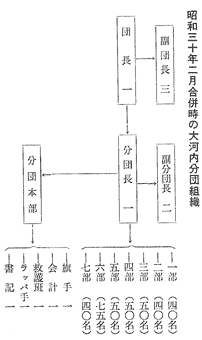 |
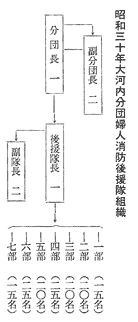 |

