(五)新身延町消防団の沿革とその活動
昭和30年2月11日、町村合併促進法によって、旧身延町・旧豊岡村・旧大河内村・旧下山村の一町三ヵ村が合併して新身延町が誕生したのであるが、消防団は他団体の統一に率先して、団の合併再編成を成しとげたのである。然しそれぞれ古い伝統としきたりを固持する各消防団の合併再編成については、並々ならぬ努力を要したのであり、左の決議事項を見てもそのあとが窺(うかが)い知られる。身延町各消防団長会議決議事項
一、新身延村発足と同時に旧四ヵ村の消防団を合して身延町消防団と称す。
一、旧四ヵ村の消防団をしてそれぞれ旧村村の名称を冠する分団と称す。
一、各団は町長職務執行者の専決処分に依り現在の正副団長をして分団長・副分団長となす。
一、身延町消防団長(一名)副団長(三名)の推薦任命は一応二月二十五日以降に延期す。
一、此の間非常災害発生の際は、村長職務執行者の代理として旧町村における一切の消防上の職務執行を支所長をして行はしむるものとす。
一、旧四ヵ村の消防に要する機具器材は向う五年内において之が整備完了を図る事。
一、防火貯水も順次整備充実を図る事。
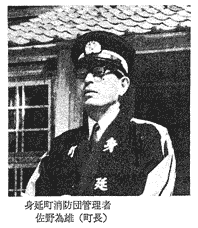 |
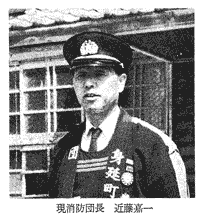 |
発足当時の団員総数は千名をこえ、その組織編成は次表の通りであった。
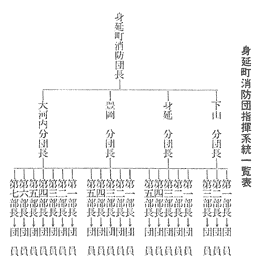 |
昭和30年2月11日 合併当時の身延町消防団現有ポンプ
種類別
分団名 |
自動車ポンプ | 手引動力ポンプ | 腕用ポンプ |
| 下山分団 | 2 | 7 | |
| 身延分団 | 1 | 3 | 7 |
| 豊岡分団 | 1 | 6 | |
| 大河内分団 | 1 | 8 | |
| 計 | 1 | 7 | 28 |
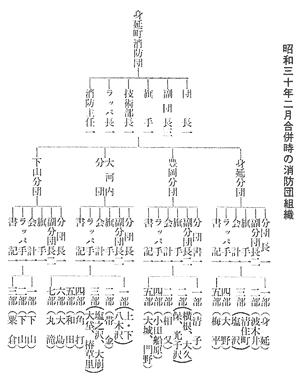 |
昭和33年には、火災現場にいち早く到達するためには消防に機動力を持たせることの急務なるを痛感し、時の機械部長川口久広等の尽力により下山分団に三輪自動車ポンプを配置し、消防力の飛躍的増強をはかった。
昭和37年4月1日、身延町条例第6号による身延町火災予防条例が公布され、火災の未然防止に対する予防消防の制度が確立された。
 |
 |
 |
 |
消防団員の公務災害補償に付いては特に万全の対策を立て、山梨県町村消防団員公務災害補償組合に加入し、消防団員全員の負担金を公費支弁して後顧の憂を除き、消防活動に安心して挺身できるよう、合併と同時に災害補償制度を確立し、今日に至っている。
更に昭和41年3月31日、条例第25号により「身延町消防賞じゅつ金条例」を公布し、消防業務に従事しその職務を遂行したことによって災害を受け、そのために死亡し、または不具廃疾になった場合においては、最高100万円までの賞じゅつ金を授与することを規定し、町自体としても消防団員の公務災害に付いては最善の措置を講ずることとしている。又昭和41年4月23日、規則第一号により「身延町賞じゅつ金審査会規則」を定め、本条例の適用についてもこまかい配慮を決めている。本条例の公布は、山梨県においては正に嚆矢であり、全国的に見ても当時他に一町を数えるのみであった。このことは本町が常に消防行政に意を用い、消防吏員および消防団員の活動に万全の配慮を講じ後顧の憂なからしめんとする意図の現われであり、地方行政のある一つの水準を示すものとして、高く評価すべき措置である。
賞じゅつ金支給については次の表による。
殉職者賞じゅつ金
| 功績の程度 | 金額(単位円) | |
| (イ) | 抜群の功労があり一般の模範となると認められる者 | 1,000,000 |
| (ロ) | 特に著しい功労があると認められる者 | 750,000 |
| (ハ) | 功労があると認められる者 | 500,000 |
不具廃疾者賞じゅつ金
| 不具廃疾の程度 | 功績の程度(単位円) | ||
| (イ)抜群の功労があり一般の模範となると認められる者 | (ロ)特に著しい功労があると認められる者 | (ハ)功労があると認められる者 | |
| 第1級 | 1,000,000 | 750,000 | 500,000 |
| 第2級 | 900,000 | 670,000 | 450,000 |
| 第3級 | 800,000 | 600,000 | 400,000 |
| 第4級 | 720,000 | 535,000 | 360,000 |
| 第5級 | 630,000 | 470,000 | 315,000 |
| 第6級 | 550,000 | 410,000 | 275,000 |
| 第7級 | 470,000 | 350,000 | 235,000 |
| 第8級 | 400,000 | 300,000 | 200,000 |
昭和39年6月30日、条例第18号により「身延町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例」が公布された。
次にその主なる条文を抜粋する。
身延町非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、消防組織法第十五条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第二条 退職報償金は、消防団員として十五年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
本条例公布により、非常勤の消防団員にも退職報償金が支給されることとなり、明治27年(1894)2月、消防規則の公布により初めてわが国に公設消防が設置されて以来の画期的制度が施行されたのである。この条例実施によって、比較的に報いられる事の少なかった消防団員にも、行政の温かい配慮が払われることとなった。更に昭和43年9月、本条例の一部を改正し、退職団員の待遇改善を図るための支給額が引上げられ、優遇措置を講ずることとなった。現行支給額は下記の通りである。
退職報償金支給額表
| 階級 | 勤 務 年 数 | ||
| 15年以上 20年未満 |
20年以上 25年未満 |
25年以上 | |
| 団長 | 55,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
| 副団長 | 50,000 | 65,000 | 75,000 |
| 分団長及び 副分団長 |
45,000 | 60,000 | 70,000 |
| 部長及び班長 | 40,000 | 55,000 | 65,000 |
| 団員 | 35,000 | 50,000 | 60,000 |
条例制定により支給した退職報償金は次のとおりである。
| 年度 | 人員 | 金額 |
| 昭、39 | 50 | 1,895,000円 |
| 昭、40 | 50 | 1,920,000 |
| 昭、41 | 46 | 1,855,000 |
| 昭、42 | 81 | 4,395,000 |
昭和40年10月10日、身延町消防団統合十周年記念式典が盛大に開催され、規律訓練ポンプ操法、婦人消防後援隊による救急法の訓練等を行ない、歴代の団長、副団長、婦人消防後援隊長への感謝状の贈呈、次いで人員、機械器具の検閲、分列行進を行ない、いよいよ整備され近代化する身延町消防団統合10年の姿を示した。次に身延町消防団10年の現有勢力を掲げる。
| (団員数) | ||||
| 本団 | 6名 | |||
| 豊岡分団 | 187名 | |||
| 大河内分団 | 272名 | |||
| 下山分団 | 162名 | |||
| 身延分団 | 272名 | |||
| 計 | 899名 | |||
| 婦人消防後援隊 | 650名 | |||
| (ポンプ) | ||||
| 豊岡分団 | 自動車ポンプ | 1台 | ||
| 小型動力ポンプ | 4台 | |||
| 大河内分団 | 自動車ポンプ | 1台 | ||
| 小型動力ポンプ | 3台 | |||
| 手引動力ポンプ | 5台 | |||
| 下山分団 | 三輪自動車ポンプ | 1台 | ||
| 小型動力ポンプ | 1台 | |||
| 手引動力ポンプ | 1台 | |||
| 身延分団 | 自動車ポンプ | 2台 | ||
| 小型動力ポンプ | 4台 | |||
| 手引動力ポンプ | 4台 |
最も困難視された定数削減がこれといった混乱と動揺を起すことなく、きわめて平穏に成しとげられたことは、本町の消防史の中でも高く評価されるべきことである。
 |
 |
身延町歴代消防団長
| 団長氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 | |||
| 佐野為雄 | 昭和30年4月1日 | 昭和30年12月31日 | 消防協会南部支部長歴任 | |||
| 田京駒男 | 昭和31年1月1日 | 昭和31年12月31日 | ||||
| 小山栄 | 昭和32年1月1日 | 昭和32年12月31日 | ||||
| 鈴木正巳 | 昭和33年1月1日 | 昭和33年12月31日 | 消防協会南部支部長歴任 | |||
| 網野正一 | 昭和34年1月1日 | 昭和34年12月31日 | ||||
| 大久保豊繁 | 昭和35年1月1日 | 昭和35年12月31日 | ||||
| 鴨狩富治 | 昭和36年1月1日 | 昭和36年12月31日 | ||||
| 平田一三 | 昭和37年1月1日 | 昭和37年12月31日 | ||||
| 上平浅蔵 | 昭和38年1月1日 | 昭和38年12月31日 | ||||
| 望月民部 | 昭和39年1月1日 | 昭和39年12月31日 | ||||
| 小林正雄 | 昭和40年1月1日 | 昭和40年12月31日 | ||||
| 熊谷儀信 | 昭和41年1月1日 | 昭和41年12月31日 | 消防協会南部支部長歴任 | |||
| 遠藤百治 | 昭和42年1月1日 | 昭和43年3月31日 | 消防協会南部支部長歴任 | |||
| 近藤嘉一 | 昭和43年4月1日 | 昭和45年3月31日 |
| 年度 | 副団長氏名 | |||||||
| 昭和30年 | 田京駒男 | 小山 栄 | 市川正美 | |||||
| 昭和31年 | 小山 栄 | 市川正美 | 上平浅蔵 | |||||
| 昭和32年 | 鈴木正巳 | 上平浅蔵 | 松野久男 | |||||
| 昭和33年 | 網野正一 | 望月利夫 | 松野久男 | |||||
| 昭和34年 | 大久保豊繁 | 鴨狩富治 | 佐野安太郎 | |||||
| 昭和35年 | 粟冠盛夫 | 平田一三 | 川村藤十郎 | 望月民部 | ||||
| 昭和36年 | 川村藤十郎 | 佐野逸平 | 志村国為 | 小笠原敏光 | ||||
| 昭和37年 | 遠藤百治 | 田中喜内 | 木内悦治 | 熊谷儀信 | ||||
| 昭和38年 | 望月忠常 | 池上 正 | 小林正雄 | 佐野大作 | ||||
| 昭和39年 | 遠藤宝作 | 近藤嘉一 | 遠藤善男 | 鈴木 孝 | ||||
| 昭和40年 | 土屋正六 | 佐野達夫 | 千頭和吉久 | 若林貴一 | ||||
| 昭和41年 | 望月照義 | 佐野初雄 | 遠藤 孝 | 遠藤 実 | ||||
| 昭和42年 | 遠藤琴吾 | 望月長夫 | 木内達明 | 久保忠良 | ||||
| 昭和43年 | 望月敏雄 | 藤田 正 | 望月鶴吉 | 滝川 新 | ||||
| 昭和44年 | 佐野淳司 | 若尾幹之助 | 長田利男 | 佐野重昌 | ||||
| 年度 | 下山分団長 | 身延分団長 | 豊岡分団長 | 大河内分団長 | ||||
| 昭和30年 | 上平浅蔵 | 鴨狩 広 | 鴨狩富治 | 鈴木正巳 | ||||
| 昭和31年 | 広島 勉 | 鴨狩 広 | 鴨狩富治 | 鈴木正巳 | ||||
| 昭和32年 | 広島 勉 | 一宮市松 | 望月利夫 | 佐野安太郎 | ||||
| 昭和33年 | 川村藤十郎 | 大久保豊繁 | 佐野正久 | 佐野安太部 | ||||
| 昭和34年 | 川村藤十郎 | 望月民部 | 粟冠盛夫 | 平田一三 | ||||
| 昭和35年 | 遠藤百治 | 佐野逸平 | 志村国為 | 小笠原敏光 | ||||
| 昭和36年 | 遠藤百治 | 田中喜内 | 木内悦治 | 熊谷儀信 | ||||
| 昭和37年 | 望月忠常 | 池上 正 | 小林正雄 | 佐野大作 | ||||
| 昭和38年 | 遠藤宝作 | 近藤嘉一 | 遠藤善男 | 鈴木 孝 | ||||
| 昭和39年 | 土屋正六 | 佐野達夫 | 千頭和吉久 | 若林貴一 | ||||
| 昭和40年 | 望月照義 | 佐野初雄 | 遠藤 孝 | 遠藤 実 | ||||
| 昭和41年 | 遠藤琴吾 | 望月長夫 | 木内達明 | 久保忠良 | ||||
| 昭和42年 | 望月敏雄 | 藤田 正 | 望月鶴吉 | 滝川 新 | ||||
| 昭和43年 | 佐野重昌 | 佐野淳司 | 若尾幹之助 | 長田利夫 | ||||
| 昭和44年 | 中村虎雄 | 岡本平八郎 | 市川 孟 | 佐野 静 |
身延町消防団 機械器具施設一覧表 昭和43年10月31日現在
| 分 団 名 |
部名 | 部員数 | ポンプ数 | 水利施設 | 夜警 詰所 |
水防 倉庫 |
火の見 | 管轄人口 | ||||||
| 自動車 | 三輪車 | 手引 動力 |
可搬 動力 |
腕用 | 消火栓 | 40m3 水槽 |
その他 水槽 |
|||||||
| 下 山 分 団 |
第1部 | 38 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1,107 | |||||
| 第2部 | 34 | 1 | 6 | 3 | 891 | |||||||||
| 第3部 | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 311 | |||||
| 身 延 分 団 |
第1部 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,845 | ||||||
| 第2部 | 43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,016 | ||||||||
| 第3部 | 28 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 231 | |||||||
| 第4部 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 977 | ||||||||
| 第5部 | 42 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 421 | |||||||
| 豊 岡 分 団 |
第1部 | 21 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 382 | ||||||
| 第2部 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 373 | |||||||
| 第3部 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 360 | |||||||
| 第4部 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 444 | ||||||||
| 第5部 | 34 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 485 | ||||||
|
大 |
第1部 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 269 | |||||||
| 第2部 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 377 | |||||||
| 第3部 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 510 | |||||||
| 第4部 | 35 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1,057 | |||||
| 第5部 | 21 | 1 | 1 | 4 | 6 | 499 | ||||||||
| 第6部 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 707 | ||||||
| 第7部 | 29 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 453 | ||||||
| 合計 | 20部 | 599名 | 6台 | 1台 | 5台 | 13台 | 71 | 22 | 72 | 20 | 6 | 52 | 12,695 | |

