(六)身延町消防団ラッパ隊とその活動
昭和30年4月、身延町消防団発足による組織編成に伴い、本団にラッパ隊長を置き、各分団にラッパ隊副隊長を置く。以来鋭意技術の錬磨に努め、昭和40年、昭和42年の両年にわたり、3月7日の消防記念祭に参加、県下消防団の先頭に立って甲府市内を行進した。
昭和43年5月、山梨県総合防災訓練に参加、同年11月23日、山梨県消防総合訓練大会に参加するなどその活躍ぶりはめざましいものがある。次表にラッパ隊の正副隊長名を掲げる
 |
| 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | ||
| 大野武雄 | 昭和30年4月1日 | 昭和43年3月31日 | ||
| 依田 勉 | 昭和43年4月1日 | 現 |
| 年度 | 下山分団 | 身延分団 | 豊岡分団 | 大河内分団 | ||||
| 自昭和三〇年 至昭和三六年 |
石川注樹 | 河内賢治 | 堀内勝英 | 依田 勉 | ||||
| 昭和四三年 | 堀内徹三 | 遠藤徳好 | 堀内勝英 | 片田 稔 |
二、消防協力団体
(一)婦人消防後援隊とその活動
消防に対する婦人団体の協力応援は、警防団当時より誠に多大なものがあり、戦後消防団に改組してからも更にその必要性が高まり、各団においても後援隊の組織化に積極的に熱意を注いだ結果、婦人団体の協力も具体化し、次第に後援隊の制度が確立されてきた。昭和30年2月、四ヵ町村の消防団が合併して身延町消防団として改組されるや、各分団毎に後援隊設置の機運が急速に高まり、各分団に正式に設置されることとなった。
婦人消防後援隊の活動目標は、一般家庭における火災の未然防止運動の普及徹底、厳重なる月例かまどの検査、水火災発生時の協力体制等、消防団の活動に積極的に協力応援するにあり、幾度かの水火災発生時における本町婦人後援隊の活動は、誠に目ざましいものがあった。
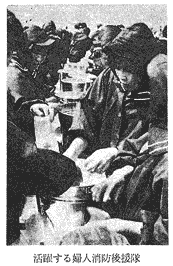 |
次に歴代隊長名を掲げる。
身延町歴代婦人消防後援隊長
| 年度 | 下山婦人消 防後援隊長 |
身延婦人消 防後援隊長 |
豊岡婦人消 防後援隊長 |
大河内婦人消 防後援隊長 |
||||
| 昭和30 | 石川春子 | 渡辺恵美子 | 星野とし | 伊藤まさじ | ||||
| 〃 31 | 望月七七江 | 大橋富士子 | 佐野いつ | 〃 | ||||
| 〃 32 | 望月善子 | 芦沢花代 | 佐野いゑ子 | 片田とよの | ||||
| 〃 33 | 深沢菊江 | 〃 | 〃 | 佐野道子 | ||||
| 〃 34 | 深沢小夜子 | 佐野八千代 | 鈴木秀子 | 市川延子 | ||||
| 〃 35 | 伯耆きく江 | 〃 | 佐野菊江 | 小林なみ | ||||
| 〃 36 | 望月幸江 | 中里智恵子 | 小林あき | 鈴木もと子 | ||||
| 〃 37 | 望月ことじ | 望月まつ | 佐野久美子 | 雨宮若江 | ||||
| 〃 38 | 遠藤秋子 | 雨宮嘉悦子 | 小野まち代 | 鮎川ふさ江 | ||||
| 〃 39 | 向井ひろ | 斉藤花恵 | 遠藤文江 | 谷野今江 | ||||
| 〃 40 | 遠藤徳子 | 佐野良子 | 柿島きわの | 佐野君江 | ||||
| 〃 41 | 石坂節子 | 内藤はる代 | 遠藤喜代子 | 佐野たつ子 | ||||
| 〃 42 | 遠藤静枝 | 望月光子 | 鴨狩らく江 | 市川よしの | ||||
| 〃 43 | 山内みどり | 熊王千代江 | 市川梅子 | 滝川八千代 | ||||
| 〃 44 | 望月房子 | 稲葉ふで子 | 大沢迪子 | 浅原よしの |
(二)少年消防隊とその活動
昭和年代の初期、本県消防はその機構、人員、機械等形式内容ともに充実し、昭和8年全県公設化の目標が打ち出され、昭和11年4月全県下に公設消防組が設置された。この機運に乗って、防火思想の普及はまず子供から家庭へとのねらいをもって、各小学校、各地域に少年消防隊が結成組織され、防火思想の普及徹底がはかられた。
本町においても、昭和7年身延少年消防隊の創立をはじめとして、昭和8年1月下山少年消防隊、昭和8年2月豊岡少年消防隊、大河内北部、大河内南部少年消防隊等の設立を見ている。
峡中日報発行「山梨消防現勢」昭和11年版に身延少年消防隊が紹介されているので、次にその全文を掲げ当時の活動状況を偲(しの)ぶこととする。
日蓮大聖人の霊域、身延山を有するその身延町は教育上に於ても峡南の中枢であり、其の教育も国家主義宗教の感化によって愛国的犠牲の熱血を以って鳴るのだ、其の現れの一として身延小学校の少年消防隊を見ることが出来る。校長を総裁に、高等二年受持の訓導を隊長として全職員の熱心指導の下に尋常六年と高等一、二年を以て組織せる此の消防隊は、昭和七年の創立以来、定められたる訓練要目に従って熱烈に之を実行し奉仕的活動に専念するは勿論、町内各戸のかまどの検査を行ない、町消防と共にその演習に出動する等々、訓練の熟達ぶりと秩序の整然たると行動の敏活さとに於て、大人の消防も常に驚嘆する程の実績を示し、尊王愛国の大精神に出発せる挺身奉仕の実は躍々として表明され、以て模範少年消防隊と謳(うた)はれている。
戦後、消防組織法、消防法等の公布により、消防はその本来の使命達成に向って消防近代化への歩みを進めることとなったのであるが、昭和25年12月、少年時代から火災予防の知識を培うため、国家消防庁から「少年消防クラブ」の育成について指示が出され、それに基づいて本県においては、県と県教育委員会が協力、極力組織の指導に努めた結果、全県的に普及組織されたが、本町では、各小学校においてしばしば防火訓練等を実施し、火災時における避難訓練、救護訓練等を行ない、防火思想の普及に努めている。また冬季の火災多発時においては、部落毎に各戸を巡り、就寝前のひとときを「火の用心、火の元に注意」等火の元の見まわり等について家々の注意をうながして回ったことも、少年消防隊員活動の想い出である。公設消防の整備化された現在では、これらの活動はすべて見られなくなり、少年消防隊の組織もなくなったが、学校等においては自主的な立場において、避難救護等の訓練を時に応じて行なっている。

