第三節 火災と消防
本町の火災で記録に残る火災は、主として下山地区および身延門内地区に発生している。古来殷賑(いんしん)を誇った地区として人家が密集していたことにもよるが、火災発生に対する消火施設等ほとんど見るべきもののなかった時代のことで、気象等の悪条件下に発生した火災についてはどうすることもできなかったことが推測されるのである。
明治8年(1875)1月4日、わが国においては、始めて消防出初式が東京で行なわれた記念すべき日であるが、同年1月10日、身延山に大火災発生し、山内の七堂伽藍ことごとく烏有(うゆう)に帰した。
また明治20年(1887)3月4日午後2時仲町より出火した火災はおりからの強風にあおられて仲町、下町、上町の200戸の町家を焼き尽し、さらに仮三門と、この付近の寺院の多くも全焼した。明治8年の本山をはじめ数多く支院等を焼失した大火に続いて、身延山は致命的大打撃をうけたのである。
当時の身延山は、限られた行事の時以外は参詣客も少なく現代とは全く比較にならないものであったから、町民も本山で働く職人以外はほとんど他所へ働きに出るか、山仕事に入るという状態であったから、家に残っている婦女子だけでは到底この大火を防ぐことは不可能であったろうことが想像される。
この大火で家財を失って途方にくれ身延を離れて行くものもかなりあったといわれ、従ってその後の復旧は遅々として進まず、櫛の歯が抜けたようなさびしい門前町が何年も続いたという。三門も二十年後の明治四十年に至って漸く復興を見たのである。
と教報みのぶにある。この大火で家財を失って途方にくれ身延を離れて行くものもかなりあったといわれ、従ってその後の復旧は遅々として進まず、櫛の歯が抜けたようなさびしい門前町が何年も続いたという。三門も二十年後の明治四十年に至って漸く復興を見たのである。
明治25年(1892)の下山に発生した火災は、焼失家屋270戸と称され、今に至るも下山大火の悲話を伝えている。
近代に至っては昭和18年(1943)の下山大工町の大火(焼失家屋50戸)以来、本町の消防の施設設備の充実と、防火思想の普及徹底とにより、大火災の発生はほとんどなくなっている。
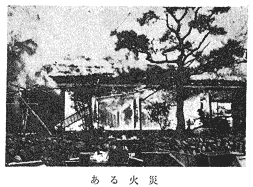 |
参考までに、明治以来の大火災を表1に掲載することにする。
表1 明治以来の大火災一覧表
| 部落名 | 火災の年月日 | 罹災世帯数 | 備考 |
| 身延山 | 明治8年1月10日 | 本堂、諸堂、142棟 町家 10戸 |
|
| 身延町門内 | 明治20年3月4日 | 200戸全焼 | |
| 身延町下町 | 明治25年2月28日 | 13戸全焼 | |
| 下山村 | 明治25年8月25日 | 280戸全焼 | |
| 大河内村角打 | 昭和4年4月19日 | 身延駅全焼 | |
| 豊岡村門野 | 昭和15年5月22日 | 15戸全焼 | |
| 身延町片隈 | 昭和16年2月3日 | 23戸全焼 | |
| 下山村 | 昭和18年3月18日 | 50戸全焼 | |
| 身延町梅平 | 昭和24年1月28日 | 身延小学校全焼 | 校社内より出火 |
昭和30年2月、四ヵ町村合併以来、消防の機械化、施設設備、内容の充実強化については前述した通りであり、防火思想の普及徹底と相まって大火災の発生はほとんど防止して来たのであるが、単独火災といえども年々損害額の増大していることは、地震・雷・火事・親父の言葉通り、火災の人的物的損害のどんなに恐しいものであるかを如実に物語っているのである。
参考までに、最近7年間の火災統計を表2に掲出することとする。
表2 最近7年間の火災統計
| 年度別 | 火災件数 | 焼失面積 (平方メートル) |
被害世帯 | 損害額 |
| 昭和37 | 3 | 266.10 | 3 | 1,778,000円 |
| 〃 38 | 4 | 684.00 | 4 | 4,150,000円 |
| 〃 39 | 4 | 285.80 | 7 | 6,083,000円 |
| 〃 40 | 4 | 344.54 | 4 | 7,500,000円 |
| 〃 41 | 5 | 316.65 | 6 | 6,008,000円 |
| 〃 42 | 2 | 306.00 | 2 | 10,840,000円 |
| 〃 43 | 2 | 2,522.00 | 2 | 34,058,000円 |

