四、身延町防災対策とその活動
昭和22年10月18日、法律第118号によって「災害救助法」が公布された。その第1条には
この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行ない、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
とあり、第1章総則、第2章救助、第3章費用、第4章罰則から成り、全文48条におよんでいる。本法の公布により、国が災害にかかった者の保護と救助に温い手を差し延べることとなり、不時の大災害を受けた者も、復興と再生への希望を持って力強く立ち上ることができるようになった。本町においても、昭和34年8月台風7号と昭和41年9月の台風26号の大災害には本法の適用を受け、被害者の救済に、荒廃した郷土の復旧に、めざましい活動を展開することができたのである。昭和36年11月15日、法律第223号によって「災害対策基本法」が公布され、災害に対する基本的行政が確立した。
その第1条(目的)に
この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧および防災に関する財政金融措置、その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
とある。国はまた、昭和35年に災害に対する国民の認識を深め、災害に対処する準備を固める目的をもって、毎年の9月1日を「防災の日」に定め、不時の災害にそなえる心がまえを養うこととしている。本町においても、これに呼応して、水防訓練を行ない、一朝有事の際にそなえることとしている。
こうして本町においては、昭和37年10月10日条例第29号により、身延町防災会議条例を制定公布して、防災のための措置を講ずることとしている。次にその概要を記述する。
身延町防災会議条例
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法第十六条第五項の規定に基づき、身延町防災会議(以下「防災会議」という)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一、身延町地域防災計画を作成し及びその実施を推進する。
二、身延町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
三、前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づき政令によりその権限に属する事務。
(会長及び委員)
第三条 (略)
(専門委員)
(専門委員)
第四条 (略)
(議事等)
(議事等)
第五条 (略)
等からなり、防災計画を作成実施することを定めている。更に昭和37年10月10日、条例第30号により、身延町災害対策本部条例を公布し、対策本部を組織している。
本条例の概要は下の通りである。
身延町災害対策本部条例
(目的)
本条例の概要は下の通りである。
身延町災害対策本部条例
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法第二十三条第六項の規定に基づき、身延町災害対策本部に関し必要な事項を定める事を目的とする。
(組織)
(組織)
第二条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部長は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
(部)
第三条 (略)
(雑則)
第四条 (略)
等からなり、災害対策本部の機構を定め、常時防災に対する体制の整備を行なっている。(雑則)
第四条 (略)
(1)身延町災害対策本部の編成
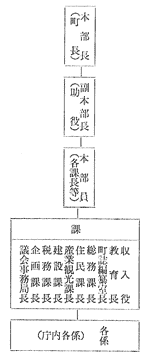 |
(2)警報の種類
| 区分 | 警報等の内容 | |
| 気象情報 | 台風その他の異常気象について、その状況や経過、見とおしを 具体的に速やかに地域住民に知らせるものである。 |
|
| 気 象 注 意 報 |
(水防関係) | 風雨、大雨、洪水、大雪等の注意報がある。 |
| (凍霜害関係) | 霜、異常低温等の注意報がある。 | |
| (火災関係) | 強風、異常乾燥注意報等の注意報がある。 | |
| 気象警報 | 暴風雨、暴風雪、大雨、洪水等の警報がある。 | |
(3)注意報、警報の基準(山梨県防災計画より)
| 注意報 | 警報 | 備考 | |
| 風速 | 夏…毎秒20m以上 冬…毎秒15m以上 |
毎秒20m以上 | 注意報で火災気象通報 |
| 雨量 | 日雨量が100m/m以上 | 日雨量が200m/m以上 | |
| 積雪 | 10㎝以上 | 30cm以上 | |
| 異常乾燥 | 実効湿度60%以下 最少湿度30%以下 最大風速毎秒10㎜ (すべて見込のとき) |
注意報で火災気象通報 |
(4)県庁内部の伝達系統(山梨県防災計画より)
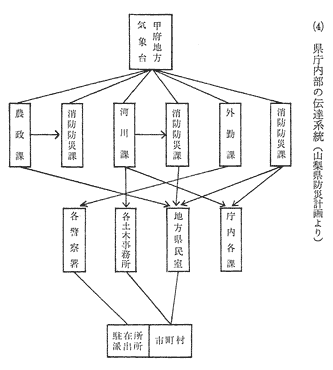 |
(5)配備の基準
| 種別 | 配備時期 | 配備の要領 | 配備人員 |
| 第1 配備 |
1.大雨、台風期に次の各注意報の1以上が県下に発表された時
①大雨注意報②風雨注意報 ③洪水注意報 2.その他本部長が指令した時
|
1.地方県民室、土木事務所よりの雨量水位等の情報を収集する。
|
1.各課の少数人員にて情報活動にあたる。
|
| 第2 配備 |
1.大雨、台風期に次の各警報の1以上が県下に発表された時
①大雨警報②暴風雨警報 ③洪水警報 2.その他本部長が指令した時
|
1.情報の収集を強化する。
2.各課長は逐次本部長に報告する。
|
1.本部員は本部に参集する。
2.配備につく職員の人数は各課長において増減する。
|
| 第3 配備 |
1.災害が発生
2.本部長が配備を指令した時
|
1.災害活動に全力を集中する
2.各課長は状況に応じ逐次本部長に報告する
|
1.所要人員全員をもって災害活動に全力を集中する。
|
| (注) | 災害の規模及び特性に応じこの基準によりがたいと認めたときは臨機応変の配備体制を整える。 |
なお、防災活動については、本町防災会議条例第5条の規定に基づいて、身延町防災会議運営要領を定め、あらかじめ万全の措置を講じている。
次に昭和43年度、身延町地域防災計画書についてふれることとする。
昭和四十三年度身延町地域防災計画書 身延町防災会議
第一章 総則
第一節 目的
この計画は、災害対策基本法第42条の規定により身延町の地域に係る災害対策に関し、おおむね次の事項について定め、もって防災の万全を期するものである。
第一節 目的
この計画は、災害対策基本法第42条の規定により身延町の地域に係る災害対策に関し、おおむね次の事項について定め、もって防災の万全を期するものである。
1、町の区域内における公共団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務または大綱
2、防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防に関する事項別の計画
3、災害に関する予報又は警報の発令、伝達、避難、消火、水防救助及び衛生その他の災害応急対策に関する事項別計画
4、その他必要な計画
第二節 防災機関の処理すべき事務または業務
第三節 町の地勢と災害記録
第二章 災害予防計画
第一節 防災訓練計画
第二節 防災知識普及計画
第三章 災害応急対策
第一節 組織計画
第二節 職員の配置及び動員計画
第三節 気象の予報及び警報伝達計画
第四節 被害報告計画
第五節 広報計画
第六節 避難計画
第七節 医療防疫計画
第八節 食糧計画
第九節 輸送計画
第十節 消防計画
第十一節 水防計画
第十二節 障害物除去計画
第十三節 教育計画
第十四節 自衛隊派遣要請計画
第四章 災害復旧計画
以上本町の地域防災計画は、一分のすきもない綿密さをもって、周到に組み立てられているのである。第三節 町の地勢と災害記録
第二章 災害予防計画
第一節 防災訓練計画
第二節 防災知識普及計画
第三章 災害応急対策
第一節 組織計画
第二節 職員の配置及び動員計画
第三節 気象の予報及び警報伝達計画
第四節 被害報告計画
第五節 広報計画
第六節 避難計画
第七節 医療防疫計画
第八節 食糧計画
第九節 輸送計画
第十節 消防計画
第十一節 水防計画
第十二節 障害物除去計画
第十三節 教育計画
第十四節 自衛隊派遣要請計画
第四章 災害復旧計画
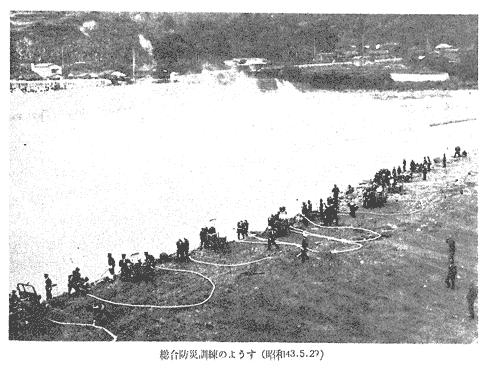 |
五、総合防災訓練の実施とその意義
昭和43年5月29日、身延町は県と共催の下に、山梨県総合防災訓練を大野の富士川河原で実施し、実戦さながらの猛訓練を行なった。 台風0号の襲来により、集中豪雨と富士川の大洪水に身延町一帯は甚大なる災害が発生している、との想定に基づくものである。この訓練の目的は、「災害対策基本法及び山梨県地域防災計画に基づき、各種災害対策の実施に習熟し、防災関係機関相互の協力体制を緊密にするとともに、町民の防災に対する理解と防災意識の高揚を図る」をねらいとして行なわれたのである。
本訓練の参加団体は、地元身延町消防団を始め、婦人消防後援隊、婦人会、町職員ら700人、県警本部、日赤山梨県本部、自衛隊、電々公社、東京電力、県職員、各市町村消防関係者等、あわせて1,500人、富士川河畔に繰り広げた防災訓練は、小・中学生など2,000人の見学者に深い感銘を与えた。
その訓練項目は、水防訓練、消防訓練、各種救助訓練、警備訓練、各種支援訓練、通信施設復旧訓練、電力施設復旧訓練等多彩にわたり、身延町防災計画の完壁を期する上に、所期の成果を十二分に発揮することができた。

