第四節 身延入山
一、入山の聖意
「日蓮聖人の身延御入山の聖意に就いては古来種々の説をなすが、幕府三諫を契機として万年広布を期された」(日蓮聖人の生涯)と塩田義遜師は述べている。確かに諸説はあるが、塩田師の説は簡にして要を得ている。すなわち「本より期せし事なれば、日本国の亡びんを助けんがために、三度いさめんに御用ひなくば、山林にまじわるべきよし存ぜしゆえに、同五月十二日に鎌倉をいでぬ。」(光日房御書)と、古聖賢の例に習って身延入山をなされたが、これはいはゆる「真に用ひられざるを識ったが故の」絶対絶望の遁(とん)世では決してなかった。下山鈔に
国恩を報ぜんがために三度までは諫暁すべし、用ヒずば山林に身を隠さんとおもひし也。又上古の本文にも、三度のいさめ用ヒずば去レと云ふ。本文にまかせて旦く山中に罷(まか)り入りぬ。
とある。この旦(しばら)らくが重要である。すなわち聖人無限の大慈悲心は決して三諫をもって終わるものでなく、旦(しばら)く山中に遁(のが)れて、彼(幕府)の大驚覚(近く蒙古来襲という)を俟(ま)って、最後の極諫を行ない、もって「公聴対決」「邪法禁止」「法華国教」を強く待望し給うて、従来の語諫をしばらく止めて、山林に遁(のが)れんと言われたものである。
以上は外、国家諫暁の一方面より見た入山の聖意であるが、更には進んで内には、著述子弟教養もって大法を万年に伝えんための入山であった。
また松木本興は「三諫不容を、一つの鎌倉を去られる条件となし、今迄の鎌倉における言葉による諫言に一応終止符を打ち、黙々の間に、天地法界を動かしての諫暁を続けつつ、万年弘布の基礎を固めようというのが入山の聖意である。」と推測する。(「身延のお祖師さま」より)と述べ、また田辺善知は「聖人の御入山は人を怨(うら)み、世を拗(す)ねた遁(とん)世ではない。北条幕府の頑迷にあきれて、現在の幕府を見限っても、後には洋々たる希望が溢れている。すなわち広宣流布の理想を、これから弟子等を督して、万年の後までの計を立てねばならない。三度諫めて用ひられざる故に、山林に交った。」のみではない。「妙法独り繁昌せん」(如説修行抄)時を理想としての行動であった。(一閻浮提第一の日蓮)
以上表現に別はあるが、塩田師と同意である。なお聖人は文永11年4月大三諫を終って、突然に鎌倉を去らんと決心されたものではなかったことは、建治元年すなわち御入山翌年の次の御書に見て明白である。
たすけんがために申すを此程あだまるる事なれば、ゆりて候ひし時、さどの国よりいかなる山中海辺にもまぎれ入るべかりしかども、此事をいま一度平左衛門に申しきかせて、日本国にせめのこされん衆生たすけんがためにのぼりて候ひき、又申しきかせ候ひし後はかまくらに有るべきならねば、足にまかせていでしほどに、(高橋入道殿御返事)
また聖人が前々から身延入山を考えられ、かつ身延に永住されようとされたものではないことは、御入山直後の「富木殿御書」に 十七日このところ、いまださだまらずといえども、たいし(大旨)はこの山中心中に叶てへば、しばらくは候はんずらむ。結句は一人になりて日本国に流浪すべきみ(身)にて候。
とあるに見て明らかである。しかし遂に最勝の地、終の栖(すみか)として身延に居を定められたのであった。二、波木井実長公
波木井氏の家系、所領等について、諸家に異説があっていずれに拠るべきかに迷うものが多々である。比較的最近の研究に成るところの早川達道の「富士日興上人身延離山の研究」並びに宮崎英修「波木井南部氏事跡考」は、いずれも綿密な研究がなされているが、なお両者間に必ずしも同意を見ない点がある。早(しばら)く両師の意見を摘記し、其他「身延山史」等を引用して項目を進める。早川達道は、「波木井氏は甲斐源氏の一流で、源頼義の子・新羅三郎義光から出た。義光の子・刑部三郎義清、甲斐国市川に住んで、逸見冠者清光を、清光は加賀美次郎遠光を生んだ。遠光の三男を光行といい、同国南部に住して南部を称した。これが南部氏の祖である。光行に数子があり、或は四子、五子、諸家譜一様ではない。
波木井実長は光行の子で、また小四郎といい、三郎ともいい、六郎ともいう」
宮崎英修は、「実長ははじめ彦三郎といったが、世人「彦」字を略して三郎と呼び、後六郎と改めた。日蓮聖人に深く帰依し、所領身延山を寄せて大いに外護につとめ、永仁五年(一二九七)九月廿五日天寿を全うして卒した。世寿七十六歳」
実長は光行の次男、または3男、あるいは6男であるといわれ、この他に4男5男という説もあり、諸本一様ではない。
頼朝上恪(らく)の際、実光(兄)とともに供奉(ぐぶ)に加わった当時は、三郎といっているから、実長は事実は三男ではなかろうか。
光行は治承4年(1180)7月頼朝の石橋山挙兵に従って功があり、それで甲斐の南部を与えられ、後文治5年(1189)7月頼朝の奥州征伐に従って勲功をたてた。奥州において、九戸・閉伊・鹿角・津軽・糠部の5郡を領する。
こうして建久2年(1191)12月下旬甲斐の南部より糠部に入り、同郡平郎坂に住して、三戸の城成るやそれに移り、次いで奥州南部氏の基をなし、領内を総称して南部と呼ぶ、一族従って奥州に昌(さか)えた。実長八世の子孫政光八戸に移り八戸南部氏(後の遠野南部氏)と称するまで波木井の庄に住した。
実長の子息についてはまた諸説があって一様ではない。早川、宮崎両師ともそれぞれ20頁にわたって綿密な考証をされている。いま早川師の結論を見るに、「若し此の推測にして誤りなくんば、実長の子息は三人、長を次郎実継といい、その裔は後奥州へ移ったものである。次は弥三郎実氏といい、また宮原に住んだので宮原殿とも称せられ、後常陸に移り住んだものである。その次はすなわち弥六郎長義であり、原に住めるより、また原殿とも呼び、甲州に留まったものである」
家継が家督を継いだことは諸系図の大体一致する所であり、また日蓮聖人遺文、実長消息等によっても、それらを知ることができるから今実継をもって、長子、嫡子とする。
また祖師伝が、弥六郎長義を一所において「三郎清長」といっているのは、長義が実は3男なる辺についてその様にいったものではなかろうかとも考えられる。
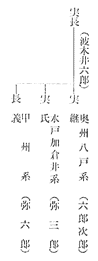 |
実長に四子あり、長子は彦次郎、次郎、或は六郎次郎と呼び、字を清長、諱(いみな)を実継といい、次男を弥三郎、六郎三郎と呼び、字を家長、諱を実氏といい、三男を孫三郎、(弥三郎)六郎四郎と呼び、字を光経、諱を祐光といい、四男を弥六郎と呼び諱を長義、法名を日教といったということを知ることができよう。
波木井氏の入信について見るに、文永元年(1264)(聖寿43)富士日興師によって実長の第3子、弥六郎長義が先ず帰服し、次いで実長の妻妙徳尼が入信した。続いて実長も日興上人により文永6年(1269)入信7年ごろ直接聖人に帰依したものと考えられる。
妙徳尼の伝は不明で、波木井円実寺、梅平鏡円坊、長円坊(現在は鏡円坊に合併)また南部の妙浄寺にも墓はなく、玉沢の「境持院日通師」の「門葉縁起」には「奥州にて死せるものか」とし、「日蓮宗大観」に至っては、宮城県伊具郡北郷村妙立寺開基、妙円日義をもって実長の後妻とする。しかしこの人は「攷異」によれば、実長の長女である。しかるに弥三郎実氏の母にして、実長の妻たる妙徳尼の墓は、水戸在加倉井妙徳寺に現存する。すなわち常州で死んだことは明白であるが、その族称、郷貫に至ってはやはり詳(つまびら)かでない。同時に実長の妻が何故に、甲州を去って常陸に行ったのかも詳細になし得ない所である。
また実長の最初の信仰は真言であったと見る。それが当時一般の仏教状勢に従って、聖人に知遇を受ける以前においては念仏者となっていたものであろう。
なお早川師は「実長の信仰を検討するにはこれを聖人御在世と、滅後とに分けねばならない。既に其間には大なる相違があるからである」と述べ「聖人入滅後における輪番制とその推移」において、その信仰状態について詳説されているがここでは略す。一方宮崎師はこれについて「実長が宗祖に帰依するまでの宗旨及び信仰は何であったろうか。先ず南部氏の宗旨が、何宗であったかを考えると真言宗であったらしく思われる」「その真言は東寺流であったと思われる」「実長の旧宗も真言であることは明白であるが、その実際に信じた宗旨は必ずしも家伝のものであるとはいえない」
「実長はじめ一同がまずもって日興の化に浴したことは間違いない」また入信の時期については「実長の入信は日興に依って、文永六年(1269)の頃に入り、6、7年の頃、直接聖人に帰依するに至ったものと考えることができる」といい、更に次の通り付言されている。
「さて実長の信仰がいかに堅固に持続されていたかは既に述べた如くであるが、それ故に性格は狷介不羈(けんかいふき)の所があり、信仰に関すること以外では、大聖人の教示に対してもそれに従わないで自分の思い通りにしようとすることもあった」「初発心の師として日興の苦労は並大抵ではなかったことであろうが、実長の性格は到底自分の主張を捨てて、それに従うことはできなかった。かくて実長は自義に同ずる温厚な日向に帰し、純信、厳粛の日興と袂(けつ)別するに至った」
三、御草庵での起居
身延山史によると 人皇第九十代後宇多帝の文永十一年(一二七四)六月十七日は実に聖祖棲神の霊窟たる世界の聖地、身延山開闢(びゃく)の嘉辰なり、中略、而(しか)して弘安五年(一二八二)九月八日御年六十一歳、身延山を発足せらるる迄八年五ヶ月実に三千日の御在山なり
宗祖が終の住み家と選ばれた身延はいかなるところであろうか。御入山翌年の文永12年(1275、4月25日建治と改元)2月16日安房の「新尼御前御返事」に、身延の景観を次のように報じている。
此所をば身延の嶽と申ス。駿河の国は南にあたりたり、彼国の浮島がはらの海ぎはより此甲斐国波木井の郷身延の嶺へは百余里に及ぶ。余の道千里よりもわづらはし。富士川と申ス日本第一のはやき河、北より南へ流レたり。此河は東西は高山なり。谷深く、左右は大石にして高き屏風を立テ並べたるがごとくなり。河ノ水は筒ノ中に強兵が矢を射出したるが如し。此河の左右の岸をつたい、或は河を渡り、或時は河はやく石多ければ、舟破して微塵となる。かかる処をすぎゆきて、身延の嶺と申ス大山あり、東は天子の嶺、南は鷹取の嶺、西は七面の嶺、北は身延の嶺なり、高き屏風を四ついたて(衝立)たるが如し
以上のような身延山は、はなはだ辺鄙(ぴ)の地ではあるが、風光明媚(び)であって閑寂(かんじゃく)、聖人自らも、 天竺(印度)の霊山(霊鷲山(りょうじゅせん)、釈尊が法華経を説法した所)此の処に来れり、唐土の天台山(支那に於て法華経を以て立宗した天台大師の開基道場)まのあたり此処に見る。我身は釈迦仏にあらず、天台大師にては無けれども、まかるまかる(専念して)昼夜に法華経を読み、朝暮に摩訶止観(天台宗の重要解説書天台大師三大著述ノ一)を談ずれば霊山浄土にも相似たり、天台山にも異らず。(松野殿御返事)
霊筆を振るって四方の檀越に、身延の風光を披露せられたのであった。故に聖人は御心も安らかに、御読経、門下の教養、著述等後代万年のため種々の御準備に過されたのであった。翌建治元年(1275)には「撰時鈔」「教行証御書」等の御述作があった。またこの年には後年京都開教の重任を果たし、宗祖の遺命に応えた経一丸(日像)が7歳の身をもって日朗に伴われて入山した。また遠く佐渡から阿仏房が87歳の老の身をもって師の許に詣でたが、更に翌年および弘安元年(1278)と3回登延した。
翌建治2年3月16日、旧師道善御房が死去せられ、この通知は間もなく身延に届いた。12歳以来恩愛の旧師の死を聖人は深く悲しまれ、追懐と報恩とに明かし暮されること約4ヵ月、聖人は旧師への心こめての手向草もがなと7月21日上下2巻の書を述作せられ、同月26日弟子日向をつかわして、墓前に供えて読誦せしめられたのが有名な「報恩鈔」である。本鈔は「立正安国論」「開目鈔」「本尊鈔」「撰時鈔」とともに「五大部」として数えられ、重要な御書であったが、明治8年(1873)1月10日の身延山大火に惜しくも焼失した。ただし先師の写本および少々の聖筆断片が今日格護されている。
翌3年には、四条金吾頼基公が、主君江馬殿より法華経の信仰を捨て、日蓮房への帰依を止めよ、との問責状を受けたことに対し、「頼基陳状」を代筆して、四条氏の信仰堅持を慰問激励された。
文永11年に入山の際のかりそめの草房は4年の後建治3年には柱朽ち、壁おち、月は住むにまかせ、風は吹くにまかせる程に大破した。聖人はこのいぶせき住居を「夜火をとぼさねども月の光にて聖教を読みまいらせ、われと御経をききまいらせ候はねども、風おのずからふきかへしまゐらせ候」と詩化されている。そして「十二の柱四方にかうべをなげ、四方の壁は一どにたふれぬ」の状況であったので、居合わせた学生達を督励して雪の中をかろうじて応急の修復をなした。
建治3年の修復もやがて朽ちて、弘安4年(1281)10月には、間10(18.18メートル)四面の堂があらたに建立され、11月24日盛大な開堂供養を行ない、身延山妙法華院久遠寺と命名された。
天台大師講、延年の舞(僧家の一種の舞)が行なわれ「空晴れてさむからず。人のまいること洛中鎌倉の町の申酉の時のごとし」(地引御書)とその盛大な有様を報じられている。
身延の僧坊には聖人を中心としてどの程度の人数が住んで居たのだろうか、文永11年5月17日波木井着と同時に遣わされた富木氏への御書に「けかち(飢渇)申スばかりなし。米一合もうらず、がし(餓死)しぬべし。此御房たちもみなかへして但一人候べし、このよしを御房たちにもかたりさせ給へ」と歎かれている。
弘安元年(1278)11月の池上氏への御書には「人はなき時は四十人、ある時は六十人」とあり、更に翌弘安2年8月の曽谷氏の御書には「今年一百余人の人を山中に養ひ」とある。
入山以来次第に僧侶や訪客の増加して行く有様がうかがわれる。同時にこれらの人々を不便な山中に養わねばならぬ聖人の心労も多大であったことは幾多の書状に示されている。
一、聖居九年の供養物
聖人御在山九ヵ年の衣食はどうして補われたのであろうか。信者の供養物について、文永11年より弘安5年の秋までの状態を御書について見ると下の通りである。| 1、富木氏夫妻 | 11回 | 19種 | 1、国府尼 | 1回 | 1種 | |||||
| 1、四条氏夫妻 | 11回 | 27種 | 1、新尼御前 | 1回 | 1種 | |||||
| 1、池上氏夫妻 | 10回 | 18種 | 1、大尼御前 | 1回 | 1種 | |||||
| 1、南条氏夫妻 | 41回 | 109種 | 1、桟敷女房 | 1回 | 1種 | |||||
| 1、太田氏夫妻 | 6回 | 12種 | 1、妙心尼 | 3回 | 4種 | |||||
| 1、曽谷氏夫妻 | 2回 | 4種 | 1、妙密上人女房 | 1回 | 1種 | |||||
| 1、西山殿 | 4回 | 7種 | 1、兵衛志女房 | 3回 | 5種 | |||||
| 1、松野殿 | 6回 | 12種 | 1、日女御前 | 2回 | 4種 | |||||
| 其他種々 | 1、治部房祖母 | 1回 | 4種 | |||||||
| 1、高橋氏 | 1回 | 5種 | 1、松野殿後家尼 | 3回 | 15種 | |||||
| 1、三沢殿 | 1回 | 4種 | 1、妙法尼 | 2回 | 3種 | |||||
| 1、内房尼 | 1回 | 1種 | 1、窪尼 | 7回 | 9種 | |||||
| 1、秋元氏 | 1回 | 2種 | 1、中臣某女 | 1回 | 1種 | |||||
| 1、国府入道 | 1回 | 6種 | 1、玉日殿 | 1回 | 1種 | |||||
| 1、浄蓮坊 | 1回 | 1種 | 1、某尼 | 1回 | 2種 | |||||
| 1、大井荘司 | 1回 | 4種 | 1、智妙尼 | 1回 | 1種 | |||||
| 1、六郎次郎殿 | 1回 | 2種 | 1、治部房 | 1回 | 3種 | |||||
| 1、堀田某 | 1回 | 1種 | 1、伯耆房 | 1回 | 1種 | |||||
| 1、新池氏 | 1回 | 1種 | 1、妙一尼 | 1回 | 1種 | |||||
| 1、中興入道 | 1回 | 1種 | ||||||||
| 1、十郎入道 | 1回 | 1種 | ||||||||
| 1、阿仏房尼 | 3回 | 7種 |
もちろんその他の日常の賄は波木井殿の御供養に頼られたことと推測される。
二、阿仏房と千日尼
聖人の御在山9ヵ年間に、阿仏房が90歳におよぶ老齢で3度身延を訪れたことは忘れてならないことである。阿仏房はもと遠藤為盛といって、順徳天皇に仕えた武士であった。承久3年、上皇の佐渡遷幸に随侍して24年の長年月奉仕したが、上皇おかくれの後は入道して阿仏房といい、真野山陵のほとりに住居を構えて妻とともに専心上皇の冥福を祈念し、念仏三昧に日を暮した。島へ流されて来た聖人を、一途に阿弥陀仏の敵と思い、これを殺そうとしたが、塚原の三昧堂で聖人の説を聞いてその理に服した上は、たちまち強烈な法華経の信者となって聖人のために身命を惜しまなかった。
聖人身延入山の後3度登山したが、最後の弘安元年(1278)7月には、90歳の身を交通不便の山河幾百里の道を越えて師を訪れた。妻の千日尼について、千日の名が起ったのは、順徳上皇が都に帰り給うことを望まれる御心を察して、3年の間水ごもりをしたので1000日といい、また聖人への供養からとったともいわれているが、夫に劣らぬ強信者で、信仰も人格もしっかりしていたことは、聖人が千日に下された消息を見ても知られる。夫の阿仏房を3度まで身延に師をたずねさせたのも妻千日の心であった。千日尼への書に
地頭・念仏者等日蓮が庵室に昼夜に立ちそいて、通ふ人もあるをまどはさんとせしに、阿仏房に櫃(ひつ)をおわせ、夜中に度々御わたりありし事、いつの世にかわすらむ。只悲母の佐渡国に生れかはりて有るか
阿仏房は弘安元年第3回目登山の際に聖人より日得と名を授けられたが、翌2年3月21日91歳で寂した。弘安3年、子の藤九郎盛綱は遺骨を負って身延に登った。

